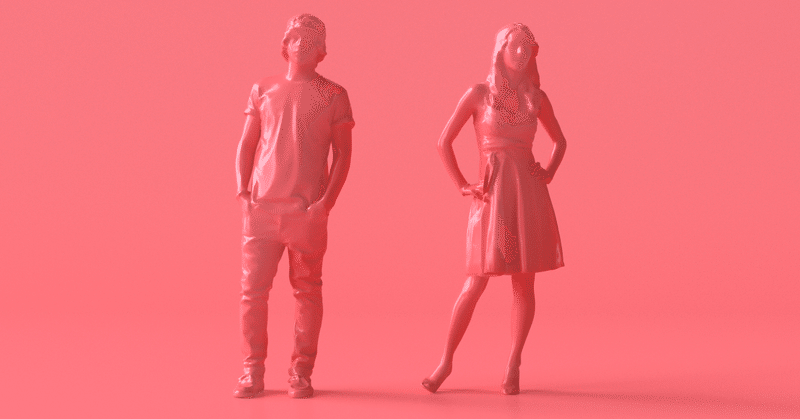
同族嫌悪(前編)【feat.レッド】
一つ、心理テストをしよう。
赤、白、桃、紫、青それぞれに、自分にとって当てはまる異性を思い浮かべてほしい。
さながらポケモン。得意なタイプと苦手なタイプはどこにでも発生する模様。
・赤:兄(姉)
・白:尊敬
・桃:弟(妹)
・紫:一発ヤリたい
・青:本当に好きな人
これは10年以上前、もうとっくに捨ててしまった本に載っていたものだ。ただ今回取り上げるのは、必ずしもこれに縛られたものではなく、単純に「その色に当てはまる人」に対して自分が強いか弱いか。
振替で初めてのクラスに顔を出すと、見たことのある打ち方をする男がいた。フォームはもとより、スイングスピード、コンパクトなスイング、走るヘッド、低い弾道。速さと回転量、回転量の割に軽い打球。それはレッドだった。
最初全然分からなかったのは、驚くほど痩せていたからだ。チュートリアルの福田が、一時ものすごい痩せ方をしたことを思い出す。
球出しを終えると、ストレートのラリーに入る。レッドと打つのは実に4ヶ月ぶりだった。
「お願いします」
相変わらず声がでかい。前も言ったが、基本大人のテニスは驚くほど静かだ。それはレベルが上がるほど顕著で、それぞれが「自身の課題とのみ向き合う個の集団」、「個人技を寄せ集めの人達でする」訳なのだから、至極真っ当なことだった。それでもごくたまに中級にも目立ってうるさい人がいる。私が知る中では、自分含めて3人。
打ち出されたボールは伸びる伸びる。バウンド後、ネット上を通過した高さを保ったまま手元まで届く。放物線の頂点からなかなか落ちない。
3、4年前、まだ私の打点が低かった頃、下手するとボーリングですか?という軌道を描いていたラケットは、この「落ちない打球」と完全に相性が悪かった。必死で打ち返しても、自分の打点に合わせるため、下がりに下がらされたのはベースライン3メートル後ろ。そこからボーリングの投球フォームで打ってネットを越える訳がない。ロブに逃げようものなら、回転量に負けてたやすくアウトした。〈あの人中上級じゃん?〉
そううれしそうに言っていたレッドは、次からまた何事もなかったかのように元のクラスに戻った。すなわち同じ時間帯の隣のコートの中級に、だ。「その人」以外まるで相手にならない。コスパが悪すぎると思ったのだろう。
それから私が初級にいた5年間、ずっと隣のコートにいた。
打ち返す。ラリーで必要なのは深さよりも速さ。同じ所に返せるコントロール力。
サービスラインに設定した目標は、けれども球威に押されてベースライン一歩手前に落ちる。角度を調整してもう少し手前。
レッドの打球は回転量が多い割に速い。重いけれど回転量にしては軽い。そのギャップが、それは、よく見れば何だ、私の得意な球種だった。
速さに合わせる。目標はサービスライン。
どうしても押されてしまう。けれども結果的にそれはベースライン一歩手前に落ち続けた。深さではなく速さを求めた打球は、相手の懐に食い込む、徐々にその打球が乱れ始める。
レッド、赤は本来私の得意なタイプだった。ただ、純粋に力に押し負けていた。だから対応できるようになれば結果は変わった。
動揺。ハナっから歯牙にもかけていなかった女に押されている事実。バックハンドがサイドラインを大きく割る。戻さなきゃと焦ってガシャる。赤は。
気負いの色。自負の色。強烈な自我の色。
集中し、自分がどうしたいかに焦点を当てているときは手のつけようがない。けれども、通用しないとなると、心が真っ先に乱れ始める。「取り返さなきゃ」そうしてそれは本来「人を助け、補えるだけの兄気質」に強く作用する。勝手に自分を焼き始める。だから対戦するとしたら、何よりまずそのベクトルをその人自身に向けさせる。すなわち3球連続でミスさせる。全てはそこからだった。
三球。交代。その時だった。
「もう一球お願いします」
男が取り出したは隠し球。この時何が起こったか。
それは「ムキになった男がこのままでは終われないと主張した」だけではない。その、よく通る声。いいか。
一目で分かる実力者が、ホイと現れた女に「お願い」したのだ。それはその場に居合わせた男全員の意識に作用した。この瞬間、私は女ではなく、彼らにとって「全力で叩き潰さなければいけない獲物」に変わったのだ。
何より、この時起こったのは、「追う側」と「追われる側」の逆転現象。
全ての音が掻っ消える。
脳裏に浮かんだのは、数年前、打ちっぱなしを見ていた旦那に言われたこと。〈必死感すごい〉
そんなつもりはなかった。好きで、自分が打ちたいように打っていた。
学生テニスが抜けなくて、調整とか知らなくて、ただ自分の思い描いた弾道が描ければそれで良かった。いつだって自分視点だった。他人から見てどう、ということに思い至ることがなかった。
言われて思い返してみれば、コーチにも「力を抜け」と言われていた。どのコーチも言っていた。けれどどうしても「7割の力で打つ」ことが、「タイミングを合わせる」ことができなかった。確かに上手い人ほど全ての動作が緩やかで一定で、テイクバックから急にラケットヘッドが加速することはなかった。
ただ、それでも自分の望むリズムでラリーができればそれで良かった。
誰に何と言われようと、私のテニスはそれで完結していた。けれど。
〈必死感すごい〉
全身が焼けるようだった。
それはたぶん、誰しもが思っていたこと。
婉曲に、それを矯正しようとしてくれていた。
ラリーができる人にこだわるのは、「自分の望むリズム」でやり取りできる人が少ないから。当たり前だ。人の声に耳を傾けようとしない人相手に続けるラリーなんてない。ごくたまに声をかけられるのは「速いボールを返せた」という、その人の今いる環境内で発生しない事案、その人自身の自己肯定がためだった。直に言おう。
メガネくんは誰でもいい。
私はメガネくんでなければいけない。
このことこそが、温度差の最大の原因だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
