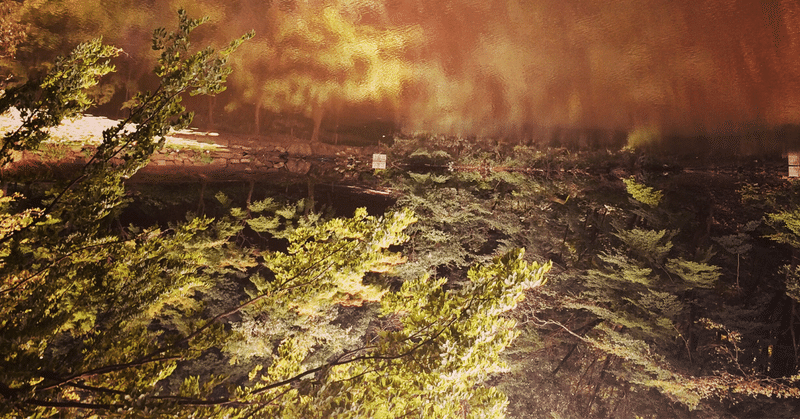
合作小説「きっと、天使なのだと思う」
合作小説「きっと、天使なのだと思う」
第10話~最終回~
だから……生きてください。
それが、いつも通りの……何の変化の無い日常だったとしても……それが、私の願いです
ゴンドラがゆっくりと降下しながら、少しずつ地上に近づいている。窓の外を見れば、あんなに小さかった建物や車も徐々に見慣れた大きさに戻り、シーンと静まり返ったゴンドラの周りには、相変わらず風船が浮遊していた。
「……分かった」
僕が頷くと、ようやくクラリネットとテトラが笑った。そして、左肩にバシッとアルファベットの手の感触が走る。
「約束ですよ。本当は屋敷で言うはずだったのですが……フフッ」そう言うと、クラリネットはスッと立ち上がり、窓の外の風船を指差した。
すると、風船はパンッと派手な音を立てながら一つずつ弾けていき、あっという間にゴムの破片へと姿を変えてしまった。
そして、クラリネットは優しくテトラを抱き上げると、もう一度、僕に微笑みかける。
「それでは……」
「待って!」
その時、僕はクラリネットの言葉を遮った。その様子にクラリネットは少し驚いた表情を浮かべ、テトラは耳をピンと立てている。
「……もう、会えないの?」
あと数分で地上に到着するであろうゴンドラの中で、僕は往生際の悪い男が言うような台詞を口走っていた。
今まで三十年も生きてきた中で、こんな歯の浮くような台詞を放ったのは生まれて初めてだ。それに、何故、このような言葉が出て来たのか、自分でも不思議で堪らなかった。
別に恋をしたわけでもない、
ただ、『不思議な少女』に――
「雪道様……」
「悪いな……俺たちにはまだ、やることが残っているんだ」
「雪道。次、私たちに会うときは……もっと素敵な方になっていると信じてるわ……」
長いまつ毛を揺らし、クラリネットが微笑みながら言った次の瞬間、突然吹きつけた風がゴンドラを強く揺らした。
「おっと!」
予想外の出来事に、僕は咄嗟にゴンドラの手すりに捕まった。風はすぐに止んだようだが、キィキィと鈍い金属音が反響している。
「皆、大丈夫か?」
そして、皆の安否を確認しようと顔を上げた瞬間、もう、そこには三人の姿は無かった。クラリネットの姿も、テトラの愛らしい体も、アルファベットの気配も、全て……。
「――ありがとうございました」
観覧車を降りると、先ほどの係員の女性と目が合った。そして、僕の背後を一瞬だけ見た後、ポツリと呟いた。
「……お連れの方は?」
ひょっとすると、彼女にはアルファベットの姿が見えていたのだろうか。その時、僕は平常心を装いながら彼女に、こう問いかけた。
「……僕、ずっと一人でしたけど。どんな方でしたか?」そう言うと、彼女はギョッとしながら、必死に言葉を紡ごうとしていた。彼女には大変申し訳ないのだが、アルファベットがどんな姿をしていたのか、どうしても知りたかったのだ。
「えっと……背の高い……大柄な男性でしたよ。外国人でしょうか……」
「そっか……ありがとう。変なこと聞いてすみません」
「えっ……あぁ……」
少々混乱気味の彼女に会釈しながらその場を離れると、びわ湖タワーのゲートへ足を向けた。
その途中、『さようなら びわ湖タワー』と書かれた大きな看板が目に飛び込んできた。看板をよく見ると、今月末で閉園するとのことだ。
そして、近くにいた係員に聞いたところ、閉園後、園内の遊具は外国へ渡ることが決まっており、観覧車はベトナムで第二の人生を歩むそうだ。
初めてここに来たのは、何歳の頃だっただろうか。大きな観覧車を初めて目にした時から比べると、良い意味でも悪い意味でも随分と成長したと思う。
もしかすると、あの三人に会えたのも一つの成長なのだろうか。
最後に観覧車を見上げた後、僕は静かにびわ湖タワーを後にした。園内から聞こえてくる賑やかな子供の声は、あと数日で薄れていくのだろうか。
そう思うと、急に視界がぼやけた。「いい年して、何泣いてるんだ」と、アルファベットの呆れた声が聞こえることもなく、僕は涙をぬぐいながら、最寄りの駅に向かって歩いて行った。
しばらく歩いていると、突然、チリン――と、風鈴の音が鳴り響いた。ハッとして周りを見渡すが、そこには誰の姿もなく、あの車の姿も無かった。
よく見ると、駅前商店街にある古い電気店の前を歩いていたようで、店の軒先にある錆びた風鈴が鳴っていたようだ。
もう、すっかり秋も終わりが近付いている頃なのだが、夏の置き土産はゆらゆらと心地良さそうに秋風に揺れていた。
「ハハッ……」
風鈴を眺めていると、つい、三人に出会った日のことを思い出した。今度会うのは、何十年後かにしていただきたいな、と考えながら、再び駅に向かって一歩踏み出した、その時。
『今、入ってきたニュースです』
電気店の前にあるテレビから聞こえてきたアナウンサーの声に、僕は思わず足を止めた。
『先程、東京都港区の警察署前で男が暴れているのが発見されました。取り押さえた警察官に対し、男は“ひき逃げ犯は俺だ。今、乗ってきた車で轢いた。怖くなって逃げた”と供述しているとのことです』
ひき逃げ、というキーワードに、反射的に手が震える。偶然にも、場所は僕の勤務先がある港区だった。あの日、僕を轢いて逃走した犯人は、今も平然とした顔で生活しているのだろうか。
『警察によりますと、男は三か月前に港区で男性をひき逃げして重傷を負わせた犯人と見ており、調べに対し、男は“白い大男とウサギに追いかけられて逃げてきた。途中、女の子に変な液体を飲まされた。自首しろ、と迫られた”と、意味不明な供述をしているとのことです。警察では――』
その瞬間、僕の背後に生暖かい風が走り抜け、錆びた風鈴を再び揺らした。同時に、ズボンのポケットで振動を始めた携帯電話を取り出すと、『母』と表示された画面を確認する。
「も、もしもし……」
通話ボタンを押すまで、どのくらい時間がかかったのだろうか。そして、犯人が見つかった、と興奮気味に話す母の話を聞きながら、僕は、時折、チリン――と揺れる夏の置き土産を眺めていた。
【終】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
