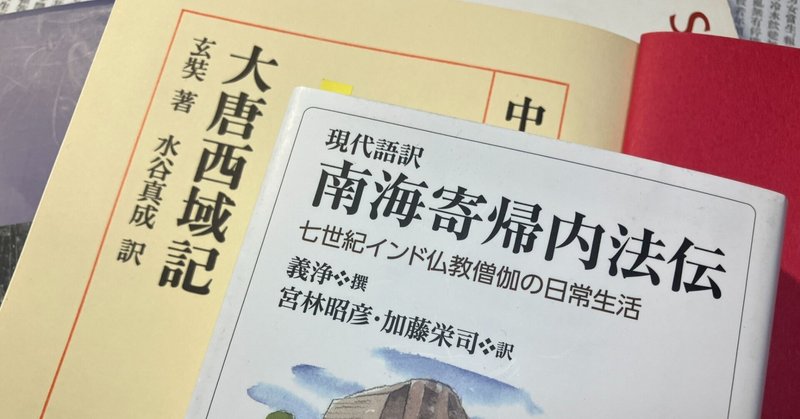
鬼子母神の説話と図像
以前、「鬼子母神」のことを書きました。改心した鬼子母神に対し、柘榴は人肉の味がするから人が食べたくなったらそれを食べるようブッダ釈尊が教えたという、仏典にはないあの「俗説」。あの話の出どころを探ってみたわけですが、今のところまだわかりません。
仏典では「もし人が食べたくなったら」という万が一のことは想定されていないようですが、しかし、善神となとなって子どもを食べなくなった鬼子母神の「今後の食事問題」の対策は、仏典にも書かれています。
唐の義浄三蔵(635~713)訳『根本説一切有部毘奈耶雑事』という律文献(vinaya、僧団内の規則)の第31巻には、こう書かれています。
「世尊。我及諸児従今已去何所食噉。仏言善女。汝不須憂。於贍部洲所有我諸声聞弟子。毎於食次出衆生食。并於行末設食一盤。呼汝名字并諸児子。皆令飽食永無飢苦」(『大正新脩大蔵経』第24巻より)
訳すと次のようになるでしょうか。
改心した訶利底(鬼子母神)は、ブッダ釈尊にこう尋ねます。
「世尊よ、私と私の子どもたちは、今より以後、いったい何を食べましょうぞ」
すると、ブッダはおっしゃいました。
「善女(仏教に帰依した女性のことで、ここでは訶利底)よ、心配する必要はない。贍部洲(古代インドの世界観で、世界の中心にそびえる須弥山の南側にある人間の住む大陸)において私のあらゆる弟子に、食事のときにはいつも(食前に少量を取り分けて衆生のために)衆生食(生飯)を出させ、僧侶たちの下位に食事を(訶利底のために)一盆設けさせ、また、あなたの名前とあなたの子どもたちを呼び、足りるだけ皆に食べさせて、とこしえに飢え苦しめさせない」
訶利底の「我及諸児従今已去何所食噉」というブッダへの問いかけに「反語」的なニュアンスが感じられることにも違和感を覚えますが、それよりも、訶利底は、突然どうして自分の子どもたちの今後の食事について困ったのでしょう。
というのも、人の子を食べていたのは訶利底であり、呵利底の子どもたちではないのですから、つじつまが合いません。これはかねがね、おかしいと思っていましたが、森雅秀先生は『仏教の女神たち』の中で次のように指摘されています。
「『雑事』では、このやりとりがあったから、伽藍の食堂で鬼子母神やその子どもたちに毎食、食べ物を供えるようになったとあるが、逆であろう。もともと、そのような習慣があったから、それを裏付ける物語が創作されたのである。図像が物語を生み出したのであって、物語から図像が生み出されたのではない。これは一般の説話図の成立とは反対の流れである」(森雅秀氏『仏教の女神たち』春秋社、2017年)
鬼子母神に関しては、具体的なイメージが先にあり、それを説明するような物語が必要とされて説話が生み出された、というわけです。
これは説話と像や絵画のかかわりを考える場合、忘れてはならない視点だと思いました。
「仏伝図」も「涅槃図」は物語が先にあり、それに即して図像が生み出されたと考えられてます。説話の図像というもののだいたいはそういうもので、物語(口承であっても)のテキストに即してつくられた。ですから森先生は、鬼子母神の説話は、説話と造形作品の関係を考えるうえで重要な意味を持つと指摘されています。
すると、説話の成立に先立ち、鬼子母神にまつわるどのような習慣があったのかということになりますが、それはもはや、失われてわからないのでしょう。しかし、『根本説一切有部毘奈耶雑事』の漢訳者・義浄三蔵による下記のような現地の記録は、参考になるのかもしれません。
義浄三蔵は、現地インドの寺院で、鬼子母神が実際どのように供養されていたかを見聞し、『南海寄帰内法伝』という見聞録に書き残しています。
義浄三蔵がインドに行ったのは玄奘三蔵の数十年後のこと。玄奘三蔵とは違い、陸路(シルクロード)ではなく南シナ海、スマトラを経て海路で渡りました。義浄三蔵は玄奘を深く慕っていたと伝わっています。
さて、義浄三蔵によると、当時インドの諸寺院では、門に付随する小屋のところか厨房のあたりに鬼子母神の像や絵を祀っており、その図像は、母が一人の子どもを抱き、膝の下あたりに3人から5人くらいの子どもたちの姿が表わされたものだそうです。
その前に毎日さかんに食べ物が供えられる。そして、鬼子母神は四天王の衆と同じ仏法の守護神であり、大きな勢力があるから、病気があったり、子どもがいない人は、鬼子母神に食べ物を供えて供養すれば皆願いが叶うとされている、ということです(参考:義浄著、宮林昭彦・加藤栄司訳『現代語訳 南海寄帰内法伝: 七世紀インド仏教僧伽の日常生活』宝蔵館文庫、2022年)。
森先生によると、「もともと、そのような習慣があったから、それを裏付ける物語が創作されたのである。図像が物語を生み出した」ということになるわけですが、ポイントは、「病気」と「子ども」にあるのではないかと思います。
『根本説一切有部毘奈耶雑事』によると、鬼子母神、すなわちハーリーティー(サンスクリット語はHārītī、音訳は訶利底、呵利底など数多くあります)は、もとの名を「歓喜」といいましたが、彼女は過去世の因縁により、他の家の子どもを食べる「薬叉女」となりました。
この「薬叉」や「夜叉」(サンスクリット語のyakṣaやパーリ語のyakkhaの音写語で、女性のそれはyakṣanī、yakkhinī)と呼ばれる存在は、仏教が生まれる前からある民間信仰の神霊・精霊のような存在であったといわれます。それらは恵み深く、しかし、信仰・供養しない人間には悪疫(怖い伝染病など)をもたらしたりもする恐ろしい存在でもあったようです。
民間信仰の神々を持つ人々のところへ仏教が伝わっていくなかで、在来の神々が仏教の神々として位置づけられていくとき、「実はその神は仏教の守護神であった」ということが語られるのなら、やはり在来の信仰の様態をふまえた説明になっていなければならないことは想像できます。鬼子母神もそのようにして、仏教に転じた薬叉神であったという説明が生まれたのかもしれません。
最も古い時代のハーリーティー像は、ガンダーラ地方やインド北西部のアジャンターなどで見つかっているそうです。おそらくそのあたりに、ハーリーティー信仰の起源があったのでしょう。
また、玄奘三蔵は『大唐西域記』において、健駄邏(ガンダーラ)にはブッダ釈尊が鬼子母神を教化した場所、「化鬼子母の遺跡」があることを報告しています。
「梵釈(梵天と帝釈天)の窣堵波(ストゥーパ・塔)から西北へ行くこと五十余里、窣堵波がある。釈迦如来がここで鬼子母を教化し人を害しないようにされた所である。それでこの国の俗として祭って後嗣(世継ぎの子)を願うのである」(水谷真成訳『大唐西域記1』、中国古典文学大系22、第2版、平凡社1984年)
鬼子母神が実在したのかどうかはわかりませんが、フランスの考古学者・仏像図像学者のアルフレッド・フーシェ氏(1865-1952)は、『ガンダーラ考古游記』の中で次のように記しています。
「ハーリーティーとは、世の母親たちを震えあがらせる天然痘の女神以外のなにものでもなかった。〈中略〉村人たちによるとその場所の本来の名は、サレー・マク(逐語訳すれば「赤顔」)であると固くいいはった。サレー・マクとはまさに天然痘のことだ。彼らの話はこうである。天然痘にかかった子どもたちをそこへつれてゆき、彼らのあどけない口の中に、ここの土を一つまみ入れる。それから彼らのターヴィーズ(首にぶら下げたお守袋)にもすべり込ませる。すると彼らはすぐにこの病気から快復するというのだ」(フーシェ著、前田龍彦・前田寿彦訳『ガンダーラ考古游記』同朋舎、1988年)。
フーシェ氏は、パキスタンのペシャワル近郊にあるチャルサダという都市遺跡の少し北にあるサレー・マケー・デーリー、すなわち「天然痘の土丘」を、玄奘三蔵のいう「化鬼子母の遺跡」に比定しています。その丘は、高さ18m、幅120m、長さ180mの塚(山本智教氏「ガンダーラ仏教美術派の遺跡(下)」『密教文化』1979年128号)。
フーシェ氏は、今はイスラム教徒の地であるその場所において、「イスラーム教徒の間に、例外的にヒンドゥー教の、さらには仏教の伝説さえものが生き残っている」と述べ、仏教美術学者の山本智教氏(1910-1998)も、1970年代、「いまでも天然痘に特効ある霊地としてイスラム教徒である住民に信じられ、子供をもつ母親たちが参詣する。玄奘が伝える鬼子母神が釈尊に教化された所というのがここである。鬼子母神というのは hariti(詞梨底母)といい、子供を殺す恐るべき天然痘を鬼神化したものである。それは深く信仰されて子供の守護神、さらに進んで子授けの女神とまでなった」(山本氏、前掲書)と書かれています。
神の名が変わり、あるいは時代を経てそれが忘れられても、また、それを語る教義・教団が移り変わっても、伝説と信仰が残るということ。このことに対し、フーシェ氏はこう述べています。
「おそらく、伝説が生きているのは母親たちが宗教の別などにあまり重きを置いていなかったおかげだとしなければなるまい。彼女たちにとっては、自分の子どもを救うことになるのなら、どんな方法でもよかったのである」(フーシェ氏、前掲書)
ここで「宗教」と訳されている言葉が、フーシェ氏の原文(“Sur la frontière indo-afghane Alfred Foucher”, Le Tour du Monde, 1899)ではどのような言葉であるかは非常に重要ですが、私はまだ原文を確認できていません。
しかしながら、自分の子どもたちを救いたいという人々の親としての本質的な一心と、人々が「宗教の別などにあまり重きを置いていなかった」ということが、伝説や信仰の継承に重要なはたらきをなしたファクターであったとみる一見「逆説的」なこの見解は、教義や教団を持ち体系を有する「religion」としての宗教と、それとは異なる「practice」としての民間信仰および「図像=イメージとしての民間信仰」の、とても興味深い関係を示唆しているように思えてなりません。
