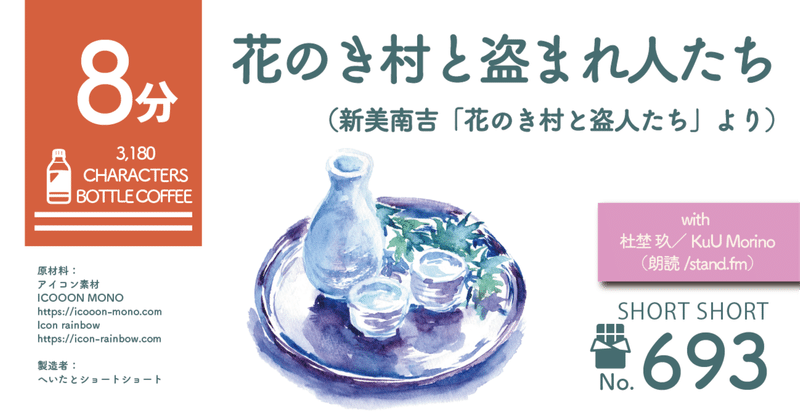
掌編小説 花のき村と盗まれ人たち(新美南吉「花のき村と盗人たち」より)
杜埜 玖/KuU Morinoさんに朗読して頂きました。是非お聞きください。
むかし、花のき村にひとりの村役人が住んでいました。
白髪頭で、いつも眼鏡が鼻の先から落ちかかるようで、ちょっと押したらその場にぺたんと座り込んでしまいそうな、弱そうで頼りなさげな老人でした。
ある、夏の初めのこと。松の林にジイジイと蝉が鳴いている昼頃、この村役人の老人はこっそりと村の入り口の、水車のあたりの見回りをしていました。
というのも、かつてこの老人が働いていた名古屋の大きな役所のお役人から「この辺りに泥棒の一団がやって来たらしい」と手紙をもらっていたからです。
「この村の人たちは、みんな『うぶ』だからな」
老人が普段決して見せない鋭い目で、水車のすぐそばのやぶを睨みます。草むらの中に鼻を突っ込むと、草いきれに交じって、微かにタバコが匂いました。村では買えないような上等なタバコの香りです。余所者が近くにいるに違いありません。
「何か、おかしな人が来なかったかね」
いつも通りのにこにこした顔で、村役人の老人は村の人たちにたずねて回りました。ある人は「釜を治してくれた人がいた」と言い、またある人は「腕のいい錠前屋を見た」と言い、小金持ちの酒屋の店主ときたら「大工らしい男がしきりと感心するので家にあげて座敷の天井を見せてやった」と自慢げに言いました。
「不用心にも、程がある」
呆れながら懐手で川沿いを歩いて行くと、ピイヒャララと生垣の花菖蒲ごしに村の爺さんが上機嫌で竹笛を吹いているのが見えました。そのすぐそばに、村では見かけたことのない子供が笑っていて、くるくるとその場で回ったかと思うと、「そおら」と掛け声を上げて、とんぼかえりを七回もしてみせました。
村役人の老人は目を丸くして、まさかあれが盗人ではないだろうとひとりで納得して、疲れた足で家に帰って行きました。
その日の夜は、綺麗な月が空にのぼりました。
普段は誰も客の来ない村役人の老人の家の戸を叩くものがあります。
「お客です」
下男の声に老人が膝をさすりながら玄関に行くと、ぼんやりと照らされたうつぎの白い花や柿の木を背にして、髭を生やした屈強な男と、青年が二人、それに昼間見たとんぼかえりの子供が立っていました。
「あのう……すいません」
子供が申し訳なさそうに言ったのに、老人がはっとなりました。つい癖で、このおかしな五人組を舐めつけるように睨んでいたのです。あはははは。老人はなるべく人が良さそうに笑いました。それから頭をかいて言いました。
「こりゃあ、すまん、すまん。わしは、役目から人を疑うのが癖になっていてな。余所者を見かけちゃあ、ぬすっとじゃないかと思ってしまうんだよ。ま、勘弁してくれ」
「いやいや。わしらは旅の者でして。余所者には違いありません」
髭を生やした男がからからと笑って、村役人の老人もまたにこりと笑いました。下男だけが眉をひそめて村役人の老人を見ています。普段世話をしている下男にはよくわかっていました。この老人はこうして人の良さそうなふりをしては相手を油断させ、やがて何もかも白状させてしまう狡賢い人物なのです。この五人は盗人か、あるいはもっと何か他の罪を犯した悪人に違いありません。なにしろこの老人が見込んだのですから。ちらり、と老人が廊下の奥を見ました。下男は小さく頷きました。これからこの怪しい者たちに酒を飲ませて口を開きやすくさせる。それも下男にはよくわかっていたのです。
「お疲れだろう。今日はいい酒が手に入ったんだが、ひとりで飲むのは寂しくてなあ。ひとつ、つきあいなされ」
村役人の老人に勧められるまま、哀れな五人の下手人たちは縁側に並んで座らされました。下男がいそいそと酒と肴と子供にはお菓子を運ぶと、やがてひとりの村役人と五人の下手人たちはすっかりくつろいで、十年も前からの知り合いのように、愉快に笑ったり、話したりし始めました。下男は内心わくわくしていました。さあ、こいつらは一体どんな悪いことをしたのだろうと思ったのです。
髭の男はいかにも大泥棒、というふてぶてしい顔付きをしていましたし、青年二人の手は職人らしくタコできたり爪が曲がったりしていました。くったくなく笑う子供もそれが「ふり」だとしたら、大した詐欺師に違いありません。ちょっとした自慢話からも下手人の悪事を暴き出すのが村役人の老人です。下男は言われるがままに酒と肴を運びながら、白状するのは今か今かと待ち構えていました。
ところが、酒と肴とお菓子をすっかり平らげると、五人の下手人たちは何を白状するでもなく席を立ちました。玄関でお礼を言って、去って行きます。村役人の老人も赤い顔をして、笑いながら見送りました。下男は目を丸くして老人に聞きました。
「いいんですか? あいつら帰しちゃっても?」
「いいんだ」
にっこりと笑って老人は言いました。
「あんなに油断して、すっかり自分を信じてかけらも疑わなかったあの五人が、大した盗人であるはずはないだろう」
下男と老人が手を振って見送っていると、突然髭の男がくるりと踵を返し、ひとり、二人の目の前まで戻ってきて、微かに震えた声で言いました。
「わしらは、実はぬすっとです。わしがカシラで残りは弟子です」
老人が鼻から落ちそうになるメガネを慌てて押さえました。「なんでわざわざ」と言いかけたのを遮って髭の男が続けます。
「いや、驚かれるのはごもっとも。わしもこんなことを白状するつもりじゃなかった。けど、あんたがあんまりいい人で、わしらを心から信じてくださるものだから、あんたを騙すのが申し訳なくなった」
思わず吹き出しそうになる下男を村役人の老人が睨みつけました。ひ、と小さく下男の声が漏れました。髭の男はそれにはちっとも気づかず、今度は老人のか細い両手を自分の大きな両手でつかんでぼろぼろと泣きだしました。
「わしは散々悪いことをしてきた。だが、残りの若いのは、今日弟子になったばかりで何にも悪いことはしておりません。どうか、見逃してやってください」
村役人の老人が、髭の男の肩越しに心配そうにこちらを見ている三人の影を認めました。顎から首を振って、「行け」と示します。一度では足りず、三度繰り返してようやく、名残惜しそうに影が去って行きました。
酷く酔っ払って泣き止まない盗人のカシラを下男が客間に寝かせると、村役人の老人はすっかり散らかった縁側に戻りました。腕を組んで月を眺めます。
「結局、疑い深いのはわしだけか」
大きなため息と一緒に言いました。
ふふ。下男が転がったお茶碗やお皿を片付けながら、老人にばれないように笑いました。心の善いところばかりでない自分の主人のそういうところが、なかなか気に入っていたからでした。
ショートショート No.693
このお話は新美南吉「花のき村と盗人たち」のパスティーシュです。
実際には花のき村にやってきた5人の盗人のお話を、ほぼシチュエーションは変えずに、村人たち側の話に置き換えています。老人の村役人と下男は原作に出てきますが、こんなに擦れた、現代的な人物ではありません。
「ごんぎつね」や「手袋を買いに」ほど有名ではない作品なのは、全体を通じた牧歌的な雰囲気が「小説」と言うには物足りない感じがするからでしょうか。
それでもやはり、私が書いた話では触れなかった盗人たちの改心の部分に、新美南吉作品に多く登場する「孤独」「ひとりぼっち」という課題を抱えていると思います。盗人のカシラは「他人に信じてもらうこと」でその課題を乗り越えます。「村というものは、心のよい人々が住まねばならぬと言うことにもなるのであります。」と結ぶ「花のき村と盗人たち」。これだと心の汚れた人はどうすれば……!? と人ごとではなくなりそうなので、そんなに澄み切った心を持たない、けどひとりぼっちでもない二人を住まわせてみました。
そして、本作、noteとstand.fmでご活躍中の杜埜 玖/KuU MorinoさんのLive放送でご朗読いただきました。どうもありがとうございます!
くぅさん、いつもありがとう。
