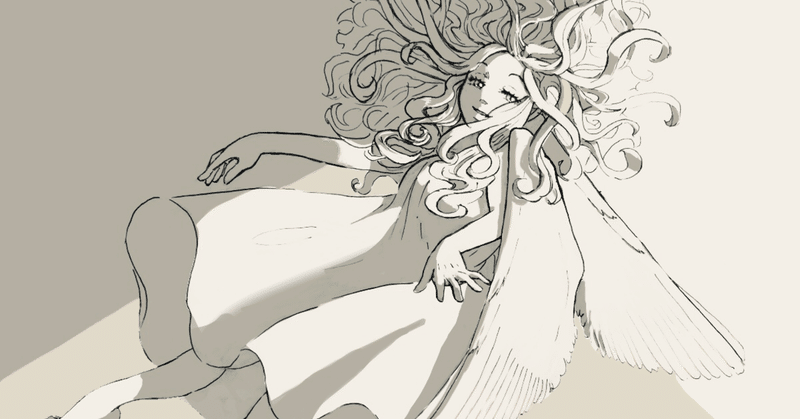
【小説】『マダム・タデイのN語教室』9/10の上
未読の方はまずこちらから↓
(10回中9回目の上:約4100文字)
LESSON CLOSE 的外れこそ救われる
違う!
この人は悪じゃない! この人に罪は無い! それなのに、ああ神様! この人も連れ去ってしまわれるのですか?
「田出井さん?」
声を掛けられて我に返った。
「ああ。ごめんなさい。ちょっと日の光が、目に入って見えにくくて」
長く買い手が付かなかった、隣の洋館平屋建てを、キレイにリフォームして住み始める、って挨拶に来たその人を見るなり、頭の中に、とても自分のものとは思えない感情と言葉があふれ出て来た。
たまに、あるの。出て来たからって何を言い切れるとも思わないから、口に出す事なんかまず無いけど。
幽霊なんかはそんなに信じていないし、霊感があるとも思わない。強いて言うなら毎日木や花や葉っぱに触れているから、ううん、枝を切る時草を抜く時にいつも、「ごめんなさい」を言っているから、じゃないかなって気がしている。
「お父さんと、二人暮らし? 感心ね」
見たところまだ二十二か三ってところなのに。
「お母さんは?」
「いません。初対面の方にこんな話も何ですけど、顔も知りません」
落ち着いた話しぶり。ニコリともしなければ、哀しげに声を落とす様子も無い。
「背も高いし格好良いから今まで、モテてきたでしょ」
「ご冗談を。誰からも、好かれた事なんかありません」
「自分でそう思っているだけじゃないの?」
母親も、彼女もいない、となると、頂き物のカルピス瓶でも渡しながら言っておこう。
「すみません。ウチはその、カルピスは……」
「そのうち出来るわよ。あなたの事を、命がけで守ろうとしてくれる人が」
もしかすると守り切れはしないのかもしれないけど、現世の話、とも限らない。
「お世辞にしても大袈裟ですね」
「だから少しくらい笑っていなくちゃ。せっかく気になって近付きたいって人が、嫌われたんじゃないかと思って避けて通っちゃうわよ」
カルピスのボトルを抱えたまま少しだけ、クスッときたみたいで、
「なるほど。これが『お節介』というものですか」
嫌味でもなく本当に、初めての事で新鮮、みたいに言ってきた。
「ええ。ついでに覚えておいて。名前はお節介の節子です」
来週はもしかしたら、体調を崩しているかもしれないから、約束はしないでおいた。
この先の約束もやめましょう、と言ったら、ステファニーは意外そうな、そして寂しそうな顔をしていたけど、
「だってあなた、もう自分で勉強できるわよね? もしかして、勉強からは離れるかもしれないけど、N語は好きでいてくれるでしょう?」
「はい。だけど……、まだわからないコトたくさん……」
「だから、『教える』とか『雑談』とかじゃなくて、これからは、おしゃべりしましょう。水曜日のこの時間は必ず家にいるから、話したい事があったらいつでも来て」
「え」
一瞬疑問に聞こえたけど、ステファニーは前から気になっていたものが見つかった様子でいた。
「『e』でおわる、あった……」
私はつい笑ってしまう。
「ああ。そうね。だけど、ほら、終わってない」
「ホントウだ」
そう言って可愛らしく笑ってくれたけど、結局それからステファニーが、我が家にやって来る事は無かった。
車イスに乗ったステファニーを、見かける事も無くなった。次の週の公園にはご主人が、ただ一人で来ていて、
「よし。ここは一つ俺が」
と夫が腕まくりをし出したけど、黙っとれやこのハゲ。
「大丈夫よ」
夫婦になって長いものだから私は、本音はともかく波風を立てない言い方を、心得ている。
「あなたはそこで、私を見守っていて下さいな」
微笑んであげると「そうか。よし」とか言いながら、枝を整えるフリをしている。
近付いて行くとご主人は、朗(ロウ)は、タートルネックのニットにジャケットを羽織って、薄めだけれど何か文庫本を広げていた。一瞬悪いかな、と思ったけど、
「こんにちは」
声を掛けると顔を上げて、少し微笑んでくる。
「今日は、お一人?」
「はい。誘っているんですけどこのところ、編み物に熱中してしまって」
文庫本には紐を挟んで閉じて、ベンチの隣を空けてくれるから、私はトートバッグ一つ分の間を空けて座った。
「奥さんが、貸して下さったんですよね? 本に毛糸も」
「余計な事をしたかしら」
「いいえ」
「5歳くらいまではお母さんがそばにいて、枕元でよく編み物してたらしいわ」
「そうですか。それは、聞いていませんでした」
その後聞かされた話で、もしかしたら、ステファニーは「呪い」のようなものを掛けられる子で、それを「殺す」と表現していたのかもしれない、と思ったけど、証拠になるような話でもない。
「今月は、ステファニー調子崩していないみたいね」
「はい。編み物に集中しているせいでしょうか」
落ち着いた話しぶり。少し肌寒い季節にちょうど合う。
「正直に言ってちょっと、残念なような、同時にホッとしているような。来月は調子を崩してほしいような、来月も、崩さずにいてほしいような。複雑です」
「お世話をしているのは楽しかったでしょうから」
「はい」
「同時に苦しくもあったでしょうから」
「ええ」
文庫本は閉じられたまま手元にある。
「読書の、邪魔になったかしら」
「いいえ。内容はもう、分かっているんです」
見せられた表紙は街角に立つ、不機嫌そうな男の子のイラストで、不機嫌だって分かるのに絵柄がやわらかくて微笑ましい。タイトルは、『車輪の下』。
「ご存じですか?」
「いいえ。知らないけど、可愛らしい表紙ね」
答えると朗は「そうですよね」って、聞こえてくるみたいに微笑んだ。知らない事に、読んでいない事は恥じゃない。もちろん。
「面白い?」
「面白いですよ。文章は」
目元の笑みが無くなった。元から「微笑み」だったけれど。
「内容は、残念ながら僕には、そこまで……、『嫌い』と言い切ってしまえるくらいかもしれない。それでも『面白い』と感じながら、読み進めて行けるんです。すごい事ですよね、それって」
「そうね」
「父は」
口にして少し、下唇を噛んでから続けてきた。
「外国語の作品に、N語訳で触れる事を認めなくて。『N国に生まれた事は不幸だ』『N語話者である事は、国際社会において明らかに障害だ』と」
「かわいそうな人ね」
思わず口にすると朗も、少し吹き出す。
「小説自体『時間を浪費するわりに必要な知識は得られない』と、価値を認めていなかったんですが、『車輪の下』はお気に入りみたいで、だけど、父が語ってくる感想が、どうも僕にはしっくりこない。父はただ表面の、起きた事ばかりを理解しているんじゃないか。そんな感想を語って欲しくて、書かれた話じゃないんじゃないかって」
表紙に目を落としてまた少し、笑みを強める。
「可愛らしいですよね。本当に。こんな表紙になるなんて、僕は、D語で読んだ時には思ってもみなかった。だけど、不思議としっくりくる。父の感想なんかより、ずっと」
私の方に傾けて見せてくる。
「父が正しいとは限らない、と気付かせてくれた、僕にとっては記念すべき作品を、父が嫌っていたN語で、これから読んでみようかと」
可愛らしい、だけど小気味の良い抵抗に思えて、私も微笑んだ。
「良いじゃない」
「もしかしたらD語で読んだ時よりも、僕は、感動してしまうのかもしれない。だけど、それはこの小説が、『N語によって歪められた』わけじゃ、ないですよね?」
「ないわよ。だって、N語で暮らしているんだもの」
「ええ。ただ、それだけの事だ」
自分に言い聞かせるみたいな、朗の声を聞きながら、私は著者名とタイトルのメモを取った。
「ヘルマン・ヘッセね。読んでみようかしら」
「ええ。お勧めします。だけど、読む前からこんな事を言ってしまうのも何ですけど、僕は先生には『イヤな話だ』って、笑い飛ばしてもらいたい気がする」
「『先生』って、やめてちょうだい」
感想を決められた事よりもそっちの方が気になった。
「隣のおばちゃんなんだから。結局その場しのぎの間に合わせくらいしか、教え切れなかったし」
「ステファニーが、楽しそうでした。今も楽しそうに、話しかけてきます。それ以上に教えるべき事なんて、あります?」
「それはステファニーの興味とか、ご主人に関心があったからじゃない?」
「自信につなげないのはN国の悪いクセですよ」
一理あるような気もするけどN国は、ずっとこうやって暮らして来たんだし、自信に思っていないわけでもない。ただ表立っては誇らない方が、波風が立たないとされているだけで、
「お父様の、葬儀はきちんと済ませたの?」
話相手を一旦、油断させたいだけだったりもする。
私は笑顔のままだけど、朗は笑みを消した。本は膝の上から私に見えない側の隣に移して、顔は正面を向いて両手を組み合わせる。
「……何を、どこまで聞いているんです?」
「それを話しちゃったら訊問にならないじゃない」
「訊問ですか。なるほど」
頷いて、笑みは浮かべてきたけど口元だけ。
「僕は、何もしていませんよ。もちろん、ステファニーも、何も。だけど、二人ともただ見ていただけの父の頭が」
ステファニーとは違って胸の辺りで両手を広げたけど、見えていた位置の違いかもしれない。
「吹き飛んだ、なんて話を、誰が信じてくれると思います?」
吹き飛んだ、という表現は今初めて聞いた。爆発、とはちょっと違うみたい。
「それでもねぇ。現地の警察とか、お医者さんとか呼んで死因を、調べてもらうべきだったわ」
「その間ステファニーはどうすれば?」
まずはステファニーを持ち出して来た。
「そもそも酷い目に遭いかけて、怯えていたし、自分のせいだ自分が殺したんだって、取り乱していた。僕だってそんな場所からは、すぐに逃げ出してしまいたい」
「せめて彼女は何もしていないって、その場で分からせてあげる事は出来なかった?」
「僕だって完全な一人には、なりたくなかった」
なるべく顔には出さないようにしたけど、心の内で一つ、頷いていた。
イントロダクション
LESSON 1 | LESSON 2 | LESSON 3
LESSON OFF
LESSON 4 | LESSON 5 | LESSON 6
LESSON CLOSE(上・中・下)
ディテクション
何かしら心に残りましたらお願いします。頂いたサポートは切実に、私と配偶者の生活費の足しになります!
