
Luke’s Story 201-225『ふつうになりたい』Struggle to become an ordinary person
ついにその時が来ました。先生は、まるでルークの存在にずっと気付いていたかのように、こちらを振り返って言いました。
「ルーク、新しい学校はどう?」
(いまだ!)
怒りの言葉を投げつけようと先生の顔を見た瞬間、ルークはハっとして、攻撃するのをやめました。
そこにいたのは先生ではなく、ふつうのおばさんだったからです。
The time finally came. Ms. Hystery turned toward Luke as if she had been aware of his standing around her.
"Luke, How is your new school?"
(Now is the time!)
Luke looked straight at Ms.Hystery to throw angry words, but suddenly realized he couldn't.
That was because the person standing there was not a teacher but an ordinary woman.

(ここにいるのは先生じゃない。ちょっと歳を取った、ふつうのおばさんだ!)
ルークは心の中で叫びました。そして、瞬く間にいろんな考えが頭の中を駆け巡りました。
(この人は、学校という組織で仕事をしているふつうのおばさんなんだ。先生が暴力をふるったり高圧的な態度で生徒をしかることがふつうとされる価値観を守って、まじめに働いているだけなんだ!
この組織で、悪い生徒を差別するのはふつうのことじゃないのか?彼女みたいなまじめな人が、良い生徒を悪に染まらないようにアドバイスするのはふつうのことじゃないのか?)
(She's not a teacher. An ordinary woman who's a bit old!)
Luke shouted in his mind. And then, in the blink of an eye, many thoughts went through his mind.
(She's just an ordinary woman working in an organization called "school". She's just working diligently, respecting the values that make it normal for teachers to use violence and coercive attitudes to discipline their students!
Isn't it normal to discriminate against bad students in this organization? Isn't it normal for a serious person like her to advise good students not to be influenced by evil ones?)

(彼女は今、ボクを嬉しそうに見ている。不良からまじめになった生徒だと思いながら。
この人は、もう若くはない。ボクが何か言ったところで、今さら変われないだろう。
それに、彼女を尊敬して目標にしている子たちがいる。そのキラキラしたものをボクの一言で壊してしまっていいのか?
この人が誇りに思ってきたであろう教員生活を、ボクの一言でダメにしてしまっていいのか?彼女の残り少ない人生を失望で埋め尽くしていいのか?
このふつうのおばさんが、最後に「ああいい教員生活だった。」と言えるようにしてあげたほうがいいんじゃないか?
(She is now looking at me happily, believing I have gone from delinquent to diligent.
She's not young. I wonder if my words can change her now.
Besides, some of her old students look up to her and aim for her. Can I destroy that sparkling thing with just a few words?
Is it right to ruin her life as a teacher, which she would have been proud of, with my words? Is it OK if I fill the remaining years of her life with disappointment?
Wouldn't it be better to let this ordinary woman say at the end of her life, "Oh, that was a good teaching life."?

ルークは笑顔をつくり、先生に「楽しんでいます。」と一言だけ言いました。
(ボクのにらんだ顔が怖すぎたんだ。
ボクの不良のフリがうますぎたんだ。
ソラの教えてくれた話が本当だったとしても、ふつうのおばさんとは戦えない。)
言葉のナイフを胸の奥にしまいこみ、ルークはゆっくりと家に帰りました。
Luke smiled at Ms. Hystery and simply said, ”Enjoying."
(Perhaps she was too afraid of the look on my face, and I was too good at pretending to be a punk.
I can't fight an ordinary woman, even if what Sola said was true.)
Tucking the knife of words away in his mind, Luke slowly made his way home.

それ以降、もともと特別な人には見えなかった先生たちが、ますますふつうの人に見えるようになりました。
その気持ちが先生たちにも伝わるようで、にらむのはやめているのに、怖がられることがありました。
ひとりだけ、授業でみんなが問題を解いている時に、ルークの席まで話をしに来てくれる先生がいました。
そんな人はめったにいないので、ルークはうれしくなって先生を笑わせてあげました。
友だちのように話をしてくれる先生とだけ、仲良くなれたのです。
After that, teachers, who had never looked like special people to Luke, began to look more and more like ordinary ones.
They seemed to tell how he felt, and even though he had already stopped glaring at them, they would sometimes tell somebody that he was scary.
Only one teacher would come to his seat to chat with him when everyone was on a problem during a class.
Luke was so happy because he rarely had such a teacher, so he would make him laugh.
He became friends with those teachers who only talked to him as if they were friends.

「人と良い関係を築くコツは、ほめることです。その人のいいなと思ったところを素直に言葉で伝えましょう。人は、自分をほめてくれる人を、なかなか嫌いにはなりません。」
先生はそう教えてくれましたが、ルークは「学校でひとりぼっちにならないために人をほめる」というわざとらしいことをする気にはなれませんでした。
粗探しが得意なルークにとっては、失言で人を怒らせないように注意するほうが、よほど大切なことでした。
"The key to building a good relationship with someone is to praise them. Be honest in your words about what you like about that person. It's hard for them to dislike those who praise them."
The teacher said so, but Luke was not inclined to do the deliberate thing of praising people to avoid being left alone at school.
It was even more important for him, who was good at finding faults, to be careful not to say anything that gets on people's nerves.

そして、ほめた時にうっかりいい人だと思われるのは嫌なので、人をほめる時には欠点にも触れるようにしました。だから、クラスメートには「ほめられてるのか、けなされているのかよく分からない。」と時々言われました。
ある日、小さなことで、ふと友達をほめた時に、「うれしい。」と言われました。
「え!?うれしいの?」
「うん。きみは本当のことを言うから、きみにほめられるとうれしい。」
(ボクにほめられるのがうれしいだって!?ボクのこんなほめ言葉で?)
ルークは心の中で口をあんぐりと開けました。
Not wanting to be seen as a good person by praising people, Luke started giving praise to them along with their flaws. So his classmates sometimes told him, "I'm not sure if you're praising or belittling me."
One day, when Luke praised his friend for a small thing, the friend said, "I'm happy. "
"What? You are happy?" Luke asked.
"Yes. You tell the truth, so I am happy when you compliment me."
(You're happy that I praise you? With a compliment like this from me?)
Luke's mouth gaped open in his mind.

(彼が今よろこんでいるのはボクがいい人だからじゃない。ボクの分析が的確だと思っているからなんだ。
他の誰でもない、ボクにほめられて、うれしいと言ってくれているんだ。
ボクなんだ。。)
そう考えると、体がだんだん熱くなってきました。
(He's happy about the praise, not because he thinks I'm a nice guy, but because he thinks my analysis is accurate.
He says he's happy to be praised by me, nobody else. It's me...)
Luke's body started to feel hotter and hotter.

ボクの言葉で喜ぶ人がいるならと、ルークは時々人をほめるようになりました。
でもそれは、思ったより簡単なことではありませんでした。
人が沢山いると、ほめ言葉が矛盾するからです。
きれい好きな子をほめている時に、見た目を気にしない子が隣を歩いていた時は、冷や汗が出ました。
(ちがうんだ!正確に言うと、こっちのキミはいつも清潔感があふれていていいと思うし、そこを歩いているキミも、それはそれで味があっていいと思うんだ。その方が楽だし、実際ボクもそういうタイプなんだ!
だから、こちらのキミは、身だしなみを整えるようなめんどうなことを毎日きっちり出来るのはすごいことだと思うんだ!)
人を同じようにほめるのはとても難しく、ほめることも疲れるなあと思いました。
(If they feel happy with my words...)
Luke began to praise others from time to time, but it was not as easy as it seemed.
That was because where there are not a few people around, compliments can be contradictory.
When Luke saw a boy who didn't care about his appearance passing by while complimenting another boy who liked to be clean, he broke out in a cold sweat and thought in his mind,
(No, no, no! To be precise, I think you standing next to me always look clean and tidy! And you, walking there, I like your cozy fashion too. I think I'm actually like you!
And you, standing next to me! So I think it's great that you always keep yourself well-groomed. I can never do that!)
It was very difficult to praise people precisely and in the same way, so Luke was often worried.

そんなことより、ルークにとってはB.Bの特別な家来になるほうが、よほど重要なことでした。
自分が好きな人達から評価されるのであれば、他の人たちのことは気にならなかったからです。
その評価を受けるための大前提が、ふつうの人のように振舞うことでした。
(B.B.は、いつボクを特別な家来に任命してくれるのかな。)いつも、そう思っていました。「願えばかなう。」そう信じていました。
What was much more important to Luke was to become B.B.'s special retainer.
He didn't care about the rest of the world as long as he received positive evaluations from those he loved.
The prerequisite for receiving such recognition was to act like an ordinary person.
(When will B.B. appoint me to be his special retainer?) Luke always wondered, but he believed what he wished for would come true.

「君の鉛筆、すごくきれいに削れているね。どんな鉛筆削りを使っているの?」
ある日、筆箱を整理していたら、B.B.に話しかけられました。
「ふつうの鉛筆削りだけど?」ルークがそう答えると、B.B.が言いました。
「じゃあ君の削り方がうまいんだ。」
(うわあ、かしこいB.B.にほめられた!きょう、鉛筆を削ってきてよかった!)
ルークは心の中で叫びました。
そして、なんとも思っていないそぶりで「君の鉛筆も削ってあげるよ。」と言いました。
帰り道、こっそり文房具屋さんで新しいえんぴつ削りを買いました。
そして、家じゅうのえんぴつをかき集め、夜遅くまで黙々と、えんぴつの先をとがらせる方法を研究しました。
"What type of pencil sharpener do you use?"
One day, B.B. asked Luke while he was organizing his pencil case.
"Just a regular pencil sharpener," Luke said.
"Then you are very good at sharpening pencils!"
(Wow, smart B.B. is praising me!
I'm glad I sharpened my pencils today!)
Luke exclaimed in his mind.
And with an unconcerned look, he said, "I'll sharpen your pencils too."
On the way home, Luke secretly went to a stationery store and bought a new pencil sharpener.
Gathering all the pencils in the house, he worked on the way to sharpen a pencil until late at night.

夜がふけるにつれて、ルークの心もだんだん暗くなってきました。
(いままでボクは、ろくな目にあってないけど大丈夫かな。。えんぴつを削っていたら、「B.B.の子分になった。」って、からかわれたりしないかな。。。
ボクがなりたいのはただの子分じゃなくて、とくべつな家来なんだ。。
ボクは目立つから、いつも誰かに見られているし、敵がいる。それに、なんだってすぐにバレてしまう。
うっかり気になる女の子の話をしたら、みんなにバラされたこともあったな。。
鉛筆を削って大丈夫かな。B.B.との関係が悪くならないかな。
ボクは本当に、ろくな目にあわないんだ。)
As the night wore on, Luke's mind became darker and darker.
(I wonder if my classmates will make fun of me for sharpening B.B.'s pencil, saying I have become his subordinate.
I don't wanna be one of his subordinates. I wanna be his special retainer.
I'm always being watched and have enemies because I stand out. No matter what I do, someone finds out.
Come to think of it, I once accidentally told someone about a girl I was interested in, and they told everyone about it.
I wonder if my relationship with B.B. will deteriorate by sharpening his pencil.
I'm always getting into trouble.)

次の日、ルークは本を読むふりをしながら、B.B.の鉛筆を削っていました。
真剣にしていることをB.B.に気づかれないように、そして、削り過ぎないように気を付けながら、あっと言う間にえんぴつをピンピンにしました。
きれいになったえんぴつをB.B.に渡しながら「また時々削ってあげるよ。」と言いました。
こうすることで、B.B.にすら家来になっていることを気づかれることはないと思ったからです。
誰にも気づかれないようにえんぴつを削って戻すたびに、ドキドキしました。
Luke was sharpening B.B.'s pencils while pretending to read a book the next day.
While being careful not to make them too short, he sharpened them at full speed so that B.B. would not notice how serious he was being.
Handing the pencils to B.B., he said, "I'll sharpen them again from time to time."
This way, Luke thought, even B.B. would not notice that he had become his retainer.
Whenever Luke sharpened B.B.'s pencils and put them back without anyone noticing, he felt like a thief and was very nervous.

かしこくてキチンとしているB.B.の机には、きれいに削ったえんぴつが良く似合いました。
それを遠くから眺めることが、ルークの楽しみになりました。
(きれいにするのは壺じゃなくて、えんぴつだったけど、ボクはついに特別な役割をうけたまわったのだ!)
The beautifully sharpened pencils looked great on the desk of B.B., the smart and neat boy.
Luke enjoyed looking at them from afar.
(It was the pencil, not the pot. But B.B. finally gave me a special role to play!)

(吾輩は、B.B.のえんぴつ削り係である。
だれも知らない。
B.B.の机にあるその黄色いえんぴつも、あの赤いえんぴつも、
削る使命を負っているのは吾輩である。
願いは叶うのだ。
吾輩はやっぱり、念力が使えるのだ。)
そしてルークは一人の家来として、B.B.の取り巻きの前ではどんな人に対しても、「ふつうのいいやつ」を演じるようになりました。
(I am the sharpener of B.B.'s pencils. No one knows this.
I am the one who is on a mission to sharpen cleanly that yellow pencil and that red pencil on B.B.'s desk.
My wish has come true.
I am the one who has superpowers, after all.)
And so Luke became B.B.'s loyal retainer, playing the "ordinary nice guy" to whoever B.B.'s followers were.

(なんていい気分なんだ!)
ルークは浮かれて歩いていました。いつもの街が、キラキラして見えました。
「すみません。」
急にとなりから声が聞こえました。
振り向くと、知らない男の人が立っていました。
「雑誌のアンケートをしているんですが、協力してもらえませんか?」
(What a good feeling!)
Luke was walking buoyantly through a familiar town, which was glittering.
"Excuse me."
A voice suddenly called out from next to him.
Luke turned around and saw a man he didn't know standing there.
"I'm doing a survey for a magazine. Could you help us?"

それは、男の子なら誰でも知っているファッション雑誌でした。
ルークはちょっといい気分になって、「もちろんです。」と言いました。
でも、ただのアンケートのはずなのに、なぜだかそのまま少し離れた建物の中まで連れていかれました。
「しまった。建物の中になんか入りたくないよ。すぐに断るべきだった。。」
不安な気持ちで出口を確認しましたが、間も無くアンケートが始まりました。
それは、自分の「体型」に関する簡単な質問でした。
てきぱきと正直に答えていたら、質問はあっと言う間に終わりました。
(え?もう終わり?)
そう思っていると、その男の人は、続けて言いました。
It was a fashion magazine every boy knew.
Luke was a little pleased and said, "Sure."
But for some reason, even though it was supposed to be just a little survey, the man took Luke straight into a building some distance away.
(Oh shoot. I don't want to go inside the building. I should have said "No." right away.)
Luke checked how to get out of the building with a sense of uneasiness, but the survey soon started.
It was a simple questionnaire about "Body Shape."
Luke answered quickly and honestly, and the man finished questioning in no time.
(What? Already done?)
The man continued to speak.

「実は、あなたの気になる体の部分を短期間でスリムに出来る機械があります。
いくつか体験プランがありますが、12回払いにすれば、毎月ほんの少しの支払いで済みますよ。」
(え?
この人、何を言ってるんだ?
正直に答えたのに、それが目的?
そもそも本当に雑誌のアンケート?
料金が高すぎて、ボクには払えないよ。。)
断る言葉を考えながら、その男の人の顔を見ていたら、光るものがルークの目に入ってきました。
(あれ、この人、汗をかいてる。)
"Actually, we have machines that can slim down the areas of your body you are concerned about within a short period.
Several plans are available, but if you make 12 payments, you'll only have to pay a little each month."
(Hey, what is this guy talking about?
I answered honestly, and that's what you wanted?
Was it a magazine survey in the first place?
The fee is too high for me to pay.)
Luke was looking at the man's face, thinking of words to say no. Then, something shiny caught his eye.
(Hey, he's sweating.)

(うわっ! すごい汗!)
でも、この人はなぜ、こんなに汗をかいているんだろう。。説明をしているだけなのに。。
若く見えるけど、もしかしたら家族がいて、子供にご飯を食べさせるために働いているのかな。。。
いや、妹の学費を稼ぐために必死なんだ。。。
説明にうんうんとうなずきながら、ルークはいつのまにかお小遣いの計算を始めていました。
(なんとかなるさ。)
ルークは結局、分割払いでそのプログラムを申し込み、家に帰りました。
(Wow! He's sweating like crazy!
But why is he sweating so much while just explaining?...
He looks young, but maybe he has a family and is working to feed his children...
No, he is struggling to earn money for his sister's tuition...)
While watching him sweat, Luke started calculating his allowance before he knew it.
(I'll manage it somehow.)
He ended up signing up for the slim-down program with installment payments and went home.

ルークは持っているお金をかき集め、頭の中で計算をしていました。
(毎月のおこづかいを支払いに回しても、これではやっぱり足りない。
アルバイトをしなくては。。
でも、人と話すのは苦手だから、困ったな。。。)
ちゃんと仕事をするのは初めてのことなので、いろいろ悩みましたが、誰とも話さずに済みそうな花農家でアルバイトをしようと思いました。
Luke gathered all the money and did the math in his head.
(Even if I put my monthly allowance into the payments, this would not be enough.
I must get a part-time job. But I'm not good at talking to people...)
Luke had a lot of worries because it was his first time becoming a part-time worker, but he finally decided to take a job at a flower farm, where he wouldn't have to talk to people.

(もしアルバイトがうまくいかなかったら、家の庭掃除を手伝ってお母さんからおこづかいをもらおう。)
緊張しつつも、ルークはそんなのんきなことを考えながら、アルバイトの面接に行きました。
花農場のおじさんは、予想よりはるかに良い人でした。
「好きな時間に来ていいよ。」と言ってくれました。
(If the part-time job doesn't go well, I'll help clean the yard at home and get some extra money from my mom.)
Although nervous, Luke went to the interview for the part-time job with such optimistic thoughts.
The the owner of the flower farm was much nicer than he expected.
"You can come any time you want," he said.

「わからないことは何でもポピーちゃんに聞いてね。おーいポピーちゃーん!」
おじさんが叫ぶと、お花畑から女の子が顔を出しました。
(うわー。。。)
美術館の絵で見たような、まばゆいばかりの女の子がルークのほうに歩いてきました。
「はじめまして。」
ルークは頭がぼーっとして、アルバイトに来たことを忘れそうになりました。
やさしいおじさんとかわいい女の子ときれいなお花に囲まれて、アルバイトは夢の国で遊ぶ時間になりました。
"Ask Poppy anything you don't understand. Hey, Poppy!" said the flower farm owner.
A girl appeared from the flower garden.
(Wow.)
A dazzlingly lovely girl Luke had seen in a portrait in a museum somewhere walked toward him.
"Nice to meet you."
Luke felt dizzy. He almost forgot that he had come to work.
Surrounded by a kind owner, a lovely girl, and beautiful flowers, his job became a time to play in dreamland.
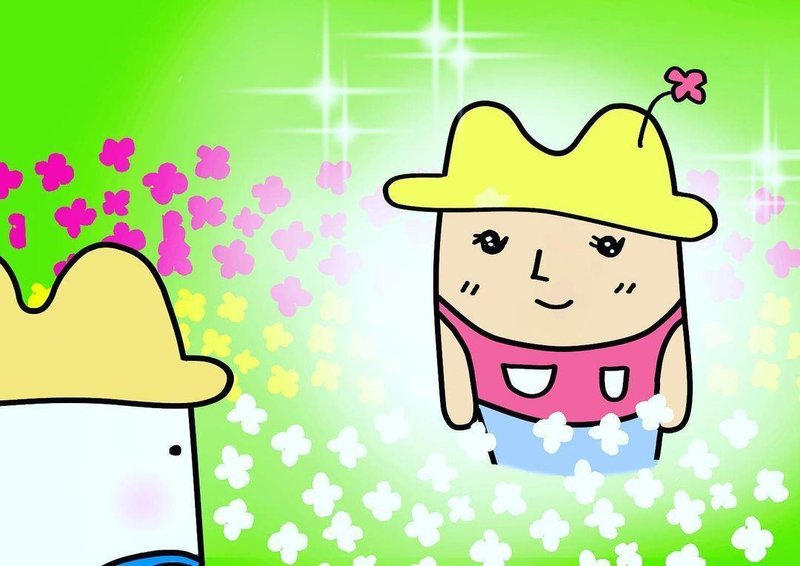
(なんだろう、楽しくてしかたない!
学校では特別な家来になれるし、アルバイトでも夢の国に行けるなんて!)
そんな生活が幸せすぎて、家に帰っても思わず顔がほころんでしまいました。
(本当に?夢を見てるのかな?)
ルークは生まれて初めて自分のほっぺたをつねりました。
誰もいない空の上から大声でさけびました。
「ヤッホーーーー!」
たくさんの苦しかった思い出が、少しずつ消えていきました。
(What's going on? I'm having so much fun!
I can't believe I have become B.B.'s special retainer at school and also a part-timer in Dreamland!)
Luke was so happy with such a life that he couldn't help but smile when he got home.
(I'm not dreaming, am I?)
Luke pinched his cheek for the first time in his life.
He shouted from the empty sky, "Yoo-hooooooo!"
He was beggining to forget all his hardships.

ポピーちゃんは、不思議なところがある女の子でした。
「ルーク、あなたの鼻はどこにあるの?一体その鼻は、つまむことができるの?」
普通なら、「なんて失礼な。」と怒るところですが、ポピーちゃんはニコニコしながら続けて言いました。
「あなたの顔を、ここに置いていってちょうだい。」
(この子はボクの見た目をなんとも思わないどころか、逆に気に入ってるんだ。。なんという感性の持ち主だろう。)
初めは気を使っているのかなと思いましたが、何度も同じ言葉を繰り返すので、ルークはポピーちゃんが大好きになりました。
Poppy was a girl who sometimes said something unique.
"Where is your nose, Luke? How on earth can you pinch it?"
Luke would normally have been angry at such a person for being so rude, but Poppy was smiling.
"Please leave your face here," she continued.
(Not only does she not think anything of my appearance, but on the contraly, she likes it very much. What a sensibility!)
At first, Luke thought Poppy was just being considerate, but as she repeated the words over and over again, Luke grew fond of her.

「この喜びを表現したい」そんな気持ちでいっぱいになりました。
人けの少ない道で自転車をこぎながら、少し大きな声で、同じ歌を何度も歌いました。
Luke was dying to express this joy.
Pedaling his bicycle on a deserted street, he sang the same song over and over in a slightly louder voice.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
