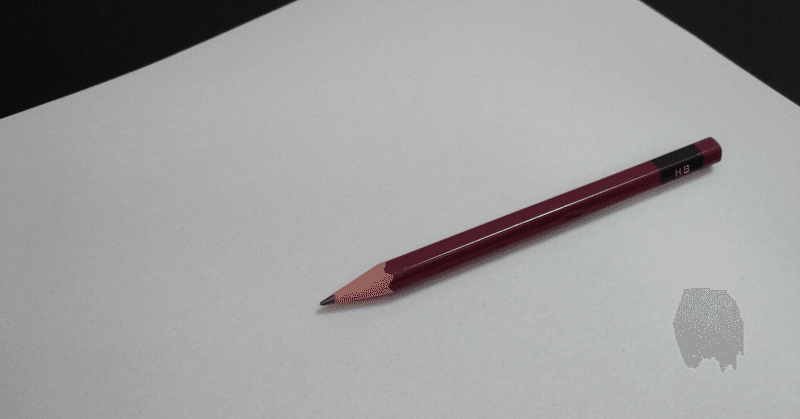
犯したいほど憎い 1.5
自分が小説を書かなくても生きていける人間なのだと周野才斗が受け入れるまで、そう長い時間は要らなかった。
表現をしないことに我慢ならない人種が世の中にはいるという物語に憧れていた。戦火の中、数秒後にその原稿が焼かれる運命だとしても文を綴る。読んでくれる人はいなくても、部屋に原稿を積み上げる。作家はそういう生き物なのだとまだ心の何処かで信じてはいて、それ故に才斗は自身は作家ではなかったのだと認めていた。
これはこれで前向きな態度であるつもりだった。
周野才斗は作家ではない。サラリーマンだ。それは何も悪いことではないだろう。優劣なんてあるわけもない。
大体、そんなことを言ったら罰が当たる。就職できたのは志望通りの業界、業種で、友人や家族には内定をもらった時には「流石!」と言われた。入社後も上手くやれている自信はある。お世辞抜きの賞賛を浴びているなと実感できる場面も多く、それを、成果と言えるほどの成果のあげようもない若手のうちの評価なんてと謙遜できる余裕さえあった。
それでも、たとえば職場で「周野くんの文章、読みやすいよね」と資料を褒められる時、家に帰って長い夜を持て余す時、胸のどこかが疼く。そうしてから指ではなく、胸か、と苦笑をする。
「まだ、書いてないんですか?」
間野賢也にそう聞かれたのは、学園祭の打ち上げにOBとして参加した時だった。大学近くの安居酒屋の二階、貸し切った座敷席の端っこに二人だけがいる空隙のような瞬間があって、そこを突くように尋ねてきたのだ。
就職を意識してだろう、間野は髪を切っていて、眼鏡の向こうの瞳の輝きは、才斗を射抜くように真っ直ぐだった。「もう書かないんですか」と聞くような無遠慮さも、心に抱えているものとは別の話をしてお茶を濁す不誠実さも、どちらも持たない間野の好ましさに才斗は素直に応じることにした。
「書いてないよ」
「そう、ですか」
あの日、才斗が言い放ってしまったことを知っている後輩はグラスへ視線を落とした。
「間野は偉いね。四年になっても、ちゃんと書いて」
才斗は、傍らに置かれた《未来埠頭》の表紙を叩いた。
間野は音を出さずに数瞬、唇を震わせてから。
「書きたかったんで」
才斗は「偉いね」と微笑した。心の底からの一言だった。
今も、本屋に足を運ぶことはある。
数年前のように足繁く通うことも、そんなにあるはずもない変化を捜して棚差しの背表紙を眺めることはなくなった。そんな自分を自覚することが嫌で、あえて例の名前を捜すことをすることも多い。カサブタを剥がすことを楽しむような、そんな気分だ。彼は順調に新刊を出している。純文学というジャンルを思えば異例と言っても良い。頭の中にあるものを外に出さなければ仕方ない人種であるということなのだろう。この世界を自分の目で見て、そうして、書くべきものを見つけて、切り取る。それに喜びを覚える小説家になるべくして生まれた人間なのだ。
そんなことは決してない、とは、勿論、才斗は承知していた。
抜け殻のようだと自らのことを考える時、その、「ようだ」という言葉自体に嫌気がさす。何かを喩えるような言葉遣いの時点で、そこに普通に生きる以上の何かへ手を伸ばそうとしているような雰囲気が出る。
そのくせ、そうした思い上がりを振り払おうと視線を動かした時に飛び込んでくる世界は、息を呑むような迫力があり、表面に浮かんでいるもの以上の何かを孕んでいるように見えて仕方がないのだ。昼間の上司とのやり取りを思い出し朝だというのに位置のずれたネクタイピンを相手の気持ちの隠喩と結びつける一文を作ってしまう。久々にLINEをする友人の息遣いを画面の向こうから感じ、返事を待つ数秒ににやけてしまう。
これを何かにできるかもしれない、とは才斗も考える。
それでも手を動かしはしない。だって自分は、書かなくても生きていける人間だから。ほら、明日も仕事だ。準備をして、眠ろうじゃないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
