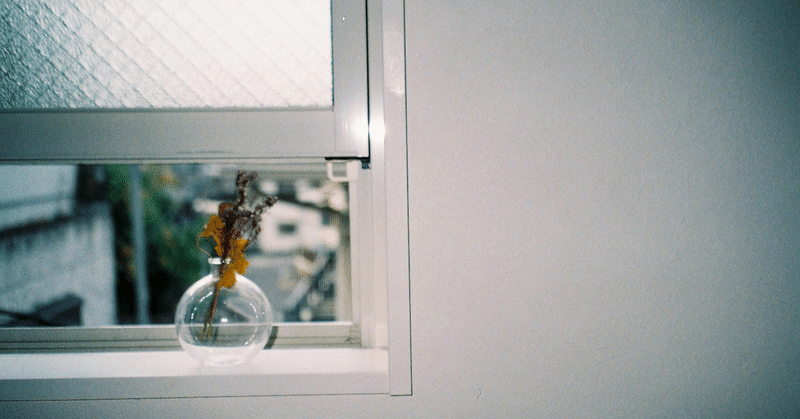
たくましさがコンプレックスだった私は、たくましさを対価に変える道を選んだ
「ほんと、昔からたくましいよなあ。なんでそんなにたくましいの?でも、そこが○○ちゃんらしいというか、中1のときからずっと変わってないよなあ」。
そう伝えてくる彼女の目はとてもキラキラしていた。私に「憧れる」という言葉をかけてくれる数少ない友だちは、10代の頃から私のたくましさをこれでもかというぐらい褒めてくれる。
そのまっすぐな言葉に少しの照れと、感謝の「ありがとう」が言えたとき、私はほんの少しだけ自分のことを受け入れてあげられたような気がした。
◆◆
「すごいね。ほんと、たくましい。なんでも任せられる」「今日出勤してくれてよかった~おかげでお店がまわる!」「もう一人で全部の業務やった方が早いんじゃない?」。
何度も何度も言われてきた言葉たちは、自分を認めてもらえているような気がして素直に嬉しい気持ちで受け取ることができる。でも、なぜか言われるたびに心がギューッと締め付けられるような気持ちにもなった。
あれはいつだっただろうか。
今から5年以上前、飲食店で働いていたときのこと。お店の開店準備をする時間になると、店長はいつもアルバイトの子を連れて買い出しに出ていた。当日出勤するアルバイトは決まって二人だったので、選ばれるのは私か誰かだけど、そこで買い出しに連れて行かれるのは必ず決まって私以外の子だった。
店長は良い人だったと思う。よく話しかけてくれたし、お店のことも良く見ていて、それぞれの特性にあったことを任せてくれた。関わっているなかで嫌なことは何一つとしてなかった。
でも、ここで働いていたことを思い出すたび、頭に浮かんでくるのは、朝の買い出しに連れて行ってもらえず、ただお店にぽつんと一人残り、掃除をして、お皿の準備をして、予約席を確認して、ひとりで重たい机をくっつけて、たまに調理場にいる人と何気ない話をした時間を過ごしていた自分の姿だった。
この時間が嫌な時間だったかと言われればそうではない、むしろ一人で黙々と作業ができる時間は好きだったし、自分が頭で描いたように作業が進められるのは丁寧にパズルのピースを埋めていくような感覚で、とても楽しかった。
そんなあるとき、開店前ギリギリになって帰ってきた店長と他のアルバイトの子を見て、なぜだか涙が止まらなくなったことがある。もちろん、みんなの前じゃなくて、トイレでこっそり、いや、ボロボロ泣いた。
そのときの私が思ったのは、「私だけ連れて行ってもらえないなんて!」とか「私も今度連れて行ってほしい」とかそんな嫉妬の感情じゃなくて、「私って何してるんだろう」みたいな無の感情で、ぽっかり心に穴が開いてしまったみたいだった。
開店前に泣いたので、「開店したらいつも通り業務をするんだ!」と意気込みながらホールに戻ると、店長が話しかけてくれた。
「ごめんな。○○ちゃんにはいつも助けてもらってるし、○○ちゃんにしか頼めないことが多いから。ほんと、いつもありがとうね」。
今になっても忘れられない言葉は、当時の私にボディブローみたいに効いて、危うくそのまま膝から崩れ落ちそうにもなった。
これじゃあ、まるで私がただ買い物に行けないことに拗ねたみたいじゃないか…と恥ずかしくなって、突然溢れた涙も、まだまだ弱い自分のことも恨んだ日、私はどうして涙を流したんだろうと不思議に思った。
次の出勤時、気を使ってくれた店長が私に声をかけてくれて、一緒に買い出しに行くことになった。車の助手席に座り、ただスーパーで買い物をする時間は、正直あまり楽しいものではなかった。
お店の準備はできているんだろうか。今日は結構予約があったけど、大丈夫なんだろうか。そんな不安を感じながらお店に戻ったとき、私の目に飛び込んできたのは、完璧に準備が仕上がった店内だった。
「なんだ、私がいなくても、当たり前に準備はできるんだ」。
なんとも当たり前のことかもしれないけど、当時の私には「自分がいなくても物事が完璧に進んでいく現実」が何よりもつらかった。
もちろん、「私がいなくちゃこのお店はダメだ」なんてことは一度も思ったことはなかったけど、どこかでその片鱗を期待をしていた自分がいることに気付いたとき、自分の惨めさに嫌気がさした。
私はずっと「たくましさ」にすがりついていただけで、本当の自分は別にたくましくなんてなくて、なんとなくただ生きていたらそう言われるだけの言葉に「そうなのかもしれない」と調子に乗って流されていただけだった。
自分のことをほんの少しでも特別な存在だと思ってしまっていた自分に気付き、そしてその特別が本物じゃないと明確に分かったとき、私は自分の価値なんてものはこの世にはなくて、なら、何が私の価値なんだろうと思うようにもなった。
あれからもう5年以上経つけど、今も「たくましさの呪い」が自分の中から消えることはなく、私はずっとたくましい自分でいることに依存し続けている。
でも、それが自分の存在価値なのだ。それしか認めることしかできないなら、いっそのこと、「たくましい自分を愛して、それをお金という目に見える価値に変えよう」と思ったのがここ3年ぐらいの話。
ライターの仕事だけじゃなく、得意だと思っていた「サポート」を仕事に加えるようになった。やりはじめてみて思ったのは、サポートという仕事は特別な仕事ではないかもしれないけど、知識も経験も必要で、極めれば「私だからできる」に変えられるかもしれない可能性があること。
その可能性を感じたとき、心のどこかで自分のことを特別だと思わないとやっていけなかったあのときの自分に手を差し伸べて「道はある」と声をかけてあげたくなった。
そんなことを思い返していると、ずっと思い出せなかった記憶の蓋が突然パカッと開いて、これまでの思い出が出てくるようになった。
働いていたお店の屋根を大工さんと一緒に登って見た景色があまりにも綺麗だったこと、夜勤中にお店に届いた大きなテーブルをあまり喋ったことがない他店のヘルプの人と組み立てたら、その人が異様に面白い人だったこと。
どの記憶にも共通するのが「○○さん、お願いできる?」という言葉。雑用じゃなくて、信頼されてるから頼んでもらえた出来事を私はちゃんと記憶の中に「良かったこと」として閉まっていた。
正直今も、このたくましさに悩まされることはあるし、それがダイレクトに自分の孤独に繋がっているとも思う。
昔から私は誰かにSOSを出すことが苦手だから、自分で全てを抱え込んで、最終的には爆発して、立てなくなることも日常茶飯事。それでも、復活すれば弱さなんてものは一瞬にして消え去り、また「たくましい私」として歩み始める。
世間的な「女性らしさ」や「守りたい」といったものから離れたところに生きている人間であることもよく分かってる。
だからわたしは、「せめて、このたくましさを対価に変えるのだ」と思いながらこれからも生きていくんだと思う。
でも、こうやって自分のたくましさを対価に変える方法を取り入れてから少し変わったことがある。それは、少しだけ誰かを頼ることができるようになったこと。
たくましさは対価で、私にとっては商売道具でもある。それを失わない選択をするために、友だちに「これが今はつらい」と話せるようになった。これは弱さを見せてるんじゃなくて、あくまでも「たくましさ」を仕事にし続けるための、仕事の相談。そのぐらいの気持ちでいられると少しだけ楽になれる。
わたしはずっと抱えてきた「たくましい」というコンプレックスを、対価に変えることで少しずつだけど、自分の「たくましさ」を愛していきたい。
大切な時間をいただきありがとうございます◎ いただいたサポートで、サスケにチュールを買います。
