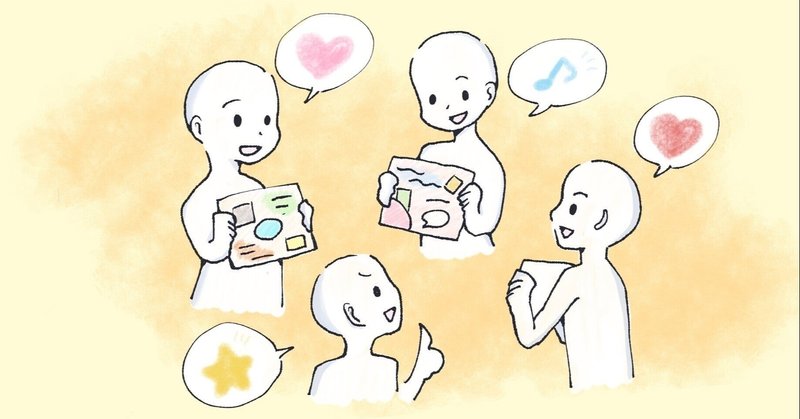
中学校社会科教員が育っている。若い先生方に期待がふくらむ。
先日、中学校社会科の自主研究会に参加しました。土曜日の夜の開催に、私も含め13名の参加がありました。そして、その研究会を通して、「中学校社会科教育の将来は明るい」と強く感じました。
1 今回の参加者
本年度はコロナ禍で予定通り実施できませんでしたが、通常は年4回実施し、今回は年度内の最終回となります。参加者は冒頭のとおり13名で、「部活動の練習試合に行ってきた」と言いながら参加している先生もいます。
参加者の内8名は、採用10年目までの若い先生方です。さらに、その中には教員養成系大学で当自治体の社会科教員をめざしている学生(3年)の参加もありました。
また、今回はじめて参加するという先生は、私が以前勤めていた郡部の学校(80km超の遠方)からでした。本研究会の活動が掲載された新聞記事を読んで連絡をとったとのことでした。学びへの意欲が行動を起こし参加が実現したということです。すばらしいです。
2 今回の内容
実践発表が2つ。
その①は、採用4年目の先生の地理的分野(オセアニア州)でした。
単元の学習課題は「オセアニア州は、今後、どのような国や地域との結びつきを深めていくか」というものでした。まず予想し、その予想の根拠となるデータを調べ理由付けを行う。続いて、グループ等で交流し、他者の考えを参考にしながら、自分の考えをより確かなものにしていくという展開です。
私は、「課題を主体的に追究しようとする」(単元目標の一部)なら、仕掛けや支援等を考慮した上で、生徒発信の課題にする必要があるのではないかと思いました。
そして、単元の学習課題を解決するために、教科書をどのように活用するか、言いかえると、必ずしも掲載順に扱う必要はないだろうということです。さらに言えば、生徒個々の課題解決のプロセス(生徒の学習計画)によれば、学級全体で同じように扱う必要はないだろうということです。
また、発表で、学習課題の答えの根拠が1つなら「おおむね満足」、2つ以上なら「十分満足」とありました。私は、「十分満足」は「おおむね満足」の中で質的な高まりや深まりがあるものと理解しています。根拠の数が多いことが質的な高まりや深まりになるのかということを、参加の先生方に授業実践を通して研究してほしいとお願いしました。
実践発表②は、教員養成系大学大学院生の研究レポートでした。
残念ながら、この大学院生は出身自治体での教員採用が決まって転居したため(予定通り2月実施なら参加可能だった)、本研究会の幹事が代理発表しました。「向上主義学力論」という私は聞いたこともないことを研究されていました。本人がいらっしゃればいろいろとお尋ねもできたのに、残念でした。
それにしても、どのようなつながりで、大学院生の方が発表することになったのかは知りませんが、本研究会の広がりを感じます。
最後に情報交換を行いました。
その内容は、振り返りの方法やタブレット端末の活用、学習評価やテスト問題の作成などについてです。
振り返りについては、書かせてそれにコメントを記入するなど、ていねいに行うとかなりの負担になることから、どのようなやり方が望ましいのか?
タブレット端末については、すでに一人一台の配置を終えている学校から活用事例の紹介があり、休憩時間等の使い方に対する懸念などが出されました。
学習評価にについては、主体的に学習に取り組む態度をどのように見とればよいのか。また、思考・判断・表現を問うテスト問題は、どのように作成すればよいのかなどの悩み(疑問)が出されました。
これらの話題に、授業をすることのない者(私)の無責任な発言を許していただくなら、次のような思いがあります。
振り返りについては、先生方の負担になるようなことはしなくてもよいと思っています。ただし、単元の終わりには、自身の考えの変容を振り返らせたり、その変容にかかわった他者(仲間)の存在を自覚させたりすることが重要だと考えています。負担軽減ということでは、タブレット端末のアンケート機能等を活用することではないかと思います。
休憩時間のタブレット端末の活用については、他者を傷つける道具として使うことは許されませんが、自由に使わせてよいのではないかと思います。私自身、タブレット端末で何かを調べているとき、気が付けば別のことを見ていることがあります。それが人間だと思いますし、その余計なところで新たな発見があるかもしれないと思います。何より、休憩時間に課題解決に向かおうとする生徒の意欲を削ぐことはすべきではないと思います。
主体的に学習に取り組む態度の評価については、「粘り強い取組」の側面と「自らの学習を調整」の側面のイメージが『学習評価の在り方ハンドブック』(令和元年6月 国立教育政策研究所)に記されています。ということは、学習活動の中に、生徒が「粘り強さ」を発揮したり「調整」したりする場面をつくっておく必要があると考えています。そのためには、単元の学習計画を綿密に立てる必要があると思います。学習評価を充実させることは、まず授業改善に取り組むことからだと思います。
テスト問題の作成については、教科書等の持ち込みに耐えうる問題というのが私のイメージです。
いずれにしても、試行錯誤を繰り返しながら、よりよいものを追究してほしいと思います。
3 この自主研究会について
私は、曖昧な記憶ですが、平成5年から参加しています。同年代の先生が発表する内容は専門的すぎて、教材研究等を十分にしてこなかった私にはとても難しく理解しがたいものでした。ただ、当時、郡部の学校に勤務していた私は、都道府県庁所在地で開催されるこの研究会に行くのが楽しみでした。
その後、私は学校を離れ社会教育に携わっていたこともあり、再び本研究会に参加するのは10数年後のことになります。ですから、現在まで約30年続いていることになります。長いブランクを経て再び参加できたのは、実践を通して人材を育てようとする先輩方の熱い思いとそれに実践で応えてきた各世代の先生方の努力のおかげと感謝したいと思います。
今日的な課題について、若い先生方と語り合えることを本当にうれしく思います。若い先生方の今後の活躍に期待するとともに、私も学び続けたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
