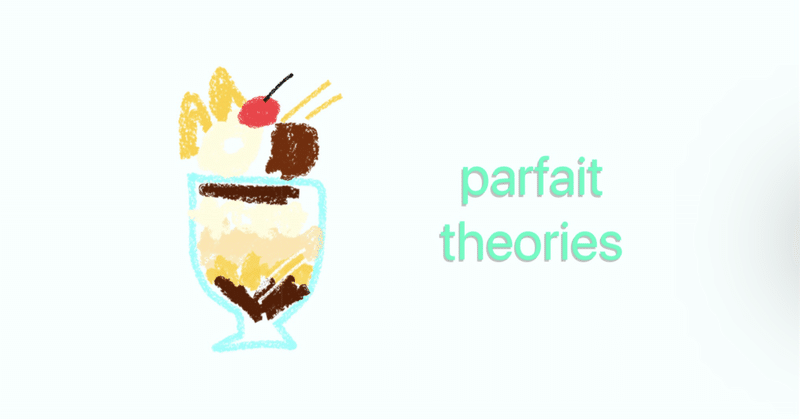
趣味が合う≠(エッセイ)
17歳の私は、趣味が合えば、同じものが好きな人でさえあれば、気が合うと思っていた。
いまは、そうではない。
もちろん、趣味も気も合う人というのはいる。だからこそ、それが十分条件ではないかと錯覚してしまう危なさがある。
たとえば実家の本棚に並んでいる児童書や親の本、買い集めた漫画などが同じ人は、家庭環境や思春期の大事なものが似ているわけで、思考材料も似通っていてゆえに、大事にしている道徳倫理などが合うことも多い。
中高時代までは、趣味が合うほど気が合うという相関関係が例外なく実証されており、やりたい曲ベースでバンドを組めば楽しい、本の貸し借りをした仲であればお弁当が盛り上がる――それは、圧倒的な真理だった。
文学部に進学することが決まった時、それは期待に胸を膨らませたものだ。文庫本をポケットに入れているような素敵な学友たちと昼夜談義を交わし深い仲になることを夢見ていた。
しかし、現実は甘くなかった。私の卒業した私立の中高一貫校というのはまずもってそもそも倫理道徳がほぼミリ単位でしかズレがないという前提があるなかで、ただ趣味が合う人をさらに絞ると、めっちゃ楽しい!というだけだった。
私は少しずつ、自説に違和感を覚え始めた。
同じ映画がすごく好きで沢山語れたひとから、飲み会で信じられない様な貞操観念を聞かされるなんてことが多々あったり。一歩先をゆくヴィレバンの様に漫画のセンスが良いひとでも借りたお金を全然返さなかったり。私にとってこれらはかなりショックだった(無論、向こうからしても合わないなあと思われていたのだろう)。
もしかすると、どんなものを美しいと感じ、どんなコンテンツを摂取することに時間を使いたいかということと、人間同士として気持ち良く過ごすために大事にする価値観というのは、全然違うのではないか。大学に入った夏頃にはそう思うようになった。
もちろん冒頭で述べた様にそのどちらもがスッと合う人はゼロではないけれど、それは地上の奇跡と呼ぶに足ることだ。そしてそんなものだけを求めては、気の合う人というものには極めて出会いづらい。
私はだんだん、その人が好きなものと同じくらい、人間性がマッチするかをようになった。書いてみると当たり前だが、それが革命になるくらい私は趣味厨だったのだ。
胸を張って言おう。自己紹介のひとことで好きなバンドを答える時、そんなに恐れ合う必要はない。好きなものがあるか、人の好きなものを聞く姿勢があるのか、それが問題だ!
全く自分と違う分野でも、情熱を傾けているものがあれば、人同士で話し合うことができる。
正直、そうした寄りかかるものが全くない人がどうやって立っているのかは未だ分からないけれど、そうした人にもきっと言葉にして聞こえてこないだけで、何かしらの精神的な支えがあるはずだと思っている。
実際、私は大学に入ったばかりのタイミングで、まあまあ趣味の合うパートナーと別れて、とても趣味の合うひとやあまり趣味の合わない人と遊びに行ってみた結果、そこまで趣味は合わないかもしれないが人間的にこれ以上まともな人はいないだろうと感じた人とお付き合いをして、いまも一緒に住んでいる。
パートナーは私の蔵書の1/10もピンと来ないだろうし、引き止めないと史跡の看板は素通りし、私がドライブのBGMを選ぶと3曲も経たず主導権を奪い返そうとするけれど、でもとても気持ちの良い暮らしをともに送っている。感謝とか謝罪とか相談とか協議とか、自分の機嫌を取るとか、TPOの捉え方とか、そういうものの摩擦がないからだ。
余談だが、趣味も気も合う友人と一緒に住んでいたこともあり、あれももちろん最高で素晴らしい生活だった。
同じものが好きでも気が合うわけではない!
これは学生時分の私に聞かせたら目を引ん剝いて驚くと思うけれど、大事なひとつの持論である。
parfait theories🍴
ビリーの人生の中で培った持論をまとめておきたいという試みです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
