
前方後円墳の考察⑪「卑弥呼の鬼道は道教か」
卑弥呼の鬼道が道教であった可能性はあるのでしょうか。卑弥呼が女王として共立されるに足る力、すなわち、道教の教えを会得し、修行を積み、様々な術を実践できる力を持っていた人物であったかどうか、ということです。
道教ではこのような力をもった人に様々な呼称をつけています。「道士」とは出家を原則として道教の教えを極めようとする修行者で、仏教でいう僧にあたります。これに対して「巫祝(ふしゅく)」はもともと雨乞いの祈祷師であったり、神憑りをして神意を伝えたりする特殊能力をもった呪術者です。また、「童乩(タンキー)」は信者の悩みや願いを聞き、解決に導く役割を果たす人で、神の霊を自らの体に降ろして異言を吐いて問題の処理を行います。女性の童乩は「紅姨(アンイイ)」と呼ばれます。卑弥呼の鬼道は巫祝または紅姨のイメージになるでしょうか。
後漢書によると倭国大乱の時期が桓帝・霊帝の間、すなわち148年から189年となっていますが、先に見た通り、この時期はまさに道教の勃興期にあたっており、道教の二大教団である五斗米道や太平道が興って隆盛を極めた時代に重なります。徐福以来、すでに倭国には神仙思想が広まっていたとは思いますが、この時期に早くも道教が倭国に伝わっていたとは考えにくいです。そんな時代にあって倭国大乱を収めるために女王として共立された卑弥呼が「道士」「童乩」「紅姨」といった立場で道教と関わりを持っていたのでしょうか。
卑弥呼が中国人だとすれば、中国で道教をマスターして倭国にやってきた、たとえば、184年に起こった黄巾の乱を逃れてやって来た、あるいは道教を布教するために倭国に送り込まれた、といった可能性はあるでしょう。しかし倭人の言葉を話せない卑弥呼が自らの持つ道教の力を倭国の首長たちに知らしめて190年頃に女王として共立されるにはあまりに時間がなさすぎます。逆に卑弥呼が倭人だったとすると、そもそも中国で道教を学ぶ動機がないし、仮に中国に渡ったとしても言葉や文字の壁があるため、それほど短時間で会得することは不可能と思われます。
つまり、中国において道教が成立して隆盛した時期(太平道や五斗米道が成立した時期)と倭国大乱から卑弥呼共立に至る時期がリアルタイムに重なっていることが、卑弥呼が道教の力をもって女王に共立されたと考えることを困難にしているのです。百歩譲ってその可能性があったとしても、黄巾の乱の鎮圧にあたった曹操が道教を認めるとは考えにくい。つまり、道教を奉じる卑弥呼を親魏倭王に任じることはあり得ないと思います。
曹操は184年に起こった黄巾の乱において、潁川(えいせん)の黄巾賊を討伐した功によって済南国の相(行政長官)に任じられていますが、宗教が民衆の心をつかんで狂信的になることの怖さを知っていた曹操は、済南付近に600余りあった前漢の城陽景王劉章の祠や桓帝が老子を祀った濯竜宮などを破壊しています。道教についても、五斗米道の信者は四川の根拠地を追われて中国の南北に散らばることになり、また、道士を集めて厳しく監督したそうです。
以上のことから、卑弥呼の鬼道が道教であったと認めることはできないと考えます。また、道教が神仙思想を取り込んだのが葛洪の抱朴子以降、つまり4世紀以降のことなので、仮に卑弥呼が道教を会得していたとしてもそこに神仙思想の概念は包含されていなかったことになります。
(つづく)
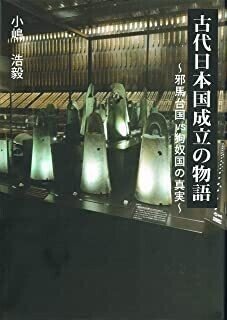
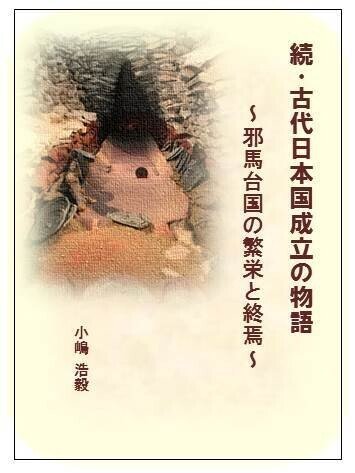
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
