
憑在論と幻想文学 アーサー・マッケン篇
まえがき
何度も当note/当資料室内で述べてきたことだが、日本の憑在論と音楽の接続は、ほぼすべてマーク・フィッシャーと彼がウォーリック大学在籍時代に所属したサイバネティック文化研究ユニット経由の資本主義リアリズムが入り口になっている。それは(生活圏内に大学、クラブ、程度の差はあれど文化的な施設があるような)都市生活者のサイクルが孕む矛盾を呪い、反面その永劫的な再生産から抜け出せないという前提を受け入れたうえで生き抜くという、サッチャー時代の英国ポストパンク的な態度とも換言できる。しかし、当座たる英国のジャーナリズム内で憑在論のタグがつけられている音楽の中には、レイヴやポストパンクそれぞれの全盛期よりもさらなる過去を志向した、霊的なアナクロニズムによって稼働するものがある。その射程は連合されたイギリス以前の、ウェールズやスコットランドといった国々はおろか、キリスト教伝来前のケルト文化にまで及んでいる。郊外に残る森やストーンヘンジといったオブジェとして残り続けてきた過去の残滓は戦後モダニズムの象徴たる都市開発に押しのけられるようになったが、同時にそれへ対抗するかのようにポピュラー文化の中で思い出され、憑在論者たちを育んだ。その一例がJ.R.R.トールキンやC.S.ルイスが描いた準創造の世界、あるいはフィッシャーやベリアルの心にとり憑いていたMRジェイムスが雰囲気として描き出した異界だった。とりわけMRジェイムス(BBCは68年に『笛吹かば現れん』のドラマを製作している)やアーサー・マッケンといった怪奇小説、日本でいうところの幻想文学は、英国式憑在論のリアリティを補強すると同時に、きわめて土着的な性格にも気づかせてくれる(英国的なもの、さらに拡げてヨーロッパ的なものへの回帰が、90年代のEU発足に反発するかのように勃興したネオフォーク運動とも繋がっているのは否定できない)。数が少ないとはいえ、フィッシャーもレイノルズもこの角度から音楽を語っているのだが、あまりに自分たちの出自に傾いた視点ゆえか深入りはしてこなかった。とりわけレイノルズはあまりに英国人的な背景に対してアンビバレントな感情を抱いており、Moon Wiring Clubのようなレトロマニアを讃えながら、後述するGhost Boxのアーティストたちを寵愛する自分に対して「更年期を迎えた男性の趣味に過ぎないのではないか」と自嘲的に考察している(ゆえにアメリカでも同じような作家乃至運動がないかどうかを探し、フリーフォークやヒプナゴギック・ポップへと辿りついた)。
こうしたコンテキストが日本の(音楽)ジャーナリズムに輸入されていないのは、文化的な共通項が少なさゆえだろうか。しかし前提を持たないからこそ知識として受け入れることもできる。たとえばロブ・ヤングによる霊的フォーク史『Electric Eden』でも頻出する「Pastoral」(パストラル。牧歌的の意)は、この英国土着な角度から憑在論を語る上で助けてくれる概念である。特定の作家を例示して同概念を紹介した記事もあるので、そちらも併読してもらいたい
。
マーク・フィッシャーがパストラル憑在論について書いたテクストを挙げるとすれば「消滅する大地について」(『The Weird and the Eerie』、邦題『奇妙なものとぞっとするもの──小説・映画・音楽、文化論集』収録)だろう。ブライアン・イーノのアンビエントシリーズ最終作『On Land』をMRジェイムスと接続したもので、アンビエントのコンセプトが薄暗い望郷の念と結びついたことに着目している。『On Land』は大都市ニューヨークに滞在していたイーノの懐郷(それは反アメリカという英国的な態度も含んでいると思われる)が根底にある作品で、いくつかの曲名はイーノが過ごしたサフォーク州の地域からとられている。アンビエントの第一弾『Music For Airports』は米国が生んだミューザックへのアイロニカルな回答であったが、『On Land』はよりぞっとするもの・奇妙なものを内包した英国らしさ、つまりはパストラルに回帰したのである。ここも過去に言及したことがあるので、以下の記事をついでに参照のこと。
いつも通り前置きが長くなって恐縮だが、本記事ではパストラル憑在論と英国幻想文学の代表たるアーサー・マッケンのつながりを思索した。またまた過去の記事への案内になってしまうのだが、こちらの記事や『MUSIC+GHOST』という本の内容を反復する部分も多いため、未読の方はこれを機にお求めください。
ノスタルジーとしての法悦(エクスタシー)
憑在論においては重要だが、アルコールがごとく使う者を骨抜きにもする概念がノスタルジーである。時にはレイヴを通過してきた若者たちが歳を重ね、かつての光景が払拭されてしまった都市を嘆く時に抱かれるペシミスティックな回答として。一方ではサイモン・レイノルズ『Retromania』で提示される発展のヒントとして、ノスタルジーは創造の出発点になっている。しかし、パストラル憑在論におけるノスタルジーとは、流行り廃りというモードの枠で囲い込めぬ超感覚的なものであり、言語によって理屈づけしがたいファンダメンタルな感情である。それは曖昧で表立つことは少ないかもしれないが、絶えることもない。
夢と魔の世界を隔てる境界線をあぶり出すアーサー・マッケンの小説が誘発するノスタルジーは、彼本人の言葉でいうなら「法悦」(エクスタシー)と呼ばれるものであり、「日常から遥かに遠ざかること」と説明されている。森を駆け巡る牧神たちや、窓に映った何かの「この世ならざる形相」といった形象はその法悦を可視化したものであり、それらを恐れつつも誘われてしまうのが伝統的な英国人の感性なのだ。この古く奇妙な英国怪奇の感覚は、江戸川乱歩に「郷愁としてのグロテスク」という小文をもってマッケンを称賛せしめ、同文を引いた種村季弘は「郷愁としての恐怖」(牧神社発行『牧神』マイナス3号より)という言葉を添えた。
この感覚を誘発するものが、マッケンを育んだといっても差し支えないウェールズ郊外の風景であり、近代化が進んだ今日でもなお遠い過去の想像を続けさせる森、丘、遺跡といったランドマークたちである。これらが英国人にとってのリミナル・スペースとなっているからこそ、『不思議の国のアリス』のウサギの穴があり、バーネット『秘密の花園』は今日も瑞々しさを失わない。
パストラル憑在論の一翼を担うGhost Box Records、Moon Wiring Club、そしてThe Memory Bandら親類がいずれも2000年代前半に登場したことは偶然ではない。彼らは形式的なフォークソングの伝承を目的にしたThe Imagined Village(これも2004年発足である)と違い、三十代を迎えるころには周りから消えていた過去を思い出した。それはキリスト教的啓蒙思想に由来するリベラルな公共デザイン(マーク・フィッシャーはこれをポピュラー・モダニズムと呼んだ)と隣り合わせになった、(超)自然への記憶であり、幼少期に感じていた郷愁としての恐怖を思い出した世代である。彼らがノスタルジーを実感する年齢であったのはもちろん、DJカルチャー経由のレアグルーヴ発掘に伴い、過去の音楽の再検討を実感していことも大きな要因であった。同時代を象徴するサンプリング技術は、彼らに過去との対話を実現させた。たとえば
Ghost Box共同設立者ジム・ジュップは、自身のプロジェクトBelbury Polyで、ジョセフ・テイラーが残した最古のフォークソングの録音をサンプルして「Caermen」を書いた。
Caermen(カーマエン)とはアーサー・マッケンの出生地であるウェールズのモンマスシャー州に属する町である。この地域はアーサー王の戴冠式が行なわれた土地としても知られているが、その実態は朽ち果てた遺跡の残骸が点在する典型的な郊外であった。ゆえに墓場や精神病院が建てられるなど、「普通」を称する社会のしわ寄せを受けてきている。この土地が持つ荒涼としたムードとそれが幻視させたものをマッケンは自身の半自伝的小説『夢の丘』の書きだしに凝縮している。「空にはあたかも大きな溶鉱炉の扉をあけたときのような、すさまじい赤光があった」(平井呈一訳より)。
マッケンに対して同時代から反応した作曲家がジョン・アイアランドだった。牧歌調(パストラル)の曲を多数書いていたアイアランドは、ある日駅で売られていたマッケンの作品集『House of Souls』に感銘を受け、「マッケンの小説を経過していない人は私の音楽を本当の意味で理解できないだろう」とまで残している。果てには自身が丘を歩いている時に目にした幽霊たちの様子をしたため、マッケンに送りつけさえした。マッケンからの返事はただ一言、「あなたも見たことがあるんですね!」であった。アイアランドは「Maidun」や「The Forgotten Rite」といった曲をマッケンに捧げた。
伊福部昭とともに新音楽連盟を発足し、西から東にわたるクラシックの普及に尽力した三浦淳史は著書『アフター・アワーズ』内で、アーネスト・ジョン・モーランの音楽における地理性を指摘している。モーランはマッケン狂いのジョン・アイアランドに師事し、地元であるノーフォーク州の民謡蒐集にも精力的な一作曲家だった。フレデリック・ディーリアスの研究者であったピーター・ウォーロック(二人ともパストラル憑在論とクラシックを語るうえで重要な作曲家だが、今回では説明を割愛する)と交誼を結んでいたモーランは、やがてケルト総本山たるアイルランドに移住するのだが当然の成り行きに思えてしまう。
話をモーランの音楽に戻すと、代表曲「Lonley Waters」はノーフォーク地方の民謡から主題を断片的に引用したもので、そのイメージは湿原や川に発するものであった(イーノがサフォークの特徴を『On Land』で夢想したことも思わせる)。三浦はこの曲を例に挙げて、英国におけるパストラル・ミュージックの条件を定義する。曰く「英国のパストラル・ミュージックでは、主旋律を奏でるのは草笛を思わせ得るオーボエでなければいけない」。フルートを奏でて人を惑わす牧神パンがいるからして、管楽器が持つ蠱惑的な響きへの関心は、英国〜アイルランドの音楽を構成する精神的要素なのである。
ダークリヴァー
森、丘、湿原、そして川といった地形は都市開発によって侵食されていくことで、人間の記憶の中でのみ存在するようになる。逆説的にモダニズムが古代への関心をたぎらせたからこそ、トールキンによる『ホビット』や『指輪物語』のペーパーバックが爆発的に売れ、中つ国の名を冠したヴェニューMiddle Earthがロンドン市内にできあがるのであった。
ロンドンは変わりゆく都市の最先端であり、同時に点在する過去を残した多層的な異空間である。何をかくそう、ウェールズからこの街にやってきたアーサー・マッケンは、古書店で働きながらケルト文明が残るカーマエンに望郷の念を膨らませ、彼いうところの法悦を描いた。マッケンの倫敦愛は彼が想像したキャラクターにして、何割かは自身の投影たるディレッタント、ダイスンが登場する作品にて描写される。例として『The Inmost Light』(邦題『内奥の光』)冒頭でダイスンが旧友サリスベリと再会したときの会話を引く。
大都市学。–つまり、ロンドンの生態学さ。これはね、文字どおりにも、また理論の上から言っても、人間の知性が考えうる最大の名目だぜ。いまでもぼくは、このロンドンの厖大さと複雑さを考えると、われながら圧倒されてしまうことがよくある。たとえばパリはね、あすこはある程度の研究をつめば、ひととおりの知識をつかめるようになれるが、ロンドンというところは、これはつねに神秘だよ。かりに君がパリへ行けば、『ここは女優の住んでるところ、あすこはボヘミアンの住むところ、ここはごろつきの住むところ』と言えるだろう。ところがロンドンはまるで違う。そりゃ洗濯女の住んでる区域はどことどこだと、正確に町名を指すことはできるだろうが、あすこの二階にはカルディの根を勉強している男がおるし、すじ向かいの家の屋根裏では、無名の画家が刻々に死に瀕しているかもしれんしな」。
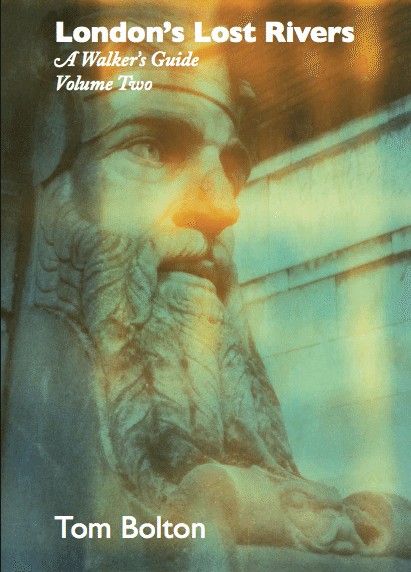
未来と過去が同居するロンドンのシンボルに数えられるのが川である。市内を通る水路は無数の川へと続いているが、中には地図に載らない水路、地図に記名されぬ川というものがある。これは英国民俗学において欠かせない要素のようで、トム・ボルトンによる失われた水路探索本『London’s Lost Rivers』のように、名もなき(忘れられた)川を扱う書籍は少なくない。
川をたどることで街を抜け出し、文明人の手がまだ届いていない異界へとたどり着くのではないか。この英国人の本能的な予感を音楽へと置換していたのがCOILであった。インダストリアル・ミュージックのパイオニアたるThrobbing Gristleから派生したCOILは、カバラ数秘術から北欧神話にいたる異教の知識で音楽を構築し、古代ヨーロッパ的なものへの執着を強めた。そこには上でも述べた川の崇拝があり、「Dark River」、そして「The Lost Rivers of London」なる楽曲によって主張されている。後者はトム・ボルトンの書名を見れば、その研究にも明らかに影響を与えていることがわかる。
レイヴ・カルチャーの現場にもいたCOILのメンバーは、フェアライト以降爆発的に進歩するサンプリング技術に執心し、テクノロジーを持って超自然的なものへと繋がるパストラル憑在論の実践を果たした。名作『Love's Secret Domain』収録の「Chaostrophy」は断片的なサンプルをツギハギしたドラッギーなモンタージュだが、最後にオーボエによる物悲しい(どこかアルメニアのトゥドゥク的な)主題が流れてくる。三浦淳史によるパストラル・ミュージックの定義が実演されたかのようだ。「The Lost Rivers of London」の名が川に落ちて亡くなったといわれるヒューバート・クラッカンソープの詩から名がとられたこと、アーネスト・ジョン・モーランもまたアイルランドの河川に落ちて亡くなったということと併せて、COILがクラブ・カルチャーやインダストリアル・ミュージックといった78年以降のタームだけでは捉えられないことは留意しておくべきである。
ゴースト・ストーリー復刻運動
マッケンをノスタルジーの象徴として再評価したのはGhost Boxに限らない。Current 93のデヴィット・チベットは90年代の時点で英国幻想文学、本国でいうところのghost storyと音楽を接続していた。C93の92年作『ThunderPerfectMind』は、アポカリプティック・フォークと呼ばれるスタイルの決定版で、当時の時点でグループ史上最大のセールスを記録した。その資金を用いて設立されたのが幻想文学専門の復刻レーベル「GHOST STORY PRESS」だった。チベットは交流ある古書店や文学研究者たちを一様に巻き込んで、埋没していた作家たちを復刻した。当初はラヴクラフトやハーバート・ラッセル・ウェイクフィールドらに着手する予定だったが、原本入手の難しさからか見送られ、アーサー・グレイ、ヴィンセント・オサリヴァンといった作家たちが少部数で再発されたのだった。グレイに関しては別名義「Ingulphus」で書かれた『Tedious Brief Tales Of Granta And Gramarye』が第一弾として復刻され、これは本国としても異例の試みであったとされている。チベットはデヴィット・キーナン『England's Hidden Reverse』の中で、この復刻運動が直面した偶然の神秘を回顧している。
『Tedious Brief Tales』の原稿が印刷所に送られた直後に、オリジナルを2部手に入れたんです。1つはカバーつきで、もう1つは作者のサインが入っていた。こういうことがあるんですよ。

Ghost Story PressのカタログにはMRジェイムスも名を連ねており、これだけでもチベットが憑在論者たちに10年以上先駆けていたともいえる。だが、より驚くべきは当時からチベットがトマス・リゴテッティと繋がっていたことだろう。思弁的実在論や反出生主義など、2010年代以降の非キリスト教的と呼べる世界観を補強する分野に強い影響を与えている作家だが、90年代の時点では当然現在ほどの知名度を持っていなかった。チベットとはラヴクラフトやグノーシス的死生観で通じ合ったようで、Current 93と連名のプロジェクト『In A Foreign Town, In A Foreign Land』も発表している。これはリゴッティの小説にCDが付けられたアイテムで、Ghost Story Pressの仕事の延長とも呼べる一冊(一枚)だ。なお『In A Foreign Town, In A Foreign Land』は、2022年になんと映画化された。

肝心のマッケンはというと、復刻の対象にはなっていなかった。しかし、ある意味でマッケンはチベットにとって重要な存在として90年代に再臨する。それはCurrent 93のインスピレーションとしてであり、小説から名をとった「The Inmost Light」三部作が作られたのだ。このトリロジーはチベットが敬愛するルイス・ウェインやチャールズ・シムズらの人生に没入した成果であるが、マッケンは第3の主題として存在していた。幼少期に幻想文学を読んだときの恐怖を思い出し、そこに恋しさ≒ノスタルジーを感じたチベットは、すでに開花させていたフォークソング〜マーダーバラッド様式にマッケン的な法悦を盛り込んだ。二作目にあたる『All The Pretty Little Horses』はこの時期のC93のピークと呼べる秀作で、ニック・ケイヴとともにリゴッティもその声をアルバムに封じ込めた(2018年の『The Light Is Leaving Us All』にてリゴッティは再び「ゴースト・ボイス」という名目でC93と合流する)。
三部作最後の『The Starres Are Marching Sadly Home』ジャケットは、アルバムのミックスも担当したスティーヴン・ステイプルトンによるものだが、この絵ほどマッケンの描く恐怖を表したものはないだろう。・・・でもGhost Story Pressが出したヴィンセント・オサリヴァン作品集にも同じ絵が表紙として使われていて、ちょっと統一性を欠く結果となった。なぜなのか?

最後に日本へと目を向けてみる。この記事で述べてきたマッケンやMRジェイムスら多くの幻想文学作家を邦訳したといえば、平井呈一の名が真っ先に挙がるだろう。パストラル憑在論は英国の音楽だけでなく、平井が社名を考えた(案を大量に送ってきた)牧神社や、雑誌『幻想文学』が果たしてきた海外文学の紹介・研究に尽力してきた人たちのことを思い出させてくれた。そして法悦こと超自然的ノスタルジーを誘発する作家が日本にもいるだろうか、と思考を促しもするのだ。そこで幻想文学に多少馴染みがある方ならば、平井呈一が師事したともいえる永井荷風を思い出すのではないか。荷風の描く小説、徹底的な「場所」の描写に埋め尽くされた『墨東奇譚』などは、ノスタルジーという色彩を持って現在に過去の色彩をほどこすパストラル憑在論の典型ではなかろうか?マッケン的な恐怖の感覚は岡本綺堂のような作家に譲るとして、過去と現在を繋ぐ場所性においては、下町の水路や橋含む「道」に執心した散歩狂いこと荷風を看過はできまい。次の記事では荷風のみならず、失われた過去を燃料とする日本の音楽家についても書いてみたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
