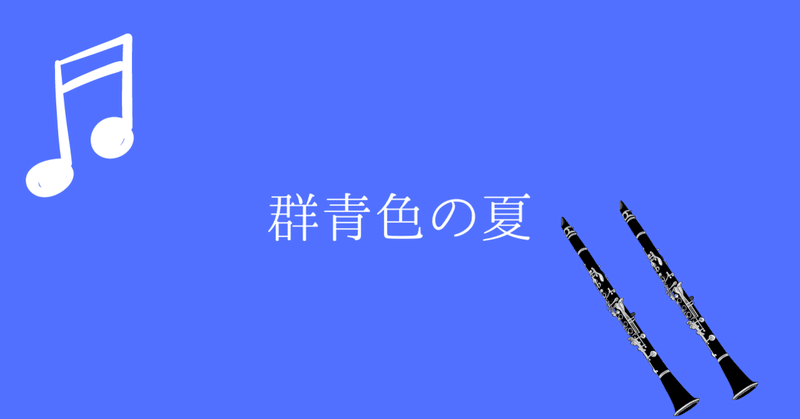
【小説】群青色の夏 4
僕がそう言うと、万里子は納得がいかないような顔をしながらも、こくりと頷き、それ以上の反論はしてこなかった。僕には、万里子の納得のいかない気持ちがよく分かったが、先生がオーディションをしてメンバーを決める以上、そこは僕たちの手の届かない神域なのだとも思っている。
だから僕は、万里子のパートリーダーとしての焦りや不安を感じ取りつつも、信じようと彼女に投げかけたのだった。それは中学生の僕に出来る最大限の行動だった。
五月に入ってもパートが決まらず、やきもきしているのは万里子だけではなく、それは一年生も一緒だった。オーディションとパート決めのためにクラリネットと、トランペット、そしてパーカッションの基礎練習ばかりの毎日に、緩やかにけれど確実に飽きを感じ、そして締まりのない練習になっていく。
僕たち三年生はその状態にも危機感を持っていた。飽きや締まりのない練習はいつしか不満に変わり、そして退部に繋がるからだ。僕たちの学校は今年十三人の新入部員しか獲得出来なかった。
三年生が二十五人、二年生が二十三人で、毎年二十人以上の新入部員が当たり前だった吹奏楽部は今年、先生曰く十年ぶりに二十人を下回る新入部員しか獲得出来なかった。来年のコンクールは四十人足らずで出場することが決まってしまった。
部員獲得で上手くいかなかった僕たちは、この一年生達に退部をしてもらっては困るのだ。だからか、どうしても今年の一年生には甘くなりがちで、二年生はそれが面白くないようだった。
それを感じ取りつつも、パートが決まるまではお客様だと思って一年生を扱い、楽しい部活の雰囲気の中パートが決まるまで頑張ってもらいたいと必死に繋ぎとめていた。
一年生の中には吹奏楽部に入ると確固たる信念をもって入ってきた一年生も勿論居て、その子たちに関しては何も心配していなかったが、問題はなんとなく入ってきた子たちだ。なんとなく入ってきた子たちは何となく退部してしまう。
なんとしても十三人だけは守り抜きたい――
僕らはそう思いながら一年生に接していた。早く今月の半ばになって、パートが決まればいい。それは僕らの総意だ。パートさえ決まれば、新しい練習が始まる。自分たちの居場所が一年生にも出来る。
コンクールメンバーだって確定して、コンクールの練習も本格的になる。二、三年生はもう譜読みが済んで、一応合奏だって出来る状態だ。一年生のオーディションに合格した二人はその中に入る。一気に進むコンクール練習に、ついてこられるのだろうか。沢山の不安が渦巻く、五月の頭。僕らの最後の夏はもう、動き始めていた。
よろしければサポートお願いします。頂いたサポートは治療費や創作活動に使用させていただきます。
