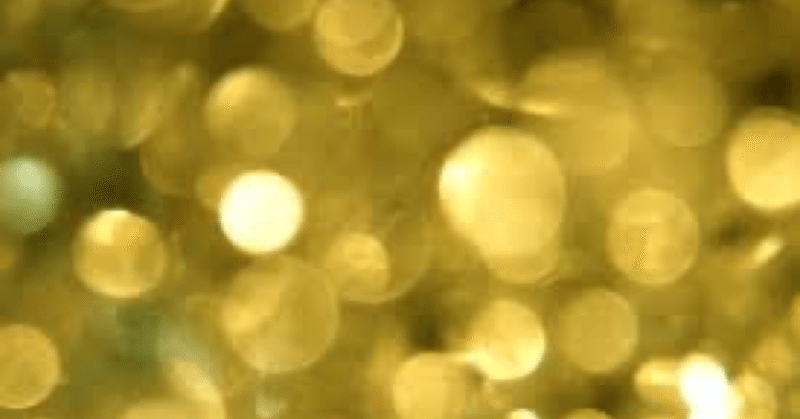
「祖父について」
祖父について書いてみようと思う。その前に、俺の生まれた街について。
俺が生まれた家は、市内を横断する唯一の私鉄「K」駅近くの国道沿いにあった。国道沿いだと言っても、歩道のかわりにあるのは下水の側溝で、コンクリートの蓋が所々ついているだけだった。大雨が降れば水が溢れた。俺たちは側溝に落ちないように、足元に若干の注意を払って歩かなきゃならなかった。国道には自家用車以外に、実に多くの種類の自動車が走っていた。大型トラックや、ゴミ収集車、セメントミキサー車、レッカー車、もちろんバスやタクシー。いろんな自動車がタイヤを軋ませ、排気ガスを撒き散らしながら堂々と走っていた。
脇道に入れば舗装されていない道ばかりで、家と家の間に空き地が点在していた。そこそこ広い空き地があれば、そこで俺たちはバンドベースとか、キックベースとか、あるいは缶蹴りとかして遊んでいた。夏になれば砂利道沿いに植えられていた桑の木にとまったセミとか、カミキリムシとか、早朝、運の良い日はカブトムシやクワガタを取ったりもした。草の匂いに紛れて、お菓子屋さんの厨房で焼いているケーキの甘い匂いがしたり、家の前に停まったバキュームカーから糞尿の悪臭が漂ってきたりしていた。俺たちはそのたびに、鼻から大きく息を吸い込んだり、あるいは眉間に皺を寄せて鼻を摘んだりしていた。
家は祖父の代から魚屋を営んでいた。
魚は魚屋で買い、肉は肉屋で買い、野菜は八百屋で買い、靴は靴屋で買う。それが当たり前で街全体が一つの商店街だった頃の話だ。
魚屋を営んでいた祖父は変わり者で市場から実にいろんなものを仕入れてきて店頭で販売した。
発端はスイカであった。夏場、祖父が仕入れてきたスイカはマグロのお造りの隣に陳列された。今思えば、冷蔵庫の管理温度帯も鮮魚と果物では違うはずで、そういう意味では実におおらかな時代であった。
近所に住む常連客にスイカは意外にも好評だった。味をしめた祖父は、次々と【魚ではない】ものを市場から仕入れて店頭に並べた。
冷蔵ケースの中には、魚の隣に野菜、果物、その脇に祖父が設置した回転什器には缶ジュースが所狭しと並べられた。挙げ句の果てには、店の前に鉢植えや花まで陳列し販売していた。もはや、魚屋の面影などどこにもない。
わがままな祖父は、思いつくまま商品を仕入れ、販売は父や母に丸投げであった。しかし、祖父の死後、父は当然のように魚以外の販売をやめた。【魚でない商品】はひとつ残らず店内からひっそりと姿を消した。
それは、 街にまだ食品スーパーというものが存在していなかった40年前の出来事であった。
祖父の死と、少し俺の弟ついて。
家の向かいは酒屋さんだった。その酒屋には一杯飲み屋が併設されていて、販売コーナーから扉一枚を隔てたこの向こう側に十坪ほどの空間があり、カウンターと丸椅子が並べられていた。
恰幅の良い祖父は、夕刻になると白い襦袢に茶色の腹巻姿で、下駄をからんからんと鳴らしながら、向かいの酒屋に出かけていく。そして、浴びるように酒を飲み、散々酔っ払って家に帰ってきた。
祖父が帰宅した時間が俺たち一家の夕食の始まりであった。祖父が食卓につくまで料理に箸をつけることは許されない。
幼い頃すでに亡くなっていた祖母は別として、両親と祖父、そして弟、五人で食べる夕食は、ひどく憂鬱な空間だった。祖父は酔っ払った状態で延々と誰に話すわけでもなく独り言を宣っていた。そうかと思えば、突然大きな声で、母の作った料理が冷めていてまずいだとか騒ぎ出す。
祖父以外は食事中、一言も口を聞くことはなかった。テレビ番組は祖父の好きな時代劇とかのチャンネルに合わせられ、夏の扇風機は祖父にだけ風を送る。祖父以外は皆、汗をだらだら流しながら箸を突いていた。
たまに柄の悪い酔っぱらい仲間を連れてきて夜中まで、大きな声で騒ぎながら酒を飲むこともあった。そんな時、俺たちはすぐに二階の寝室に避難したが、母だけは文句も言わず、酒やちょっとした煮物や焼魚を作って出していた。
飲み屋で喧嘩してビール瓶を振り回し、店のガラスを割ったこともある。父母は「ごめんなさい、ごめんなさい」と言ってひたすら店主に頭を下げていた。
そんな酒癖の悪い祖父を二つ下の弟はひどく嫌っていた。「あんなやつ、早く死ねばいい」何度も俺に向かってそう言っていた。
祖父が胃癌に侵されたのは俺が実家を離れ都内の大学に通っていた頃だ。発覚したときはすでに手の施しようのない状態だったという。
大学から帰省するたびに、祖父を見舞いに行った。しかし、当時全寮制の工業専門高校に通っていた弟は一度として祖父の見舞いに行くことはなかった。
帰省するたびに針金のように痩せていく祖父に酒を飲んで威張り散らしていたかつての面影はまるでない。干からびた声でただただ「家に帰りたい、家に帰りたい」とぶつぶつと独り言を繰り返していていた。
大学三年の夏、祖父は死んだ。葬儀で親戚連中が涙を流すなか、俺の家族は誰一人として泣かなかった。父母はただただ忙しく動き回っていた。そしてそこに弟の姿はない。祖父をひたすら毛嫌いしていた弟は葬式の時にすら帰ってこなかった。
それが俺の祖父だ。このように偉大な祖父の血はもちろん俺にも流れている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
