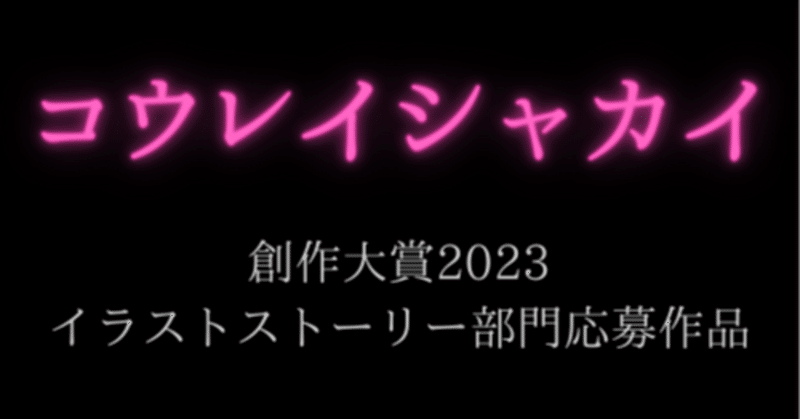
【小説】コウレイシャカイ 第十三話(創作大賞2023・イラストストーリー部門応募作品)
「······敵はチャンスをあげるといいつつ街中で戦いを起こすことで人々の死への恐怖を煽り、自分達の目的を達成するつもりです」
フレイヤが言うと葛野は舌打ちし、
「だがやるしかねえだろ。絶対に止めてみせる」
その言葉にサラディンは重々しい声色で、
「私があのとき、あいつを止めていればこうはならなかった。だが私は不死などには興味が無いし、自由を与えられたなら戦わない選択だってできると思った······すまない」
「サラディンさんのせいじゃありません。今はできることをしましょう」
「おいバイフィールド······何かてきぱきしすぎてねえか?大丈夫か?」
葛野の問いにフレイヤが答える前に、エディソンが彼に非難の視線を浴びせた。
「フレイヤさんだって大変なんだ。わかってやれ。それより、僕の方はいつでも準備できてるよ。退霊装置も使える状態にある」
「そうか、家康に感謝だな」
呟いて葛野は席を立ち、本部席のマイクで同僚達に呼びかける。
「治安部隊の全隊員に告ぐ。各自出撃準備を整えろ。この戦いで最後にする。全力で敵を倒して市民を守り、絶対に生き残れ!」
葛野はマイクから離れると自らも準備のために本部室を出ていき、サラディンがその後を追う。エディソンはフレイヤを小さく見やったが、何も言わずに席を立った。
(私も······行かなきゃ)
残されたフレイヤは駐車場へ向かい、空色の軽自動車を病院まで走らせる。深夜の道路は誰もいなかった。夜明けにはここにもまた多くの死が転がってしまうのだろうか。そう考えたフレイヤはアクセルを踏み、悪い想像を断ち切る。
病院に入ると事情を把握している看護師に許可をもらい、個室病棟に通してもらった。まだ新しい乾いていないサインペンの文字で『宮沢』と書かれた部屋へ入る。
電気のついていない病室は、少しだけ消毒液のにおいがした。ベッドに寝かされている赤髪の女性はまだ目を開けず、傍らの丸椅子で俯く少年はまだ眠っていなかった。
「······鹿嶋くん」
フレイヤが呼ぶと鹿嶋は目だけをゆっくりとこちらへ向け、すぐにベッドの上へ視線を戻した。
「······どうしたんですか」
「その······謝りにきたの。日咲ちゃんを殺したのは私なのに、それに気づいても言えなかったことを。ううん、日咲ちゃんを殺したことを、謝りたい」
「いいですよ、謝らなくても。俺には怒る権利も憎む理由もありませんから。日咲がいいって言ったなら、それでいい」
鹿嶋の声色は無機質で、平坦で、空っぽだった。何の感情も込もっていなかった。何の感情を込めればいいのかわからなかったのかもしれない。
「俺を迎えに来てくれたんですよね?わざわざすみません。俺、絶対にあいつを倒しますから」
「そうじゃないよ」
立ち上がろうとした鹿嶋の肩を押し留めてフレイヤは強引に座らせ、眼が合わずとも彼の顔を見つめて言葉をつなぐ。
「鹿嶋くんは、これ以上戦わなくていい」
「······いや、俺はまだやれます。大丈夫です。日咲にまた会うためにも、最後まで戦わせてください。宮沢さんが意識を取り戻しても日咲が退霊していたら、降霊研究を使わせてもらう必要がありますから」
言いながら鹿嶋はまっすぐな眼でフレイヤを見据え、
「俺は、戦います」
「降霊研究が凍結された」
フレイヤも、少しも眼を逸らさずに告げ返した。
たった今、自分が一人の少年の希望を打ち砕いてしまったことを、フレイヤは再びはっきりと認識した。鹿嶋がどんな期待を寄せて自分を頼ったのか、フレイヤは充分にわかっている。だからこそ、彼の望みを絶った理由を示さなければいけなかった。
「鹿嶋くん、この研究は······いや、私は多くの人を傷つけた。だからもう降霊研究は続けられない。会いたい人に会えるなんてすごく素敵な研究のはずだったのに、私のせいで誰かを死なせた。だからもう、鹿嶋くんが戦っても日咲ちゃんを降霊させることはできなくなった。だからごめんなさい。私のせいで君と君の大切な人がまた引き離される。君はもう戦わなくていい。君のこれまでの頑張りを、私が全部無駄にしたから······」
これまでに数え切れないほど鹿嶋への謝罪を繰り返してきた気がする。それでも、今回で最後だ。きっと鹿嶋は許さないだろうし、もう鹿嶋と会うこともない。彼を元の日常に返して、自分は罪を償って、別々の道を進んでいく。フレイヤの境遇に涙を流してくれた少年に見せていい涙など無いのはわかっているから、震えそうになる声を必死に落ち着けた。
「······そうですか」
呟いたきり鹿嶋は押し黙り、沈黙がフレイヤを苛烈に責め立てる。許されるはずがないのにわずかな慈悲を求めていた自分が情けなかった。
「······ごめん、行かなきゃ」
自分は鹿嶋の前から逃げ出そうとした。やらなければいけないことがあって、その準備に向かおうとするのは当然なのに、それがとても卑怯なことのように感じた。フレイヤ=バイフィールドは、そういう人間だった。
「フレイヤさん」
黙って病室を去ろうとすると、鹿嶋に呼び止められた。
「フレイヤさんが降霊研究をする理由って、何ですか?」
「······陶磁器戦争で犠牲になった家族や友だちに会いたい。たったそれだけだよ」
「······そうですか」
応えて、今度こそ鹿嶋は沈黙を選んだ。それで、本当に最後なのだとわかった。
フレイヤは病院を離れ、戦場へ向かう。
「緊急連絡システム抜きで避難勧告をするのはやはり大変な労力を費やしますね。警戒区域の住民が避難を終えるまでに七時間もかけてしまいました」
「だからそれは必要だ、と」
「······私が選挙のために渋っていると思ってますよね?」
「違うんですか?」
富寿満が表情を崩さず尋ね返すと支倉は苦笑し、
「違いますよ。今、明日の夜明けに間に合うように優秀なITエンジニア達に作ってもらっているものがあるんです。それが完成するまでゴーサインを出せないというだけの話です。間に合わないことはないと思いますよ?」
「······具体的には何を?」
すると支倉はなぜかニヤリと笑い、
「新しい緊急連絡システムですよ」
「······流石、抜かりがない」
「いえ、下心はありません。降霊研究のレポートをいくつか拝読しましたが、『強い思いが現実となる』という点を非常に興味深く思いましてね」
そこまで言うと支倉は口を閉ざし、勿体つけるな、と内心呆れた富寿満は乾いた視線を送る。それを注目されたと解釈したのか支倉は上機嫌そうに、
「秘策を思いつきました」
日の出と共に、東洋の兵甲が街中に現れた。
避難所には他の治安部隊が待機して襲撃に備えている。だから葛野達の役割は防衛ではなく攻撃だ。あの降霊者の待つ高校へ向けて進撃し、ついに敵軍とかち合う。
「全員止まって退霊装置を準備しろ!」
葛野の号令に皆が従い、長身の葛野と同じくらいの大きさのスピーカーを何台も並べる。その間にも兵甲達は迫り、両陣営の距離は五十メートルを切った。
「どうせみんな避難してんだ、迷惑になんかなりゃしねえ!」
兵甲はさらに距離を詰め、刀を抜く。
「だから音量全開で······」
その距離はもはや二十メートルもない。弓を引き絞れば当たる。
そして、葛野は叫んだ。
「ぶちかませッ!」
直後、退霊装置が赤く光り、耳をかき乱すような甲高い音がスピーカーから一斉に発せられた。それを浴びた兵甲達は次々と白いもやとなって消え失せ、尚も粘ろうとする者には金の兜を被った戦士達が斬りかかる。
「効いてる······効いてるぞ富寿満!」
「ああ!だが油断するな。どこに始皇帝がいるかわからない!」
「ここにいる」
声がして、葛野と富寿満は視線を走らせた。黒い短髪をした線の細い少女がビルのテラスからこちらを見下ろし、爪先で床を軽く叩く。
その瞬間、退霊装置が炎に包まれ、戦士達が地面から姿を消した。
「ようやくオレも能力の使い方がわかってな。オレに反抗する学問の結晶は燃やし尽くせるし、オレに抵抗する輩は生き埋めにできる。この力でお前らを完膚なきまでに負かしてやるよ」
「そうか、なら私と手合わせ願おう」
その声に始皇帝は刀を現出し、横一文字に構える。それと同時にサラディンが地上からテラスに跳び移り、落下の勢いを活かして半月刀を振り下ろした。
「······研究所の頃からお前とは一度やってみたいと思っていた。退屈させるなよ!」
サラディンの斬撃をはねのけて始皇帝は後方へステップを取り、間合いを測って今度は自分から斬り込んだ。それを見た葛野と富寿満もそれぞれの武器を取り、燃え盛る退霊装置の横を駆け抜けて敵兵へと銃口を向ける。
「バイフィールド博士!高校に始皇帝はいない!行くなら今だ!」
「わかりました!どうかご無事で!」
富寿満に叫び返し、フレイヤは脳波連動型カチューシャに接続した二輪型のアクセルを回して朝焼けの街を走る。途中で何本もの矢が飛んでくるが、フレイヤのイメージ通りに動く二輪型は滑らかに蛇行してそれらを全てやり過ごし、矢など追いつかないスピードで振り切った。
どうやら街全体に兵甲がいる訳ではないらしい。静かな街並みにエンジン音だけが響き、前傾姿勢で白衣をはためかせるフレイヤのヘルメットからはみ出た金髪が、朝陽を浴びて眩く輝いた。
(もう太陽が丸々昇りきった。急がなきゃ······!)
市長の企みが上手くいくといいが、失敗した場合事態は一刻の猶予も無い。フレイヤはさらにスピードを上げ、体重を寄せてカーブを曲がり切る。法定速度など無視しているが、それがかえって時間が瞬時に流れていく錯覚を引き起こした。やっとの思いで高校の正面に飛び出して、フレイヤはわずかに目を見開く。
始皇帝が念のためつけていたのだろうか、複数の兵甲が槍を構えてフレイヤを待ち構えていた。その数は十を超えている。止まることはできないが、突っ込めばただではすまない。
ならばフレイヤは飛び越える。
反重力ブーツを最大出力で起動し、地面に向かって放出する。跨っていたバイクから飛び出して、一気に兵甲達の頭上を通過した。バイクが激突した衝撃で兵甲の半分は霧散し、フレイヤは空中で姿勢を制御するのにまた反重力波を使う。だが急激な出力上昇でバッテリー切れを起こしたブーツは使いものにならなくなり、フレイヤは体勢を崩して横向きのまま地面に叩きつけられた。勢いを殺せずに何メートルも転がり、タイツが裂けて長い脚から血が滲む。転がっているときにブーツも脱げた。白衣にも血が付いた。
それでも、フレイヤは進み続ける。
残った兵甲達に対してフレイヤは懐を漁り、愕然とする。家康が残してくれた退霊薬が入った注射器が割れていた。だが今は拘泥していられない。拳銃を取り出して引き金に指をかけ、乱れそうな呼吸を理性で押さえつけて一発ずつ発砲する。命中しても血は出なかった。残弾が枯渇し、撃ち抜かれた兵甲達は白い光のもやとなって立ち消え、フレイヤの指が半年前の感覚を思い出す。
(······行かなきゃ)
ヒビ割れたヘルメットを脱ぎ捨てて校舎に入り、階段を駆け上がって四階まで辿り着く。誰もいない教室が並ぶ中で、一つだけドアが半開きになっているものがあった。誘い込まれていることは明らかだった。それでもフレイヤは行かねばならない。意を決して中に足を踏み入れると電気はついておらず、ピンクのメッシュが入った黒髪をした、緑を基調とする夏用学生服に身を包んだ少女が教室のやや後方の机に腰掛けていた。
「やっほーフレイヤさん、期待通りあなただった」
磯棟の顔をした降霊者は手を振り、フレイヤはさらに進み入って教卓越しに彼女と向かい合う。教卓越しでないと不安だったが、それを認めてしまう訳にはいかなかった。
「この席、実理ちゃんの席なの」
煌々と目を輝かせて教えられるがフレイヤは険しい顔で、
「だけどあなたは実理ちゃんじゃない。日咲ちゃんでも、宮沢さんでもない。あなたは何者なの?」
「えっとそうだなあ······たくさん呼び方はあると思うよ?エリクサー、アムリタ、仙丹、他にもいろいろエトセトラって感じ。でも日本っぽいのは蓬莱かな。ワタシのことはそう呼んで?」
エリクサー。アムリタ。仙丹。そして蓬莱。いずれも飲めば不死になるとされる薬。異なる時代に異なる地域で異なる人々が追い求めた、同一にして唯一の願望。自らのことをそう称する降霊者とは、人智を超えたものを名乗る降霊者とは、まさか、
「上位存在······」
自然と口からこぼれていた。フレイヤの言葉に満足気に頷いた蓬莱は笑顔を見せて、
「そう。それでどうするの、フレイヤさん?」
蓬莱はゆったりと歩み寄り、教卓に頬杖をつき上目遣いにフレイヤを見つめて言い放つ。
誘うように。謳うように。楽しむように。嘲るように。
「あなたの手で、もう一度陵平くんの大切な人を殺してみる?」
「············俺、どうすればいいのかな」
俯いた鹿嶋の呟きは夜闇に沈み込み、目を覚まさない日咲は何も答えない。きっともうすぐこの街の運命に決着が着く。もしかしたら、この世界全体の運命だって決まってしまうかもしれない。フレイヤも、葛野も、富寿満も、他の隊員達も、みんな戦いに向かうのだろう。そんな中にただの高校生がいていいのだろうか。日咲に、フレイヤに、磯棟に。個人的なことで迷っている自分がいていいのだろうか。
「············どうすればいいのかな」
もう一度だけ、鹿嶋は呟いた。
「行っていいと思うよ」
明るくて、優しくて、少しだけ甘い、聞き馴染みのある少女の声がした。ずっと聞きたかった少女の声がした。その少女は鹿嶋の隣で丸椅子に座り、彼の膝にそっと手を乗せる。
「······日咲」
鹿嶋は少女の顔に視線を移す。焦茶色の柔らかい髪に、引き込まれるような黒色の大きな瞳。血色の良い薄い唇に、本人は気にしていた少しだけ太めの眉。鹿嶋が会いたかった稲森日咲がそこにいた。鹿嶋がベッドに視線を戻すと、そこには赤髪の女性はいなかった。
「陵平くんさ、迷ってるよね?実理ちゃんのこととか、フレイヤさんのこととか、それから······わたしのこととか」
「······うん」
頷くと、日咲は鹿嶋の顔を覗き込んだ。
「だったら、わたしからお願いしてもいい?」
「······うん」
すると日咲は姿勢を正し、
「陵平くん、助けてあげてほしい人がいます。まずはフレイヤさん。あの人には、誰かの助けが必要だから」
まっすぐに自分を見つめる日咲の言葉を、鹿嶋はただ聞いていた。
「そして実理ちゃん。精神位相からずっとあの子のことを見てた。あの子にはきっと陵平くんが必要だし、陵平くんには絶対にあの子が必要。実理ちゃんは、わたしから陵平くんを救うために、陵平くんと出会ったんだと思う」
「······日咲から、俺を救う」
口の中で繰り返す鹿嶋はわずかに拳を握り、もう片方の手で日咲の手を取って膝から離す。
「わかった。日咲のお願いなら、俺は行かなきゃ」
「待って」
日咲に引き止められ、立ち去ろうとする鹿嶋の足は簡単に止まる。きっとここで別れたら、もう会うことはできない。それを感覚的にわかっているから、鹿嶋の足は容易く止まる。
「もう一人いるの」
「······誰?」
「蓬莱······って言ってもわかんないよね。半年前にわたしに降りた子。あの子のことも、助けてほしい」
「······どうして?だって、あいつがいなければ日咲は今でも」
「そう、生きてたかも。だけどあの子が助けを必要としてるってことはわからなかったと思う」
「蓬莱······あいつに何があったの?」
「陶磁器戦争」
短く告げた日咲の声色が硬くなる。
「あの戦争で、たくさんの人が死にたくないって思った。歴史的に有名な人達の功績がこの位相で位相間現象になるように、多くの人の強い思いはこの位相だけじゃなくて精神位相にも影響する。だから精神位相にあの子が生まれたの。死にたくないっていうみんなの思いを叶えるために」
「······じゃあ、何もこんな方法を」
「普通そう思うよね。でもこうするしかなかった。これが一番効果的な方法だった。死への恐怖を与えることを選ぶしか無いほど、あの子を生み出した思いは強烈だった。不死の実現のために死を押しつける矛盾を通さなきゃいけないほど、あの子は切羽詰まってた。だけど、自分がどうして追い詰められなきゃいけないのかあの子はわかってない。だって、生まれたときからそれがあの子の使命だったから」
言ってから日咲は苦い表情を浮かべ、
「命を使う······嫌な言い方だよね。あの子は本当に、それだけのために生まれた。そこにあの子の意志は無い。自分の意志だと思い込んでいるだけ。そのために戦って、怖がられて、人を殺す」
「そんな、そんなのって」
顔も名前も知らない誰かの願いから生み出されて、自分のためになるかなんて考えられないまま突き動かされて、それが存在理由だからといって命を奪う。あの降霊者は他人の都合を押しつけられて、誰かの死を背負って、理解されないことが当たり前だと信じてきた。そういう女性を鹿嶋は知っている。あの降霊者は彼女と同じだった。間違いなく助けが必要だった。
「······悲しすぎるよね」
日咲は目を伏せ、そっと洩らした。
「どうして日咲はそんなことを知ってるの?」
「あの子がわたしに降りたときから、ずっとあの子の気持ちがわかるんだ。きっとあの子も、わたしの気持ちがわかってるはず。降霊者と被験者ってそんな感じだから」
「······どうして日咲を選んだの?」
「それはわからない。でも選ばれて良かった。苦しいことを苦しいと気づけないあの子に代わって、わたしが陵平くんにお願いできるから」
それを聞き届けて、鹿嶋は愚問だったと悟った。蓬莱はわかってほしかったのだ。どこかで救いが欲しかったのだ。鹿嶋が日咲に求めたものを、彼女も日咲に求めたのだ。
だから、鹿嶋はもう迷わない。
「ありがとう、日咲。俺がどうするべきかはっきりわかった。俺は行かなくちゃいけない」
「違うよ。行かなきゃいけないのはわたし」
そう言って立ち上がった日咲の手を、鹿嶋が取ることはない。それを受けて日咲は小さく微笑み、少しだけ眼を逸らし、すぐに鹿嶋と視線を重ねた。
「 」
たった四文字。鹿嶋の心に言葉を刻んだ日咲の頬を伝う大粒の涙が、射し込んだ朝陽を浴びて輝いた。その光がやけに眩しくて瞼を閉じ、もう一度開けると、丸椅子は消えていた。消毒液のにおいが微かに漂う病室で、鹿嶋は静かに目をこする。
「······大丈夫ですか?泣いていたようですけど」
尋ねられてから、鹿嶋は赤髪の女性が目を覚ましたことに気がついた。そして、もう稲森日咲は行ってしまったということを理解した。
「大丈夫です。少し夢を見ていただけですから。宮沢さんこそ、もう大丈夫なんですか?」
「······はい。傷は少し痛みますけど······でも、私も夢を見ていた気がします。何だか頑張っていて、とても苦しいのに、何で頑張らなきゃいけないのかがわからない夢。だけど途中からすごく幸せな夢に変わりました。ずっと会いたかった人と一緒にいられるような、見ていて楽しい夢でした」
「······そうですか」
呟いて、鹿嶋は丸椅子から立ち上がる。
「すみません、俺は行かなきゃいけません。お医者さんと看護師さんは呼んでおきますから、宮沢さんは体に気をつけてください」
「······わかりました」
不思議そうに応えた赤髪の女性は、きっと鹿嶋が何者かわかっていないだろう。それでもいいと思えた。鹿嶋のことなど知らない人生が、誰の都合も押しつけられることのない本来の彼女の人生なのだから。
「あの!」
病室から出ていこうとすると、急いだ声で呼び止められた。これくらい元気があれば、彼女はもう大丈夫だろう。
「······あなたが陵平くん、ですよね?」
思わず足を止めた鹿嶋が答えられない内に、赤髪の女性は続ける。沈黙は肯定と同義語。もしかしたらそう判断したのかもしれない。
「夢を見ている間、ずっとあなたのことを考えていた気がします。苦しいときも、幸せなときも、ずっと。だから頑張ってください。私に夢を見せてくれた人達も、きっとあなたを必要としていますから」
「······はい、頑張ります」
返して、鹿嶋は走り出す。
このどうしようもない物語に、終止符を打つために。
「リュック邪魔だな······もうこの上からでいいや」
一人で面倒そうな表情をした蓬莱の言葉に、フレイヤの視線は彼女が背負う茶色いリュックに誘導される。その表面から、黒い小さな翼がゆっくりと生え出していた。
「見ればわかるよね?ワタシの力は普通じゃない。思ったことを実現できる。そんなやつがこの街の人達全員を降霊者にできるようなものを持ってるんだよ?殺した方がいいと思わない?」
「······そんなこと」
吐き捨てて、フレイヤは二輪型に格納し待機させておいた飛行型を教室に突入させる。音波を即座に流すと同時に機体を赤く発光させ、蓬莱の不意を突いて退霊を狙った。
しかし。
「だから、こんなやつは殺してでも止めるべきだよ?」
蓬莱が笑うとフレイヤのカチューシャは真っ二つに割れ、長い金髪が頼りなく流れた。フレイヤの脳波が届かなくなった飛行型は制御を失って床へ落下し、音波は止まってもそのままだった赤い光が異常事態を告げるサイレンのように天井を照らす。
「ほら、早く止めてみせてよ」
促されるがままフレイヤは拳銃を取り出して、空の弾倉に弾を込めようとする。たった一発で良かった。それだけで、この危機は去る。きっとフレイヤは戦乱を沈めたヒーローとして讃えられるし、少女を殺すしかなかった悲劇のヒロインとして慰められる。今は自分しか蓬莱を止められないし、それが自分がここにいる目的。だから、弾を込めて引き金を引くだけでいい。そうすれば磯棟実理の命と引換えにこの街の人々は助かる。わかっていても、フレイヤはそうしない理由ばかりを探していた。
「······実理ちゃんを殺しても、あなたはまた降りてくるかもしれない。だから殺しちゃ駄目。それに、あなたじゃ直接殺すことができないから、鹿嶋くんの心を折ろうとしてる。だから不死を願わせるために日咲ちゃんを降霊させたし、実理ちゃんを死なせようとしてる。それがわかっているのに、私には撃てない」
「ご明察。でもそれって、結局フレイヤさんがこれ以上誰かを殺したくないだけだよね?」
「それは······そんなのそうに決まってる。戦争で周りの人が死んで、研究で日咲ちゃんを死なせて、これ以上誰かの死を背負うなんて私には重すぎる」
「······勝手な人」
呟いた蓬莱は右の翼を一気に巨大化させて横薙ぎに動かし、フレイヤの側頭部に叩きつけた。フレイヤは開きっぱなしのドアから廊下に投げ出されて柵にぶつかり、追いかけてきた蓬莱の左右整った大きさの翼が起こした風圧に柵ごと四階から空中へ吹き飛んだ。そのまま背の高い木に激突して枝に何度もバウンドしながら地面へずり落ちる。幹に亀裂が入っていくのを眺めたフレイヤが体を動かさなかったのは、全身の痛みのせいだけではなかった。
(······ここで死んでも、当然の報いなのかな)
蓬莱は直接的に命を奪うことはできない。だが彼女がこの木を折り、その下敷きになったとすれば、おそらくフレイヤは死ぬだろう。それがきっと、自分の都合ばかりを押しつける者に相応しい結末だ。フレイヤはそう直感して、仰向けのまま動かなかった。
それでも、いつまで経っても、フレイヤが死ぬことはなかった。
「······すごいね君、堕とし甲斐とかじゃなくてもう本気出すレベル」
四階からふわりと地上に降り立った蓬莱が気だるそうに言い、フレイヤは体を起こして状況を確認する。まだそんなことをしようと思っている自分に嫌気が差した。
だが、その少年は違った。
「フレイヤさん、日咲に会うきっかけをくれてありがとうございます。今度は俺があなたを助けたい」
「······でも、私のせいで君の大切な人達は」
「それでも」
鹿嶋陵平はフレイヤの前に立ち、もう一度頼む。
「俺はあなたを助けたい。磯棟を、蓬莱を、助けなきゃいけない。だからお願いします。謝罪も申し訳なさも必要ない。その代わりに俺を信じてください。俺を、信じてみてください」
自分は許されないことをした。そんなことはわかっている。
それでも、フレイヤは小さく頷いた。
「きっと、鹿嶋くんならできる。君が言うんだから間違いない。君は君を信じて」
その言葉に背中を押され、鹿嶋は一直線に駆け出した。
〈つづく〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
