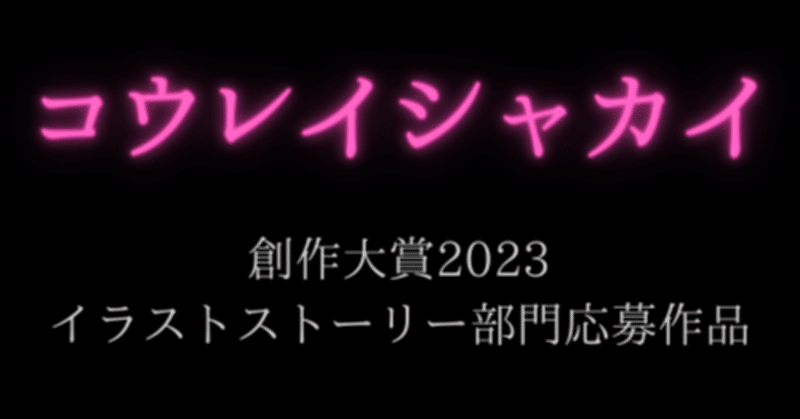
【小説】コウレイシャカイ 第二話(創作大賞2023・イラストストーリー部門応募作品)
熱の塊を押しつけられているような炎天下、睡眠不足の鹿嶋陵平は重い教科書類が詰まったリュックを背負って階段を四階まで上りきり、教室へ入る。鹿嶋の通う高校は、自由な校風と文武両道を特色と言い張るいわゆる自称進学校だ。だから八月を十日ほど残したまま授業を始めるし、大学について生徒にやたら調べさせる。だが夏休み明けの約三週間は学園祭シーズン。この期間だけは皆課せられた勉強から逃れ、貴重な青春を満喫することに全力を注ぐのだ。
それなのに。
「おい鹿嶋、お前アカツキ大学のオープンキャンパスに行ったのよな?」
「なあ、どんな感じだったか教えなさいや」
サングラスをかけたパーマ野郎と、首から安っぽいネックレスを下げたツーブロック野郎。鹿嶋が教室に入るなり、二人のクラスメイトが詰め寄ってきた。
「てめえらには学園祭を楽しもうという気概はねえのか学歴厨ども!自称進に洗脳されてんじゃねえ!」
自分が発した魂の叫びに、寝不足の頭が軋む。チンピラのような見た目の学歴厨という自由な校風(笑)が生んでしまった怪物どもを払いのけて、鹿嶋は自分の席に着いた。だが二人のクラスメイトは不満げな声を上げて、
「洗脳されてねえしな。おれが聞きたいのは昨日の事件のことよ」
「アカ大の研究所で暴動があって、研究員が全員亡くなったんだろ?お前、昨日あそこにいたんなら何か教えなさいや」
「············その話か」
鹿嶋は眠気覚ましにこめかみを揉みほぐしながら深く息を吸い、
「何も知らねえよ。というか、あそこで何かを知れたやつは今頃無事じゃないだろ」
「は〜〜〜〜っ、何か知っとけよな。降霊者と治安部隊の正面衝突があったらしいじゃねえか」
「いや、研究者が全滅する前に到着しときなさいや」
「でも降霊者も全滅したんだろ?すげえバトルだったらしいし」
「マジで物騒だよな」
「お前らどんだけねじ曲がった話を信じてんだよ。情報リテラシーは無いのか!治安部隊は間に合わなかったけど研究員にも生き残りはいるし、降霊者はこの街のどこかにうろついてんだよ!」
「「やっぱ知ってるじゃねえか」」
二人同時のツッコミを受けるが、鹿嶋としてはもうこの件を他人に話すつもりは無い。幸いにして、始業のチャイムが二人を追い払ってくれた。日本史教師が当然のようにチャイムが鳴り終わってから教室に入り、自分が遅いのではなくチャイムが早いのだと言わんばかりに今日のニュースについて悠長に語り始める。
「暴動と言うと皆さんは高校生なので聞き慣れないと思いますが、十年前の陶磁器戦争の終盤には各国で反戦を謳った暴動が発生してね、はじめは警察や軍事施設、さらには軍需工場を襲っていたんですが、やがて彼らのうちの反体制派と結びついていくつかの国で革命が起き、それがあの戦争の終結につながったという恰好になります」
(暴動ね············ありのままなんか言えないよな。昨日のこと)
教科書を開いて話を聞くフリをしながら、鹿嶋は昨日あったことを思い出す。亡き幼なじみの少女に会いたくてオープンキャンパスに行ったことすら言いたくないのに、降霊者の暴動に巻き込まれたことや、強引に特殊能力を手に入れて戦ったことなんて言える訳がない。その後も治安部隊の事情聴取を夜遅くまで受け、それが終わったら負傷の有無を調べる精密検査と称して位相間現象関係の様々な実験を行わされたのだ。結果が出るまで四時間待つと言われ、流石に帰らせてくれと頼み込んだときには既に午前三時を過ぎていた。
(めちゃくちゃ眠い。てか、真夜中だったのにフレイヤさん元気すぎだろ。研究者っていうのはみんなああなのか?いや、それとも······)
夜中に事情聴取が終わってから予備の研究所で熱心に彼の位相間現象を調べていた金髪碧眼の女性の姿が、鹿嶋の脳裏をよぎる。フレイヤ=バイフィールドが普段研究所でどのように過ごしていて、あそこにどれだけの研究員がいたのか鹿嶋にはわからないが、毎日一緒に働いていた人々を一人残らず殺されてしまったことに傷ついていない訳がない。幼なじみの少女を一人亡くしただけでも、鹿嶋は深い悲しみに呑まれた。だが数だけでいえばその何倍もの死に囲まれているはずなのに、昨夜のフレイヤはてきぱきと作業をこなしているように見えた。
(仕事をすることで悲しみを紛らわしてるってことでいいのか?そうしなきゃやってられないのはよくわかる。でも、そんなの心配すぎるだろ。俺に何かできる訳じゃないだろうけど······検査結果を聞きに行かなきゃだし、そのときに話を聞かせてもらうぐらいはできるはず)
鹿嶋は夕方にまたアカツキ大学へ訪問する約束をしている。午後まで授業があると思ったフレイヤが配慮して時間を指定してくれたのだが、学園祭期間のため今日は午前中授業だ。しかし、衝撃的な事件を体験したフレイヤを放っておいて、昼からクラスメイトとお祭り気分で準備に勤しんでいいのだろうか。ざわついた心持ちのまま、鹿嶋はノートを取り始めた。
「············結局、残ったのは始皇帝さんとスレイマンさんだけなんだ」
赤髪をポニーテールに結んだ女は広がる海を眺めながら呟くが、その声色に少しも残念そうな色は含まれていなかった。
「何人残ろうが関係無い。オレはオレの目的を果たすだけだ」
ティーンファッションに身を包んだ始皇帝は少女の細やかな黒髪を潮風になびかせ、一点を見つめている。
「だが仲間は多い方が良い。至高の帝国を維持するためには、皆が一つになる必要がある」
髭をたくわえた禿頭の男に降りたスレイマンが重厚な声で言うと始皇帝は舌打ちし、
「何だそれは、嫌味か?おいスレイマン、お前の国は六百年以上も続いたらしいな。だがオレの国はオレが死んだ後すぐに滅びた」
「······それはあなたがあまりに早く死んだからだ。反対に、私は少し長生きしすぎた。我が帝国が長らえたのも偉大な先祖が築いたものがあってこそ。それなのに私は衰えてもなお玉座に居座ったために、息子達に反乱を企てさせてしまった」
「『衰えてなお玉座に』か······お前の国の滅亡の兆しは、お前が死んですぐに現れ始めたようだな。それでもその後長い間持ちこたえたのは評価すべきことだが」
始皇帝は海風に乱された髪を片手で整えながら目を閉じ、深く息を吐く。
「もし衰えることが無く、死ぬことも無かったら、お前は玉座に座り続けるか?」
「············それが国のためになり、民が望むことであり、神がお許しになることであれば、私は永遠に我が責務を果たそう」
「············そうか」
呟いた始皇帝は数瞬の沈黙の後、目をゆっくりと開いた。
「やはり必要だ、不老不死の統治者が。オレが統一した中華も二千年以上の間にいくつもの国が興亡し、つい十年前も戦争によって強大だと思われた帝国が滅んだのだから」
「お、いいねえ。やっぱりあなたはノッてくれると思ったんだ」
赤髪の女が口の端をもち上げると始皇帝は鬱陶しそうに、
「別にお前に利用されるつもりはない。オレの力を頼っているのはお前だということを忘れるな」
「だがあなた一人では困難だ。仲間がいたほうが良い」
スレイマンの言葉に赤髪の女もうなずき、
「自由にやっていいとは言ったけど、一人だけこっち側にいてほしい人がいるんだよね。その人を迎えに行こうよ」
「なぜオレが行かなければならないんだ。勝手にしろ」
「ならば私が同行しよう。同盟を組むものには誠意を見せる必要がある。それで、その者とは誰だ?」
「エディソンさん」
スレイマンの問いに赤髪の女が短く答えると始皇帝が顔をしかめ、
「あいつは何がしたいのかよくわからん。昨日だってオレ達が外に出ようとしたときに一人だけどこかをふらついていた。あいつが加わったところで、一体何ができるんだ?」
「結局一緒に出られたんだからいいじゃん。それにあの人結構やるときはやる人だと思うし、何よりあの人の位相間現象が必要なんだよね」
「······そんなに強いのか?オレの位相間現象は刀を一本出す程度のものだというのに」
「あなた達の位相間現象はまだ馴染んでないだけで、時間が経てばきっと、あなた達が引き連れていた軍隊すらまるごと出せるようになるはずだよ」
その言葉に始皇帝とスレイマンは図らずも顔を見合わせた。大軍を率いた者として、仮に他の降霊者達が敵になったときのことを考えたのだ。両者の間を緊張が支配するが、やがて始皇帝が眼を逸らし、
「オレのことはわかった。だから早くエディソンの力を言え」
命じられた赤髪の女は安堵の息を洩らした後で眼を煌めかせて、
「それはね··················」
「段ボール足りないんだけど、誰か取り行ってくれない?」
「あと長い定規もー!」
午後二時過ぎ。クラスメイトと文化祭で発表する演劇の準備をしていた鹿嶋は大道具製作班の要望を聞きつけ、
「じゃあ俺がいってくるわ。段ボールは第四選択教室にあって、デカい定規は被服室だよな?」
「一人でいっぺんには無理じゃない?あたしも行くよ」
「サンキュー磯棟、助かる」
かくして鹿嶋は磯棟実理と共に教室を出た。展示にしろ演劇にしろネタバレを防ぐためか、どの教室もカーテンが閉められている。それでも活気と熱気を包み隠すことなどできず、学校全体が華やいでいるのを肌で感じられた。
「······ウチのクラスの演劇、あれで観客に受け入れられるのかな?」
「平安貴族版シンデレラだろ?まあ何とかなるんじゃねえの、脚本書いたやつがオリジナルの和歌まで作ってたし」
「ホント熱意がすごいよね。あたしじゃ思いつかない」
二人は階段を下り、中庭を貫く長い廊下を通って目的地に向かう。
「じゃああたし被服室行ってくるから、また合流するね」
「段ボール置き場はたぶん混んでるだろうし、先教室戻ってていいよ」
そう言って鹿嶋は磯棟と分かれ、第四選択教室に到着した。どのクラスにとっても入用のためか案の定混雑しており、今朝の日本史教師が各クラスの取り分を記録しながら段ボールを配布している。待機列の最後尾についた鹿嶋は、すぐ前に並ぶ少女から突き刺すような眼差しを浴びせられた。
「············久しぶりだな、箕篠」
「うん、久しぶりだね、鹿嶋」
箕篠麻衣。稲森日咲というもうこの世にはいない少女を巡って鹿嶋と因縁がある、細縁眼鏡をかけた一つくくりの黒髪の少女。その切れ長の目から鹿嶋に放たれる視線は、決して友好的なものではない。
「······お前のクラス、何やるの?」
「logオと∫ジュリエットdx」
「シェイクスピアを学歴厨にするな」
思わずツッコむと箕篠は苛ついた口調で、
「わたしが去年からあっためてたアイディアなんだけど」
「······もっと練れなかったの?」
「日咲は褒めてくれたよ。『面白そうだね、さすがマイマイだね』って」
箕篠の平淡な声に、鹿嶋の息が詰まった。それをわかった上で彼女は、
「······日咲と一緒にやりたかった。あの子が生きていても同じクラスになれなかったかもしれないけど、せめて日咲に見せてあげたかった。あの子と一緒にやりたいことなんてたくさんあるし、あの子にだってやりたいことがたくさんあったはず」
「それは············俺だって一緒だよ」
「あっそ」
箕篠が乱雑な返事をして、動き始めた列に合わせ二人は前へ進む。
「鹿嶋、昨日アカツキ大学のオープンキャンパスにいったらしいね。降霊研究所にいったんでしょ?」
「他のクラスにまで広まってんのかよ······」
「日咲の霊を降ろせるかもって思ったでしょ」
「············そこまでバレてんのか」
「違う。あんたの考えそうなことはわたしにもわかるってだけ。あんたが日咲の恋人なら、わたしは日咲の親友だから」
「恋人って、俺は幼なじみだよ」
「でも好きだったでしょ」
「························」
鹿嶋が押し黙ると箕篠は呆れたようにため息をつき、
「はっきり言いなよ。そうしておけば、日咲が不安がることもなかったのに。もしかしたら、死ぬことだって無かったかもしれない」
「··················かもな」
鹿嶋がようやく一言絞り出すと箕篠はすかさず、
「ねえ鹿嶋、あんたはもし日咲が生き返るとしたら、日咲に何をしてほしい?」
「俺は············俺は日咲に、一緒にいてほしい」
「あっそ············思い上がってるね」
箕篠は自分で訊いておいてそっけない言葉を吐き、
「わたしは、わたし達とは一緒にいないでほしい。もっと言えば、生き返らないでほしい」
「······どうして」
「わたしはあの子と一緒にいたい。でも、死んだ後もわたし達の都合に付き合わせるなんて嫌。死後も精神が残り続けているなら、日咲にはわたし達から自由になってほしい。だって」
鹿嶋は日咲にもう一度会いたい。それは箕篠だって同じだ。鹿嶋には、稲森日咲と過ごした日々という素晴らしい思い出を共有した者ならば、誰もがそう願うという確信がある。だが、その願いを箕篠は自ら否定しようとする。鹿嶋が目を背けたために、箕篠が彼の目の前に突きつけようとする。
「日咲が死んだのは、あんたのせいなんだから」
段ボールを抱えた切れ長の目に細縁眼鏡をかけた一つくくりの黒髪の少女がまっすぐ歩いてくるので、磯棟は思わず道を開けてしまった。それから段ボールを受け取る鹿嶋に小走りで近づく。
「ねえ鹿嶋くん」
「······おお、磯棟か」
振り向いた鹿嶋はいつも通りに見えるが、どこか声が上ずっている。少なくとも磯棟にはそう感じられた。
「さっき眼鏡かけた子と話してたみたいだけど、知り合い?」
「······ああ、うん。八組の箕篠麻衣だよ。昔なじみで去年も同じクラスのやつ」
「へー、そうなんだ」
磯棟は返事をしてから、教室に戻ろうと並んで歩く鹿嶋の横顔を見つめ、すぐに視線を逸らす。
「············どうした?」
「いや、その············」
磯棟は言い淀み、眼を泳がせる。ピンクのメッシュが入った黒髪をいじるが、いつまでも黙ってはいられない。やがて意を決して、
「盗み聞きしてたわけじゃないんだよ、ホントに。でもさ、その、八組の麻衣ちゃん?と鹿嶋くんの会話が聞こえちゃって。それで、その麻衣ちゃんって人が、『日咲が死んだのはあんたのせいなんだから』って」
「··················磯棟には関係ないよ」
「まあそう言われればそうなんだけど、でも気になっちゃて。あれ、どういうことなの?日咲って、去年鹿嶋くんと同じクラスだった稲森日咲ちゃんだよね?半年前に亡くなったっていう······でもあれは、バイト中のアレルギー発作が原因なんだよね?」
「磯棟にはどうでもいいでしょ、このことは」
「いや、その、どうでもよくは······ないよ。何というか、鹿嶋くんが誰と仲良くしてるのかなぁとか」
「関係ないって言ってんだろ」
その一言に、磯棟の心臓は凍りついた。あまりにも鋭くて強い感情が、その一言に凝縮されていた。それは敵意だった。敵意が鹿嶋の横顔に浮き上がっていて、磯棟はそれを正面から受け止めなくて本当に良かったと本気で思った。触れてはいけない部分に土足で踏み込んでしまったことに気づいたような後悔を、瞬間的に感じた。鹿嶋から向けられたその感情が、自分が鹿嶋に向けたつもりの感情とは真逆のものだったことが、磯棟にとっては大きな恐怖だった。
「··················ごめん、言い方きつかった」
「いや、そんな············あたしこそごめん」
「············そういえば」
取り繕った明るさであることは流石にわかる。それでも磯棟はまた鹿嶋が彼女に親しみやすいいつもの声で話しかけてくれたことに安心していた。
「デカい定規はゲットできたの?」
「うん。壮絶な死闘の末にね」
「何じゃそりゃ。ただのジャンケンだろ」
「ジャンケンに勝つのだって運命力が必要なんだよ!」
「運命力って何だよ······いや、『強く思えば』ってやつか」
「いや納得するんだ。昨日のオープンキャンパス、そんなに印象に残った?というか何してたの、待たせといたのに『先に帰ってくれ』なんてチャットしてきたし」
「ああ、それは······」
階段を上りきって教室に入ろうとしたところで、答えようとした鹿嶋は言葉を濁した。彼の視線の先では、昨日研究所を案内してくれた金髪碧眼の女性がグラサンパーマやチープツーブロと話している。
「フレイヤさん、どうしてここに?もしかして俺、時間間違えてました?」
(『時間間違えてました?』······って、何?鹿嶋くん、この人と約束でもしてるの?)
訝る磯棟をよそにフレイヤはにこやかに手を振り、
「大丈夫だよ鹿嶋くん。それより突然来ちゃってごめんね。ちょっと鹿嶋くんに来てもらいたいところがあって」
「来てもらいたいところ?」
「そう。でも今文化祭の準備中でしょ?だから、君の友だちに君を借りていいか交渉してたんだけど」
鹿嶋が見やるとグラサンパーマとチープツーブロはニヤニヤしながら、
「どうぞどうぞ、使えないやつですがどうにかお役立てください」
「おい鹿嶋、後で何が起きたか詳しく教えなさいや」
「使えないとか言ってんじゃねえよ。あと少なくともてめえらが期待してるようなことは起きねえから」
「勘違いするなよな?こんな美人とどっか行くんだから起きるのはお前の」
「黙れ!TPO考えろアホ!」
鹿嶋の怒鳴り声には、先ほどの激情など微塵も感じられなかった。
(······何なんだろう、あれ)
磯棟がぼんやりと考えている間に鹿嶋は他のクラスメイトにも断りを入れて、グラサンパーマとチープツーブロに段ボールを預けてフレイヤと共に階段を下りていった。
「··················行っちゃった」
校門から出ていく二人を見下ろして磯棟が呟くとグラサンパーマが、
「悪いな磯棟、鹿嶋をもっていかせちまった」
「いや、いいよ。まだ本番まで時間はあるんだから、今一人欠けても準備は間に合うし」
「そうじゃないのよな」
「············?」
磯棟が首を傾げるとチープツーブロが楽しそうに、
「おい磯棟サン、好きな男が知らない外国人美女と学校抜け出してお出かけすることに危機感を感じなさいや」
「は!?何でそういうこと言うかな!ホントにきしょいんだけど!」
磯棟が大声を上げると二人は生温かい眼差しで、
「カマかけてみたつもりだったが、やっぱりそういうことなのよな」
「ま、手遅れになる前に頑張りなさいや」
などとほほえみやがった。直後、磯棟にデカい定規でぶっ叩かれ、二人のチンピラは汚い悲鳴を上げたのだった。
アカツキ駅から直線距離で1kmほど続く飲食店街の一角にある、格安イタリアンをウリにしたファミレスのドリンクバー前。ウェーブがかった鶯色の髪の若い女性は、幼女が目の前でボタンを押してオレンジジュースを注ぐのを凝視していた。
「············おねえちゃんも、オレンジジュースほしいの?」
幼女に見上げられても鶯色の髪の女性は視線を動かさない。ただ興奮したように震える声で、
「なあ君、今度はそこのウーロン茶を注いでみてくれないか?」
「いいよ。わたしはいらないから、おねえちゃんがのんでね」
「ああ、もちろん」
幼女がグラスを設置し、背伸びをしてウーロン茶のボタンを押すのを見て鶯色の髪の女性は顔を紅潮させ、鼻息を荒くする。周りの客にヒソヒソ声で不審者扱いされても、彼女の視線は揺らがなかった。
なぜなら、彼女が釘付けになっているのは幼女ではなく、ドリンクバーの機械の方なのだから。
「で、どうしてここへ来たんですか?検査結果を聞くだけなら学校でもできたと思うんですけど······」
フレイヤのシャツと同じ空色の軽自動車から降りた鹿嶋は、目の前の建物を見て尋ねた。
「それはこれから説明があると思うよ。とりあえず暑いから中入っちゃお」
フレイヤは冷房の効いた車内から出た瞬間に噴き出た汗を白衣の袖で拭い、警備員に会釈をしてからエントランスへ入る。鹿嶋も彼女に倣って会釈をし、後を追いかけた。
鹿嶋とフレイヤがやって来たのは、治安部隊の本部だ。ここで治安部隊はアカツキ市で行われる研究を監視し、各研究所の予算が適正かを審査し、科学技術を用いた犯罪に対処するための訓練を日々行っている。治安部隊自身もアカツキ市で開発された技術を用いた装備を採用しており、昨晩事情聴取のために訪れたときにも、装備の手入れのために武器庫には明かりがついていた。
「隊長室は······こっちか」
事情聴取の部屋とは違う方向へ向かうフレイヤについていく中で、鹿嶋は何度も口を開こうとしていた。
(フレイヤさん、大丈夫なのか?今のところつらそうなところなんて見えないけど、見せてないだけかもしれないし······)
向けられた不安げな視線に気づいているのかいないのか、フレイヤは迷い無く進む。結局何も言い出せないまま、『隊長室』と書かれた表札が掲げられた扉の前に到着してしまった。
フレイヤが三回ノックをすると、どうぞ、と中から女性の声で返事があった。
「失礼します」
挨拶をして中に入ると、向かい合う革張りのソファの片方に二人の男女が、もう片方には黒いくせ毛の男性が座っていた。くせ毛の男性は昨日研究所で見た徳川家康だ。彼は他の降霊者達と行動を共にせず、鹿嶋の位相間現象の実験にも付き合ってくれた。だが男女の方はどちらも見覚えが無い。一人はフレイヤより少しだけ年上に見える、艶のある黒髪を胸の辺りまで伸ばした知的な面立ちの女性。もう一人はフレイヤと同い年ぐらいの、形のいい眉とすっとした鼻筋をもつ黒い巻き毛の男性だ。
「よく来たね。わたしは治安部隊隊長の富寿満雛菊だよ」
「現場主任の葛野剛だ。よろしく頼む」
知的な面立ちの女性と巻き毛の男性が順に挨拶した後でフレイヤが、
「改めまして、フレイヤ=バイフィールドです。アカツキ大学降霊研究所の研究員をしています」
「わしは徳川家康じゃ。授かった役職はいくつかあるが、そなたらに一番わかりや」
「「あんたには訊いてない」」
富寿満と葛野から同時に言われて家康は萎れてしまう。そんな彼を気の毒に思いながら鹿嶋も、
「俺はアカツキ東高校二年生の鹿嶋陵平です。よろしくお願いします」
「ああ、よろしく」
富寿満に勧められてソファに腰かけると、フレイヤがすぐに口を開く。
「昨晩もお話しした通り、昨日の事件の首謀者は半年前の事故の際に私が降ろしてしまった霊です。被験者である赤髪の女性についての記録は我々の研究所にはありませんでしたから、前回降霊した際にこの位相へ降りる方法を学習したのではないかと思われます」
「なら、他の降霊者も二つの位相を行き来する方法を知っているのか?」
葛野が尋ねると、フレイヤより先に富寿満が口を開き、
「その可能性は低いだろう。もしそうだったら適当な人間に降りて、いきなり研究所の外で暴れればいい」
「その通りです。現に家康さんはその方法を知りません」
視線を浴びた家康が首肯したのを見て納得したのか今度は葛野が、
「被験者である赤髪の女については現在捜査中だ。何かわかり次第報告する。それで、鹿嶋陵平と言ったか。そいつは使えるのか?」
「鹿嶋くんの位相間現象についてですが、実験を行った結果一時的なものではないことが判明しました」
「······証拠は?」
富寿満が短く尋ねるとフレイヤは家康に目をやる。家康は渋々といった表情で立ち上がり、鹿嶋の背後へ回った。そして、
「すまん」
手の中に刀を出現させ、鹿嶋の首をめがけて一気に振り放つ。刀は無防備な鹿嶋を直撃するが、その首は切断されるどころか切り傷すらつかず、逆にその皮膚に触れた刀身が消滅してしまった。それを見て富寿満は満足そうにうなずき、
「なるほど。一番の懸念点が解消されて安心した」
「それに、肌に直接でなく、鹿嶋くんが所持しているものに触れても位相間現象を消滅させられるんです」
「応用も利く訳か······期待できるな」
富寿満が細い顎に指を当てて鹿嶋を見つめるが、彼は状況をいまひとつ理解しかねていた。
「あの、俺はなぜここに呼ばれたんですか?」
「そんなの決まってるだろ」
葛野が芯の通った声で、
「お前には降霊者の強制退去をしてもらいたいんだ。退霊装置が破壊されてしまった今、ヤツらに対処できるのはお前しかいない」
「それは······降霊者達が何か事件を起こしたら、俺が現場に行って戦うってことですよね?」
「そうだ」
何のためらいも無く肯定されて、鹿嶋はひとまずフレイヤに目を向けた。降霊者達が昨日のように罪の無い人々を殺すなら、そして自分にしかそれを止められないなら、鹿嶋は戦いたい。だが、鹿嶋の意思を確認する前にフレイヤが富寿満や葛野に話を通してしまったことがどうも引っかかる。
(············いや、いいんだ。フレイヤさんにはこの状況を解決させる責任があるんだから、使えそうな駒を推薦するのは当然。それはわかってる。でも何か気になる)
若干の自己嫌悪に陥りかける鹿嶋の視線に気づいたフレイヤは、
「もちろんお礼は用意させてもらうよ」
「お礼······?」
「うん。全てが解決したら、君の幼なじみの霊を降ろす。いいですよね、富寿満さん?」
「当然だ。治安部隊としても必要経費だと思うし、治安維持に貢献してくれた者への礼は欠かせない」
形だけの笑顔を作った富寿満の発言に、鹿嶋は胸が塞がったような感覚を覚えた。頭をよぎるのは、先ほど箕篠が突きつけた言葉達。
『思い上がってるね』
『死んだ後もわたし達の都合に付き合わせるなんて嫌』
『日咲が死んだのは、あんたのせいなんだから』
(············そんなこと、わかってんだよ)
昨日までの鹿嶋なら、フレイヤや富寿満の提案に飛びついたかもしれない。だが今の鹿嶋には、日咲にもう一度会うために戦うことが、とても自分勝手なことに思えた。いや、戦わずとも日咲が死んでからの半年間、日咲に会いたいとばかり思っていた鹿嶋は、ずっと自分勝手だったのかもしれない。
「俺は············俺は戦えません」
「なぜ?」
すかさず富寿満が射抜くような眼差しで尋ねる。
「その、上手く言えないんですけど、死んだ人をこっちの都合でどうこうしていいのかなって······」
「だとよ、バイフィールド」
葛野が話を向けるとフレイヤは深くうなずき、
「鹿嶋くんの言いたいことは、降霊研究が始まった当初からずっと言われてること。それは今でも解決してない。だけど、死んでいようと生きていようと関係なく、誰かを傷つけようとしている人達を放っておけない。だから私達はやらなきゃいけない······答えになってる?」
「······なってるような、なってないような」
「とにかく」
すっきりしない鹿嶋の悩みを断ち切るようにフレイヤは一段声を張り上げ、
「鹿嶋くんは保留みたいですけど、私は現場に出ます」
「当然だ。お前には半年前からの責任がある」
「専門家は君を除いてみんな死んでしまった。できれば最前線に来てもらいたい」
葛野と富寿満が立て続けに平淡な口調で応じたのに対して、鹿嶋は動揺を抑えられなかった。
「ちょっと待ってください、そりゃ確かにフレイヤさんは専門家ですし、昨日は協力してダヴィデと戦いましたけど、元は研究員なんですよ?どうして体を張らなきゃいけないんですか」
「今言っただろ。多くの命を奪うきっかけを生んだ責任を取ってもらう」
少しの遠慮も無く告げる葛野に噛みつこうとする鹿嶋をフレイヤは手で制し、
「私は大丈夫。きちんと責任を取らせてほしい。だから止めないで」
「フレイヤさん、でも」
「鹿嶋少年」
富寿満がダーツのような声色で鹿嶋の言葉を遮り、
「バイフィールド博士が決めたことだ。君に文句を言う筋合いは無い」
(············確かにそうだ。フレイヤさんが自分で決めたこと。俺に止める権利は無い。フレイヤさんが責任を取らなきゃいけないことだし、死んだ人を生きてる人の都合で生き返らせていいのかなんて俺にはわからない。日咲が俺を動かすダシに使われていいのかなんて、わかるわけない。だけど!)
鹿嶋はフレイヤの横顔を見つめる。悲しみも疲れも滲んでいない、整った顔立ち。責任感を貼り付けられた、不安定な顔立ち。被験者が死んで、同僚が死んで、見知らぬ人が死ぬ。そんな状況を作ってしまった人間が、大丈夫でいられるほうがどうかしている。フレイヤの顔を見て、たくさんの人が既に死んだ事実と多くの人がこれから死ぬ可能性の前に彼女を一人で放り出すことなど、鹿嶋にはできなかった。
「俺も戦います」
気づけば、そう宣言していた。
「鹿嶋くん······?」
自分で鹿嶋の有用性をプレゼンしておいて、フレイヤは嬉しそうに眼を潤ませた。どうせなら最後まで取り繕ってください、と心のなかで毒づきながら、鹿嶋は富寿満と葛野に向き合う。
「死んだ人をどうこうしていいのかとか、そんな話は後回しです。俺にできることがあるなら、それは俺にも責任があるってことだ。フレイヤさんだけが背負わなきゃいけないものじゃない。だから、俺も戦います。」
「············そうか。なら話は決まったな。恋人に会えるように頑張ってくれ」
そう言う富寿満は相変わらずの作り笑顔だったが、その声色からは少しだけ鋭さが取れていた。
「一つ言わせろ」
尚も硬い声色で葛野が口を開く。
「············元々おれ達の仕事だ。おれ達にも責任はある」
「わしにもあるぞ」
「「あんたには訊いてない」」
またも葛野と富寿満から同時に言われ、ようやく口を挟めた家康はまた萎れてしまう。その様子を見たフレイヤがこぼした笑みが作り物ではなければいいと、鹿嶋は心から願った。
「では鹿嶋少年、バイフィールド博士、さっそく働いてもらおうか」
言いながら富寿満はタブレットを取り出し、画面にアカツキ駅周辺の地図とある人物の顔写真を表示した。
「アカツキ駅周辺の飲食店街で目撃情報があるこの人物にエディソンが降りている。間違いないな、バイフィールド博士?」
「はい、この人で間違いありません」
「エディソン······って、あの白熱電球とか送電システムの開発をした人ですよね?」
鹿嶋が尋ねるとフレイヤはうなずき、
「この人は最優先で保護したい。退霊じゃなくて保護ね。今後の戦いでも、きっと助けになってくれる人だから。逆に敵に回すと本当に困る」
「それは、エディソンの位相間現象が厄介なんですか?確かに電気を操るとか強そうですし」
「それもあるんだがね」
富寿満が艶のある髪を鬱陶しそうにかきあげ、
「鹿嶋少年、『発明王』と呼ばれた彼がその後半生に何の研究をしていたかわかるか?」
「··················トースターとか?」
「確かにそれもやっていたんだが、もっと長い時間を費やして、未完成に終わったものがある」
鹿嶋が首を捻るとフレイヤと富寿満は声を揃え、
「「霊界との通信機」」
「······それって、フレイヤさんがやってる」
「そう、降霊研究の先駆けだね。彼が言う『霊界』っていうのが私達で言う精神位相。でもエディソンさんがこの位相から精神位相に直接アプローチしようとしたのに対して、私達はいったんこの位相の肉体を挟んでコンタクトを取るの」
「本題から逸れているぞバイフィールド博士。ともかく、エディソンが降霊を経験したことで精神位相へのアプローチ方法を思いついているかもしれない。味方に引き込めれば退霊装置の修理改善の手助けになるだろう。だが位相間現象として既に扱える可能性だってあるから、敵の手に渡ったときのリスクは計り知れない。今ウチの隊員達が捜しているが人手が足りなくてね。捜索に加わってくれないか?」
「わかりました、行ってきます」
鹿嶋とフレイヤは立ち上がり、葛野と共に現場へ出発する。それを見送った家康は富寿満に期待の眼差しを浴びせ、
「わしは何をすればいい?」
「家康公、あなたはここにいてくれ」
「なぜじゃ?人手が足りんのであろう?」
「悪いが、あなたも降霊者の一人。現場で首謀者達と出くわした途端に裏切られでもしたら困る」
「······わしは信用されておらぬのか?」
「逆に訊くが、あなたは信用されるような生き方をしたのか?」
「それは······そなたはわしの人生を知っておるのか?」
「ああ。日本人なら大抵は知っているだろう。あなたの英雄的な側面も、食えない古狸の側面も」
「············そうか、知られておるか」
そう言ったきり考え込む家康を富寿満はしばらく眺めていたが、やがて自分のデスクに着きパソコンを立ち上げる。
「かく言うわたしも胸を張れるような生き方はしていない。そこは今も昔も逃れられない人間の課題だよ」
「······かもしれぬな」
家康の言葉を最後に、隊長室に沈黙が積もっていく。
治安部隊の隊員達と共に真夏の街を三時間ほど捜し回っても、エディソンを発見することはできなかった。脳波連動型カチューシャとリンクした四足歩行型と呼ばれる自立歩行ロボットや飛行型を駆使して駅前エリアの全ての道路を周回しても、足取りを追えない。交代制で捜索を続ける隊員達はこのまま夜まで鹿嶋とフレイヤを働かせるのを流石に気の毒に思ったのか、二人に一時間の休憩を与え、午後九時で引き上げさせると約束してくれた。暑さと空腹に負け、二人は格安イタリアンをウリにしたファミレスに直行する。
「ごめんね、安い所選んじゃって。研究者って結構貧乏なの」
席に座るなり謝るフレイヤに鹿嶋は背筋を伸ばして、
「とんでもないです、俺も金ないんで」
「ホント?なら良かった······って良くないよね、ごめん」
また謝ったフレイヤの笑顔に内心安堵しながらも、鹿嶋は彼女の心境を窺っていた。
(俺を治安部隊に売り込んだのも、一人じゃ不安だったから······ってのは考えすぎか?たぶんさっきはそれが気になってたんだけど、フレイヤさん、実際はどうなんだろう)
貧乏だと言ったわりにあれこれ頼みまくったフレイヤは、いまさら財布の中身を覗いて顔を引きつらせた。先ほどからの愉快な言動は、果たして彼女の素のものなのだろうか。
「鹿嶋くん、親御さんに連絡しとかなくていいの?」
運ばれてきたピザを切り分けながらフレイヤが尋ねた。
「俺の両親、夫婦で会社やってるんですけど、今一か月の海外出張中なんですよ。だからホントは何時まででも捜してていいんです」
「何時まででもって、疲労で倒れないでね?今日暑かったし」
フレイヤさんは疲れてないんですか。何気なく訊こうとしたがきっと否定されると思い、結局無難な質問に変えてしまう。
「フレイヤさんのご両親は何をされてるんですか?というか、ご出身はどちらなんです?」
「アメリカだよ。両親は十年前に陶磁器戦争で亡くなってるけどね。看護師だった母は西海岸奇襲作戦に巻き込まれて、海軍の父はペキン陥落戦で戦死。その頃君は小学校上がりたてぐらいだから、あんまり知らないよね。つまらない話でごめん」
気負うこと無く受け答えをしたフレイヤの遠くを見つめるような青い瞳に、小さな翳りが入り混じっていたのが鹿嶋にははっきりと見えてしまった。
「······つまらない話なんて言わないでくださいよ。フレイヤさんの、大事な人なんでしょ?」
「············そうだね。ごめんなさい」
フレイヤはよく謝る人だ。彼女と出会ったのは昨日のことだが、鹿嶋はもう何度も謝られている。だが先ほどの謝罪は、彼に向けられたものではない。それでいいと鹿嶋は思う。
「ドリンクバー行ってきます。何か欲しいのありますか?」
「えーっとじゃあ、ジンジャーエールで。無かったら何か炭酸がいいな」
うなずいて鹿嶋は席を立つ。ドリンクサーバーというらしい機械の前でジンジャーエールがあるかを確認していると、
「なあ君、ちょっといいか?」
誰かが後ろから声をかけてきた。振り向くと、ウェーブがかった鶯色の髪をした見覚えのある女性がドリンクサーバーの隣にあるコーヒーマシンを指さして、
「あれのボタンを押してくれないか?あ、カップは置かずにね」
「············嘘だろ」
「いやあ自分でもおかしな頼みをしているとは自覚しているんだが、どうも好奇心が抑えられないんだ。カップが置かれてなくてもコーヒーは注がれてしまうのかがわかれば、あの機械を分解しなくとも仕組みを調べられそうなんだよ」
「いや、そうじゃなくて」
「ん?あ、自分でやればいいじゃないかって?それはそうなんだが僕はランチで所持金を使い果たしてしまって、ドリンクバーすら頼めないんだ。まあ僕の金ではなくこの体の持ち主の金なんだが······彼女はどうも金欠だったらしい。それで協力金が出る降霊研究の被験者になったんだろうね」
「今降霊研究って言いましたよね?じゃあやっぱり······!フレイヤさん!」
鹿嶋がドリンクバーの位置から店の奥のテーブルで一足先にピザを頬張るフレイヤを大声で呼ぶと、富寿満のタブレットに表示されていた鶯色の髪の女性は目を丸くして、
「何だ、君はあの研究所の関係者だったのか。それなら良かった、ちょうど帰れなくて困っていたんだ」
唇の端から伸びたチーズをはみ出させたフレイヤはもぐもぐしながらすぐに駆け寄り、一気に飲み込んで口を開く。
「道理で街中捜しても見つからないわけだ。こんなところにいたなんて!」
「おおフレイヤさん、無事で良かったよ」
鶯色の髪の女性が、いや、昨日研究所から脱走した降霊者の一人が微笑んだ瞬間。
ファミレスの壁が爆発音と共に外側から破壊され、粉塵が舞う。店内の客が一斉に悲鳴を上げて出口へ殺到する中、ぶち抜かれた壁から二人の招かれざる客が悠然と入店してきた。
「······大砲を使うのはやりすぎたか。あやうく全員殺すところだった」
「死への恐怖を感じてもらいたいから、ワタシとしてはそれでいいんだけどね〜」
髭をたくわえた禿頭の男の重厚な声に続き、赤髪をポニーテールにした女の楽しそうな声がすっかり客のいなくなった店内に響く。出口付近の喧騒とは明らかに異質な声は鹿嶋に、フレイヤに、そして鶯色の髪の降霊者に向けられる。
「探すのに手間取ってしまった。連れて行くのにも手間取らせるな」
「迎えに来たよ、エディソンさん!」
〈つづく〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
