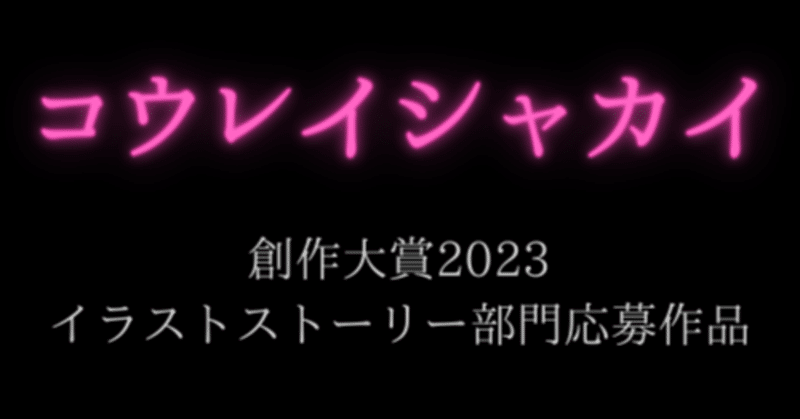
【小説】コウレイシャカイ 第三話(創作大賞2023・イラストストーリー部門応募作品)
「今からわたしに降りるのは、一体誰なんですか?」
そう尋ねる被験者の少女は、リクライニング式の柔らかな椅子に深く腰掛けていた。彼女の声色にも表情にも不安は一切無い。尋ねたのは純粋な好奇心からだろう。専門外の人間に純粋な好奇心を向けられると無条件に嬉しくなってしまうのだから、やはり自分は研究者気質だ。フレイヤはいまさら実感して少し気恥ずかしくなる。
「さっきも言った通り、『誰』っていう特定はできないかな。君にやってもらうのは、人物を指定しないで降霊を行うとどうなるのかっていう実験だから」
「そっか······じゃあメジャーな人がいいです。あと、できれば女の子がいいな」
「そう思うとそれに引っ張られちゃうから、なるべく心を無にして頑張ってほしい」
「あ、すみません。頑張ります」
肩をすぼめる少女にフレイヤは微笑み、リラックスリラックス、と声をかけて部屋の外へ出る。そこでは同僚の砧克信が既に降霊装置の電源を入れており、ガラスの向こうで椅子を倒し、ヘッドホンで耳を塞いで目を閉じる少女の様子を細かくメモしていた。
「フレイヤさん、もう始めますか?」
砧に問われたフレイヤは、この実験の責任者ということもあり少女と話していたときとは打って変わって緊張した面持ちで、
「はい。お願いします」
答えた後で、降霊装置と退霊装置が一体となった、多くのスイッチが設置されたコンポーザーを思わせる機械から角のように飛び出るマイクに顔を近づける。
「今から始めるよ。頭を空っぽにして、リラックスしてね」
スピーカーから届いた声に少女は目を閉じたまま右手を掲げ、親指を突き立てて応じた。
フレイヤは降霊装置を操作して、ガラスの向こうの部屋の温度と湿度を上げる。目標数値は室温36度、湿度80%だ。まるで風呂場のような空間にさらに操作を加えて南国に咲く花の香りを充満させ、視覚と聴覚は予め遮断しておく。室温と湿度が目標に達すれば、被験者の少女の体は霊を迎えるコンディションが整うだろう。
「······フレイヤさんは、上位存在ってやつが本当にいると思いますか?」
ガラスの向こうの気候条件が満たされるまでの待ち時間、砧が間延びした声で尋ねた。
「上位存在って、神とか天使とか悪魔とか精霊とか、そういうのですか?」
「ええ。まあ僕は外星人もその類だと思うんですけどね。UFO乗船経験者が行うチャネリングだって伝統部族のシャーマンが伺う神託だって、結局同じことをやってるんですから。あ、彼らが人間より格上だってことじゃないですよ。あくまで上の位相にいるって意味の、上位存在。で、フレイヤさんはどう思います?精神位相には人間の精神だけでなく、上位存在がいると思いますか?」
「そうですね······私はいると思います。というよりいてほしい。上位存在が私達の位相に何か影響しているなら、いつか降ろして文句を言ってやりたいです。戦争で親を奪われたり夢を諦めたりする子どもがいなくなるよう全力を尽くせって、怒鳴ってやりたい」
「なるほどー。でもフレイヤさん、怒っても怖くないですよ」
「そういうことじゃないんですって」
茶化されたようで少しムッとしながら言ったが、砧はメモを取りながらのんびりと、
「ほら、やっぱり怖くない。お、そろそろ降霊するようですよ」
機械に表示された気温と湿度は、既に目標値に達している。フレイヤはマイクに再び顔を近づけ、
「私はフレイヤ=バイフィールドといいます。あなたの名前を教えてくれますか?」
あまりにも初歩的な方法だが、こうやって確認するしかない。フレイヤが初めての試みに顔を強張らせていると、
バギンッッ!!
破壊音と共に亀裂が生じ、機械が真っ二つに分断された。
「どういうこと!?」
狼狽えたフレイヤの声が聞こえる訳がないのに、ガラスの向こうで少女が口を開く。
「ワタシが壊したんだよ」
「······あなたは誰?位相間現象は使えないはずなのに、どうやって壊したの!?」
「フレイヤさん、そんなことを訊いてる場合じゃないですよ。正体不明の降霊が反抗したら迷わず退去させる約束でしたから」
落ち着き払った砧がタブレットを操作するとガラスの向こうで壁が開き、小さな銃口が飛び出た。そこから即座に発砲された弾丸は少女の右脚を貫き、深緑色のスカートに鮮血が滲む。
しかし。
「あ、そこから攻撃できるんだ」
少女が感心した瞬間、銃口に壁ごと亀裂が走り、一気に崩壊する。そこから外へ出ようと歩き出した少女の脚の出血は、既に止まっていた。
「フレイヤさん!」
あまりに突然の事態に呆然とするフレイヤの意識を、珍しく声を荒らげた砧が呼び戻す。
「どういう仕組みで位相間現象を使えるのかわかりませんが、彼女は危険です。被験者の肉体にダメージを与えても回復されて、退霊させられません」
砧が言う間に、他の研究員達がフレイヤの元へ続々と詰めかけてきた。
「研究所内の全ての退霊装置が、突然壊れました!」
「彼女は他の降霊者の元へ向かっています!」
「フレイヤさん、判断を!」
口々に叫ばれるが、それが逆にフレイヤの思考をかき乱す。
(どうして位相間現象が使えるの?あれは一体何なの?これから何が起きるの?私はどうすればいいの?)
「フレイヤさん」
間延びした声に戻ってしまった砧に呼びかけられ、フレイヤは縋るように彼へ視線を投げかける。
「原因究明や反省なんて後からできますから、とりあえず最悪の事態だけは避けましょう」
彼が言う最悪の事態とは何か、同僚であるフレイヤには容易に想像できる。だが彼女に迫られた判断だって大人の都合を少女に押しつけた、充分すぎるほど醜いものだ。最悪と醜悪の選択が不意に訪れ、フレイヤはどんな顔をして何を言えばいいのかわからなくなる。
「あの降霊者が始皇帝の部屋に近づいています!」
不必要に怒鳴る連中は、誰も必要な措置を取らない。何をしなければならないのかわかっているはずなのに、ただわめきたてるだけだ。
位相間現象を使える降霊者が世に解き放たれてしまったら、どんな混乱が起きるかわからない。そして今は、装置を用いることもダメージを与えることもできない。ならばフレイヤが下す判断は、一つしか無かった。至極合理的で、あまりに理不尽な判断を。
「緊急時の対応については契約書通りです。被験者も同意の上で実験に参加し、協力金を受け取っています。ですから、あの降霊者が他の降霊者と接触する前に」
自分のために言い聞かせたフレイヤは懐に潜ませた拳銃に手を伸ばし、震える瞳のまま宣言する。
「被験者を殺害します」
半年前の引き金を引いた感触が、フレイヤの指先に蘇る。あのときの降霊者は赤いポニーテールの女性の姿で再びフレイヤの前に現れ、拳銃を構える彼女を見て妖しく口の端をもち上げた。まるで、嘘つきを嘲笑うように。
「あなたには撃てない。早くエディソンさんを渡してよ」
赤髪の女が言う間にスレイマンが半月刀を手の中に出現させる。拒めばどうするかは明らかだ。
それでもフレイヤは、これ以上赤髪の女に降りた降霊者の思い通りにはさせたくなかった。
「鹿嶋くん、エディソンさんを連れて逃げて!私もすぐに追いつくから!」
「待ってくれ、僕は逃げる理由が無」
「わかりました!」
エディソンが何か言う前に鹿嶋は彼女の手を引っ張り、既に誰もいなくなった正規の出口から逃走を図る。すぐさまスレイマンが追いかけようとするが、ガラスを破って突っ込んできた金属の獣の体当たりを喰らって真横に吹き飛んだ。その隙に鹿嶋とエディソンは走り去る。
「へー、殺さなきゃオッケーってスタイルなんだ」
赤髪の女に胸の内を見透かされるが、構っている場合ではない。スレイマンに激突させたもの以外にもう三体の四足歩行型がフレイヤの指示で駆けつけ、二手に分かれて赤髪の女とスレイマンをそれぞれ挟む。スレイマンは半月刀を構え、赤髪の女は動物園の客のように物珍しげな眼差しを向けた。
「ゴー!四足歩行型!」
フレイヤが叫ぶと四足歩行型は跳び上がり、牙の無い硬質な口を開く。咆哮の代わりに飛び出たのは、人間一人を覆い隠せるほど大きな網だった。磁石が練り込まれた二つの網は標的を収めるとぴったりと重なり、強固な網籠を形成する。
(こちらフレイヤ。磁石式捕縛網でスレイマンさんと赤髪の女を確保しました!)
脳波連動型カチューシャで連絡を入れるが、治安部隊が到着するまでには少し時間がかかるだろう。それまで捕縛網がもちこたえてくれるかが問題だ。
しかし。
「軍団よ、網を剥がしてエディソンを追え」
スレイマンが命ずると虚空からもやのような白い光が複数現れ、渦を巻きながら立ち昇る。それはやがて人型を形成し、色が宿り、十人以上の男達へと姿を変えた。赤い上着と白いビョルク帽を身に着けた、十六世紀における地上最強の兵士。オスマン帝国の版図拡大に貢献した、皇帝直属の戦力。腰に半月刀を携えた常備歩兵軍は速やかに三つに分かれ、一つはスレイマンを捕らえている網を引き剥がし、一つは鹿嶋達を追いかけ、残る一つはフレイヤに刀を向けた。
(自分が率いた軍隊の位相間現象をもう出せるようになったの!?)
内心驚くフレイヤは四足歩行型を操って歩兵常備軍を制圧しようとするが、それは破壊音と共に阻まれた。機械の猟犬達は全て真っ二つに分断されてしまったのだ。
(半年前と同じ。これがこいつの位相間現象!)
赤髪の女の中に潜む降霊者を睨むが、直後に歩兵常備軍が襲いかかってくる。フレイヤは靴底の反重力装置を作動させて出口方向へ一気に跳びながら攻撃をかわし、そのまま店外に脱出した。それから脳に直接届いた葛野の連絡に応じて、もう見えなくなってしまった鹿嶋達が進んだ道を辿る。葛野によれば、治安部隊が降霊者の滞在用に確保しておいたアカツキグランドホテルという駅前の宿泊施設に鹿嶋達を誘導しているらしい。
反重力ブーツのおかげで跳ねるように走るフレイヤが細い路地への入口を通過した直後、そこから二人の武装した治安部隊隊員が飛び出す。発砲許可が出ているらしく、構えた自動小銃を急接近する歩兵常備軍に容赦無く放った。走りながら後ろへ目をやると、撃ち抜かれた兵士達は血を流すこと無く体を白い光に戻して消えかかっている。
(やっぱり位相間現象であって、本当の人間ってわけじゃない。なら、迷う必要は無い!)
赤い軍服の背中が見え、その向こうに黒い短髪と鶯色のウェーブヘアも見える。フレイヤは招集した飛行型の下部から銃口を伸ばし、兵士達の背中へ弾丸を浴びせた。白い光と化して前方へ崩れ去った歩兵常備軍を突っ切り、フレイヤは鹿嶋とエディソンに追いつく。
「鹿嶋くん、グランドホテルで葛野さん達が待ってるから、そこまで敵を引きつけて確保してもらおう!エディソンさんも頑張ってついてきてください!」
「だから僕は逃げるりゆ」
「わかりました!」
ホテルまではあと300メートルほどだ。だがさらにペースを上げるフレイヤ達に、蹄が地を鳴らす音が迫る。後方を確認すると、位相間現象の白馬に跨ったスレイマンが三人を猛追していた。既にすぐには数え切れない人数にまで増加した歩兵常備軍が全速力で彼につき従っている。先ほどの隊員達は物量で押し切られてしまったのか。それとも別の道を通って来たのだろうか。後者であることを願うフレイヤに50メートル先から葛野が叫ぶ。
「急げ!追いつかれるぞ!」
「フレイヤさん、エディソンさんを抱えていってあげてください!」
鹿嶋に言われ、抱きつくような形でエディソンを抱えたフレイヤは反重力装置の出力を一気に上げる。ごく短時間しか運用できない代物なので、これでバッテリーが尽きてしまっただろう。二人はラグビーのトライのような恰好で飛び込んで葛野の背後にまわり、鹿嶋も息を切らしながらどうにか転がり込む。直後、道路脇で待機していた治安部隊達が一斉に動き出し、横一列になってスレイマンとその軍団を銃撃で迎えた。
放たれた弾丸は歩兵常備軍を次々と消滅させ、スレイマンが駆る白馬の脚に命中する。呻き声を上げる白馬と共に倒れ込んだスレイマンをさらにいくつもの銃口が狙うが、
「被験者に罪はありません!殺さないでください!」
フレイヤの咄嗟の叫びに隊員達はためらった。
「何を言ってやがる!被験者だって承知の上で実験に参加したんじゃないのかよ!」
「だけど、私はもう死なせたくない!」
「知るか、お前の都合で動くと思うな!」
葛野が噛みつき、フレイヤが歯向かう。その隙にスレイマンは大量の兵士達を突撃させ、隊員達は銃弾を浴びせ尽くす。歩兵常備軍が一人残らず消え去った、耳を裂くような暴音の後に訪れた静寂の中には、スレイマンの姿は無かった。
「······おいバイフィールド、お前のせいで取り逃がしたぞ」
苛立ちを抑えられない様子の葛野が吐き捨てたが、そんなことはフレイヤもわかっている。それでも、被験者を死なせたくなかった。例え本人が同意していて、それが確実な方法であったとしても、フレイヤは自分のせいでまた誰かが死ぬのは嫌だった。誰も死なない結末があるのなら、それを手繰り寄せてみたかった。
「エディソンさん」
被験者の女性は持久力に自信が無かったのだろうか。まだ少し息が上がっているエディソンに向き合い、フレイヤは呼びかける。
「お願いです。降霊装置の修復に、あなたの力を貸してください。エディソンさんが研究していた霊界との交信技術を、私に貸してください。このままだったら敵も味方も無関係の人も、いろんな人が死ぬことになる。そんなのは嫌だ。だからお願いします」
フレイヤの真剣な眼差しは、他の誰でもなくエディソンだけを真っすぐ捉えていた。彼女の言葉には、何の打算も下心も無かった。本当に、誰かが死ぬのは嫌だった。
それを受け止めたエディソンが少しだけ空気を吸ってから出した答えは、
「断る」
「命からがらって感じ?」
青黒い夜闇が太陽を西の彼方に追いやるのをビルの屋上から眺めながら、赤髪の女は背を向けたまま尋ねた。その声には退避してきたスレイマンに対する嘲りも失望も含まれていない。ただ、自分の発言を自分で面白がっているようだった。
「問題は無い。敵を一箇所に追い込めたのだ、あとは包囲戦のみ」
重厚な声で応じるスレイマンに対し、赤髪の女は金髪の研究員や黒髪の高校生、そして鶯髪の女性がホテルの内側へ入り、治安部隊がまた自動小銃の壁を形作るのを見下ろしながら、
「へー、自信あるね。第一次ウィーン包囲······今回のはその比にもならないだろうけど、それでも頭数は足りるの?スレイマンさんの兵士はさっき全滅しちゃったっぽいけど」
「案ずるな、我が軍団の数は十二万。まだそのごく一部を呼び寄せているに過ぎない」
スレイマンが言った瞬間、ビルの麓で白い光のもやが群れをなして立ち昇る。赤い上着と白いビョルク帽の兵士が瞬く間に道を埋め尽くすのをフェンスから身を乗り出して見下ろした赤髪の女は口笛を吹き、
「さっすが壮麗帝。キリスト教世界を震撼させた功績は伊達じゃないね。多くの人に認知されてるからこその出力だよ」
スレイマンが生み出した常備歩兵軍は整然とした動きで一つの生き物のように宵闇の中を蠢き、三本向こうの道路にまで及ぶ幾重もの包囲網を形成した。即座に銃弾の波が押し寄せ、最前線の兵士達は霧散する。
だが、十二万という兵力はたった四十人ほどの治安部隊の前では無限に等しい。現在スレイマンが現出しているのは三千人程度ではあるが、それでも定期的に突撃させて敵の残弾を枯らすには充分すぎる人数であった。それは向こうもわかっているのだろう、治安部隊は発砲をやめて各々の盾を横につなげ、ホテルから前方20メートルのところで防衛線を張る。しかし四方からやけに黒い輝きを放ついくつもの移動式砲門がホテルに照準を合わせており、赤髪の女はその手際の良さに思わず拍手を送った。
「まずは挨拶だ」
スレイマンは屋上の淵まで歩み寄り、地上の兵士に向けて片手を上げる。
そして、青黒い闇を揺さぶる轟音が放たれた。
ゴドッッ!!
腹の底に叩きつけられるような衝撃音がホテル全体を突き抜け、鹿嶋はすぐさまエディソンにあてがわれた部屋を飛び出した。長い廊下の奥、本来シミ一つ無い手入れの行き届いた壁があるはずの場所は粉々に破壊され、まだほのかに陽光の面影を残す外の景色が覗く。
「おい、無事か!?」
叫びながら、プロテクターを装備し自動小銃を握る葛野が駆け寄ってきた。鹿嶋達がいる六階まで走ってきたのだろうか、大粒の汗が額に浮かんでいる。
「俺は大丈夫です!フレイヤさんとエディソンさんは部屋にいます!」
言いながら鹿嶋は扉を開け、葛野と共に中に入る。エディソンはソファに腰掛けており、フレイヤはカーテンに隠れながら外の様子を窺っていた。
「ここは包囲されてる。さっきのは敵が砲弾をぶちこんできやがったんだ。チッ、どうなってやがんだよ。千人単位で敵がいるぞ。」
葛野が言うとフレイヤは、
「これほど位相間現象の出力が高いとは思わなかった······葛野さん、スレイマンさんが全盛期の軍団を全て出せるとすれば向こうの人数は最大十二万人です。流石にそこまでの数を瞬時に出せるとは思えませんが、ここにいる治安部隊は何人ぐらいですか?」
「俺を含めて四十八人、そのうち四十人は外で張ってる。残弾数に余裕はねえし、この建物の側面まではカバーできてねえ。増援は今要請したが、充分な戦力が揃うまでに二十分はかかるだろう。バイフィールド、位相間現象に弱点はないのか?」
「あります」
フレイヤは窓の外から鹿嶋達の方へ視線を移し、
「特定の映像と音声を流して、視覚と聴覚を通じ位相間現象を維持できない状態にします。もしかすると、スレイマンさん本人ではなくあの兵士達が目や耳にしても消滅させられるかもしれません。本人の意思に関わらず体が反応してしまえば維持できなくなったり、空気の振動や温度などに左右されたりするのが位相間現象の弱点ですから」
「そうか······だが、どうやってこの大人数にその映像や音声を届けるんだ?」
するとフレイヤは再び窓の外に目を向け、
「幸いここは駅前で、向かいのビルに大型モニターがあります。あれを使いましょう」
「なるほど。この包囲網を突っ切ってあっちのビルに渡り、映像を切り替えなきゃって訳か」
そう言って葛野はため息をついた。それを受けフレイヤは強張った声色で、
「······頼めますか?」
「やるしかねえだろ。やってやるよ」
口の端を上げる葛野を見て、フレイヤも力強くうなずいた。
「二十分ですね?それまでに映像と音声を完成させます」
「当たり前だ。お前の責任を果たせ」
言葉を交わしたフレイヤがパソコンを開き、葛野が外へ出ようとしたそのとき。
二度目の轟音と衝撃が、建物全体を襲った。
「また砲撃か!」
葛野が舌打ちすると、彼の無線機からノイズ混じりの報告が入る。
『今度は八階と九階が攻撃されたようです!』
『それと、敵から矢文が送られてきました!「エディソンを渡さないなら五分おきに砲撃を行う。引き渡せば直ちに我が軍を撤退させよう」と!』
「八階と九階だと?クソッ、一般客が避難してるフロアだぞ!」
葛野は歯噛みしてからエディソンを睨みつけ、
「おいあんた、バイフィールドを手伝え!」
「まさか、彼女がやっているのは降霊者を退霊させる準備だろう?僕の霊界通信研究は未完成なんだ、彼女一人の方がよっぽど捗るよ。それにさっきもフレイヤさん達に言ったが、なぜせっかくこの世に帰って来られた僕が自分から進んで精神位相に戻ろうとしなくてはならないんだ?僕にはやらなきゃいけないことがまだあるのに」
「やらなきゃいけないことだと?だったら尚更手伝えよ。敵の手に堕ちたら、それもできなくなるかもしれないんだぞ!」
「君達のところにいてもそれができるとは思えないがね。どうせ君達でも敵でもやらされるのは降霊装置や退霊装置の修理改善だけだろうし、僕はもう靈界分野の研究をする気は無いよ。だから逃げる理由が無いと言ったんだ」
そう言ってエディソンは立ち上がり、葛野を押しのけて部屋を後にした。
「······あんなやつに構ってる場合じゃねえか」
吐き捨てて葛野も部屋を去る。残されたのは鹿嶋とフレイヤだけだ。
(······フレイヤさん、やっぱりてきぱきしてる。葛野さんに言われたことだけじゃなくて、半年前からのことも気にしてるのか)
パソコンに向き合って黙々と作業を進めるフレイヤを見つめる鹿嶋には、じっとしていることなどできなかった。彼女が自分の責任を取ろうとしているなら、自分は日咲の死の責任をどう取ればいいのか。どの面を下げてまた日咲に会いたいなどと言っているのか。わからないのが嫌で、鹿嶋はとにかく動きたかった。
「俺、もう一度エディソンさんを説得してみます」
言い残して鹿嶋は背を向ける。
「うん、わかった」
たったそれだけ呟き、フレイヤは鹿嶋を送り出した。
「······時が経つのが遅く感じる」
思わず洩らした家康に富寿満は鉄のような表情で、
「申し訳無いが、あなたの暇つぶしになるようなものはここには置いていないんだ。この部屋には将棋盤なんて無いし、この街では鷹狩りなんてできない」
「鷹狩りか、懐かしいのう」
力なく笑う家康には取り合わずに富寿満は無線機を口に近づけ、
「本部より各班、直ちにアカツキグランドホテルにいる葛野主任達の援護に向かえ。敵はホテルを包囲している。葛野主任達は反撃方法を有しているため、それが遂行されるよう合図をしたら一斉に奇襲をかけて敵の注意を引きつけろ」
同じ内容をもう一度繰り返し、富寿満は無線機を置いた。それからすぐに家康の眼差しに気がつく。
「······フレイヤ達は危機にあるのか?」
「そのようだ。だがあなたが出る必要は無い」
「わしだって軍勢を引き連れていくことはできる。敵に囲まれておるのだろう?ならば援軍は多い方が良い」
「駄目だ」
「信じてくれ」
「さっきも言ったが、あなたの生き方は信じられるようなものではない。ここで大人しくしていてくれ」
「それはできぬ!」
家康は声を荒げるが、その顔には険しさよりも弱々しさの方が色濃く現れていた。
「確かにわしの生き方は信に値せんことはよくわかっておる。信じてくれた者を裏切り、慕ってくれた者を身代わりにし、頼ってくれた者を踏みつけにした。だが、だからこそ!そうやって生き抜き、そして死んだからこそ!今度ばかりは世話になった者を助けたい!一度死んだからこそ、自らが生き残るためでも敵を倒すためでもなく、他の者を助けるために戦いたい!だから行かせてくれ!わしを助けに行かせてくれ!」
「············素晴らしい演説だな」
富寿満は短く嘆息し、椅子にもたれかかった。言葉と裏腹に硬い表情を崩さない彼女の瞳の奥に何があるのかはわからないが、家康は決して目を離さずただ一心に彼女を見つめている。
そして、富寿満は小さく笑った。
「今は戦力が欲しい。敵の武器は近代化されたものではないから、あなたの軍が有効だろう」
「······ということは!」
「家康公、協力を要請する。引き受けてくれるか?」
「ああ、承知した!」
答えるや否や家康は勢いよく部屋を飛び出し、外へと駆け出す。玄関を出た直後に位相間現象の馬に跨がり、戦場へと急いだ。
〈つづく〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
