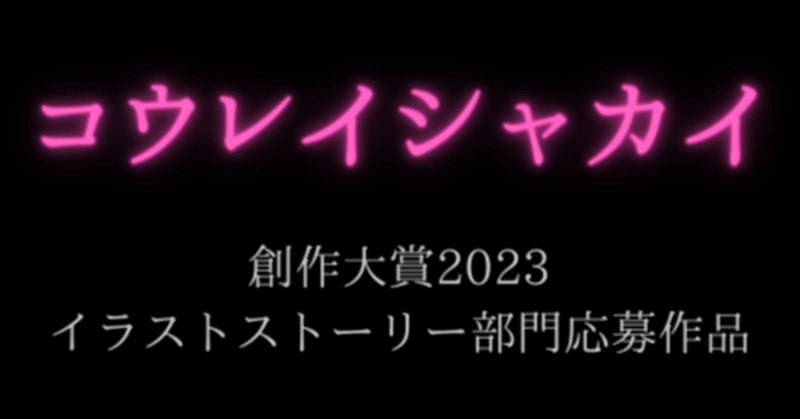
【小説】コウレイシャカイ 第七話(創作大賞2023・イラストストーリー部門応募作品)
「······ってことがあって、絶対あたしのこと意識してるじゃんって思わされたらすぐにやっぱそうじゃないかもってことが起きるんです。もう訳わかんないですよ!」
バスを降りながら磯棟はまくし立てるが、宮沢は一言も文句を言わずに静かに話を聞いてくれた。『市営団地前』という何の捻りも無いバス停の傍では既に人だかりができており、治安部隊が規制線を張って市民に逃げるよう言い聞かせているが効果は皆無だ。
「出遅れちゃったか。せっかく来たのに画面越しの方がよく見えるね」
言いつつも少しも残念がっていない宮沢はスマホを取り出しながら磯棟の顔を覗き込み、
「実理ちゃんが話してくれたから、今度はワタシが話す番。陵平くんと仲良しな女の子のこと、知りたいよね?」
「知りたいですけど······鹿嶋くんが話したがってないことを聞いてもいいんですかね」
「いいんだよ、ワタシが勝手に喋ることだから。それが自然と実理ちゃんの耳に入ってきちゃっただけ」
宮沢はバス停のベンチに腰掛け、自分の隣のスペースを手で叩く。促された磯棟が座ると背筋を伸ばして、
「稲森日咲ちゃん······は知ってるよね?」
「はい、名前だけは。それと、半年前に亡くなったって」
「うん。陵平くん、日咲ちゃんのことが好きだったんだ。でも日咲ちゃんが死んだのは自分のせいだって思ってる。だから陵平くんは日咲ちゃんのことを気にして、実理ちゃんと仲良くするのにも罪悪感みたいなのがあるの」
「······じゃあ、日咲ちゃんに鹿嶋くんは何をしたんですか?」
磯棟が恐る恐る訊くと宮沢は笑って、
「それはワタシにはわかんないな。ワタシは人づてに陵平くんの気持ちを聞いてるだけだから、その子が言いたくないことは知らないの」
「人づて?宮沢さんは占い師とか霊媒師とかやってるんですか?」
磯棟の質問に宮沢はついに吹き出した。磯棟が何がおかしいのかよくわからないでいると、宮沢は彼女の肩に優しく触れる。
「ワタシはむしろそういう人達に聞かれる側。でも結局、ワタシと実理ちゃんは同じなんだよ?誰かが言いたくないことは知らないし、教えてくれる人を捜さなきゃなんだから」
「······?」
「ワタシのことはよくわかんないままでいい。だけど、陵平くんに関してはそうもいかないでしょ?」
言いながらこちらに向けられた宮沢のスマホには、上空から見た市営団地が映されていた。治安部隊が交戦しているのはわかるが、その味方、あるいは敵はどう見ても現代日本の者とは思えない。
「ただの立て籠もりじゃないの?」
目を丸くする磯棟に宮沢は画面の隅を指さして、
「これ、陵平くんだよね?」
そこでは何十もの人に囲まれた三人の人物が立ち回っていた。一人は長い金髪の人物。一人は銃をもった黒髪の人物。そして、夏用学生服で拳を振るう人物だ。
「何で、どうして鹿嶋くんが!?」
「わからないなら行ってみようよ。ワタシもついていくから」
その提案に、磯棟は一瞬たりとも迷わなかった。申し訳程度に取り付けられたバス停の屋根の下から飛び出し、鹿嶋がいる辺りまで外周を駆ける。背負ったリュックがぶらぶらと揺れて鬱陶しい。市営団地の敷地は植え込みによって外部と仕切られているが、それをくぐってしまえば中に入ることは容易いだろう。幸いにして正面入口ほど警備が厳しくはないらしく、規制線も張られておらず見張りもいない。
「意外とゆるいね。まるで入ってくれって言ってるみたい」
宮沢の声に磯棟はうなずき周囲を見回す。それからすぐに宮沢がいないことに気づいた。
「あれ······?」
宮沢を呼ぼうとした瞬間に兜を被った男が目の前に現れ、磯棟は潰れた悲鳴を上げる。だが直後に首筋に強い衝撃を感じて、磯棟の意識は途絶えた。
治安部隊と家康軍は合わせて五千人ほどの戦力なのに対して、音波反響センサーによれば敵軍は一万に及ぶ大軍だ。通常の銃器に加えて空気圧縮型風圧切断機などの現代装備を有しているとはいえ、倍近い人数差にこちらは苦戦を強いられている。だが葛野が感じていたのは危機感よりも違和感だ。
(敵の初動が速すぎねえか?位相間現象は瞬時に出せるとはいえ、俺達が仕掛けようとしたときには既に大勢敵がいた)
そこまで考えたとき、自動小銃で王兵を薙ぎ払う葛野の通信機に通信が入る。
『こちらL班、K班と共に人質を救出しました!』
「諒解した、誰一人傷つけさせずに帰ってこい!」
葛野は命じながら刀をかわし、弓を引いた敵を撃ち抜く。だが通信機の向こうからは切迫した声が届いた。
『葛野さん、敵の数が多すぎます!待ち伏せされていました!我々の行動を予期していたようです!』
「何とか耐えろ!俺達もすぐに援護に向かう!」
葛野は叫ぶが、ただでさえ人数差がある状況でこの戦場を抜け出すことなど不可能に近い。
「クソッ!」
吐き捨てる葛野に、さらに王兵が迫る。撃てども撃てどもキリが無く、一向に先へ進めない。葛野が敵を蹴りつけながらマガジンを取り替える隙に、弓手が彼に狙いを定めた。
(対処できねえ!)
葛野が歯噛みし、ある程度の負傷を覚悟したとき。
彼を狙っていた弓手の全身に、何本もの矢が突き刺さった。
(······銃弾ではなく矢だと?)
訝りながらも弾を装填し、葛野は再び王兵を撃ち抜いていく。目前の敵を一掃し、銃声が一瞬だけ止んだ。それでも争乱は未だ彼の周りを取り囲んでいるが、
「早く助けに行け!」
その叫びだけは一直線に耳に飛び込んできた。
「すまねえ!ここは任せたぞ!」
応えた葛野は他の隊員達を引き連れて駆け出し、一度だけ声の主を確かめる。
そこで戦っていた男は、治安部隊の一員ではなかった。彼は金と銀の輝きを放つ鎧に身を包み、左手の盾で敵の刃を防ぎ右手の刀で霧散させていた。
(あれは······誰だ?)
未知の男を放ってこの場を離れていいのか。葛野が迷った数瞬の内に男は次々と王兵を斬り伏せていき、彼が進んだ跡から白い光の渦が立ち上る。それらが金の兜を輝かせる戦士達に姿を変えたのを見て、葛野は彼が降霊者の一人であることを理解した。
「私は君の敵ではない!無関係の人々が脅かされるのを止めたいだけだ!」
戦いながら叫んだ男の言葉に嘘は無い。葛野はそう直感したし、その直感を信じてみたかった。
「俺だって同じだ!」
その言葉を託して、葛野は新たな戦場へ急ぐ。今度はもう確かめることなど無かった。
「鹿嶋少年、バイフィールド博士、先にダレイオスの部屋へ向かえ!わたしもすぐに追いつくから、それまでは待機しておくんだ!」
襲い来る王兵を撃鉄のない特殊な銃で消滅させていく富寿満の指示に、鹿嶋は素直に頷けなかった。富寿満の銃がどのような武器なのか知らないし、誰が情報を敵に流しているかわからない状況下で訊くのも得策ではないだろう。それでもこの人数差の戦いで彼女一人を置いていくなど考えられない。フレイヤも同じことを考えているのか血相を変えて、
「駄目です、私も残ります!だから鹿嶋くんは先に行って!」
「何言ってるんですか、俺だけ行くなんて!」
「鹿嶋少年」
歯向かおうとする鹿嶋の言葉を富寿満は重い声で遮り、
「ダレイオス捕縛班も会敵してその対応に負われているらしい。逃げようとするヤツを押さえられるのは君だけだ」
「······わかりました」
憤りを押し潰した鹿嶋は暴れるように駆け出し、行く手を阻む王兵を消し飛ばしていく。どれだけ斬られても刺されても無傷でいられる自分が、体よく安全な場所に誘導されたのが後ろめたかった。それでも、命の危険を伴って戦っているフレイヤや富寿満が自分に向けてくれた優しさを、無視することなどできなかった。
「どいてくれ!」
鹿嶋は心に詰まったやり切れなさを吐き捨てて立ち塞がる王兵達を突っ切り、階段を何段も飛ばしながら五階まで駆け上がった。長い共用廊下に出てからは息を殺して歩き、部屋番号を目だけで確認していく。ダレイオスの部屋は階段から六番目の部屋だ。徐々に近づいていく鹿嶋の心臓が緊張に急かされ始め、いよいよ到着したところで、
『506 磯棟』
その一瞬だけ、確実に停止した。
(············は?)
意味がわからなかった。
その表札が、同姓の誰かである可能性を真っ先に考えたかった。磯棟という名字がありふれたものではないことはわかっていた。それでもただの人違いであることを願わずにはいられなかった。
敵がドアを挟んだ向こう側にいるかもしれないが、そんなことは問題外だった。鹿嶋はすぐにスマホを取り出し、磯棟に電話をかける。長いコール音の後で、無機質な不在通告が垂れ流された。
(······富寿満さん、すみません。でも行くしかない)
鹿嶋は念のためスマホから作戦本部に発信し、ポケットにしまってからドアノブに手をかける。予想通り鍵は開いていて、誘い込まれていることは瞬時に判断できた。玄関には女性向けのスニーカーがあった。毎日学校に行くと必ず目にする、自分の上の靴箱に入っているものだ。何が仕掛けてあるかわからないが土足で踏み入りたくはなかったため、悪手と知りつつも鹿嶋は靴を脱いで3LDKの部屋に進み入る。
廊下の左右に部屋が一つずつあって、右側だけ扉が開いていた。正面の扉はおそらくキッチンやリビングダイニングにつながっているのだろうが、そちらは閉まっている。だがクーラーの冷気がはみ出しており、誰かがいるのは明らかだ。ひとまず鹿嶋は右側の部屋へ忍び入り、すぐにそのことを後悔した。
あまり使っていないのか、様々な教科の問題集が積まれた勉強机がある。その隅には、その周りだけがきちんと整理された写真立てがあった。そこに飾られているのは二人の人物。一人はピンクのメッシュが入った黒髪と、ほんのわずかなそばかすの少女。もう一人は黒髪短髪で、少しだけ吊り目な少年。楽しそうに笑う二人の高校生が、修学旅行のときの磯棟と鹿嶋であることなどわかりきっていた。スマホで撮影した自分との一枚を、わざわざ印刷して部屋に飾っている。そんな磯棟を想像した鹿嶋の胸を、罪悪感が深々と貫いた。
(ごめん)
心の中で呟き、鹿嶋は一気に振り向いて拳を突き出す。そこでは王兵が刃物を突き出していたが、切っ先が鹿嶋の腹に触れると同時に彼の拳が敵の顔面を捉えた。
だが今の鹿嶋では、位相間現象の王兵がカッターナイフを持っていることへの違和感に気づけなかった。
鋭くて硬い感触を感じて前方の白い光から腹部に目をやると、ピンクの柄が入ったカッターナイフが落下していくところだった。それは床に当たると軽く跳ね、刃先が靴下の上から左足を引っ掻いた。足の痛みを感じてから、ようやく腹の出血と刺痛に意識が向く。
「············ッ!」
何てことは無い。ただ、位相間現象の王兵に実物のカッターナイフを刺されただけ。自分はかわいらしい刃物一つで簡単に傷つけられるただの高校生。そんなやつを巻き込まざるを得なくなったフレイヤや富寿満の憂慮は正しかった。そのことを今更痛感して、先ほどまでとは真逆の後ろめたさが鹿嶋の心を覆った。
(それでも······俺は助けたい)
鹿嶋は痛みを噛み殺して足を進め、リビングの扉を開ける。
目の前の光景を心が拒んだが、理性でねじ伏せて直視した。
椅子に縛られた磯棟実理の喉に、三編みの少女が包丁をあてがっている。
「鹿嶋くん、血が······!」
自分が危機的状況に置かれているときに涙声で他者の心配をするような少女が、どうしてこんなことに巻き込まれているのか。降霊者とか治安部隊とか研究員とか幼なじみとか、そんなことは一切関係無い磯棟がどうして恐怖に晒されているのか。鹿嶋は沸騰しそうな頭を必死に落ち着けて、三編みの女に語りかける。
「ダレイオス、刃物を下ろしてその子から離れろ。その子は何も関係無い」
父親を廃位させて王座を手に入れた古代オリエントの覇者が、ただの高校生の言葉を聞くなんてあり得ない。だから鹿嶋は磯棟に向けて言ったつもりだった。自分が怯まずに対峙することで、磯棟を少しでも安心させたかった。
しかし、
「そうか、ならば」
ダレイオスは手の中で包丁を弄びながら磯棟から離れ、あまりに素直な反応に鹿嶋は戸惑う。
(どういうつもりだ······?)
訝る鹿嶋の表情を見たダレイオスは小馬鹿にしたような口ぶりで、
「離れろと言ったのはお前だろ。それより、この部屋の住人でも人質に取ってくれば多少有利かもしれないと思ってこの娘で遊んでみた訳だが、まさか鹿嶋陵平の知り合いだとはな」
そこまで言って磯棟を見やり、彼女の背後に王兵を現出してその首筋に刃をあてがわせた。
「······どうして俺を知っている?」
「偉大な王の元には自ずと情報が集まるものでな。この街の住民を王の耳目とすることができるんだ。当然、治安部隊の中にも無自覚の内に私の脳と情報を共有している者がいる」
「それでこっちの動きが知られてたのかよ」
鹿嶋が吐き捨てるとダレイオスは愉悦を湛えた眼で彼の爪先から頭頂まで舐め回し、
「おい鹿嶋陵平、お前は少し元気すぎるな」
「······?」
「何言ってるの!鹿嶋くんはあんたのせいで刺されてるのに!」
磯棟が怒鳴ると、王兵が彼女の顎を掴んで強引に黙らせた。それを横目で確認したダレイオスは再び口を開く。
「鹿嶋陵平、お前も人質になれ。現状降霊者に対する直接的な有効打はお前しかいないんだろう?だったら希少価値はそこの娘よりもはるかに高い」
「······だったら、俺を人質に取って磯棟を解放しろ」
発言を封じられた磯棟がくぐもった声で何かを訴えるが、それに構うことはできない。何の関係も無い少女が危険に晒されるよりも、そっちの方がずっと筋が通っている。
だが、
「馬鹿か?この娘とお前の両方を交渉材料にした方がいいに決まってるだろう。難なら、たかだかこの国の一部と交換するのにどこまでの人命を惜しむのか試してみてもいいぞ」
ダレイオスはどこまでも高慢に要求を押しつけてきた。そればかりでなく、
「で、さっきからお前は元気すぎると言っているんだ。お前と殴り合えば私も退霊させられるかもしれないし、人質になるならもっと弱っていなければいけないだろう。私はお前の言うことを聞いたんだから、お前も私の言うことを聞け」
そう言いながら鹿嶋に近づき、応戦しようとした鹿嶋が磯棟を押さえる王兵を見やって動きを止めたのを確認すると、手持ちの包丁で鹿嶋の腹を深々と突き刺した。鋭い痛みが腹を爆心地にして全身を駆け抜けた直後、ダレイオスは適当に包丁を引き抜いて放り捨てる。傷口から鮮血が吹きこぼれ、鹿嶋は膝から崩れ落ちた。必死に視線をもち上げるとくぐもった叫びを上げる磯棟の潤んだ瞳とぶつかったが、
「もっとだ」
赤色が瞬く間に広がるカッターシャツの上から土足のままの爪先を腹にねじ込まれ、鹿嶋はついに激痛に叫んだ。そのギザギザした声と磯棟の嗚咽が入り交じったリビングダイニングでダレイオスは満足げな表情で舌打ちし、
「うるさいぞ」
苦痛に歪んだ鹿嶋の顔面に横蹴りを浴びせて薙ぎ倒し、さらに血塗れの腹を踏みつける。走り屋がアクセルを踏むように、快楽に溢れた眼差しで足に体重をかけていく。
「がっ、ぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ!?」
のたうち回ることすら許されない鹿嶋をしばらく堪能したダレイオスは不意に足を離すと、軽い足取りでキッチンへ向かった。それから収納棚をいくらか漁り、両手に何かを持って戻ってくる。それらを目にした磯棟が泣きながら言葉にならない声で懇願するが、ダレイオスはそれすらも楽しんでいるようだ。
「おい娘、こいつがどうしてここまで頑張るのか、さっき話しただろう?それをわかった上でこいつが痛めつけられるのを見るのはさぞ切ないことだろう」
「何だと······?あんた、磯棟に何を言った?」
「ただの事実だよ。それより鹿嶋陵平、柑橘類の皮剥き器とおろし金、どっちが素晴らしいことになると思う?」
「············!」
「答えないのは両方使っていいということだな?」
ダレイオスは鹿嶋の腰元へ皮剥き器の刃を突き立て、足先へ向けてゆっくりと動かす。刃は夏用スラックスを簡単に貫き、王は鹿嶋の脚に血の筋が作られていくのに連れて彼の喉から粗い叫びが飛び出るのを聞いていたが、ふとその手を止めた。
「······そのポケット、スマホとかいうのが入っているな?本部につないでいるのはわかっているぞ」
ダレイオスは皮剥き器を手放して鹿嶋のポケットへ手を突っ込み、スマホの通話を切る。それから少しの間目を閉じて、
「どうやらこの部屋のすぐ外に治安部隊が来ているらしいな。厄介な援軍もいるらしい。もしかしたら、私を確保するために突入してくるかもな」
『王の耳目』となった人々からの情報共有を受けていたのだろうか、目を開けたダレイオスは先ほど放り捨てた包丁を手に取り、
「そうなると鹿嶋は邪魔だ。今すぐ殺さなくてはな。ああ、そうだ」
ダレイオスの中でどういう思考経緯があってその結論に至ったのかはわからない。だが、確実に楽しんでいることだけは確信できる。
「なあ死ねよ、鹿嶋陵平。お前が死んだらその娘は殺さないでおいてもいいぞ?」
「······そうか」
ダレイオスの囁きに、鹿嶋は安心していた。
(死ぬのが磯棟じゃなくて、俺で良かった。俺は元々日咲を死なせてるんだ。これ以上誰かを死なせちゃ駄目だし、日咲が死んだときから俺も死ぬべきだったんだ)
ダレイオスが鹿嶋の体を押し転がして仰向けにする。それから馬乗りになって逆手に包丁を持ち、鹿嶋の喉に狙いを定める。
(俺がどうにかして時間をかけて死ねば、富寿満さん達が突入するまでの時間を稼げる。そうすれば、磯棟が助かる可能性も高まる。死んでも日咲には会えないだろうけど、今はそれでいい)
振り上げられた刃先が鈍く光るのが、鹿嶋にははっきりとわかった。
「俺が死んで磯棟が助かるなら、それでいい」
あるいは、小学三年の春だったか。
『陵平くん!あたし書道習いたいんだけどさ、一緒に行かない?』
あるいは、小学六年の夏だったか。
『陵平くん!運動会の応援団、一緒にやってみない?』
あるいは、中学三年の秋だったか。
『陵平くん!あと半年だけ勉強頑張ってさ、一緒の高校目指さない?』
あるいは、高校一年の冬だったか。
『陵平くん!修学旅行、一緒の班で行かない?』
他にも、日咲が誘ってくれたことは数えきれないぐらいあった。日咲のおかげで自分の世界が広がったことはたくさんあった。
だから、どんなときでも鹿嶋の答えは決まっていた。
『日咲がやるなら俺もやるよ』
そして、日咲の応えも決まっていた。
『ありがとう。いつもあたしのお願い聞かせちゃってごめんね』
半ばルーティンのようなやり取りを、高校に上がってからはグラサンパーマやチープツーブロに『愛の再確認』と揶揄されることもあった。日咲がそういうつもりで言っている訳ではなかっただろうが、鹿嶋の答えは本心だった。
それでもある冬の日、日咲は鹿嶋に言った。
『陵平くんってすごいね』
『······なんで?』
『だってさ、誰かに何かをお願いされたら、それをやろうとするじゃん。あたし以外の人からのお願いでもさ』
『そんなの、意識したことなかった』
『······意識したことないんだ』
日咲の言葉にどうも含みがあるように感じ、鹿嶋はすぐに己を恥じる。日咲はただ純粋に鹿嶋を認めてくれただけに過ぎないのだろうから。
『陵平くんはさ、そういう陵平くんのままでいてね。誰かを助ける陵平くんのままで』
そう言って家に入る日咲を見送った次の日、日咲は死んだ。何かを伝えるなら日咲が自分に何かを伝えてくれたあの日しかなかったのだと、鹿嶋は後になって悟ったのだった。
(······俺でも一丁前に走馬灯なんか見るのか。しかも、全部日咲のことが思い浮かぶだなんて)
刃先が一直線に迫ってくるのが見えた。腹からの出血は止まらず、灼熱のような痛みは治まらない。
『誰かに何かをお願いされたら、それをやろうとするじゃん』
磯棟が泣きわめき、必死にもがくのがわかった。鹿嶋の脳裏をよぎる声は、もう日咲のものだけではない。
『他人を死なせないために自分は死んでもいいだなんて甘い考えは捨てろ』
気づけば、振り下ろされたダレイオスの手首を掴み取っていた。
『誰も死なずにこの問題を解決できるように、私と一緒に戦ってください』
刺痛を無視し、腹に力を込めて勢いよく上体を起こす。そのままダレイオスに頭突きを喰らわせて体の上から振り落とし、強く睨んで立ち上がった。
「俺は、日咲が認めてくれた『そういう俺』のままでいたい······!」
「何を······言ってるんだ!」
怒鳴り散らすダレイオスに目配せされ、王兵は刃物を引いて磯棟の喉を切り裂こうとする。
だが鹿嶋はそれを許さない。
ダンッ!と床を踏み鳴らした瞬間、磯棟を押さえていた王兵が白い光となって消滅した。その光景を数瞬遅れて理解したダレイオスがもう一度王兵を現出しようとするが、さらに鹿嶋が床を蹴り出すと光の渦は跡形もなく消え去った。 ダレイオスは包丁を捨ててリーチの長い持ち慣れた刀を現出するが、そんなものに鹿嶋を斬り伏せられる可能性など無い。あっさりと刀を打ち破った鹿嶋はダレイオスに肉迫し、拳を放つ。辛うじてこれを避けたダレイオスが後退すると、鹿嶋は真横にあるインターホンの通話ボタンを押し込んだ。
「ダレイオスは人質を殺せない!だから来てください!」
鹿嶋が叫んでから治安部隊が突入してくるまでに、ほんの数秒のラグも無かった。玄関から一直線に駆けつけてきた富寿満や他の隊員達が銃口を突きつける前に、ダレイオスは舌打ちしながらベランダに躍り出てそのまま飛び降りる。誰も死なせないという絶対条件が破られる不安に駆られた鹿嶋が身を乗り出すと、ダレイオスが馬に乗って空中に石造りの道を生み出しながら逃げ去っていくのがわかった。
「まさか『王の道』······このままじゃ逃げられる!」
「いや、逃さない」
追いかけるために玄関へ向かう鹿嶋と入れ替わるようにベランダへ進み出た富寿満が、撃鉄のない銃にスコープとグリップを取り付けて彼を制した。
「鹿嶋少年、よく頑張ったな。後はわたしに任せろ。ここからヤツを狙撃して行動不能にする」
「でも、風圧切断機の影響で照準が定まりにくいんじゃないですか?」
「問題ない。あまりに便利すぎるがゆえに隊長にしか使用許可が降りていない装備があると言ったな」
鹿嶋が頷くと富寿満はスコープを覗き込みながら、
「それがこれだよ。電磁波ライフルだ。第二次大戦時に日本軍が電磁波を用いた殺人兵器を実用化しようとしていたのは有名な話だろう?今では電子レンジに姿を変えているがね。ともかく、これは直線距離で2キロまでなら射程範囲だ」
「でも、殺しちゃ駄目だ!そしたらフレイヤさんが」
「だから、行動不能と言ったろ?」
富寿満はなだめて引き金を引いた。音は出なかった。硝煙も無かった。その代わりに電磁波がダレイオスの下半身に命中し、それが全身に作用したのか王は落馬して道を転がった。そして、その石造りの道すらも消え失せた。
「下ではバイフィールド博士が待機している。エディソン氏の助力で開発した簡易退霊装置でヤツを無力化し、拘束してくれるだろう」
「······俺も行きます」
「結構なけがのようだが、まあいい。死なない程度に好きにしろ」
「はい、ありがとうございます」
ベランダから他の王兵を狙撃する富寿満の元を後にし、鹿嶋は玄関へ急いだ。磯棟の姿は既に無かった。隊員達に保護されているのだろう。
階段を転がり落ちるように下ると傷口が悲鳴を上げたが、黙殺する。地上に着いて駆け出そうとした瞬間、誰かに手を引っ張られた。
「ごめん、痛かったよね······?」
「······磯棟」
目を赤くした磯棟の背後では隊員達が警戒態勢を敷いているが、誰も鹿嶋と視線を合わせようとしなかった。ただ磯棟だけが鹿嶋の手を取り、その眼差しを受け止めようとしている。
「さっきのダレイオスって人とか治安部隊の人とかから、大体の事情は聞いた。鹿嶋くんがあのオープンキャンパスの日から、大変なことに巻き込まれてるって」
「······うん」
「それと、今日あたし、学校休んだ鹿嶋くんに電話するのためらった。なのに、鹿嶋くんはあたしのこと心配して電話かけてくれた······出られなくてごめん」
「あんな状況だったし、そんなのしょうがないよ」
「それと、ダレイオスが言ってたけど、鹿嶋くんは日咲ちゃんのために戦って、フレイヤさんのことを助けようとしてるって」
「それは······そうかもしれない」
磯棟の揺れる瞳に自らの眼差しを重ねようとしても、上手くいかなかった。視線を落とすと、磯棟が鹿嶋の手をさらに強く包むのがわかった。
「······鹿嶋くん、まだ行かなきゃいけないの?刺されて、蹴られて、切られて、それでもあたしを助けてくれたのに、まだ戦いに行くの?」
「······うん」
「それって、日咲ちゃんのため?フレイヤさんのため?」
「違うよ」
咄嗟に顔を上げた鹿嶋の眼差しは、磯棟の眼を通じて彼女の心に届いたような気がした。それから紡がれる、今にも泣き出しそうな少女への答えは、鹿嶋の本心だった。
「磯棟を泣かせたやつを、許せないってだけだよ」
鹿嶋は磯棟の手をゆっくりと引き離し、踵を返して走り出す。
自分のせいで涙を流した少女を、置き去りにして。
(私がこんなところで這いつくばるはずが無いんだ、私がこの世界を治めなければいけないんだ、私の思い通りにならなければいけないんだ!)
突如として襲ってきた痛みすら感じるほどの足の痺れのせいで、ダレイオスは地を這っていた。今は何とか逃げ延びて、再起のチャンスを窺わなければならない。
しかし。
「ダレイオスさん、お疲れ様」
王の行く手を塞いだのは赤い髪をポニーテールにした若い女、ある少女に『宮沢佳奈美』と名乗った人物だ。
「いいところに来た、この場からひとまず私を逃がせ」
「うーんとね、その前にまずはお礼を。あなたのおかげで陵平くんと実理ちゃんがワンステップ進めたし、これで堕とす準備ができてきた。ありがと」
「堕とすだと?」
「そう、精神的にね。肉体的に殺そうと思っても誰かさんの強い祈りがあるからなかなか死なないと思うよ、陵平くんは。『位相間現象を消す』っていう能力も一人きりの精神力じゃ無理だし、『強く思えば自分以外のものに影響を与えられる』とはいっても一定の精神力が必要なんだから、それを補えちゃうぐらいの陵平くんガチ勢には困っちゃうね。あ、そういえば何で陵平くんが直接触れずともあなたの位相間現象を消せたかわかる?」
「それは······なぜだ?」
「わかってないんだ?だったらこれからのワタシ達にはついてこれない。さよなら、ダレイオスさん。知りたかったらフレイヤさんにでも教えてもらってね」
そう言って宮沢は楽しそうに笑い、背中から飛び出た翼をはためかせて飛び去っていった。その後ろ姿に歯噛みするダレイオスの耳に、
「ダレイオスさん」
若い女性の毅然とした声が飛び込んでくる。
「もう終わりです。私の四足歩行型からは退霊用周波数の音波を流していますから、もう位相間現象を出すことはできません」
「フレイヤ=バイフィールド······!」
カチューシャをかけた金髪に白衣の女性は、自動小銃を構えた隊員達を引き連れてダレイオスに向き合う。
「勝手に呼び出しておいて都合が悪くなったら追い払うのか?弄ぶのも大概にしろ!」
ダレイオスは激昂するのに対してフレイヤは極めて落ち着いた声色で、
「それはあなたが誰の命や尊厳も弄んでいないというなら正論です。でもそうじゃない。自分の都合で鹿嶋くんを傷つけて、あの人の友だちを傷つけて、この団地の人みんなを傷つけたあなたが、訴えていいものじゃない」
「······貴様っ!ふざけるなぁぁぁぁぁぁっ!」
ダレイオスは痺れる両脚で何とか立ち上がり、フレイヤに掴みかかろうとする。被験者のことを考えると、どうせ発砲されないということはわかっていた。思うように進めず、武器も出せない。それでも体一つあれば目の前の女を殺すのには充分だろうと確信していた。抵抗されたとしても、何とか一矢報いてやろうと思っていた。
だが。
「やっぱり来ちゃったんだ」
「······はい。すみません」
「いいよ、君なら来るって思ってたから」
相手を無意識の内に自らの耳目とできるダレイオスは、かえって自分が聞いた声や自分が見ている顔が信じられなかった。刺して、蹴って、切りつけたはずの少年。今すぐにでも手当を受けるべき、立ち上がることさえ困難なはずの高校生。一歩下がったフレイヤに立ち位置を譲られた鹿嶋陵平を前にして、ダレイオスはついに動けなくなった。
「なぜだ······?」
「······俺は俺が触れている物にも位相間現象を消す力を付与できる。『あの部屋全体に触れている』というように認識を拡張させたから、お前の位相間現象を消せたんだ」
「そうではない!なぜお前はここに立っていられるんだ!?」
ダレイオスが狼狽えると、血塗れの鹿嶋は小さく笑う。
「何でだろうな」
直後。
鹿嶋の拳が顔面に突き刺さり、ダレイオスは白い光となって消え去った。
〈つづく〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
