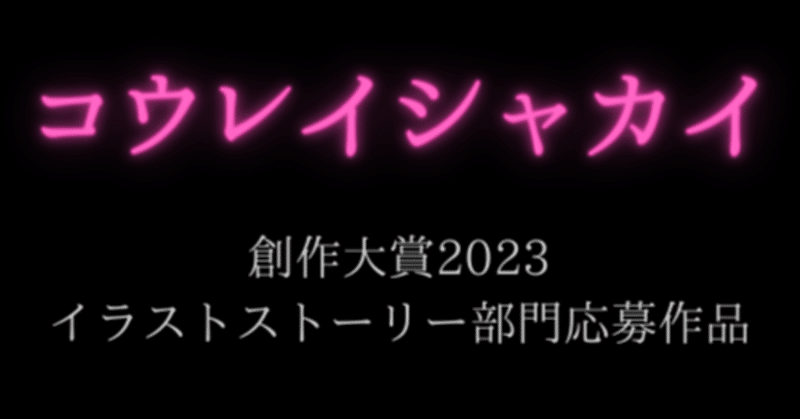
【小説】コウレイシャカイ 第六話(創作大賞2023・イラストストーリー部門応募作品)
箕篠麻衣が通う高校の学園祭は文化祭と体育祭を三日間にまとめたもので、八クラスで構成された各学年から一クラスずつ集まった合計八つのブロックが優勝を争う。体育の部のブロック演技は特に配点が高く、学園祭期間はほぼ毎日練習時間が設けられるのだ。そのため生徒達は午前の授業が終わると各ブロックの色をベースとしたデザインのブロックTシャツに着替え、一時間半ほどの午後の練習が終わると制服に戻って下校したり部活に出たりクラス企画の準備を続けたりする。
その日の練習を終えた箕篠は、できるだけ日陰を通りながら女子更衣室に辿り着いた。更衣室は他のブロックの生徒と共用であるためかなり手狭だ。お喋りをしながら着替える少女達の隙間を縫うように進んでロッカーから自分の荷物を取り、どうにかスペースを見つけたときだった。
「ごめん、一緒にここ使っていい?」
箕篠に話しかけてきたのは、ピンクのメッシュが入った黒髪の少女だ。少しだけそばかすのある顔はかなり整っており、箕篠は同じく美少女だった稲森日咲を思い出す。そういえばこの少女も鹿嶋陵平と仲がいいようで、何度か彼と一緒にいるのを見かけたことがあった。箕篠が見つけたスペースにはまだ余裕がありそうだったし、これだけ混雑しているのだから断る理由は無い。
「いいよ、使って」
「ホントに?ありがとう」
少女は荷物を置くとタオルで汗を拭き、それから爽やかな香りが染み込んだボディシートを腕や脚に滑らせていく。箕篠もボディシートで身体を拭き始めると少女がためらいがちに、
「あの······箕篠麻衣ちゃんだよね?八組の」
「そうだけど······?」
箕篠が訝ると少女は慌てて、
「ああごめんね、あたしは三組の磯棟実理」
「三組······ああ、鹿嶋からわたしのこと聞いたんだ?」
「うん。ごめんね急に話しかけちゃって。麻衣ちゃんと話してみたくて」
「わたしと?」
「うん。さっきGブロの練習チラッと見たんだけどさ、麻衣ちゃん、すっごくダンスキレキレだったね!Gブロの中で一番カッコよかったよ」
「それは褒めすぎ。まあウチはダンス部いないからちょっとコツがわかると目立っちゃうの」
言いながら箕篠は桃色のブロックTシャツを脱ぎ、後ろに手を回してボディシートで背中も拭いていく。
「実理ちゃん、だったよね。あなたがわたしに話しかけるなんて、てっきり鹿嶋······というか日咲絡みかと思った」
「えっとね······鹿嶋くん、その子のことはあまり話したくなさそうだった。だから麻衣ちゃんから聞くのもやめとく」
「······そっか」
予想は外れたが、悪い気はしなかった。磯棟は純粋に箕篠に興味をもって話しかけてくれたということなのだろう。日咲との出会いもこんな風に向こうから話しかけてくれたのだったと懐かしくなり、ふと冷たい考えが箕篠の頭をよぎる。鹿嶋はあれだけ大切にしていた、ついに言葉には出さないままだったが大きな存在だったはずの日咲から、たった半年で磯棟に乗り換えてしまったのではないか。段ボールを取りに行って鹿嶋と言葉を交わしてからの一週間、かなりの頻度で鹿嶋と磯棟が一緒にいるのを目撃したが、それはそういうことなのではないか。
「麻衣ちゃんはこの後クラス準備?」
「うん。脚本書いたのわたしだし」
「脚本書いたんだ、すごっ」
言いながら磯棟が黄色いブロックTシャツを脱ぎ、何となしに彼女の身体へ目をやった箕篠は思わず固まってしまう。出来物もかさつきも無い滑らかな肌は、肩から胸の裏にかけて赤土色に変色していた。箕篠の視線に気づいた磯棟は気軽な口調で、
「ああこれ?小さい頃に火傷しちゃって、痕が残っちゃって。でもあんまり気にしてないかな······って普通びっくりするよね、これ見たら。あたしも前までは嫌だったんだけどさ、不慮の事故っていうの?あたしが着替えてるところに鹿嶋くんが入ってきちゃって、これを見られたの。すごく気まずかったんだけど、『誰にでも抱えてるものがあるから普通のことだよ』って言ってくれて、楽になった。あ、そのときはもちろん追い出したよ?後から思い返してみてって話」
「そう······だったんだ」
なぜか自慢げに語った磯棟に応えながら、箕篠の中でほんの少しの意地汚さが暗雲のように湧き上がった。磯棟には何の落ち度も無い。だが日咲の死の要因である鹿嶋がこうもあっさりと他の女に乗り換えることが、箕篠には許せなかった。だが何も知らない磯棟は明るく、
「やっぱ八組も気合入ってるよね〜。あたしもクラス準備しなきゃ。最終下校ぎりぎりまで残って時間潰さなきゃだし」
「時間潰し?」
「うん。あたしが住んでるとこでね、何か昼前ぐらいから立て籠もり事件が起きてるんだって!それで避難指示が出てて帰れないの」
シャツを着た磯棟はスマホの画面を箕篠に見せる。そこでは災害や事件・事故の情報を市民にリアルタイムで共有するアカツキ市の緊急連絡システムからのメッセージが表示されていた。それを受けてシャツのボタンを留め終えた箕篠はスカートを手に取りながら、
「なら鹿嶋の家に泊まればいいのに」
「は!?ちょっ、何言ってんの!?いや、親が海外出張でいないとか言ってたけどさ!そもそも鹿嶋くん今日学校来てないし!」
急に顔を赤くした磯棟に、箕篠は心の中でため息をつく。少なくとも磯棟は鹿嶋を憎からず思っていることが察せられてしまい、どうしても棘で小突いてやりたくなってしまう。
「実理ちゃんが鹿嶋のこと気にするのは構わないけどさ」
スカートのフックを留めるが、この猛暑の中で下に体操ズボンなど履いていられない。足元に下ろしたズボンを屈んで回収しながら箕篠は告げる。
「あいつ、浮気性だよ。他の女の子とすぐ仲良くするし」
すると磯棟はかわいそうなほど不安げな表情のまま凍りつき、口をぱくぱくさせてしまった。
(······あなたのことだけどね)
乾いた視線を向ける箕篠は、磯棟が金髪碧眼の研究員を思い浮かべていることなど知らない。
「じゃ、またね実理ちゃん」
着替え終わった箕篠は、再び少女達の隙間を縫うようにして更衣室から外に出る。うだるような暑気がすぐにまとわりついてきたが、箕篠の気持ちがどうにも晴れないのは決してそのせいではなかった。
「······作戦については以上だ。他に連絡のある者は?」
市営団地の入口に張られた災害救護用の大型テントの内側。長テーブルを囲んでいる治安部隊の班長達や鹿嶋とフレイヤ、家康を見回して富寿満が尋ねると葛野が手を挙げる。
「さっき報告があったんだが、あの赤髪の女の身元が判明した。宮沢佳奈美、十九歳。美容師の専門学校に通っていて、アカツキ植物園のトロピカルドームでアルバイトをしている。おそらくやつの仕業だろうが、やつに関する映像証拠が尽く消されていた。だから特定に時間がかかっちまったんだ」
「トロピカルドーム······それって、南国の植物を育てるために温暖湿潤な環境を維持しているってやつですよね。半年前にあいつが降りてきたときと同じコンディションです」
フレイヤの言葉に富寿満はうなずき、
「おそらく一連の行動は宮沢佳奈美の意思ではない。彼女もまた謎の降霊者に乗っ取られているんだろう。不幸にも降霊の条件が整ってしまったということなのか······?」
「フレイヤさん、長期間の降霊で被験者の精神が乗っ取られるって言ってましたよね?それは目安としてどれぐらいがタイムリミットなんですか?」
鹿嶋が尋ねるとフレイヤは重々しい声色で、
「理論上三週間とされてるけど、前例が無いからまだわからないね······でも例外はあると予想されてる。あまりにも降霊者の自我が強いと、すぐに乗っ取られるかもしれない」
「三週間か······」
伏し目がちに呟く家康の表情は暗く、焦りを帯びていた。駅前での包囲戦から一週間、フレイヤとエディソンが協力して大規模な退霊装置の開発に取り掛かっていたが、早期にそれが完成したとしても家康は事件が全て解決するまでの重要な戦力として活動を許されている。だがあまりに長く降霊状態を維持していると、被験者の精神を乗っ取ってしまう。そのことは彼に自分とは別種の重圧を与えているのだろうと鹿嶋は思った。
「一刻も早く事件を収束させなければならない。そのためにも、この事件を解決しよう」
富寿満の言葉に皆がうなずく。立ち上がってテントを後にし、それぞれの戦場へ向かった。
今日に限ってクラスメイト達は手際が良く、何だか早めの解散ということになってしまった。磯棟はこれといってやることも無いため、立ち入りができないとわかっていながらも帰宅するしかなくなる。午後四時半だと言うのにまだ高い位置から照りつける太陽を恨めしく思いながら最寄りのバス停でスマホをいじっていると、ふと鹿嶋の顔が頭に浮かんだ。
(······いや、かけてみる?)
学校を休んだ鹿嶋に電話する。たったそれだけのことを踏み出せない自分がむず痒い。だが先ほどの箕篠の言葉は無視できない。逡巡した磯棟が結局画面を切ろうとしたそのとき、
「かけちゃえばいいじゃん」
「ひにゃあ!?」
横合いから突然声をかけられて思わず変な声が出てしまった。慌てて目をやると、赤い髪をポニーテールにした若い女性が磯棟のスマホをガン見している。その顔にどうも見覚えがあって記憶を手繰っているうちに女性は、
「気になってるんでしょ?ならかけなよ」
「え、と······いや何見てるんですか!というか誰ですか!」
スマホを体に引きつけて画面を隠した磯棟が大声を出すと赤髪の女は楽しそうに笑いながら、
「ごめんごめん、気になっちゃって。ワタシは······宮沢佳奈美。うん、そういうことにしといて」
「み、宮沢さん······?あ、あたしは磯棟実理です」
軽く頭を下げると宮沢と名乗った女性はまた笑って、
「いい子だね、実理ちゃんは。ワタシは偽名かもしれないのに」
「偽名?」
尋ねる磯棟にはっきりと答えることはしなかった。
「ワタシ、前に実理ちゃんに会ったことあるんだよ?先週アカツキ大学で。まあ会話すらしてないけど」
「あ、やっぱり。あたしも宮沢さんの顔、どこかで見たことあるなって」
「でしょ?不思議だよね、話したことも無いのに印象に残ってるんだから」
宮沢が言う間にバスがやって来て、二人は涼しい車内に乗り込む。帰宅時間にはまだ早いせいか席はどこでも空いているのにも関わらず、宮沢は当然のように磯棟の隣に座った。
「······宮沢さんはどこまで乗るんですか?」
「市営団地だよ」
「え、あたしもです!でも立て籠もり事件が起きたとかで避難指示が出てて、家に入れないんですよ」
「あー、住んでる人は大変だね。ワタシは見学のつもりで行くのに、何かごめん」
謝る宮沢の口元は、楽しそうに緩んでいる。
「お互い印象に残ってるのは、やっぱ陵平くんと縁があるからかな」
「ど、どうして鹿嶋くん?鹿嶋くんとどういう関係なんですか······?」
「そういう実理ちゃんこそどういう関係?あ、ワタシは実理ちゃんが思ってるような関係じゃないよ?だから聞かせてほしいな」
さっき話し始めたばかりなのに、宮沢の距離感が近すぎる。頭ではそうわかっていながらも、磯棟は不思議と心地よさを感じていた。先ほど箕篠からもたらされたむず痒さも、話してしまえば解消するかもしれないと思えた。
「あたし、鹿嶋くんが好きなんですけど······」
初めて声に出した自分の気持ちに、顔が燃えるような錯覚がした。それでも宮沢なら聞き入れてくれる気がして目を向けると、あんなに楽しそうに笑っていた彼女は真剣な表情で磯棟の言葉を待っていた。
それを知ってしまうと、もう話さないことなどできなかった。
「鹿嶋くんの気持ちがわかりません」
アカツキ市営団地は、七百メートル四方の区画に立ち並ぶ十六棟の建物に3LDKの部屋が詰まった大規模な集合住宅だ。鹿嶋とフレイヤ、そして富寿満の三人はその裏手から敷地内に入り、第12棟を目指している。
「······葛野や家康公が正面から切り込んでいるようだ。わたし達も急ごう」
撃鉄の無い特殊な形状の銃を腰のホルスターに携えた富寿満が物陰から様子を窺い、敵がいないことを確認すると鹿嶋とフレイヤを先導して少しずつ目的地へにじり寄る。白衣とブーツにカチューシャという恰好のフレイヤは二機の四足歩行型を伴わせ、夏用学生服の鹿嶋は手ぶらだ。
鹿嶋達が向かっているのは第12棟、ダレイオス一世が潜伏していると思われる一室だ。ダレイオス一世は位相間現象の王兵達を従えて市営団地を乗っ取り、ここを拠点にして他地域の占領を画策しているらしい。早い段階で通報があったために治安部隊が事態に気づきダレイオス軍を追い込んでいるが、彼らは三十人ほどの住民を人質に取って市営団地を含むアカツキ市の一部地域の支配権を与えるよう迫ってきたのだ。だが音波反響や熱源探知といった複数のセンサーを組み合わせて人質がどこに囚われていて王兵がどこに構えているのかを突き止め、救出部隊が動くのに合わせて葛野達が正面から突っ込み敵戦力を集めている。
「あの建物の五階、真ん中の部屋だ」
鋼鉄のように表情を崩さない富寿満が端的に告げ、鹿嶋は固く息を吸った。三人が目指すのは人質の救出でも王兵の殲滅でもない。自軍を制圧されて逃亡を図るダレイオスの確保だ。だがそれも専任の班があるため、あくまで鹿嶋とフレイヤは詰めの詰めという役回りになっている。
「······富寿満さんは隊長なんですから危険な現場に来なくてもいいんじゃないですか?」
鹿嶋が言うと富寿満は相変わらずの落ち着き払った顔で、
「隊長にしか使用を許されていない装備がある。それが必要かもしれないからな。あとは君達のお守りだよ。『誰も死なせない』というのは、もちろん君達も含んでいるんだろ?」
「······それは、できればそうがいいですけど」
「約束しろ」
鹿嶋が言い淀んだ瞬間、富寿満の声に怒気が込もった。その整った顔立ちは張り詰め、その静かな眼差しの奥はふつふつと沸き立っている。
「他人を死なせないために自分は死んでもいいだなんて甘い考えは捨てろ。そんなやつは誰も助けられないからな」
「······わかりました」
「わかったなら構わない。気を引き締めていくぞ」
そう戒めて視線を目的地に戻す富寿満は、必死に怒りを消し去ったのだ。鹿嶋はそう感じたが、今は何も言えない。
「······位相間現象の反応があります」
四足歩行型に搭載されたセンサーの数値をカチューシャで受信していたフレイヤが報告すると腰の銃に手を伸ばした富寿満が短く、
「数と場所は?」
「数は百ほど!場所は······ここです!」
叫んだフレイヤが顔を上げた直後、数え切れないほどの白い光のもやが渦を巻いて立ち昇る。それらは瞬時に人型を形成し、鉄や黄銅や木材や獣皮、様々な材質の兜を装備した兵士達へと姿を変えた。
「不死隊······!まさか残りは葛野さんや家康さん達とぶつかってるの!?」
「どうして俺達を?救出隊はどうなったんだ?」
フレイヤと鹿嶋が言う間に王兵達は刀や弓を構えた。機械と拳。攻撃される前に二人はそれぞれの武器で一番近くの敵を一掃するが、すぐに新たな王兵が迫りくる。
不死隊。アケメネス朝が誇った精鋭部隊は、一万人が一斉に突撃することにより倒せども倒せども敵は彼らの進軍を止められないという逸話からそう称される。鹿嶋達を襲撃したのはそのごく一部に過ぎないだろうが、三人で相手をするには充分すぎるほど脅威だ。だが王兵達の動きに鹿嶋はかすかな違和感を覚える。
(殺しにきていない?赤髪の女やスレイマン達とは別行動っていう予想だけど情報は共有されていて、それで俺を避けているのか?でもそれだとフレイヤさんにも本腰を入れていない理由がわからない。まさか!)
「富寿満さん!」
鹿嶋は敵を殴り抜きながら叫ぶ。視線を走らせると王兵達が我先にと富寿満に詰めより、彼女の姿は見えなくなっていた。
「鹿嶋くん、富寿満さんが!」
四足歩行型から弾丸を発射して王兵を消し去っていくフレイヤの声にうなずき、鹿嶋は道を塞ぐ敵を押しのけていく。
しかし。
「どうやら敵はわたしを狙っているらしいが」
王兵達が胸を押さえて次々に倒れ込み、白い光のもやとなって霧散していく。鹿嶋にはその光景がスーパースターが登場する際のスモーク演出に見えた。そう思わせるほど、特殊な銃を構えて直立する富寿満の姿は優美さと迫力に満ちていた。
「応戦する分には問題は無い」
そう言って富寿満は鹿嶋に銃口を向け、引き金を引く。乾いた音もわずかな煙も立たなかった。だが即座に、鹿嶋の背後にいた王兵がもやと化した。
「真に問題なのはなぜわたしを狙うのかということだ。わかるか、鹿嶋少年?」
尋ねる間にも富寿満は一歩も動かずに撃鉄の無い銃で次々と敵を消滅させ、泥臭く拳を振るいながら鹿嶋は答える。
「大将首を獲るため、ですよね!」
「おそらくな。二千年以上も昔の人間が考えそうなことだ。だが治安部隊隊長の顔ぐらいネットを使えばわかるだろうが、わたしが現場にいることまではわからないだろう」
「それでもこの人数で富寿満さんを狙ってきたってことは······」
フレイヤはその先をためらったが、富寿満は容赦なく踏み込む。それが自分の務めだと言わんばかりに。
「情報が漏れている。我々の内の誰かが、裏切っているかもしれない」
〈つづく〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
