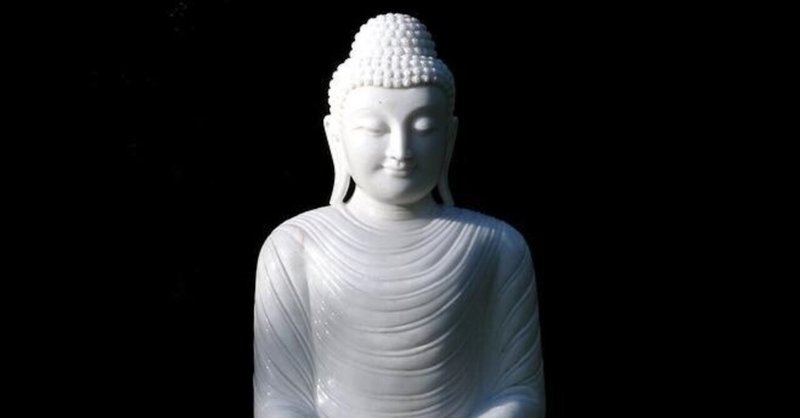
【原始仏教】六根(六処)
○正根と扶根(扶塵根)
扶根:
現代で言う原子から成り立つ物質次元の感覚器官です。肉体が有する感覚器官であり、眼で言うならば、角膜・水晶体・網膜などから成り立つ器官となります。
正根:
意成身が有する霊的な感覚器官です。真の感覚器官としての能力は扶根ではなく、正根が有します。仏教で説く「根」はこの正根を指し、六根に分けられます。六根とは「眼根・耳根・鼻根・舌根・身根・意根」です。
○命根(寿命)と六根
釈尊:
「友よ、次の五つの感官は異なる領域、異なる活動範囲があり、互いの活動領域を経験することがありません。即ち、眼の感官(眼根)、耳の感官(耳根)、鼻の感官(鼻根)、舌の感官(舌根)、身の感官(身根)です。友よ、異なる領域、異なる活動範囲があり、互いの活動を経験することがないこれらの五つの感官の拠り所は意(意根)です。また、意がそれらの活動領域を経験します。
友よ、次の五つの感官があります。即ち、眼の感官、耳の感官、鼻の感官、舌の感官、身の感官です。友よ、これら五つの感官は寿命(命根)によってとどまっています。寿命は熱(業生の火)によってとどまっています。熱は寿命によってとどまっています。寿命と熱の関係はまさに火における光と熱の関係と同様です。」
「この身体に関して、智慧豊かな人は説きたまう。三つのものを離れたならば、色形あるもの(肉体)は、捨てられたものであると観じよと。その三つとは寿命と熱と識とです。もしも、この三つが身体を離れたならば、身体はうち捨てられて横たわり、精神のないものとして、他者の食物となる。」
命根(寿命)と六根はいずれも業(カルマ)、つまりは過去世の悪行による罪障と善行による功徳から創造されると言われます。
▽煩悩→悪行→罪障→不幸な境涯・寿命・経験
▽反煩悩→善行→功徳→幸福な境涯・寿命・経験
功徳は資産、罪障は負債に例えると分かりやすいと思います。功徳は楽経験や恵まれた幸福な境涯を買うための資産となります。逆に、罪障は恵まれない不幸な境涯や苦経験によって清算しなければいけません。しかし、功徳のおかげで他者より恵まれた境涯・経験を得ようとも、それに執着すると、煩悩が沸き起こり、悪行へと繋がり、未来の不幸な境涯や苦体験へと繋がっていきます。また、それを維持しようとあくせくすると、違う苦しみが生まれ、今の好環境の崩壊した際には、崩壊に伴う苦しみ(壊苦)も味わうことになります。釈尊が苦受も楽受も非苦非楽受も全て苦しみであると説くのはこのためです。
○楽味観・過患観・出離観
六根に関する楽味観(耽溺観)・過患観(危難観)・出離観は以下のように説かれています。
釈尊:
「{眼・耳・鼻・舌・身・意}を縁として、快楽と喜悦が起こること、これが{眼・耳・鼻・舌・身・意}の楽味(耽溺)であると如実に知る。{眼・耳・鼻・舌・身・意}が無常であり、苦しみであり、変滅する本性をもっていること、これが{眼・耳・鼻・舌・身・意}の過患(危難)であると如実に知る。{眼・耳・鼻・舌・身・意}に対する欲望と貪著とを制すること、欲望と貪著とを断ずること、これが{眼・耳・鼻・舌・身・意}の出離であると如実に知る。わたくしが、このようにこれらの内的な六つの領域(六処)の楽味(耽溺)を楽味(耽溺)として、過患(危難)を過患(危難)として、出離を出離として、如実に知らなかった間は神々・悪魔・梵天とともなる世界において、神々・人間・梵天・修行者・バラモンを含む生類のうちにあって、無上の正しい覚りを覚ったと称さなかった。そうして、私に智と正見とが生じた。『わが心の解脱は不動である。これは最後の生存である。もはや再生することはない。』」
この三観の対象は六根だけでなく、五蘊などにも適用されています。四諦観と上記の三観をあわせて、七処三観と言われます。
