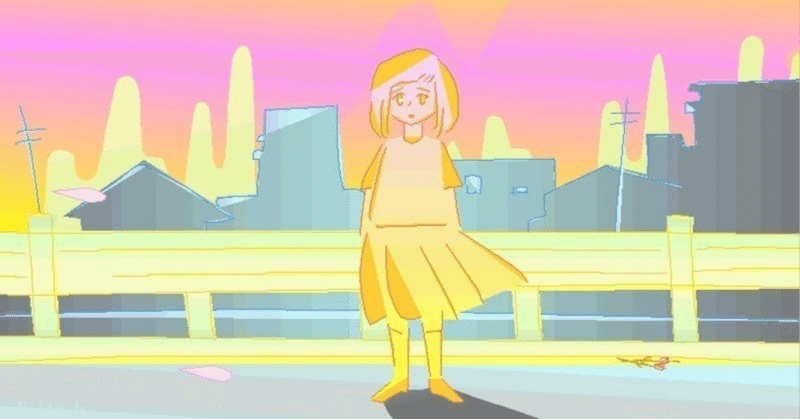
さっちゃん
僕は女の子のパンツが好きだった。たぶんマチコ先生とかカバ丸のせいだろう。かぼちゃワインのせいかもしれない。意味はよく分かっていなかったが取り敢えずパンツが好きだった。パンツが、パンツこそが目指すべき場所だった。
よくパンツを夢想していたが、なんとなくエロい気持ちというものは小学校に入る前から確かに、僕の胸の裡に存在していた。
ある日、僕はさっちゃんと家にいた。ウルトラマンのレコードを掛けて、飛び跳ねていたら針が飛んでしまって、それから聞けなくなった。飛び跳ねちゃいけないとは言われていたが、まさかそんなことになるなんて。
気を取り直してお医者さんごっこをした。何故かは分からない。
お医者さんは僕だ。そして僕の部屋が診察室だ。
さっちゃんを診察室に招き入れる。簡単な問診、エア聴診器を当てたものの、それだけではよく分からない。ベッドに見立てたソファに寝てもらって詳しく見ることにした。
この先にはおっぱいがある。緊張で震える手でシャツのボタンを少しずつ順にはずしていく。筈だった。幼い僕の手ではボタンを上手くはずすことができなかった。ようやく一番上のボタンをはずすことができたが、さっちゃんもいけないことをしていることに感付いたようだ。
辺りに気まずい空気が流れ出す。しかし、こんなところで立ち止まってはいけない。男なんだろう、グズグズするなよ。
「おやつの用意ができたよー」
階下から、僕たちを呼ぶお母さんの声がする。僕たちは返事をすると何事もなかったかのように、おやつを食べにいくのだった。
数年後のある日、それは突然やってきた。僕は四年生になっていた。いや、三年生だったかもしれない。幼馴染ではあったが、幼稚園は別、小学校に上がってからはクラスもずっと別々で、さっちゃんとはすっかり疎遠になっていた。そんな疎遠なさっちゃんの家に何故かお泊まりに行くことになった。
久しぶりのさっちゃんの家は懐かしかった。建売が定着する前だったのだろうか、近隣の家はどこも一軒一軒作りが違った。久しぶりの幼馴染の家を探検するのは楽しかった。
最初こそ楽しかったが、探検を終えてしまうと、既に共通の話題を失って久しい我々には取り立てて話すこともない。
ファミコンあるよと言われて部屋に行くと、鬼太郎の黄緑色したカセットがあった。鬼太郎しかなかった。決して新しいソフト、もといカセットではない。他にいくらでもドラクエなりグラディウスなり、ツインビーなりあるだろう。
これは昭和の悪しき商法『抱き合わせ』で無理に買わされる部類の商品、つまり面白く無いやつだと、ファミコンネイティブの僕の勘は囁いた。
しかし他にカセットは見当たらない。このままでは、場が保たない。まだ夕方だ。意を決して、僕は鬼太郎を始めた。難しくてなかなかできないんだよねと、さっちゃんとその妹が言った。
難しいとかじゃなくて、クソゲー(当時そんな言葉は知らなかったが)なんだよと僕は思ったが、期待に目を輝かせる二人に向かってそんなことは言えやしなかった。
僕は一所懸命プレイした。慣れると少し進めるようになった。バックベアードさんとは、この時初めて出会ったのかも知れない。さっちゃんの妹がウマいとかスゴいとか言って褒めてくれる。クソゲーだと思っていた鬼太郎に、僕は夢中になっていた。
晩御飯はハンバーグだった気がする。さっちゃんのお母さんは優しかった。さっちゃんの家は三姉妹で女の子ばかりだった。それでさっちゃん母には、男の子という存在に憧れというか、そんな気持ちがあったのではないだろうか。もしくは、当時の僕は線が細く、病弱で大人しかったので、単純に可愛いと思ったのかもしれない。
食後、なぜかさっちゃんとさっちゃんの妹と三人で風呂に入らされた。一番下の子は、まだ赤ちゃんだったから、基本的に別行動だった。女の子ばかりの家庭だったし、さっちゃん母がちょっと天然で何も思わなかったのかもしれない。いや、昭和なんてそんなものだったのかもしれない。
断って、変に意識していると思われるのも気まずいし、ここは心を無にして入るしかないと思った。さっちゃんは意識が幼いのか、全く気にする様子がなかった。
かくして数年越しに女の子の裸、つまり最終目的地のパンツすら超えた向こう側、に直面するという夢を超えた夢が、なし崩し的に叶ってしまった。しかし、いざその場になってしまえば、恥ずかしいだけであれだけ見たかったものは直視などできず、妹の世話に専念することでその場をやり過ごした。
翌朝、ご飯を食べると家に帰った。それ以来、さっちゃんとまともに話すことは二度となかった。外で会うと妙に照れ臭くなって、意識的に避けてしまうようになった。
そんな彼女とは、中学三年生で同じクラスになった。それまでに何があったのかは知らないが、さっちゃんはすっかり目立たない子になっていた。背は高かったがそれがコンプレックスなのか、いつもクラスの端で仲の良い子と二人ひっそりと過ごしていた。
僕が音楽室で川野に殴られるのを、さっちゃんはどんな気持ちで見ていたのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
