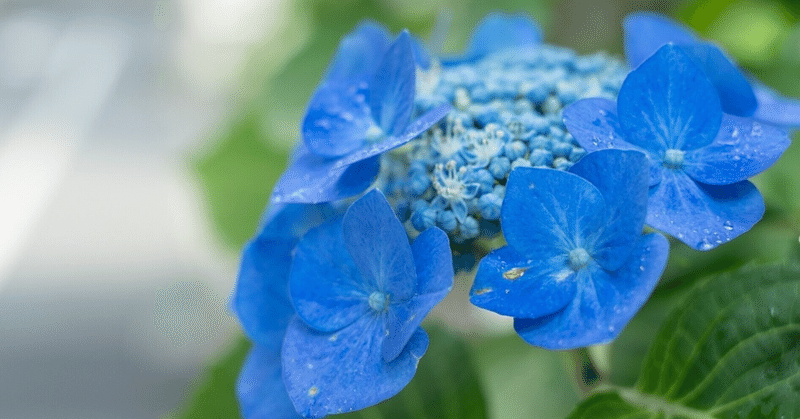
雨上がりに、もう一度。
外は雨。
夏の時期特有の通り雨だろうか。
道路を洗い流すように、ざんざんと音を立てて降り続いている。
この調子では、この後もお客さんなんて来ない。
ただでさえ、普段から客なんか来ないのに。
私がここの店番を引き受けたのは1ヶ月前。
隣の雑居ビルの雀荘でオーナーの男と出会ったのがきっかけだ。
その男は、自宅に置いていた趣味の雑貨や古着の置き場所に困っていた。
きっと奥さんに、捨てろだのどけろだのと厄介者扱いされていたのだろう。
いつも店に来るなり、その愚痴を雀荘のママに「告げ口」するのが彼の日課になっていて、店の常連である私はそれを何度も聞いていた。
ついにその男は、雀荘のママに言われた、
「それなら、倉庫がわりにお店出しちゃえばいいじゃない?」
という言葉を鵜呑みにし、まんまと路面のテナントを借りてしまったのだ。
しかし、その男は別に仕事を持っていて店番などできるわけがない(仕事をサボタージュして麻雀をするくらいの時間はあるわけだが)。
店には当然家賃がかかるわけで、せめてその分の足しになればと店を任せられる人間を探していた。
「ねえ、みさっちゃん。あなた、ヒマよね?」
人が気にしている領域にズケズケと踏み込んで来られるのは、この手の人種の得意技だ。
デリカシーのかけらもなく、目的地に一直線に走り込んでくる。
「…ママさ、そりゃやることないからここに来てるけど。そんな言い方ないんじゃない?」
「だったらさ、お店手伝ってあげなさいよ。どうせヒマな店なんだから、楽な店番よ。」
普通、店子の業況は大家として気になるはずだが、ハナから長くは持たないだろうと決めつけているあたり、さすがと誉めておきたい。
「手伝ってあげてもいいけど、私だってやることはあるんだから。」
精一杯の強がりから捨て台詞を吐いてみたが、ママの言うとおりだった。
去年の春。
私はこの近くにある大学を卒業した。
銀行に就職も決まり、順風満帆。
青春時代を過ごしたこの街とも別れを告げ、思い描く未来へ向かった。
…はずだった。
仕事を始めて半年。
理解できない理由で窓口に怒鳴り込んでくる客たち。
上司からの理不尽な叱責。
私は理想と現実のギャップに戸惑っていた。
「どうせすぐに慣れるわよ。こちらが何も言えないのを解って言ってきているだけ。諦めなさい。」
生気を失った目で伝票を捌く先輩行員になだめられてなんとかやり過ごしていたが、ストレスからとうとう起きられなくなった。
仕事を休みがちになったことが親にバレてしまってからは早かった。
心配した親が部屋に踏み込んできて、私を病院に連れて行った。
診断は、適応障害。
「ストレスになるものから離れなさい」という医者の言葉に目をつり上げた母は、銀行に怒鳴り込んだ。
「うちの娘が何をしたんですか!あなたたちがうちの娘を壊したんでしょう!」
どこの世界に自分の娘の勤め先に怒鳴り込む親がいると言うのだ。
もう一つ言えば、自分の娘が「壊れた」とはなんなのだろう。
程なくして、私は辞表を出した。
毎日苛立っていた母は我に返り、落ち着きを取り戻したらしく、私にこう言った。
「少し休んで、やりたいことを見つけたらいいわ。1年くらいなら、私が養ってあげるから。」
働いて養うのは父のはずだが、そこに父が口を挟む余地はなかった。
この言葉だけでも、母がどんな人間か分かってもらえるはず。
いずれにしても、そんなこんなで私は加療と称したモラトリアムの1年を手に入れた。
私は、大学生の時に付き合っていた男の影響で麻雀にハマっていた。
大学を卒業するころにはどこへでも一人で打ちに行くようになっていたけれど、どこへ行っても「女」と言うだけで奇異の眼差しを向けられるのがイヤだった。
「そんな打ち方をしては勝てないよ、お嬢ちゃん。」
下手なくせに分かったような口を聞いてくる男たちに辟易としていたが、ある日この店にたどり着いた。
チャキチャキとしたおばさんが一人で切り盛りしている、いわば「場末の雀荘」だった。
だけど、ママも客も私を「女」扱いしなかった。
一人の打ち手として認められたようで、すごく嬉しかった。
とうとう安住の地を手に入れた私は、気が向けば毎日のようにこの店に通った。
そんな生活を続けてもうすぐ1年になろうかとしていた。
母からの、まだ就職しないのかという催促に近い電話の回数が増えてきた。
「ねぇ、そろそろ体調も良くなっただろうし、仕事探さなきゃね?」
自分のことしか考えていない親の言葉を聞き流しながらも、内心は焦りを感じていた。
何か始めなくては。
そう思い始めていた時に立ち上がったのが件の古着屋の話だった。
渡りに船。
私はそう思った。
店はヒマ。
好きな時に麻雀を打ちに来られるだろう。
店はそう長くは続かないだろうが、何ヶ月かは「仕事をしている」という口実ができる。
こんな良い話はない。
話はとんとん拍子で進み、翌月には古着屋が出来上がった。
開店当初は学生街ということもあり、大学生や予備校生が毎日何十人も覗きに来た。
売上もそこそこだったが、それに気を良くしたオーナーは私に店番を任せるだけで、集金の時以外は全く店に顔を出さなくなった。
在庫の古着が一通り売れてしまった後。
私には仕入れのノウハウはない。
もちろん、オーナーにも。
店に閑古鳥が鳴き始めるのはあっという間だった。
そして、今日。
「この雨ではもう客なんか来ないわね。」
私は諦めたような気持ちになり、冷蔵庫からコーヒーを出してレジの奥でそれを開けた。
いつの間にか雨は上がり、空では太陽が元の位置で輝き始めていた。
コーヒーを片手にぼんやりしていると、開くはずのない店のドアが開いた。
入ってきたのは、二十代半ばくらいの短髪の男だった。
通り雨に降られたのだろうか。全身ずぶぬれだ。
男は入り口近くの棚にわずかばかり並べていたシャツを無造作につかんで、こちらへ向かってくる。
「ありがとうございます。3,980円です。」
私がタグをとって紙袋に入れようとすると、着替えたいから…という。
あぁ、そうか。それもそうだな。
私はレジの横の試着室を指差し、そこで着替えるように勧めた。
それにしても。
通り雨に降られるなんてドジな男だ。
っていうか、この通り雨に正直に「降られる」男。
根が正直なのかバカなのか。
いずれにしても、そこらへんの男とは一風違う感じがする。
私はそう思うが早いか、レジの下で置き去りになっていた粗品のタオルを取り出し、試着室の床に置いた。
「あの…良かったら使ってください。気持ち悪いでしょ?」
男は遠慮していたが、あのまま着替えたって気持ち悪いに決まっている。
我ながら、客の事をよく考えられる店長さんだと思った。
試着室から出てきた男は、濡れたままのシャツとタオルをつかみ、捨ててくれと言う。
それは構わないが、ゴミが増やされることをその日の私は良しとしなかった。
私は男からシャツとタオルを取り上げ、紙袋に包んで渡した。
「タオルのお礼がわりに、必ずまた来てくださいね。」
ホスピタリティあふれる古着屋の店長気取りだった私。
久々の仕事に気を良くしていた。
結局その男以外の来客はなく、私はいつもの時間に店を閉めた。
これから終電まで安住の地で麻雀。
これが日課だ。
シャッターを下ろし、雑居ビルの階段を登ろうとした時。
階段から降りてくる、見覚えのあるシャツの男の姿。
「あ。」
先ほど、ずぶ濡れで店にやってきた男ではないか。
「麻雀してたんですか?私もこれから行こうかと思ってたんですよ。」
しかし、珍しく常連の姿はなかったようで、卓が割れてしまったことを男が教えてくれた。
ママの愚痴を好き好んで聞きに行くほど、私はお人好しではない。
仕方がない。帰るか。
シャッターの鍵を確認して顔を上げると、駅と反対方向に男が歩いて行く。
バカ正直に雨に打たれる男がどこへ何をしに行くのか。
無性に男の行き先が気になった私は、素知らぬ顔をして男の後を歩いてみた。
が、男の様子がおかしい。
男の足取りが不安げなのだ。
行き先がわかっていないというか、歩き慣れていない様子が背中から伝わってくる。
辺りをキョロキョロしながら歩いている男。
足元がお留守だった。
わずかな歩道の段差につまづいた。
あまりに間抜けなその姿に、私はつい声を出して笑ってしまった。
そんな他愛のないことが、私たちの出会いだった。
北海道に住んでいたその男は、数日後に再び店に顔を出した。
連絡先を交換し、私たちは手紙のやり取りをするようになった。
手紙のやり取りが半年ほど続いた頃だった。
ほとんど売上がなかった私の店は、予想通り閉めることになった。
全く期待していなかった店だったが、半年も身を置いていた場所。
それなりに愛着が湧いていた。
「オーナー、閉店の話、ちょっと待ってもらえませんか?私、知り合いを通じて商品を仕入れられるように勉強しますから。」
今更そんなことを言ってみても無駄なのはわかっていたつもり。
倉庫代にしては高すぎる店賃が奥さんの逆鱗に触れたようだったから、閉店の意思決定にこの男が関係ないこともわかっていた。
私は蝿を手で払われるような扱いで店を追い出された。
みんな、自分勝手だ。
そんな思いが日に日に大きくなり、やがて銀行に勤めていた時のようにベッドから起きられなくなったが、そんな生活を続けていれば母に見つかるのも時間の問題だった。
母は以前と同じように店に怒鳴り込んだが、すでにもぬけの殻だった。
すると、母の矛先は雀荘のママに向かった。
私は、安住の地を奪われた。
暗い海の中に引き摺り込まれていくような感覚。
体が、重い。
このまま、死んでしまえばいい。
失意の中で、私は心を閉ざしていった。
耳に落ちた涙の気持ち悪さに目覚めた私。
ここはどこだ?
見覚えのない天井と部屋の様子。
窓の外には格子がはめられている。
そして、消毒薬とリネンの匂い…。
ここは、病院?
部屋のドアが開いた。
看護師らしき女に連れられてきたのは、母だ。
「ようやく、まともに話せるようになったのかしら。部屋の片付けが終わったわ。さあ、帰りましょう。」
何日くらいの間、私が入院させられていたのかはわからない。
とにかく、感情の波というか、感覚がないのだ。
それが与えられた精神薬のせいだとわかったのは後日のことだ。
母に連れられてきたのは実家だった。
「私、部屋に帰らなくちゃ。」
「大丈夫。お母さんが片付けてあげたから。今日からはここで暮らしなさい。」
小さい頃から子ども部屋として与えられた見慣れた部屋には、アパートで使っていた身の回りのものは何一つなかった。
「お母さん?まさか…。」
「お医者さんの話では、あなたは適応障害だと。仕事が辛かったのね。お医者さんのいうとおり、辛いものから離れないと体が良くならないわよね。」
初めての給料で買ったお気に入りの服も、時計も、カーテンや家具もない。
そして、あの人との手紙も、全てなくなっていた。
「お母さん!手紙は?ねぇ、机の上にあった手紙の束は…?」
錯乱したように問い詰める私の様子を、母は疎ましく思い始めたようだった。
俯き加減に首を横に振りながら、私の両肩を掴んだ。
「もう、しっかりしてちょうだい!今はとにかく体と心を休めて!」
肩を揺すりながら、涙を流して訴える母。
やがて、私の足元にすがるようにしてうずくまった母の髪に、私の涙がはらはらと落ちた。
それが、その時の私にできる精一杯の感情表現だった。
これまでの全てのつながりを絶たれた私。
それからしばらくは籠の中の鳥のような生活を送った。
最初のうちは私を患者のように扱っていた母だったが、やがていつものごとく勝手に我に返る日がやってきた。
「ねえ、美里ちゃん。体調よくなってきたみたいね。たまには外の空気を吸っていらっしゃいよ。」
全く気が進まなかったが、一度言い出したら聞かない母。
部屋から追い出された私は、やむなく最寄りの駅前にあるカフェに行った。
「今日から新作のフラペチーノが…」
店員が勧めてくる甘いものには興味がなかった。
「ホットのソイラテ。トールサイズで。」
少しだけ無愛想だったかもしれないな。
そう思いながら、窓際の席に座ってコーヒーに口をつけた。
不意に、あの日のことを思い出した。
北海道に住む、あの人と最後に会った日のことだ。
あの人は、東京から発つ日に私の店へ寄ってくれた。
嬉しかったな。
一緒に飲んだブラックコーヒーのこと…覚えてる。
元気にしているかな…そう思いながら、麗かな日差しに目を細めた。
母に捨てられてしまった手紙。
そのほかにも私のアイデンティティを示すような思い出の品を失ってしまったことを思い出し、涙がこぼれそうになった。
でも。
急に手紙が来なくなって、あの人は私のことをどう思っているだろうかと気になった。
冷たいやつだと思われていないだろうか。
そんなことが心配になったが、杞憂だと思い直した。
だって、通り雨に素直に打たれるような男だもの。
そんなことは思わないはず。
きっと、私の身に何かあったのかと心配してくれているんだろうな。
だとしたら。
心配かけたくないな。
コーヒーに再び口をつけながら思った。
「いつか、どこかで会えた時のために、元気にならなくちゃ。」
あの日。
古着屋であの人と出会ったように。
きっと私が街の中にいたら、また出会える。
そのために、私は笑顔でいなければ。
ほとんどあり得ない話だとは思う。
バカげた話だと、私もわかっている。
でも、社会とのつながりを全て失った私の心にたった一つ残ったのは、あの人と一緒に飲んだコーヒーの味だった。
だから。
あの人が見つけてくれるように、わかりやすい場所にいなければ。
数日経って私は、履歴書を持ってこのカフェに飛び込んでいた。
カフェで働き始めて数年がたった。
そんなある日、店の外で稲光が光った。
程なく、道路を洗い流すような強い雨。
あの日のような雨だ。
通り雨はすぐに止んで、街には夏の日差しが戻った。
こんな時に、あの人がずぶ濡れで飛び込んできてくれたら。
そんな都合の良いことを思ってみたりしたが、レジにやってくる客にそんなバカな奴はいなかった。
空を覆う重い雨雲。
その雲が消え、やがて晴れていく空を眺めるたびに思う。
あの人にもう2度と会うことはないだろう。
でも。
あの人が今でも、通り雨に素直に打たれてしまうような人であってほしいと願う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
