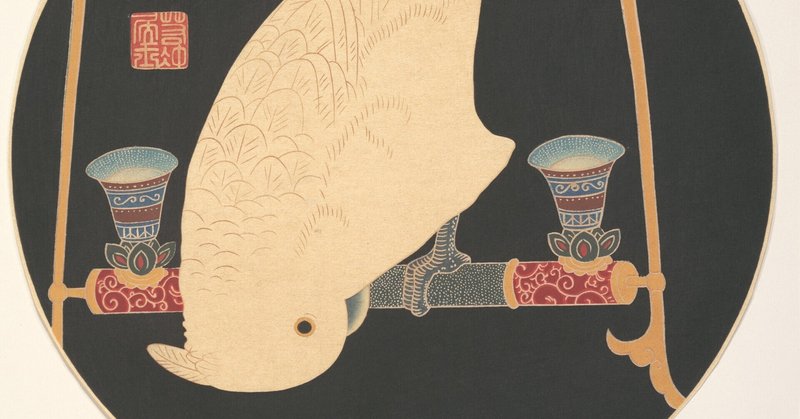
『爆発した切符』(W・S・バロウズ)を読む①
狂っているというならそう言え。おれの方はとっくに自覚があるから、少しでも理性の方に近付こうとしているんだ。もっと光を。
はじめに
最近酔った挙句にウィリアム・S・バロウズ『爆発した切符』の原書を買っていたらしい。朝の電車の中で気付いた時は何かの間違いかと思ったが、前日の夜のツイッターに購入報告が残っていたのでミスでは無かったようだ。できればワンクリで数千円が消えるKindleの仕様のせいであってほしかった。
せっかく買ったからには何かに生かそうと思ってこれを書いている。手始めに、まず作品の日本語訳を冒頭から詳しく追ってみようと思う。これはいくつかの特殊な事情のおかげで成立する試みだ。まったく実のあるものにはならないだろうけど。
ところで・・こんな文章を読む人なんていないと思うけれど、一応ウィリアム・S・バロウズという作家について触れておきたい。バロウズについて最も重要な説明はおそらく、彼がとても難解な小説を書いた、ということだ。
難解な小説ではない。「とても難解」な小説だ。たとえば『レ・ミゼラブル』や『高慢と偏見』、『月と六ペンス』といった小説は、高い評価を受けてはいても決して難解なものではない。『ボヴァリー夫人』『戦争と平和』『百年の孤独』『白鯨』まで行けば難しい本だと思うけど、バロウズの取っ付きにくさはこれらを上回る。
まあ例えるなら『ユリシーズ』や『重力の虹』などが海外文学ファンにとっては「とても難解」な作品と称して差し支えないだろう。なんでわざわざこんな区別をするかというと、別に自分の知識をひけらかすためではなくて(それも無意識の内にあるかもしれないけど)、一番の理由はこの手の作品に付きまとうある種の伝統のためだ。こうした作品群は海外文学が好きな人ですらほとんど読むことがない。しかし何故かよく話題に上がる。つまり読まないまま語ることが常態化していて、デタラメを語ってもエアプがバレない。
だからあなたがバロウズについて話したいなら、作品を読まなくても一切困ることはない。バロウズを一作でも読み通した人間を見つけるのは困難だし、万が一読破したところで何か特別な体験をする期待も薄いように思われる。この文章を書いている自分は彼の作品の全てに目を通したわけではないが、今のところ彼のカットアップに強い感銘を受けたことはない。たった数作読んだ程度のものだけど、バロウズにしては頑張った方ではないだろうか。ちなみに短編の方は結構良いかもしれない。よく名前が挙がる『おぼえていないときもある』は不思議な雰囲気を湛えてはいたし、『ジャンキーのクリスマス』は素晴らしかった。後者はフィリップ・K・ディックの『スキャナー・ダークリー』を読んで感動した人にはぜひ読んでほしいな。そうそう、難解だから優れた小説になるわけではないのだ。ジョイスやピンチョンが偉大な作品を残した一方で、たとえばサリンジャーがキャリア晩年に発表した『ハプワース16』は、別にミチコ・カクタニでなくても酷評せずにはいられないような代物だった。『ライ麦畑でつかまえて』とはあらゆる点で対照的だ。
既に前置きが長くなりつつある。まあバロウズの作品が難しいことには触れたので、『爆発した切符』が具体的にどのような作品なのか説明しよう。
ここで、バロウズの作品について説明されたある文章を見てみよう。アンサイクロペディアの「読書感想文に書くと親呼び出しになる図書の一覧」というページにこんな記述がある。
裸のランチ(ウィリアム・S・バロウズ)
ビートニク小説の金字塔と名高い名著である。麻薬、ホモ、スカトロの3語で内容を表せる小説で、そのくせ小説でありながら一貫したストーリーが全く存在しない、登場人物がいきなり出て脈絡なくいきなり消える、場面がいきなり変わっていきなり収束するなど、およそ一般的な読本とはかけ離れた内容である。この本を「理解」するのは、君が天才でもなければやめておいたほうがいい。少なくとも国語教師や県の審査員風情にどうにかなる本ではないのだ。こういうのは、真性の気狂いか、もしくは東大・京大の方々に考察・愛読してもらえばよろしい。
最初に断っておくと、アンサイクロペディアなんて普通は引用するものではない。だからこの機会は例外的なものだ。この文章は残念ながら一般向けにはとてもよい説明になっていて、投稿者は本当にバロウズの作品を読んだことがあるのだろう(読み終えたのかは定かでないが)。ちなみにこの手の文章の影響力は案外バカにならないもので、バロウズについて語る人の大半が、上のような文章をどこかで読んできてはお喋りに参加するわけだ。そして全員で記事の劣化コピーを伝言ゲームして、最終的に「バロウズは無価値で頭のおかしな人物」に行き着いて終わる。この説明を書いた人間も、ひょっとするとそうやって再生産された評論に影響されているのかもしれない。話が飛躍していないかって? いちいち根拠を上げると長くなるのでやらないけど、誠に遺憾ながら人間の言論とはそういうものだ。あなたもどこかで知っているだろう。
じゃあ本当はどんな小説なのか。結論から述べると説明は不可能である。勘の良い人間でなくても、上記の引用が実は小説の内容にほとんど触れていないことには気付くだろう。実際内容を説明するのは極めて難しいし、何なら上の記述は『爆発した切符』についてもそのまま流用できてしまう。おめでとう。だから紹介は終わりだ。不可能なので。
自分が言いたいのはこういうことだ。『爆発した切符』について知るためにはテキストを読むしかない。バロウズだけではない。すべての小説がそうだ。それが『フィネガンズ・ウェイク』でも『山月記』であってもだ。そうしないと間抜けな事態に自ら加担することになる。プルーストの『失われた時を求めて』はとにかく長いことで有名な小説だが、作者がその長大な作品の中に一ページたりとも非凡でない文章を書かなかったことはほとんど知られていないのだ。ついでにマドレーヌにかこつけてプルーストの話をする人間は、当該の下りが百を超える印象的な場面のたったひとつに過ぎないことをご存じないだろう。プルーストの読者はマドレーヌが引用されるたびに大げさに眉を顰めている。フラ文でマウントは基本なので。
もう同性愛の描写があるだけで作品を褒めそやす時代でもないし、ヒッピーも廃れて、世界の文学的関心はとうの昔に別の場所へと移っている。今この時代、ウィリアム・S・バロウズは純粋にテキストの力だけで読者を引き寄せなくてはならない。ある意味ではそれが古典になるということだ。「文学研究が栄えるには作者の死を待たねばならない」という主張に自分は半分だけ賛成で、正確には「時代が転換するのを待たねばならない」のだと思う。まあその両者が同値なことはあるかもしれない。巨匠の死というのは物理的にも精神的にも時代を転換させるからね。でもたとえばトマス・ピンチョンなんて覆面作家だから現実への影響力はほぼ皆無だし、既にブームも下火だから改めて死んだところで文学全体への影響なんてわずかだろう。バロウズは? バロウズも昔は文学界の現代アートとしてある程度受容はされていたんだ。
へえぇ・・・バロウズが! 地上波に! 全く信じられない。自分の生まれる前にこんな時代があったのか。まあ、この回は流石に参加者の集まりが悪かったらしいけどな。でも現在の地上波における文学の地位を考えると驚異的なことだ。アメトーーク!で「ビートニク大好き芸人」なんてやってる光景を想像できるだろうか。
不可能だ。ビートは死んだ。そもそもバロウズ自身も四半世紀前に死んでいる。でも、墓場から古典を掘り起こすのに遅すぎるということはない。
日本語訳は山形浩生氏が自身のHPに掲載している部分訳による。
BJ、動きがわかるか?
長旅。乗客はおれたちだけ。だもんで、お互いとことん知り尽くして、あいつの声やテープレコーダの上でちらつくあいつのイメージが、自分の内臓の動き自分の呼吸音心拍並におなじみとなっちまった。愛しあってるどころか、お互い気に入ってすらいないけど。あいつを見る時、おれの目には必ず殺意が宿る。おれを見る時、あいつの目には必ず殺意が宿る。
2人の男が旅をしている。彼らはあまりに長い時間をともにしたので、お互いの所作すら自らの動きの延長のようになってしまった。でも旅を通してより親密になったわけでもなくて、むしろお互いに敵意を向け合う関係のようだ。
ところで「テープレコーダーの上でちらつく」あいつのイメージとは何だろう? 一緒に旅をしている相手の声をテープレコーダー上で聞くことなんてあるのかな? おそらく、お互いの不在時にカセットテープを介して言付けや連絡を吹き込んでいたのだろう。便利になった時代にはちょっと想像が難しいけどね。
プヤのカーバイド・ランプに照らされた殺意で外は雨、まったくずぶ濡れの地域でアグアルディエンテに茶とカネラを入れて灯油臭さを消して飲んでると、あいつがおれを呑んだくれのクソ野郎よばわりして、すると確かに殺意が使いたてのナイフみたく鮮血まみれでテーブルの向こう側にあった……
「プヤのカーバイド・ランプ」
PUYAはアウトドア製品を扱うインドネシアの会社のようだ。英語だと「ピューヤ」と読みそうだけど、現地語ではこの発音が正しいらしい。アグアルディエンテはコロンビアで飲まれる蒸留酒のこと。
薄暗い雨の中で酒を飲んでいたところ、唐突に「飲んだくれのクソ」だと罵倒され、驚いて視線を向けると連れが敵意のこもった目でこちらを見つめ返していた、というシーン。
先月の新聞日曜版のコミック欄(あいつはそれを「例のジョーク」と称してて一字一句残らず読み、時には丸一時間もかけてた)を読み終えて、カンバス布張りの椅子に、じっと身動きせずにすわってるのはメキシコの潮河のほとりでヤツの目には鈍い殺意、ひょっとして十年か十五年もすれば、あの時あいつの取った動きがわかるかもしれないあいつはアマチュアのチェスの名手で、実はそれに手持ちの時間の大半を注ぎ込んでいたけど、時間ならいくらでもあった。一度相手をしようと言ったら、ヤツはこっちを見てにっこりして曰く「あんたに勝ち目はないぜ」
椅子に座っている相手はどうやら新聞を読み終えたところのようだ。場所は天候の悪いメキシコの「潮河」のほとり。潮河とは潮の満ち引きがある川のことで、つまり二人の背後には荒れた大河があるわけだ。同行者が敵意を向けてきた理由は今となっても分からない。
同行者は空き時間の大半をチェスに費やす人物で、旅の間も熱心に取り組んでいたらしい。話し手は同行者の気を紛らわすために、相手が得意なチェスの勝負を持ちかける。同行者は笑顔で承諾した。
笑顔はやつの最高に不愉快な部分で、と言うか、やつの不愉快な部分の一つではあって、顔がまっ二つに割れてそこから肉食軟体動物みたいなまったく異質の何かがのぞくんだけど、とにかくおれはまったく出鱈目に駒を進めて最初の数分でヤツのクイーンを取った。やつはクイーンなしで勝ちやがった。おれは目的を果たしたんで興味をなくした。
薄気味悪い笑顔だ。不気味な捕食動物のよう。しかしチェスの勝負で話し手が適当に負けたことで、とにかくその場は収まった。
パナマで天井の扇風機の下、チンボラゾからの冷や風に乗って、リマの瓦礫を横切り、エスメラルダスの泥道から立ち上ぼる、あいつの平板な合成っぽい下品なCIA声……基本的にヤツは完全に頑固で身勝手な人間で、立場とかメリットだけを基準にものを考える、効率的だけど極度に限られた知性体だ。それ以外の水準でものを考えることにはまるで興味を示さない。ちなみに非常に残酷なヤツだったけど、残酷な行為に中毒してるわけじゃなかった。その機会さえあれば残酷になった。その時はにっこりして目を細めて、鋭く小さいサバクギツネみたいな歯が、すべすべした黄色い顔の中で青紫色した薄い唇の間からのぞく。でも、おれ自身の過去にだって、すぐにでも忘れちまいたいことが多少あるってのに、他人のこと言えた義理でもねえか……
キューバからエクアドル、ペルーへと向かう道中。旅の同行者は陽気なムードとはほど遠く、感情を抑制したCIAの工作員のようだった。冷酷で融通の利かない人物。まあ過去に出会った他人をあまり悪く言うものではない。自分にだって忘れたい過去はあるのだから。
言いたいのはつまり、おれたち別に相手が好きなわけじゃなくて、たまたま同じ船、同じ船室、そしてしばしば同じベッドを共有してることが多いってだけのことで、何百万回もいっしょに喰った飯や内臓の動きでのゲップや吐息(ヤツはとんでもないイビキをかく。黙らせるのに寝返りをうたせるか腹這いにさせるんだが、すると目をさまして暗い部屋でにっこりして「妙な考えは起こすなよ」とつぶやく)や心拍でお互いに熔接される。それどころかヤツの声は毎秒二十四駒に切断されて、おれの呼吸や心拍と接合されてるから、おれのからだまで、やつの声が止まったら自分の呼吸も心臓も止まるものと信じこんじまってる。
「そうだねえ」とやつは晴れやかな笑みを浮かべる。「確かに優位には立てるねえ」
分かりやすく書くと作者のウィリアム・バロウズはバイセクシャルの元バックパッカーなので、こうした同性愛的な関係がよく描かれる。大変よいですわね。
おれがヤツを殺そうとするとき、その方法はだいたい直接的だ……ナイフ……銃……もちろん手を下すのはだれか別人だ、おれも社会的な面倒に巻き込まれる気はなかったから……自動車事故……溺死……あいつがボートから潮河に飛び込んだときには、おれの脳裏にサメが浮上した……おれはあいつを助けに行って、引き裂かれて死にゆくヤツのからだを万力のように抱きしめると、向こうは出血多量で抗うこともできず、ヤツの最後に見るのはおれの顔となる。
ゲイの執念の描写。苦手だったら読み飛ばせと言いたいところだが、この先も猥雑な話がずっと続く。
あいつはずっと、おれの最後に見るものが自分の顔であるべきだと計画していて、やつの計画だとそれは歓びの園を舞台にしたシネラマ映画の連続であるべきで、ありとあらゆる自慰と自虐行為を見せていて若い子には特に必要で、みんな電気仕掛けで技術的でどこにでもすわればなにやらセックス車輪が尻をはさみこむか脊椎の中心をはさみつけて電子絞首台がベルトコンベア式におまえを殺しそこで監督が命令をがなる:「そこで絞首台を目にしたときに、うんこと小便をもらしてそれにまみれちゃってくれ。下剤をうまくシンクロさせてくれよ。それと無情な絞首係の男に訴えかけるような目つきをしてやってくれよ、そいつはおまえの肛門まぶダチなのに、それがおまえの首を吊ろうとしてるわけで、そこにドラマってヤツがあるんだからな」
「いかれた状況だぜ、BJ」
上に同じ。突っ込んだら負けだ。BJというのは同行者の名前かな。
このシーンは同行人によるスプラッタ映画の妄想だ。
映画の内容はといえば、街中の椅子でもベンチでも座った瞬間に拷問装置が作動しケツか脊椎が挟みつけられて首を吊られる世界の話で、同行者としてはこの装置に話し手が吊られ、死の直前に処刑人を演じる自分に向かって目線で命乞いをしてほしい、と述べている。大変にイカれていて良い。
でどうやらこの腐った若き王子は動くときに腐乱臭を放つようだがおおむねこいつはほとんど動かないし囚人の一人に目をつけていて自分専用の魚少年にしたてたがってるがもっと若い生成家たちがこちらに向かってくるところだ。パルチザンがスタジオのウィングを一つ占拠して紅衛兵を呼び込んだ……
この辺からがウィリアム・バロウズのカットアップ作品が難しいと言われる所以だ。こんなものをさらっと読むには並外れた読解力が必要なので、こうして一文ずつ進まないと理解が難しくなってくる。内容は前節の妄想映画話の続きだ。
同行人は映画の中であまり出番がない設定のようで、目を付けていた少年を手籠めにしようなどと考えていたある日、パルチザンと紅衛兵に踏み込まれてスタジオを制圧されてしまう。よくあるホモの妄想話である。
ちなみに文中の「紅衛兵」は原文だと”NOVA boys”になっている。理由は分からない。
「さて青年諸君はこの状況についてどう感じておるかね? ほら、自分を表現するんだ……ここは進歩的な学校なんだから……これら映像と連想の若者たちはいまや庭の入り口にいてインター言語の旗を掲げている……わたしが『イヌども』を見たら彼女の四年生のクラスが恐怖で金切り声をあげておれは舗装を見てそっちのほうが安全だと思った……ピンボールみたい道具越しに敵を攻撃……シフト ティルト GOD 映画を STOP せよ。一フレームごとによく見るんだみんな……」
ああ~^・・・あれ?
いかがわしい映画撮ってたら過激派に踏み込まれたシーンのはずだったのに、何か思ってたのと違う展開になった。「イヌども」というのは踏み込んできた人たちのことかな。
このシーンはこうだ。スタジオを制圧したパルチザンに向かって同行人は話し掛ける。「革命思想に燃える若者よ、自分を表現してみよ!」庭に集った連中に視線を向けると女の子の一団が悲鳴を上げたので、道の舗装の方を見ていることにした。別に直接危害を加えずとも、映画製作者は映像をこねくり回すことで十分他人を傷つけられるからね。GOD映画ってなんなのだろう。
「連中はこんなひっでえ軟体動物を持っててそれが絞首した少年たちを食って肉体も魂もオルガズムにおそわれてしかもそいつが分泌して全身にぬりたくる粘液のおかげで食われて喜んでて、でもちょっとあまりに個人的なことをしゃべりすぎてるかも」
これからは映画の設定の続き。「連中」というのは映画の世界でスプラッタ首吊り装置を管理する支配者層(同行者を含む)のことだ。そいつらは首吊り装置とは別に気持ち悪い軟体動物を飼っていて、吊られた少年たちは捕食されてしまうのだが、同時に軟体動物が分泌する粘液で少年たちはオーガズムに達して歓喜するらしい。
ちなみにこの括弧付きの台詞は回想ではない。語り手がわれわれ読者に向けて喋っているものだ。そもそも映画の話はすべて同行人の妄想で、その内容を語り手が再び読者に語るというのが元々の流れなのだけど、説明に熱が入って「ちょっと個人的な細かい部分に入り込み過ぎた」と語り手が反省しているわけ。ここで時間軸が一瞬だけ回想から現実に戻っているのが分かる。
ここから分かること。バロウズの作品は別に小説としての体裁をなしていないわけじゃない(そう見られても仕方ない面はあるが)。単に極限まで不親切な文章で、最低限の筋や文脈が破綻寸前で辛うじて繋ぎ止められているだけのこと。ある意味では余分なものが一切そぎ落とされた小説といえるだろう。ハサミと糊で適当に作った文章などではない。知らんけど。
「諸君らこんなことに我慢してる気か? 異星の軟体動物なんぞに食われてひりだされるんだぞ? 軍に志願して世界を見ましょうある巡視部隊が思い浮かぶんだがこいつらは川沿いの町を解放中にセックススキンの中毒を拾ってきやがった。このセックススキンってのは川にいるムシみたいなので、全身を第二の肌みたいに包み込んで、ゆっくりと修復不可能に人を食いつくす……それでこの子たちは平原を横切るときに太陽でセックススキンが焼け落ちて駐留地にたどりついたときには這うのがやっとで傷口が震えてて半分食い尽くされてほとんどウンコでからだの一部がぼたぼた落ちてるようなざまで、それで大佐を呼んでくると曰く、せいぜいできることはこいつらの頭蓋骨をぶち割って屋外便所に埋めてやるだけだ、そうすればこの臭いはなんとか気づかれずにすむかもしれないと思ったんだが議会でなにやら「讃えられざる英雄たち」とかなんとかいうくせえ話が起きて、大統領自らその屋外便所に名誉負傷勲章を釘でうちつけてその屋外便所はいまでも見られるよそのいばらの向こう側だ……
ここで再び時間軸は妄想話へと戻る。話し手は映画製作者(同行者)、聞き手はスタジオに踏み込んできたパルチザンの青少年諸君だ。
「青少年諸君、現実を直視しろ!軍隊に志願すれば世界の真実が分かるかもしれないぞ。ある巡視部隊は川沿いの街を解放したときに別の軟体動物に出くわしたんだ。そいつは人間を包み込んだ挙句に粘液で溶かして喰っちまうんだぜ! 部隊の一人に犠牲者が出て、基地に連れ帰っても手の施しようがないから屋外便所に埋葬するしかなかった。そしたらなぜか政治家たちが死んだ兵士を英雄扱いして、そいつの勲章が打ち付けられた便所が今も向こうにあるんだ」
単にこう書けば済むことをあえて崩してみせるのがカットアップという技法だ。
さてこれで諸君らにもここでの状況ってものとわれわれが直面すべき問題について多少なりともご理解いただけたかな……たとえばある若い兵士は仲間をセックススキンから助けようとしてそれがかれに寄生していまや仲間のほうが嫌悪でかれを避ける……だれにでもあり得るんだぞわかるか、そして最悪なのはそんなことじゃなくていつ何時自分の相棒が異星ウィルスに乗っ取られたとわかるかもしれないってことで、実際に起こってるんだ残酷な白痴笑いがコーンフレークスを食べながら……息をのんで脇の武器に手を伸ばしてよきカソリック教徒らしく自分の魂を守ろうとする……手遅れ……神経中枢は、おまえのネスカフェにそいつが仕込んだ恐怖のボアボアのために麻痺している……そいつはおまえをゆっくり残酷に食らうつもりだ……ここの状況は干し首製作者たちが「迫害されているという思いこみ」と称したものを兵員の間にはびこらせておかげで士気は目に見えて下がった……これを書いているわたしは、バリケードを築いて自らを上級士官室に閉じ込め、少尉から身を守っている。
この軟体動物こと「セックススキン」は異星から来たウイルスでもあるそうだ(ここでは生物とウイルスを特に区別していない)。軟体動物にやられるだけでも十分最悪だが、仲間がやられたことに気付く方がなお悪い。気が付いて自殺しようとしても手遅れ。コーヒーに仕込まれた「ボアボア」によって恐怖を増幅され、自ら死ぬこともままならず、ゆっくり残酷に食われるしかない。『たったひとつの冴えたやり方』みたいだな。「ボアボア」ってなんだ?
ともあれ、軟体動物こと異性ウイルスに乗っ取られた「連中」が軍隊のメンバーに「自分たちは迫害されている」という意識を植え付けたせいで現場は大混乱。こっちの展開は『虐殺器官』みたいだ。「これを書いているわたし」は「少尉」から逃げるためにバリケードまで築いたらしい。ただ事でない大惨事だな。
ちなみに「これを書いているわたし」とは、
①話し手が語る思い出話の中の②同行者(BJ)の妄想映画話の中で③同行者がパルチザンに対して行った演説で引用される④軍隊の物語を記録した著者(軍人)
のことだ。容赦ない入れ子構造なので念のため。
少尉は『神が遣わされたあなた専属のかわいい絞首係』と自称しやがって、あの尻尾のないクソ猿め、あいつが外で泣き言を言ってメソメソしてんのが聞こえるし、大佐は窓の前でせんずりこきながらジェミニ・セックススキンを指さしてやがる。
地獄
大尉の裸の死体が旗ざおからぶら下がっている。任務についている者のなかで、正気なのはわたしだけだ。もはや手遅れとなった今になって、われわれが何を敵にまわしているのかがやっとわかった:健康で健全な精神の持ち主を、まちがいなくウィルス出の卑しい泣き言まみれの人間もどきにしてしまう生物兵器だ。連中の手に落ちるくらいならわたしは自害することにした。ここの状況がどんなものかを知れば、教皇もまちがいなくお許しくださるだろう。あとどれだけ持ちこたえられるかはわからない。酸素の残りも尽きかけている。『爆発した切符』という SF 小説を読んでいるところだ。物語はここで起きていることと妙に似ていて、だからときどきわたしはこの兵舎の一室は遥か彼方遠い昔の古本の一場面にすぎないと自分でも思いこみそうになって基地の司令部からの支援がまるでないことからすればそうであっても不思議はないだろう」
なんとこの本そのものが出てくる。『はてしない物語』のような児童向けファンタジーでも見かける手法だ。使い古されたメタフィクションが登場すると安心するね。普通はこういうところで「おっ、尖ってる!」となるんだろうけど、今までが少々異常だったからな。
「動きがわかるか、BJ? こういうパトロールすべて、敵の前線の何光年も後ろで切りはなされてしまってどっかのケツのでかいガム噛みいの漫画読みいの三等軍曹に連絡して基地司令部につないでもらおうとしているんだが基地司令部なんかなくてなにもかもが腐ったアンダーベストみたいにバラバラになりつつある……それでもショーは続く……愛……ロマンス……きみの心を引き裂いて喰っちまうような物語……さてこんな構図はいかがかな? 聞いてるのか BJ? 清潔な暮らしをしてるまっとうな重金属小僧と、緑の銀河系からやってきた冷たいグラマラスなエージェントがいて、彼女は小僧をセックススキンで破滅させる任務を負っているんだが小僧に惚れちゃってどうしても踏み切れずしかも任務に失敗した者に課せられる口にするのも忌まわしい拷問のため自分の故郷にも戻れないので、二人は手に手をとってジェミニ宇宙カプセルに乗り込んで、痕跡もなく永遠に宇宙をさまようとか?」
唐突なおねショタ展開。お前ノンケかよ
最後に「軟体生物」「重金属小僧」について説明が要るだろう。ドラッグをやると周囲の人間が重金属の塊とか軟体動物に見えるそうで、これはバロウズの小説を読む上での前提知識となっている。詳しくは山形浩生『たかがバロウズ本』を参照のこと。ちなみに自分はこのような表現に気後れしてしまったし、ドラッグ体験を「ディック的感覚」のような形で一般の読者に伝えきったPKDの評価を改めるべきと感じた。
続かない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
