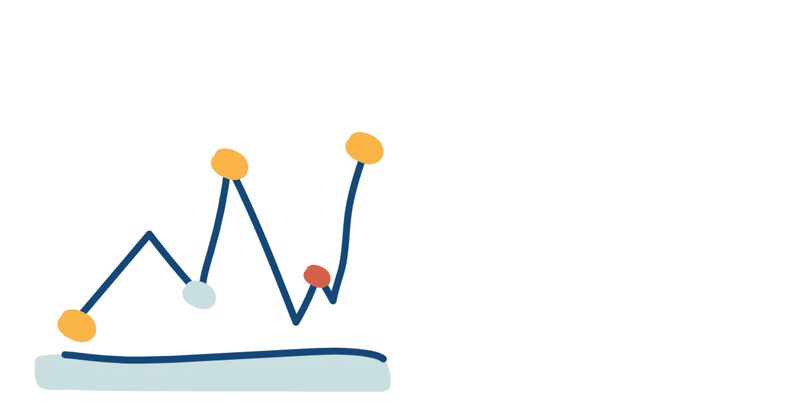
特定のシステム
最近、女性作家の書いた小説を努めて読むようにしている。理由は、特定のシステム(考え方)から距離を置くためだ。
気がつけば、男性作家の書いた小説ばかり読んでいるような気がする。お気に入りの作家はミシェル・ウエルベックとポール・オースター。ウエルベックのお家芸は「モテない男の呪詛」だし、ポール・オースターの小説は基本的に「自分に無頓着であるが故に限界をこえて崩壊」という印象がある。
オースターの小説の無頓着さは主に精神的な部分だと思うが、私は自分の身体に無頓着な部分があり、肉体的な痛みや辛さを限界まで口に出せない性質だ(痛みに涙が滲んでも「痛い」と口に出せないし、39度代の高熱になるまで体が怠いことを認められない)。
マッチョな美学に満ちた小説(ヘミングウェイとか)を読んでいる間に、「泣き喚くなんてみっともない。黙って耐えろ」みたいな精神が自分の中に巣食っているのではないかと怖くなる。
ウエルベックの小説の話もする。
「服従」という小説の中に「一回ごとのフェラチオが、一人の男の人生を正当化するに十分だった」という一節がある。馬鹿馬鹿しいほど大仰な性的快楽の意義づけであるが、少し広義に「女性が、ある男の人生を意味あるものにする」という概念として捉え直すと、この概念がどれほど多くの人の心を捉えているかということに驚く。
例えば、スピッツの歌詞でこんなものがある。
君と出会えたことを僕 ずっと大事にしたいから
僕がこの世に生まれて来たワケにしたいから
(恋のうた)
恋愛中の相手への思い入れを歌っているわけであるが、これも「女性が、ある男の人生を意味あるものにする」の表れのように思われる(「君」の性別が不明なので、相手が女性とは限らないが)。
恋愛のアドレナリンが出ている時に「(君を)僕がこの世に生まれて来たワケにしたいから」などと相手に言われれば嬉しいだろうが、冷静になると、ちょっと危ない。それは愛情なのだろうか?ただ単に自分の人生の意味を他人に押し付けているだけではないだろうか。それは、つまり先程の「女性が、ある男の人生を意味あるものにする」の恋愛オブラートに包まれた甘いバージョンなのではないか。
まぁ、スピッツはこの辺りの「君を、君だけを」という重さを脱した感じがするというのは別の乱文に記載している。
小説も歌詞も現実ではなく桃源郷になれるわけで、その桃源郷では「女性が男性の人生を正当化」してくれる。今はなかなかそういう瞬間に出会えなくても、いつかは。その希望がねじくれかえった時、「女が相手にしてくれない。不幸の源泉は全部そこだ」という状態に陥る。
女性によって人生の不幸が消えるというのは、まぁ、現実的ではない。ただの女性の神格化だ。恋愛しようが結婚しようが、結局は人間同士なので、人間関係が一つ増えるだけだ。
個人的な女性の神格化(迷惑をかけない範囲で)は致し方ないとして、問題はこの女性を神格化して自身の精神を救う夢見がちシステムが、どうも普通だと思われていることである。
男性が作詞する曲の歌詞、男性作家の小説から端を発して、この夢の世界が現実を侵食し、夢が現実にならないことに憤りを覚える人間を産むまでに膨張しているのではないか。
かくいう私も、過去、このシステムを構築していた。構築したシステムを通して世界を見ていた。ある日、夢でしかないと気がつくわけだが。
(ウエルベックの小説も「彼女」という自分を正当化してくれた存在は最後は主人公の前から姿を消す。「彼女」による正当化は夢のように消えて、痛々しい現実が戻ってくる)
さて、いつの間にか特定のシステムに自分が囚われている時、その中にいると気がつくためには他のシステムを知るしかない。
というわけで、まずは、男性作家ばかり読んでしまうのをやめようというわけだ。男女で分けるのは安直な感じもするが、50:50にした後に新しい視点で好きな小説を見つけようと思う。
恋のうた、10代の頃は大好きだった(今も思い詰めない程度に好き)。この「他者による自分の正当化」というのは本当に魅惑的で抗い難い。
最後まで読んでくれてありがとう。
