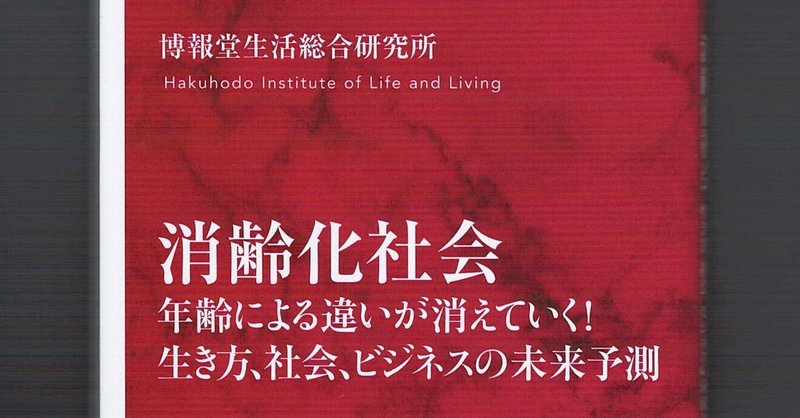
『消齢化社会』を読む

博報堂生活総合研究所 著
集英社インターナショナル新書 (2023.08.12.)
【消齢化社会とは】
生活者の意識や好み、価値観などについて、年齢による違いが小さくなる現象
博報堂の生活定点のデータをもとに「消齢化社会」が提唱されています。
【博報堂生活総合研究所】
【はじめに】
価値観や嗜好の多様化がすすみ、生活者をデモグラフィック(まとまり)で捉えることが難しくなってきました。
団塊(大衆)から、分衆そして「個」へ。
1982年(昭和57年) 『生活新聞』
スニーカーミドル
友達親子
【消齢化の背景】
生活者の気力や体力、ないしは知識の面で年齢による違いが小さくなっている。
p.44
かつての70歳と、現在の80歳が感覚的にだいたい同じ。
p.46
「出来る」が増えた。
p.49
生き方の選択肢が広がり、ライフステージと年齢が乖離した。
p.71
【Point】
1) 能力の面で、年齢に囚われず「出来る」ことが増えた
2) 価値観の面で、世代交代や時代の共有を経て、社会から「すべき」が減った
3) 嗜好や感心の面で「年相応」から「したい」が重なった
p.79
【消齢化の未来】
コーホート分析で、果たして今後も このような消費傾向が続くのか?分析する。
(英: cohort [ˈkoʊhɔrt]・独: Kohorte [koˈhɔrtə])
長期にわたる時系列のデータをもとに「世代」「年齢」「時代」の3つの要素について分析する。
pp.86〜90.
【事例】
ハンバーグ
調理済み食品
【領域】
1) 個人の生きた
2) 人との関わり方
3) 社会構造
4) マーケット
pp.104〜131.
【消齢化社会への8つのヒント】
1) 人口減少を社会の量的と見て「消齢化」を質的変化と見る
2) シニアがどんどん若々しくなっている。若者がどんどん成熟している
3) 「高齢化」を「消齢化」と見る
4) 年代別の分析(デモグラフィック)を疑う
5) 見た目の印象に引っ張られない 先入観に囚われない
6) 「同質化」ないし「均質化」ではなく「収束化」と捉える
7) 次に消えるモノに着目する
8) 新たなモノサシを探す
pp.206〜217.
【ブックレビュー】
2023.10.06
