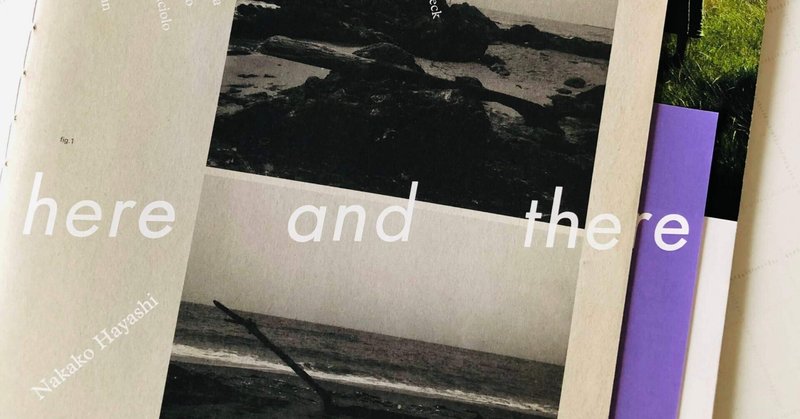
尊重と配慮の地道な積み重ね|『here and there』vol.15
『here and there』vol.15
belonging ーどこに誰といて、何をするか?


読みながら回想している。
本屋青旗さんでの15号刊行記念の展示(2022.7.1~7.18)と、7月9日に行われた編集者の林央子さんとデザイナー尾中俊介さんのトークイベント「編集者とデザイナーの相互侵犯、ともにつくる理由」。
対談は、“聞く整体”みたいだったなぁ。
聞いているうちに、おふたりの話す内容に向いていたはずの意識と目が、「…(それは、わたしにも、身に覚えある)」と、焦点がグルンと自分のほうに反転して、サーチライトで内側の暗闇を照らされるような。
「表す側は、権威の側に立ってしまうことがある」「振るわれたときは権力になってしまう、そのチカラの強さ、影響の大きさを想う」
そういった意味のことを聞いているときだった。
対談の中で進む、おふたりのお仕事のお話から離れて、自分自身が編集者だったときのことを思い出していた。進め方がまずくて、取材相手の信頼を損ねてしまったこと。余裕がなくて、対話を飛ばしてしまったこと。
逆に、こちらが対話を飛ばされてしまったこともある。自分が個人的な感想として送ったメールのなかの一文を、受け手の編集者の方に一言一句違わず、そのヒトのコラムに、あらたなフィクションとして混ぜ込んで、公の媒体に載せられてしまったのだ。知ってから「どういうことですか?」とたずねたら、「君のため」と言われた気がするけれど、釈然とはせず、その人への憧れはしぼむ一方だった。
後年、そういうことってよくあるのかなぁ?と、近しいライターさんや出版関係の知人にたずねたら、「じつはわたしもありますよ、しかも丸パクリとか。でも出てしまったものに、何も言えなくて、、、」と同じやるせなさを感じたことのある方や、「そりゃアカンやつやろ」と同じ違和感を感じる方たちに出会えて、ようやく自分の感覚を取り戻せた。(もう見失わないと思うけど、揺らいだら何度だってココに戻ってこよう)
そうやって、「意図とは違うように使われたくなかった」のに、自分が編集者として動いたときに、立場も媒体も違うし、まったく別のケースなのだけど、同じような思いを取材相手のかたに味わわせてしまったのは、どういう皮肉だろう。版元がそこそこ大きな企業で、部数もそこそことなると、こちら側がじゅうぶんに権威である自覚があった。読者の反応を思うと、著者の強すぎる見解を「そのまま載せるわけにはいかないのです」という対話を、じゅうぶんに重ねる必要があった。それをする余裕がなく、こちらで直した文章を掲載するという自分の未熟さ。この十字架は消せないなぁ。
今は組織に在籍しての編集のお仕事からは離れているけれど、所属がどうであれ、そしてどういう現場であっても、人とつながってなにかを進めるときには、林さんと尾中さんがおっしゃっていたように、「だからこそ、つくるときには(その合間にも)時間をかけて、取材相手との対話を重ねて、状況に耳を傾ける」。どんなときも、そうありたいと願う。
「なにを出してなにを出さないか」「強すぎるときは、あえて弱めることを意図するときだってある」、尊重と配慮の地道な積み重ね。
対談をお聴きしたことで、自分の経験のいずれとも、一生モノのメジャー(測り)として持ち続けようと、あらためて思ったから、対談の終わったあと、林さんにサインをいただく際に、感謝と同時に、身の上で起こった経験を一生だいじにしようと思いました、ということを短くお伝えした。
そして、やはり対談後だからなのか、今号の『here and there』を読んでいて思うのは、表されていることと、そのバックグラウンドが近く感じられるということ。登場するのはいずれとも遠い存在で、自分との日常とはかけ離れているのだから、なにげないようですごいこと。
「どこに誰といて、何をするか。日々の選択や行動は、批評行為だと私は考えています。」
林さんは今号 belonging issue で、自らの個人媒体をつくることは、「制度的に疲弊しているとしか思えない主流のファッション界やジャーナリズム、雑誌媒体への批評」であると初めて明言したとおっしゃっていた。
見つける、近づく。その姿こそが、書物の本性。
遠くに行って、見て聞いて、少しあたらしくなった自分に帰って来れる。
また一冊、すばらしい書物に出会った。
星の一葉 ⁂ 光代
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
