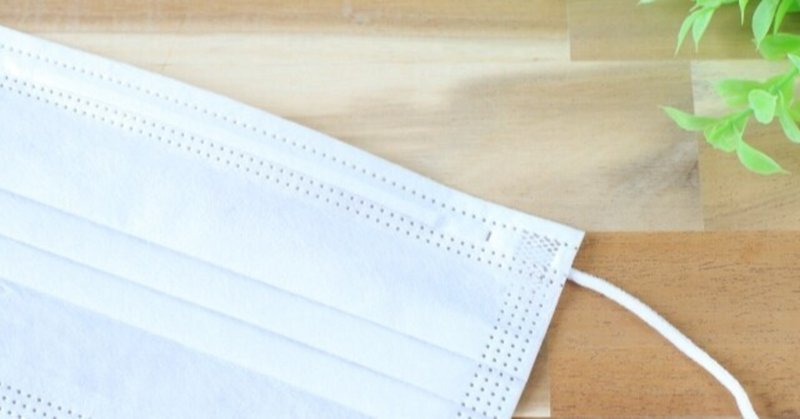
コロナ禍で得たものを活かせば、得られなかったものも手に入る?コロナ禍の学生に大学と社会ができること。
4月に入ってから大学に足を運ぶと、学生たちの姿をよく目にするようになりました。2年前までは当たり前の風景だったのに、ひさしぶりに見るとその活気に驚かされます。コロナ自体は収束したとは言えませんが、大学の日常という意味では、だいぶと戻ってきたのではないでしょうか。今回、見つけたプレスリリースも、そんな大学生活の回復を感じさせるものです。微笑ましいと思いつつも、しばらくはこういう取り組みを意識的にやらないといけないのかな、という気もしたりします。
取り上げたリリースは、京都産業大学の新入生歓迎イベントです。調べてみると、今年は京産大以外にも多くの大学が対面で新歓イベントを開催しているようです。
新歓イベントは、例外なくどの大学のものも新入生を歓迎するために開催されます。しかし今年に限っていうと、このイベントの役割は新入生のためだけではないように思います。というのも、今回、ホストとなる大学2・3年生は、コロナ禍のなかで大学生活を送っており、学生同士が対面で力を合わせる機会が少なかった世代です。とくに授業のグループワークなどではなく、“みんなで協力して本気になって遊ぶ”という経験になると、ものすごく少なかったのではないでしょうか。そういう意味で、今年の新歓イベントは、大学2・3年生のためにもあるように思います。
共感してくれる人がいるのではないかと思うのですが、半オフィシャル・半遊びのような出来事ってすごく思い出になりやすいんですよね。学祭であったり、ゼミ旅行であったり、何かしらの公的な大会に出場したことであったり。普段の授業でもなければ、単なる遊びでもない、非日常的な出来事。今回の大学2・3年生にとっての新歓イベントもそれに入るように思います。
現在の大学2・3年生は、必ずしも必要ではないことのために対面で長時間、人と一緒に何かをやるということを推奨されない環境にずっといました。これって、大学生活の思い出づくりという面では、かなりの痛手です。現段階ではわからないものの、学生たちの愛校心にも、何らかの影響を与える可能性は十分にありえます。
では、コロナ禍の制限も次第にゆるまってきたし、半オフィシャル・半遊びのような出来事を仲間と積み重ねていこう!となっても、こういう出来事って常にあるわけじゃないんですよね。これまでであれば、それでも大学生活はある程度スパンがあるので自然といくつか経験ができました(人によって差はあったとしても)。だけど、現在の大学2・3年生は、経験できる期間が従来に比べて明らかに短いわけです。
でも、ですよ?だからといって、思い出づくりが足りていないだろう大学2・3年生のために(救済措置的な)イベントをやりますと言われると、抵抗を感じる人ってそれなりにいるように思うのです。なんというか、取ってつけたようなフォーローって嫌じゃないですか……。
それよりも現在の大学2・3年生は、コロナ禍で大学生活を過ごした稀有な人たちなわけで、この経験を必要とする誰か(新入生など)に伝えるなど、経験を活かす取り組みやイベントが増えていくのがいいように思います。大学2・3年生を、助ける、ではなく、活かす、という視点でしょうか。これだと受け取る側にとっても有用だし、大学2・3年生もやる必然性が感じられ、すんなりと取り組めるように思います。おまけに、社会的な意義が感じられるので、就活で使うエピソードとしても使えそうです。
繰り返しになりますが、現在の大学2・3年生は、コロナ禍の大学生活を経験した非常に貴重な人たちであるとともに、リアルで力を合わせて何かを成し遂げるという経験があまりできていない人たちです。この2つの要素を上手く組み合わせることで、大学2・3年生にとっても、社会にとっても良きことができるんじゃないか。だいぶと勝手な思い込みが入っているんですが、そんなことを思うのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
