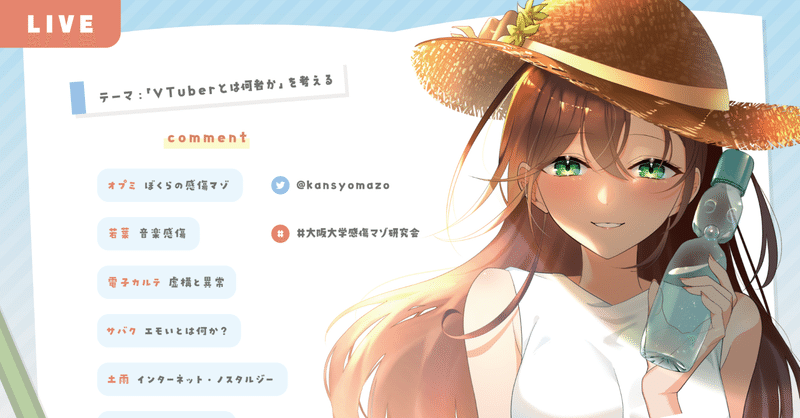
「VTuber の倫理学」を検討する──バーチャル・アイデンティティと「場」の形成
この文章は、2023年5月に発行された『青春ヘラver.7 「VTuber新時代」』に収録されたものを一部修正・改稿したものです。特に、VTuberにおけるレイヤーの問題は本筋を分かりにくくしていたため削っています。完全版はこちらの会誌で読めます。
また、こちらの文章に関して、主に表現論に関する記述(『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』や「縫い付けられた声」を引用しているあたり)は泉信行さん、主に推しとコミュニティの箇所に関してはバーゲンバーゲンさんに丁寧な批判・検討を頂いております。こちらも併せてお読み頂けると、より理解が深まるかと思います。
1ー1 序文に代えて
本題に入る前に『青春ヘラver.7』でVTuber を特集した経緯を説明させて欲しい。
僕がVTuber を初めて見たのは、2017年12月だった。とあるまとめ記事を読んだことでその存在を知り、以降は「にじさんじ」を中心にどっぷりとハマっていく。とはいえ、立ち絵を使って配信するニコ生主や3Dのアニメーションを見慣れていた自分にとって、バーチャルYouTuber が新しい存在だという認識はなかった。そもそも、中学3年生だった自分が「技術的にすごい」とか「キャラクターとして新しい」など考えるはずもない。彼ら/彼女らはごく当たり前にバーチャル世界に存在し、僕はごく当たり前にそれを受け入れていた。
高校生活を通してすっかりVTuber の魅力に取り憑かれていた僕は、それからも熱心なリスナーであり続けた。やがて季節が流れ、推しが燃え、あるいは引退し、新しく増えることもあった。
ところで、光があれば常に影があり、それはインターネットにおいても例外ではない。VTuber を楽しむ中で、いくつもの炎上に立ち会ってきた。当人の不適切な発言や行動が要因となった炎 上は一旦置くとして、その中には「VTuber という存在の特異さ」 が呼び水となった炎上事例も多かった。一口に「VTuber」といっ ても、実際には様々なタイプが存在する。そして、存在の仕方が異なる対象をひとつの言葉で名指すことは、ある種の暴力性すら 帯びることとなる。
例えば、映画内で悪役を演じた俳優がいたとして、「その役に対して非難する」のと「その俳優に対して非難する」のは決定的に異なる。この感覚は、きっと読者の方々にも了解していただけるだろう。だが、VTuber に対して投げかける言葉は、常にこの両者を反復するような曖昧さを持つ。それはひとえに、VTuberという存在が新しく、既存のキャラクターや作品の概念に囚われないような位置を占めるからだろう。
とはいえ、VTuber の存在論を考え、検討しようとする試みはこれまでにも行われてきた。有名な例としては『ユリイカ2018年7月号 特集=バーチャルYouTuber』があり、内容的にも示唆に富んだ論考が多数収録されているが、様々な変化を 迎えた2023年においてはやはりアップデートされるべきだと 常々感じていた。もちろん、山野弘樹「『バーチャルYouTuber』 とは誰を指し示すのか?」や原田伸一郎「バーチャルYouTuber の人格権・著作人格権・実演家人格権」など、有益な論文はその後もいくつか書かれている。だが、やはり『ユリイカ』のように、 様々な視点からVTuberについて考えた文章を多く掲載した本が読みたい。視点の違いが対立を生み、対立が対話を生むと僕は信じている。それが、『青春ヘラ』でVTuberを特集するに至った経緯である。
1ー2 なぜ倫理学なのか?
さて、経緯を説明した上で、本稿の目的を示したい。先に挙げた『ユリイカ』に収録されている文章の多くは、「VTuber の存在論」に焦点を当て、「VTuber とはどのような存在なのか?」 という問いについて検討したものがほとんどだった。当時はまだ詳細に言語化されていなかったため、バーチャルYouTuber に関する特集の話題がそうなるのは妥当なことだろう。2018年 に出版されたとはいえ、皇牙サキの「ギャップ型/ブースト型」 の分類や難波優輝の「三層理論」など、今日においても充分に適 用可能なものも含まれている。仮にそれらが理論として100点満点ではないとしても(というより、時が経てば理論と実情との齟齬が生じるのは当然である)、それを満点に近づける仕事は自分には向いていないだろう。ならば、「VTuber の倫理学」を立ち 上げる仕事を僕は請け負いたい。
ところで、品川哲彦の『倫理学入門』には、次のような記述がある。
近代化とは、価値観を共有する者たちから成る共同体が価値観の異なる人びとに開かれてゆく過程である。現代の多くの国々は母語が異なる移民を受け容れている。こうした価値多元社会では、誰でも自分がよいと思う生き方を追求してよいし、本人が選んだ生き方を尊重すべきだという考えが社会に共通の規範として認められている。この規範は道徳に属す。
これにたいして、多様な生き方の選択肢とその選択肢のなかから自分の生き方を実際に選ぶことは──自分が生まれ育った共同体のなかで身につけた生き方を選ぶ場合もあれば、あるいはそれに反発して社会のなかで見聞した別の生き方を選ぶ場合もある──倫理に属す。
鑑賞者の視点に立てば、「自分も他人も、どんな推しがいてもいいし、あるいはいなくてもよい」という道徳はある程度共有されているだろう。もっとも、他人の推しを否定するような行為や、推し活を強要するような輩は論外である。かつて本間ひまわりが言ったように「みんな推しがいて、推しがいる」のだ。一方で、我々が自ら「この子を推す」と選択することは、倫理である。このような論理は宗教と近いと感じる方もいるだろう。実際、品川もその点についてすぐに言及する。
倫理的判断は、世界のなかにあるものや世界のなかに起きるできごとをどう評価するかを表明し、世界をその判断が推奨するように変えていこう、あるいはその判断が警告しているふうにならないように抑止しようと呼びかける。宗教は、なぜ、世界のなかにそういうものが存在しているのか、なぜ、世界のなかにそのようなことが起きるのか、それらに見舞われた私たちの人生にどのような意味があるのかについて教えさとす。いずれも現実を伝えるのではなく、現実をどのようにうけとめるかを語っている。だから、宗教はその信奉する教条に応じた倫理をもつのである。
推しは神に等しいと言いたくなるくらい尊い存在かもしれないが、決して事物の存在理由を教えてはくれないし、教条に応じた倫理を提供してはくれない。倫理を作るのはそこに与する関係者 や鑑賞者であり、事象を評価し、世界を変えていかなければならない。存在様式の複雑なVTuberにとって、それは一層重要な事柄となる。だからこそ、「VTuber の倫理学」が要請される。
敢えて遠回りな言い方をしたが、正直に言えば僕は、「VTuberに関する炎上が少しでも減れば良いな」という一心で本稿を書いている。理論という道具は既にあるのだ。それをどう使えば良いのか、誰も知らないことが問題ではないのか。倫理とは一人で作るものではないと既に述べたが、もちろん本稿自体が何かしらの教条や倫理を示すわけではない。それらは大勢の人々が対立し、対話する中で生まれるのだ。せめて、そのささやかな糸口にでもなってくれたら、あの頃好きだった推しに報いることが出来るのではないか。そんなことを思っている。
1ー3 倫理学が要請される諸条件
「VTuber という存在の特異さ」が炎上事件の原因となってしまうことがあると先に述べたが、具体的な事例としては2022年11月に「にじさんじ」を卒業したアクシア・クローネの例が挙げられる。詳細を記しはしないが、彼にとって最も問題だったのは「視聴者の鑑賞方法」ではなかっただろうか。苦手なコメントや不適切な距離感(ガチ恋等)を予め示していたにも拘わらず、 一部の過激なファンは止まらず、結果として追い詰められてしまった。もちろん、過激な行動や誹謗中傷は断じて許される行為ではない。だが、まさにこのような事例こそ、VTuberという困難を象徴しているように思う。
少なくとも、VTuber とはフィクショナルなキャラクターではない。アニメキャラクターに誹謗中傷するのとVTuber に誹謗中傷を行うのでは、やはり大きく意味が変わってくる。本来キャラクターに向けては適切である言葉が、VTuberに関しては 不適切となることもある。逆に、VTuber に対しては適切であるものの、実在する人間に対しては不適切にもなり得る。つまり、VTuber を形成するアイデンティティ(以下、バーチャル・アイデンティティ)が複雑かつ不明瞭であるため、正しい向き合い方が難解なのだ。これを、一つ目の問題「バーチャル・アイデンティティの困難」とする。
一口に「VTuber」と言っても沢山のタイプがいることは既に述べたが、今度はタイプ別にも鑑賞態度の判断が要請される。それをさらに細かくしていくと、そのVTuber 独自の規範が発見されていく。VTuber の鑑賞者は、無意識下で何重もの鑑賞態度の決定を行っているのだ。
(1)人間やキャラクターとは違う、「VTuber」としての鑑賞態度
(2)VTuber をタイプ別に分類した上での鑑賞態度
(3)そのVTuber 特有の鑑賞態度
一つ目と二つ目は、「バーチャル・アイデンティティの困難」に起因する見方が可能だろう。だが、(3)が求められる理由は何だろうか。これまでの鑑賞経験から推測するに、これはVTuber 文化──ひいては「推し」文化特有の傾向であると考える。これを、二つ目の問題「推しが生み出す『場』」としておこう。「推し」とは、ファンが共有する「場」を生み出す装置である。すなわち、推しの数ほどその「場」は存在し、それぞれが成立するための規範がある。問題は、その規範はあまり明文化されておらず、ほとんど暗黙の了解とし成立している場合も多いことだ。明文化されていない倫理は法律よりもアップデートが遅く、共有に時間がかかる。「半年ROMれ」はその難しさを端的に表している。 よって、次章からは「VTuber の倫理学」が必要だと思う理由の二つ──バーチャル・アイデンティティの困難と、推しが生み出す「場」──をそれぞれ検討する。
2ー1 バーチャル・アイデンティティの生成
VTuber のアイデンティティとはどのように形成されるのか。ここで検証すべきは、やはり先に挙げた山野の「穏健な独立説」(ただし、その後書かれた文章では「穏健な還元説」と記述されている)だろう。
一度、議論を整理する。『ユリイカ』に収録されている論考は、皇牙サキや新八角がそうしたように、「両立説」を採用するものが多い。つまり、VTuber の存在を、「アバター(ガワ)」と「配信者(中の人)」の二項対立の中で生み出されるものとして捉えているのだ。しかし、これだけでは「XというVTuber は、配信者AおよびアバターBが相互作用することによって現れるXである」という直感的な鑑賞を説明出来ないと山野は述べる[1]。その上で、ポール・リクールの論を援用しながら、「身体的アイデンティティ」、「倫理的アイデンティティ」、「物語的アイデンティティ」を提示し、それらが同時に生起するような形でVTuberのアイデンティティは生まれるとするのが「穏健な独立説」である。これにより、VTuber は単なる配信者でもアバターでもない独立した第三の存在として認識される。
畢竟、これだけでもバーチャル・アイデンティティの困難が証明できたように思えるが、本稿ではアイデンティティを「身体」に基づいて生起するという前提を導入して検討してみたい。この前提は、アニメやマンガ等のキャラクターは「身体」を保持していないが、VTuber には「身体」のようなものを感じ取ることができ、だからこそVTuber は単なるキャラクターでも配信者でもないと主張するものである。まず確実に「身体」を持つ存在をフィクショナルに鑑賞する方法として、我々が演劇を観る際に捉える「身体」は、以下の三種類に分類できる。
①上演時のセリフによって創られる登場人物としての「身体」
②生身の役者の「身体」
③舞台上で二つの身体の組み合わせによって観客が認識するような「身体」
舞台鑑賞をする際、基本は③の方法で身体を捉えるだろうが、当然①に限定したり②に限定したりすることもあるだろう。あるいは、②と③を重ねてみるような鑑賞も想定される。また、演劇という形式に限って言えば、全体的なストーリー単位での鑑賞とミクロな場面ごとの鑑賞を個別に行うこともあり得る。これらは意識的に切り替えられるものではない。
だが、もちろんこの分類をそのままVTuber に当てはめることは不可能だ。それは、主に次の二つの理由による。
・ 演劇において観客が目にするイメージは常に②だが、VTuber においては「身体」を持たないアバターである
・演劇には「脚本(物語)」があるが、VTuber にはない
「『物語』の不在」については三章で詳しく論じるため、ここでは一つ目の問題を重点的に扱おう。注意したいのは、VTuber のタイプによって「身体」の意義が異なる点だ。VTuber を六つのタイプに分けた山野もこの点については自覚的で、「本稿においては、これまでVTuber のタイプを六つに分けて説明をしてきた。そして、本節において明示せねばならないことは、それぞれのVTuber のタイプに応じて、「アバター」の意味合いが大きく異なってくるということである」と述べている[2]。
「アバター」の意味合いが異なることは、それぞれのVTuberにとっての「身体」の意味合いが異なることと同義である。その最たる例は「バ美肉」だろう。少々脱線するが、ここで一度、ことさら極端な「身体」性を持つ存在としての「バ美肉」を考えたい。
「バ美肉」とはバーチャル美少女セルフ受肉の略であり、当初は性差に限らず美少女アバターを纏って活動していればバ美肉と見なされた。しかし、現在では社会的に男性と規定される者が美少女のアバターを纏うことを指すことが多い。
この時、バ美肉した主体は奇妙な身体性を持つことになる。それはまるで男性的な身体と女性的な身体が重なるような、ある種の捻れを含んだ身体性である。これを、日本でも伝統的に描かれてきた「異性装」の系譜として捉えることも不可能ではない。古典的な例では、アマテラスはスサノオと一対になるのではなく異性装によって両性を重ねることで単体でも皇祖神にふさわしい神格を示そうとした例がある。だがアマテラスを持ち出して女性が男装する論理は説明出来ても、逆は説明出来ない。アマテラスが威厳を示すには、強い男性性を帯びる必要があり、性の越境が実はジェンダーバイアスを強く浮き彫りにしているのだ。この点に自覚的なのが『とりかえばや物語』で、女君は過去に獲得した男性性を抱え込み葛藤しながらその後も生きていくが、男君は女装時代を過去のものとして切り離している。要するに、異性装には常に男女の非対称性があり、特に男性が女装することの説明にはなり得ない。
VTuber の現状を見ている限り、男性が美少女アバターを纏う「バ美肉」のケースは多くても、女性が男性アバターを纏うことは圧倒的に少ない(鈴鹿詩子や勇気ちひろが限定的に男性キャラを演じるような事例はある)。なぜこのような現象が起こっているのだろうか。
その答えとなりうるのが、江口啓子「異性装の恋──異性愛と同性愛が交わる場所」(『異性装 歴史の中の性の越境者たち』集英社、2023年)で紹介されている、シュミット堀佐知の提唱する「美のヒエラルキー」である[3]。顔立ちと装いをそれぞれ男性的/女性的の軸で分けると、合計して四つのクラスターが生じる。前近代では、「顔立ちが女性的で装いが男性的」という状態が最も評価された。『源氏物語』における光源氏の容姿の描写を読めば明らかなように、顔立ちと装いのコントラストが強いほど魅力的に捉えられていたのだ。逆に、「顔立ちが男性的で装いが女性的」という状態は最も評価が低い。現在一般に見られるバ美肉は、「顔立ちが女性的で装いが男性的」という条件に当てはまっている。
そもそも、中世文学における異性装の物語には、男女の境界を超えうる身体は「未成熟」かつ「圧倒的に美しい」必要があった。当然、これは生身の身体に大きく左右されるため、年齢を重ねた「おじさん」にとって異性装のハードルは非常に高いものとなる。ところが、バーチャル空間に身を投じた場合、視覚的にはアバターに統一され、生身の身体は隠蔽される。そのような状況下において、自分のなりたい姿=美のヒエラルキーの最高位を目指そうとするのは不自然なことではない。
「男性が女性的な身体を纏う」例は他にもある。やや遠いかもしれないが、漫画評論家の永山薫は、エロ漫画の画期的だった点を「マチズモからの脱出」と「ヴァーチャルな身体としての『少女』」だと整理する。80年代のロリコンブーム以降に見られるエロ漫画は、エロ漫画家自身が描かれた少女に乗り移りたい欲求を満たすためのヴァーチャルな身体として機能しているのではないか、というのが彼の推論だ。「(エロ漫画作家や読者は)女の子になりたい」のではないかとベテランエロ漫画編集者が言っていたとの証言もあり、これはVTuber にも共通する問題意識だろう[5]。
あるいは、この感覚をボーカロイド/ボカロPの問題圏にまで敷衍することも可能かもしれない。和田たけあきは、インタビューにて以下のように語っている。
ちょっと気持ち悪い話なんですけど、ボカロに歌わせて、動画にボカロのキャラを出して、さっきも言ったように歌詞では意外と自分の言いたいことを言っていて……そうすると自分がボカロになったみたいな感覚になるんです。たぶん、美少女の絵を描いてる男の人にもこの感覚はわかってもらえると思う。「アオイホノオ」にも出てくるガイナックスの赤井孝美さんに、誰だったかが「女の子を描くってことは女の子になりたいの?」って聞いたら、「そうかもしれないです」って答えたらしくて。カルロス袴田(サイゼP)さんっていう、イラストも描くボカロPがいるんですけど、彼も「やっぱりあんだけ描いてたら自分が初音ミクとか音街ウナになった感覚ない?」って聞いたら「めっちゃあります」って言ってました(笑)。
ともかく、少女を自身のバーチャルな身体として捉え、それを纏う行為は何も最近になって登場したわけではない。先程、美のヒエラルキーの例を持ち出したが、バ美肉を行う者が全員「顔立ちが女性的で装いが男性的」な理想像を目指しているわけではない。特に装いは内面に密接に結びつくため、バ美肉した上で内面まで女性的になるタイプもいれば、あくまで男性的なままに留まる者もいるだろう。
伊藤慎吾は、2010年前後に見られた男の娘ブームを例に、「ジュブナイル・ポルノを従来のゲイ小説とラノベの中間と位置づけると、ラノベは性的描写を避けたソフトなゲイ小説。ラノベにおける想定読者は多くが男性であるため、それに合わせて男の娘は心身共に女性的だが、コスプレは想定層などいないので中身が女性というわけではない」と整理する[4]。バ美肉の場合も、想定される層によって内面は左右されると考えられる。
VTuber の「内面」について考えた時、ここでもう一つの疑問が湧き上がってくる。それは、「バ美肉したVTuber にガチ恋した場合、それは異性愛か同性愛か?」という疑問である。もしも自分自身もバーチャルな存在である場合(VRChat など)、VR空間が男女という二項対立に囚われない空間であると主張できればこの疑問は問題にならない。実際、お砂糖文化とはそのようにして成立しているのだろう。だが、配信などで見るVTuber と我々は空間や次元を共有しているわけではなく、鑑賞者側も同じく性別が自由というわけではない(後に出てくる新八角の主張を踏まえれば、鑑賞の際に虚構的空間を共有するから問題にならないという言い方はできるかもしれない)。
この場でどちらかと答えを出すことはできない。暫定的に言えるのは、VTuber 文化におけるガチ恋的な感情は、同性愛的性質と異性愛的性質を同時に含むではないかということだ。少々主張が散らかってしまったが、ここで伝えたかったのは、バ美肉という極端に捻れた身体性を体現できてしまうほど、VTuber における身体性は特殊なのだ。
2ー2 完全なリップシンクアニメとしてのVTuber
前節では、VTuber のアイデンティティの困難を、その特殊な身体性に見出し、極端な例としての「バ美肉」を考えた……とは言いつつも、かなりバ美肉に踏み込みすぎて本来の目的を忘れてしまいそうだったので、一度アニメキャラクターにおける「身体らしき何か」とVTuber の持つ「身体」の違いを洗い出したい(僕はアニメキャラクターは「身体」を持たないという立場のため、「身体らしき何か」と表している)。
結論から言えば、VTuber はリップシンクを徹底しているが、アニメキャラクターはリップシンクを徹底していない。この一点が、「身体」を感じさせるか否かを分ける要素である。VTuberをリップシンクが徹底されたフルアニメーションとする見方は、黒嵜想「縫い付けられた声」(『ユリイカ2018年7月号 特集= バーチャルYouTuber』青土社、2018年)が既にあるが、ここでは補助線としてもう一つ文献を引用したい。
程斯「アニメ・キャラクターとアニメ声優を同一視する現象の原理的基盤をめぐる一考察」は、アニメキャラクターとその声優が同一視され、互いに連想される回路を考察している。
結論を先に言えば、本稿はその原理が、抽象度の高い線画記号による人物造形、リミテッド・アニメーションの手法、そしてリップ・シンクしない声を併用する日本のテレビアニメが生み出すキャラクターの独特の身体性と、第二次声優ブーム以来成立してきたアニメ声優のスターダムによって構築されるアニメ声優の身体性との、両方に基づいていると考える。後に詳述するが、アニメ・キャラクターもアニメ声優も、幻想的な統一性と有機性のない独特な「身体」を有しているからこそ、ファンの読み込みが可能となり、キャラクターと声優との間の回路もそれで成立するのだと本稿は主張する。
前提として、日本では長年リミテッド・アニメーションがメインストリートとして使われ、それはディズニー的なフル・アニメーションとは異なるリテラシーを育んできた。ぎこちない動きこそがアニメキャラクターの特殊な性質を強調しているのだ。その場合、動きのバリエーションが少ないかわりに、それ以外の要素の情報量が多ければ多いほどアニメーションとしては成功となる。よって、アニメキャラクターを成立させる視覚的記号は密度が高く、それ単体で性質を表現できる必要がある。
程斯はそこで、そのようなアニメキャラクターの成⽴を⽀える諸記号は、まさに組⽴図の諸パーツのようなものであり、互いに個々の性質を強く主張しつつも、⼀⽅ が他⽅を⽀配することなく、アニメ・キャラクターの「⾝体」──その「組⽴図」から連想される総体としての何か──を⽣起させているというトーマス・ラマールの論を引用する。
すなわち、リップ・シンクしないアニメにおいては、声は動く唇に完全に還元されることも、映像に支配されることもなく、それ自身が映像とは異質なものであることを明らかにするように機能している。このことによって、声は視覚的要素に従属するものではなくなり、視覚的要素と並列するもの、つまりラマールの言う「組立図」の一パーツとなる。したがって、アニメにおける声と視覚的な諸記号の間には、一方が他方を支配するような力関係は存在せず、すべて「組立図」に描かれる諸パーツのように並列され、キャラクターの「身体」生起に加担していると考えられる。アニメにおける声がしばしば「アニメ声」と呼ばれるような、現実にはありえないほど特徴的な声であるのも、そのためである。
一方、VTuber は完全なリップシンクを実現していることが多い。その場合、確かに「声」の要素はVTuber の確かさを感じさせる「身体」として立ち上がるが、それはアニメキャラクターにおける「身体」とはまず間違いなく異なるものである。僕が程斯の指摘する「身体」がVTuber の保有する「身体」と同一でないと考える一因は、アニメキャラクターの場合に連想する「身体」は、声優自身の肉体を少なからず拠り所としていると感じるからだ。つまり、アニメキャラクターに感じる「身体」は、我々が現実に存在すると知っている声優の肉体を依り代として拡張された「身体」であり、そこにはやはり非対称性がある。VTuberの場合、声の主が隠蔽されているからこそ、完全な形での(人間とは異なると断言できるような)「身体」が浮かび上がるのではないだろうか。
「アメリカのアニメーションにおけるプレシンクされリップ・シンクを達成された声は、目の前の身体を人間に擬装させ、「人間/非人間」の境界を危うくさせる」[6]という細馬の言葉の通り、VTuber の「身体」はキャラクターでありながら限りなく人間に近いアンビバレントな状況が生み出すのではないか。その意味で、やはりVTuber の存在は、人間ともキャラクターとも言えないバーチャル・アイデンティティは困難としか言いようがない。
3ー1 「推し」文化を代表する存在としてのVTuber
さて、本章では、VTuber の倫理学が必要とされるもう一つの理由として、「『推し』が生み出す『場』」の存在について考える。
以前書いたnote において、僕はこのようなことを主張していた。
我々はVTuber の何を好いているのか。それは、配信者が作る「コミュニティ」なのだ。アバターや配信者を好いているのはもちろんだが、最終的な価値はファン同士で形成する共同体が担っていると推測する。
このコミュニティでは、ただファン同士が繋がっているだけではなく、配信者に対して総ツッコミを入れたり、あらゆる反応を示してそのVTuber を共に形成していく。リスナーを一つのまとまりとするならば、VTuber は複数でありながら一つのまとまりであるリスナーと対話しているのだ。ファンネームやファンマークはその意識をより支えているだろう。
ずいぶん前に考えた主張ではあるが、今でもこの推論が大きく外れているとは思っていない。やはり、VTuber 文化における「場」の存在は無視できない。もしこの主張に付け加えることがあるとすれば、「場」の存在が特徴的に現れているのは、なにもVTuber 文化に限った話ではない。むしろ、「推し」文化がこれまでの「萌え」や「担当」と最も異なる点こそが、共有される「場」という存在ではないのか。
一度、議論を整理しよう。「推し」という言葉は、AKB48の総選挙が発祥であるという説があるように、元々は現実のアイドルやタレント等に向けられる言葉だった。その点、何らかの対象への愛情表現であるという共通項を持ちながらも、主に二次元キャラクターを志向していた「萌え」とは一線を画す用語だった。しかし、「推し」文化の現状を見て頂ければ分かるように、昨今の「推し」は現実のアイドルからアニメ・マンガのキャラクター、果てには友人などの卑近な人物にすら向けられうる言葉となっている。これには、「推し」という言葉の持つクリーンさ(従来のオタクらしいダサさを捨象したイメージ)や、「萌え」がメイド喫茶やコスプレを例に、二次元だけに留まらなくなった結果として別の用語が必要とされたことなど、様々な理由がある。
だが、ここで見落とせない点が、「推し」にはコミュニティを志向するニュアンスが含まれていることだ。これは、「俺の嫁」に代表されるような一対一を意識した「萌え」には見られない特徴である。女性アイドル文化が発祥の言葉とはいえ、「推し」文化の成長に腐女子的な勢力の貢献があったことは無視できない。それは、例えば『ユリイカ2020年9月号 特集=女オタクの現在』のサブタイトルが「推しとわたし」であったり、それに収録されている原稿の多くが「オタク」と「推し」という用語を立脚点に論を展開したりしていることからも見て取れる。そして、彼女たちが誰かを「推す」場合、そこには常にコミュニティの存在があった。
そもそも、「オタクが何かのもとに集まる」運動が起こったのは、『海のトリトン』を好きになった女性が自主的にファンクラブを結成したのが最初だと言われている。オタクが集まり、コミュニティを作ることに関しては女性が先駆してきたと言うこともできるかもしれない。では、女性オタクが中心となった「推し」文化において、なぜ「コミュニティ」が重要視されたのか。これは様々な言い方ができるだろう。筒井晴香は「『現場』を伴うコンテンツの隆盛、また活動の場としてSNSのウエイトの大きさ」が女性オタクの活動をソーシャルなものにしたと指摘している[7]。また田中東子は、ファンカルチャーや二次創作の世界が個々人の事情やライフスタイルの違いをはねのけて女性が集団化できる貴重な場として機能していることを指摘し、それが一つの塊として社会的に影響力を持つかもしれないとまで主張する[8]。
ここまで女性の活動に絞って述べてきたが、もちろん現在の「推し」文化全体に極端な性差は見られない。個人的な印象としては女性の方が「推し」文化への融和性が高いような気もするが、VTuber に限って言えばそれほど男女差があるという感覚はない。
ともかく、「推し」文化においてはコミュニティの存在が重要になってくる。そして、それはVTuber も例外ではない。だが、VTuber における「場」とは、単なるファンコミュニティには留まらない。確かに、Twitter におけるファンマークやファンネーム、配信やファンアートのハッシュタグはリスナー間の連帯を高め、より強固なコミュニティの醸成に寄与しているだろう。だが、一般的に「推し」と名指される存在とVTuber には決定的な差がある。VTuber には、「物語」が欠落しているのだ。
3ー2 VTuber と物語と「場」
「場」の存在とVTuber の物語を結びつけた論考としては新八角「月ノ美兎は水を飲む」があり[9]、本節はこの論考を中心に話を進める。新の主張において、重要と思われる論点は以下の四点である。
・ VTuber には一つのまとまった「物語」がなく、従って「正しい像」が存在しない。
・ 現実の「中身」とバーチャルな「器」が隔てられているからこそ、両者を橋渡しする「虚構の約束」が必要であり、それによってVTuber と視聴者の間に共有される「場」が要請される。
・ 言い換えれば、VTuber が開いた虚構の中に、視聴者もまたバーチャルな肉体を投影することで、「場」を共有している。そこに、VTuber の存在感──すなわち「確かさ」が立ち上がる。
・ また「物語」を否定し、キャラクターを崩すことで視聴者と
協働して新たなキャラクターを創出する「場」が要請される。
一章三節でも述べた通り、演劇作品やアニメとは違い、VTuber には脚本や物語がない。そこにはオリジナル、つまりは演じるべき像は用意されておらず、新も言うように、オリジナルが常に二次創作的な要素を帯びる。よって、VTuber の「物語」とは視聴者が参画することによって生起されていくものなのだ。山野が持ち出した「物語的アイデンティティ」の説明にもオーディエンスの存在は重要であるとの記述が見受けられる。VTuber は、「物語」が不在だからこそ、鑑賞者の能動的な参画がないと成り立たない。
実は、「鑑賞者の能動的な参画がないと成り立たない」存在は、現代美術のフィールドにおいても見られる。それは、ニコラ・ブリオーによって提唱された「リレーショナル・アート」と呼ばれる一連の潮流だ。近年では「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」という包括的な用語で括られることもあるが、いずれにせよ全ては彼の書いた『関係性の美学』に端を発している。
1990年代、現代美術界では「他者」に対する関心が高まると同時に、「関係性」への関心も高まった。ここにおいて鑑賞者と作品という二項対立は曖昧になり、人と人の関係性を生み出す媒体として芸術の可能性が模索されるようになった。その好例がゴンザレス=トレスの作品であり、彼の挑戦した「私的空間を公共圏に持ち込む」試みにブリオーは強く惹かれていた。ブリオーが注目したのはゴンザレス=トレスのような「鑑賞者の介入を要請するような作品」であり、1990年代のアート界で躍動している要素は「インタラクティブ、ユーザーフレンドリー、関係的な概念」であると述べる。山本浩貴は『現代美術史』にて、その状態を「そこではもはや芸術は鑑賞者によって見られるだけの静的オブジェクトではなく、『社会性を生産する場』として動的に理解されます」と形容する[10]。
リレーショナル・アートでいうところの「関係性」とは、〈作品- 鑑賞者〉、〈鑑賞者- 鑑賞者〉の両方の意味がある。第一に鑑賞者の参入がなければ成立せず、その上で鑑賞者同士の交流が生まれるのが特徴とされる。
これらの特徴を概観してみて、VTuber 文化と重なる点はないだろうか。VTuber は「物語」を欠いており、鑑賞者との相互作用によってそれを形成していく。従って、鑑賞者の存在なしには成立できないと言える。加えて、「推し」という御旗をもとに生まれる交流の可能性、そしてファンネーム・ファンマークで与えられる連帯感は、たしかに鑑賞者同士の関係性を構築している。
ブリオーは、ギー・ドゥボールが予期した「スペクタクル社会」への対抗手段としてリレーショナル・アートを提唱した。すなわち、情報消費社会に組み込まれた資本主義のシステムの上で、生活のすべてがメディア上の表象としてしか存在しなくなり、データベース的にしか世界を読み込めなくなる社会──受動的で動物化した「萌え」文化とオタクと換言しても良い──を革新するものとしても能動的な「推し」文化は隆盛したのではないか。そこでは関係性の美学に基づくコミュニティが形成され、VTuber 文化はその代表例と化している。
このように両者の構造を似たものだと捉えるならば、リレーショナル・アートに寄せられた批判をVTuber 文化に適用することにもある程度の妥当性があるのではないか。ただし、VTuberは(配信する側からすれば)芸術作品ではなくあくまでエンターテイメントであるという認識が大多数だろう。よって、社会性を欠いていると喝破するようなタイプの批判は意味を成さない。ここで取り上げたいのは、建築家のマーカス・ミーセンが『参加の悪夢』で行ったような類いの批判である。
ミーセンは、昨今のリレーショナル・アートなどに代表されるアート・プロジェクトにおける「民主主義的プロセス」は、単に既存の秩序を追認するだけであって、そのような構造の中では社会を変えるようなラディカルな変化や政治的に意味のある不同意は起こりにくいことを問題視している[11]。VTuber にラディカルな変化や政治的に意味のある不同意を求めてなどいないと言いたい気持ちは一度抑えて、「既存の秩序を追認するだけ」という部分に着目したい。やや強引かもしれないが、VTuber の提示する配信ルール(概要欄に明示的な形で記載されている注意や、メタ発言を禁止する等の暗示的なものを含む)を「民主主義的プロセス」と考えた場合、根本的な部分においてVTuber のコミュニティは常に危うい局面に晒され続けることになる。極端な話、構造が同じである以上、同じような炎上やトラブルは永遠に起こり続けるのだ。
曲解だと思われるだろうか。しかし、VTuber を観測していても、似たようなトラブルが起こってコミュニティ内で分断が起こる様子を、僕は何度も見てきた。もちろん、これはVTuber に限らずインターネットのコミュニティであればどこでも起こりうることだが、VTuber に関してはそのアイデンティティの難しさからトラブルが起こりやすいことは既に述べた。なぜなくならないのかと言えば、ビショップが関係性の美学を批判した上で指摘するように、「推し」文化もリレーショナル・アートも、共同体の実現を妨害や阻害する人を排除することで成り立つからだ。異分子の排除しか維持の方法を持たない共同体は、その一点において致命的な脆弱性を露呈している。
では、炎上を克服し、コミュニティとしての強度を増していくためにはどうすれば良いのか。ミーセンの言うように、ラディカルな変化や政治的に意味のある不同意を積極的に起こせば良いのか。おそらく、そうではない。ソーシャリー・エンゲイジド・アートの代表的論者であるグラント・ケスターは、リレーショナル・アートのインタラクティブな側面に着目した。彼は、対話やコラボレーションはアーティストと非アーティストを分かつヒエラル
キーを破壊し、制作過程における両者の平等を達成するために不可欠であると主張する。一章で触れたように、「対話」が重要なキーワードとなるのだ。この「対話」は、作品(VTuber)と鑑賞者(視聴者)の間でも、鑑賞者と鑑賞者の間でも発生する。
対話によって、アーティストと作品(見られる客体)は他者(見る主体)の創造性やイマジネーションを借りることができる。アーティスト一人では開けなかった可能性がそこにはあり、より良いコミュニティの在り方が提示されうる。
だからこそ、対話を通した倫理の蓄積が必要とされる。VTuber 文化の価値とは「場」としてのコミュニティであり、それを維持するために「VTuber の倫理学」が欠かせないのだ。
3ー3 これからのVTuber のために
まとめに入ろう。本稿では、「VTuber の倫理学」を立ち上げる糸口を掴もうとしてきた。倫理学が必要とされる理由はVTuber という存在の特異さに他ならず、なぜそのような特異さが生まれるのかをVTuber の特殊な「身体」に基づくアイデンティティ形成の面、それから「推し」文化に特徴的な場」の存在から考えた。
最後に、VTuber の倫理学と直接の関係はないが、触れられなかった論点だけ示して本稿を終える。VTuber の中には、特徴的な語尾や口癖を用いるライバーが多く存在する。かつて斎藤環は『網状言論F改』や『戦闘美少女の精神分析』にて、存在していないものにリアリティを与えるのが特徴的な語尾などの「言葉」であると主張している。言葉は現実の覆いであると同時に、その覆われているものをリアルに見せる効果を有しているという。問題意識としては吉岡乾「ことばとVTuber と戦争と」[12]に近いだろう。いずれにせよ、今後はVTuber の喋る「言葉」と、それが与えるリアリティについて研究していきたい。なぜならこの世界では、言葉が対話を生み、対話が倫理を育てていくのだから。
【追記】
ここから先は原稿執筆時ではなく、2024年1月時点での追記です。上記原稿を書いた時は、演劇の例を出していることからも分かる通り、「VTuber」を一人の「人格」として扱うニュアンスが強かった気がします。ところが、最近VTuberを考えるにあたっては、「VTuber」をひとつの「作品」という単位で捉えることが可能ではないかと感じています。すなわち、配信者AおよびアバターBが相互作用することによって現れるXとは、鑑賞対象としての芸術作品ではないか、ということです。
そう捉えたとき、上記の「バーチャル・アイデンティティの困難」という問いは、「VTuberにおける”作者”とは誰か?」という問いに置き換えることも可能ではないでしょうか。先日、ゲンロン友の声を読んでいると、以下のような記述がありました。
最後に触れておきますが、これはじつは哲学的にはとても大きな問題です。人間は、人格を想定することなしには世界を理解することができない。人間はあらゆるところに「その背後にある人格」を見出す動物で、だから作品にも作者を見出してしまう。その条件からは逃れられない。それがいまぼくが記していることですが、ぼくの考えでは、おそらくは人間が神や陰謀論を必要とするのもまさにこの理由によっています。ぼくたちはあらゆるところに作者を見出す。だから神も見出す。陰謀を見出す。そして神や陰謀の観念抜きでは、世界をどう理解していいのかわからなくなってしまうのです。
人は、あらゆる作品に対して「人格」のようなものを想定し、「作者」という虚構の単位を扱う、扱わざるを得ない。古来から自然を神の産物と捉えて「人格」の名の下で思考してきたように、VTuberという現象および作品に対しても、「相互作用によって生まれるX」というものを思考しなければならない。こう換言した時、初めて「VTuberのアイデンティティとはどこにあるのか?」と問うことができるのではないかと思います。
[1] 山野弘樹「「バーチャルYouTuber」とは誰を指し示すのか?」『フィルカル Vol. 7,No. 2』(株式会社ミュー、2022年)
[2] 山野弘樹「「VTuber の哲学」序論――多様化するVTuber と「身体」としてのアバター」『Fashion Tech News』https://fashiontechnews.zozo.com/research/hiroki_yamano
[3] Sachi Schmidt-Hori.“Non-Binary Genders in the Genji, the New Chamberlain, and Beyond.” In The Tale of Genji.ed. by Dennis Washburn, 1282–1295. New York: W. W.Norton & Co., 2021.
[4] 永山薫「セクシュアリティの変容」『網状言論F改』(青土社、2003)
[5] 伊藤慎吾「稚児と〈男の娘〉」『異性装 歴史の中の性の越境者たち』(集英社、2023年)
[6] 細馬宏通『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか アニメーションの表現史』(新潮社、2013年)
[7] 筒井晴香「孤独にあること、痛くあること」『ユリイカ2020年9月号 特集=女オタクの現在』(青土社、2020年)
[8] 田中東子「分断と対峙し、連帯を模索する」『現代思想 2020年3月臨時増刊号 総特集◎フェミニズムの現在 』(青土社、2020年)
[9] 新八角「月ノ美兎は水を飲む」『ユリイカ 2018年7月号 特集= バーチャルYouTuber』(青土社、2018年)
[10]山本浩貴『現代美術史- 欧米、日本、トランスナショナル』(中央公論新社、2019年)
[11]Markus Miessen. The Violence of Participation(sternbergpress, 2007).
[12]「ことばとVTuber と戦争と」『ユリイカ 2022年8月号 特集= 現代語の世界』(青土社、2022年)
参考文献(引用で紹介したのものは除く)
上田由至「ソーシャリー・エンゲイジド・アートにおける「参加」概念と
その内実」『文化交流研究室』第15号(2020), 21-34.
原田伸一郎「バーチャルYouTuber の人格権・著作人格権・実演家人格権」
『静岡大学情報学研究』第26巻(2021), 53-64.
本橋裕美「異性装を解いた彼ら/彼女らはどこへ向かうのか」『異性装』(集英社、2023年)
阪本久美子「シェイクスピアのオールメイル上演の愉しみ方」同書
斎藤環「「萌え」の象徴的身分」『網状言論F改』(青土社、2003年)
皇牙サキ「「声」という商品のパッケージとしてのVTuber」『ユリイカ
2018年7月号 特集=バーチャルYouTuber』(青土社、2018年)
難波優輝「バーチャルYouTuber の三つの身体――パーソン、ペルソナ、
キャラクタ」同書
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
