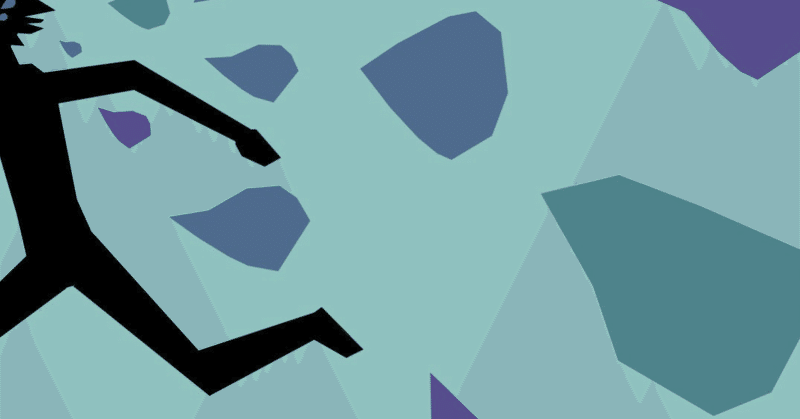
泣いた赤おには「究極の未完」だ。十数年越しの再読を経て、感じること。
「泣いた赤おに」は「究極の未完」だ。
十数年振りくらいに濱田 廣介さんの
「泣いた赤おに」を読み、そう思った。
「読み終わった後にどれだけ語りたくなるか」が
その作品の良し悪しを測る物差しとするのであれば、
この十数年の間で「泣いた赤おに」はわたしにとって
とてつもない名作になってしまったようだ。
読み終わって数週間も経つのに、
未だに脳内でストーリーを反復し、
登場人物(鬼物)の心情に思い廻らす。
初めて読んだのは小学生の頃だろうか。
「何かを得るためには何かを失う」という、
なんとも味気ない、冷めた訓戒めいたものを
なんとなく感じ取っただけだったが。
今の自分は、当時の自分が出した結論に、
「そんな渇いたメッセージで終わるはずがない。もっと、何かあるはずだ」
と、激しく挑戦状を叩きつける。
青おにの協力を得て人間と共に生きる機会を得た赤おには、
青おにとの日常を失う。
そして。
この先青おにが戻ることはあるだろうか?
それはいつなのか?
青おにの帰還があるとすれば、それは一体何を意味するのか?
青おにと赤おにの(一時的かも知れない)離別は、
この物語の結末に、どう色を添えるのか?
と、ここで気づく。
「泣いた赤おに」は、まるで「未完」だ。
青おにとの離別という、赤おにに大打撃を与えたであろう
衝撃的なイベントの先が描かれない、圧倒的、未完。
そもそも。
青おにとの離別までの経緯についても、
真実は、全く描かれない。
赤おにはなんで人間と関係を持ちたかったのか?
青おにはそれをどう受け止めていたのか?
離別後の、二人の心情は?
などなど。
淡々と、静かな唐突さを以って、物語は綴られる。
登場人物(鬼物)の限られた模写を通して、想像するしかない。
この物語を完結させるためには、自分で想像するしかないのだ。
きっと往々にして作品と呼ばれるものたちは
こういった要素があるとは思うのだが。
「泣いた赤おに」は一層、この「未完」の要素が強いように思う。
究極の未完であるからこそ、
物語の紡ぎ手としての自分が暴れだす。
この後の筋を描くのは、自分なのだ。
わたしは読み手から、書き手に変えられてしまう。
赤おには、青おには、どうなるか。
人間たちとの関係はどうなるのか。
わたしが描くしかない。いや、描きたい。
そして物語を描く中で、気付いたりする。
自分や世界、そしてその関係に対して、
自分が望むもの、信じているもの、大事にするものを。
自分が紡いだ物語の中には、
“わたし”が表現される。
さて、今日の自分は、
「泣いた赤おに」の続きを、結末を、
どう思い描くだろうか。
今日の自分は、どんな自分だろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
