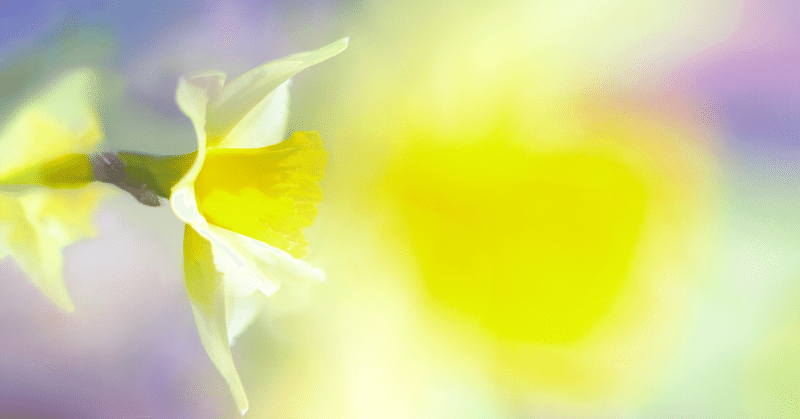
絵画空間(時・空軸の交換など)//モーリス・ユトリロの無重量感
2010.03.19 Friday | category:雑記-絵画・美術
2002年12月13日/24日:HPに記載したもの
絵画空間(時・空軸の交換など)
形而上絵画~未来派にかけては、絵画空間といういわば“生まの”時間軸を欠いた次元の中で、その非運動性/静止性というものを存分に発揮させようとする傾向と、その逆を行くもの、つまり時間軸の空間化をあらゆる手段で試みる傾向のものとがある気がする。
前者は典型的にはモランディのようなもの、その他(ミロの一部やキリコ、カルラ等)多くの形而上絵画作品、またマグリットのようなシュルレアリスムも一部分、そうした〈要素〉を含むであろう。(それのみでないが)
後者はたとえばボッチョーニなどの生々しげな手法によるなだれるような絵画に典型的に見出される。ボッチョーニでは、ラファエロ辺りから既に見いだせる古来からの手法の延長のように、複数の人を用いて継承される挙動の連続性=時間軸の空間化・軸の交換処理 をほどこすなり、同じく(運動する複数の)影で、それを暗示する、という方法をとる。
他方、知的なもの?の介在を示唆する一群によく当てはまる前者―*キュビズムのやったことも或意味そういう訳だし、モンドリアンの具象性排除も或る種そうした意味をおのずと含んでくるだろう。当然それはデュシャンらのダダイスムやデ・シュティルにも通じている―に関しては、そもそもそれらを惹起させたセザンヌの試み自体、その目的を持っていた。
*…これに就いては、「否。キュビスムとは断続的“運動”性そのものだ」と言えるかもしれないが、時間軸の空間化ないし空間軸の時間化とは変幻するものの同一「次元」への閉じこめを意味するのであって、おなじものの多様相を二次元へと封じ込めることによって見事に生きた運動体の統合的―諧謔的でもある―静止性を実現するともいえるのである…
が、二次元世界という空間軸で時間軸の示唆を行うには、色値変化か、動作所作――運動という非連続の連続――の帯びる指向性によってそれらを擬似的に暗示させるしかないのであって、そういう意味ではこうした傾向というのは必然といえば必然なのでもある…。
ただ形而上学絵画という、既得観念の陥穽・錯覚を逆利用したかのような一連の絵画が、どちらかといえば静止的な様相をおびるというのはおもしろい。―彼ら自身、或る種の観念至上主義に居る という場合も、あり得る―
こうした時代のなかで、ユトリロのもつ静止性というのは、―見ようによってはたしかに、彼の筆致の上/下向・奥行きのなさが及ぼす独特の非現実感覚が、一種トリック絵に見えなくもないような、少し特異な感も与える。しかしここに通底してある「厚みのなさ」!は――かれの孤独と不可分である。
“生まの”時間軸を欠いた次元” とは何か、について――現在は画家の転生史という観点から考え直すことが出来る気がしている。不思議なことに、また興味深いことには、形而上絵画の画家には、エジプト由来の魂が多い。したがって彼らの意匠は ある同じ定型を、おのずから志向しているのである。これについては別途述べる。(23/08/08 追記)
モーリスユトリロの無重量感
建築物における〈厚みのなさ〉といったのものは、写実主義にもあるし、形而上絵画にもある。写実主義においてはそんなことはありえないように一見思われそうだが、かなり透徹した写実主義、その極地にも現れる。
カナレットなどはその典型で、写実性そのものに於ては頂点にあるひとりだと言ってよいのだろうが、重力感といたものはかなり削がれている。そういう性質が、かたやターナーのような茫洋さへ、かたやボニントンなどの印象派に“通じる”人びとへと受け継がれていったようにみえる。
*私の手にある小さな美術書では、ボニントンはカンスタブルやドラクロワの路線を継ぐとしてあるが、むしろカナレットからくる要素も大きいように見える。色彩などは、(ドラクロワ→)カンスタブルからのちのテオドア・ルソーに通じるような所があるが。
ボニントンに於ては、建物の厚みのなさは、ターナーの宙に浮いたような茫洋とはまた少し違った、特有の精妙さの中で継承されていったように見える。
他方、写実主義と逆に、印象派はみな厚みを帯びないかといえば、意外にそうでもない。モネの教会も、シスレーの教会も、輪郭のさほどはっきりしないスタイルのなかで、ものの厚みと質感を光と影を通して間接的に時間の経過と共に具現している。
さてユトリロの建物の厚みのなさは独特である……。筆致としてはかならずしも薄弱でなく、輪郭線を強く出し、入念に「黒」を入れてものの境界線をはっきりと打ち出しているのだが、その建物の存在自身はというと、まるで舞台の建て具のように、厚みを帯びていないのだ。
あるいは右半分がすっぱりと切り落とされたような哀愁をたたえた教会があったりする。
パリの急坂の路地の果て、遠くにみえる長い階段も、徐々にのぼっていく辛さを演出しているというよりは、むしろ垂直に立った塀にひとが何人かへばりついている―しかも、宙に浮いた格好で!―とでも言うようだ。
こういう厚みのなさ、奥行きと重量感のなさとは何であろうか。 かれの実存は孤独の宙に浮いたようだ。しかしそのような非現実性のなかにこそ、かれの虚脱感にも近い哀愁がただようのである。
無重量感とは、つよい輪郭線によっても、黒を多く使う明快なコントラストによっても克服される事なくにじみ出うるのだというのを、かれの絵から知らされる。
noteに、サポートシステムがあることを嬉しく思います。サポート金額はクリエイター資金に致しますとともに、動物愛護基金に15%廻させていただきます♡ m(__)m
