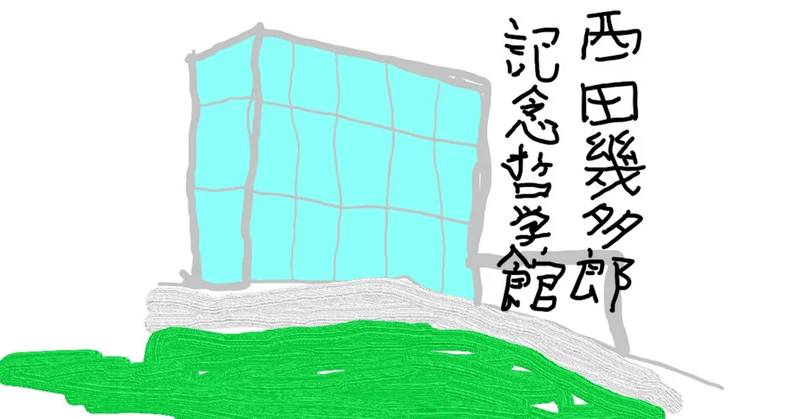
西田幾多郎の生命哲学④
そして、もちろん考えるべきことは、眼はいったん形成されると、それで進化を止めてしまうわけではないということである。眼は「個体」においてつぎつぎと形成され、それらはそれぞれが「問題」である世界に対する、まさに種的で歴史的でもある「解答」をなしている。しかし、光という課題は与えつづけられる。それはまさに無限の課題として与えられる。だから生命は、ある局面においては、まったくあたらしい眼をつくりだすものであるのかもしれない。まったくあらたな視覚の器官を発生させるものであるかもしれない。しかしそれも、個々の眼を生み出している、「個物」の「動揺」する「現在」こそにゆだねられている。
生命は、生きているかぎり、自ら動くものとして、こうした「問題」を解きつづけることをやめはしない。「問題」としての光を解きつづけることが、視覚をもって生きていくということである。
(檜垣立哉『西田幾多郎の生命哲学』)
「問題」が生体をつくりだす。要はその「問題」を身体の諸器官がいかに認識するか、「問題化」するかにある。そのありさまは「動揺」という表現で言われている。問題を知るため、見るために眼はつくられる。だから、眼が先なのかもしれない。その眼は問題に応じて進化し、深化する。眼が視覚を擁する。そして問題の源泉でもある光をまた擁している。問いそのものが構造を容認して、問いに対する「解答」が構造を準備する。構造なのか、「問題」なのか、その選択ではなく、構造が「問題」なのだと言い切れるような構造(それは認識によるメタ構造であるかもしれない)こそが重要なのであり、眼が眼を見るような構造(デリダなら膣状陥没というかもしれない)がここでは出来しているのだ。主観である眼が客体である眼を見る、あるいは見られる。その相互作用の中に歴史が刻まれ、時間が彫りこまれる。眼が眼であることをやめた時、歴史は閉じ、時間は終わる。だから、眼は見続けなければならないし、見られ続けなければならない。それが生物における進化というものなのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
