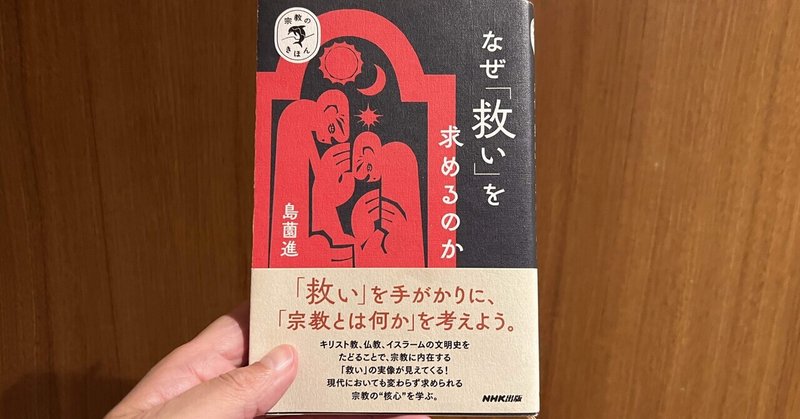
『なぜ「救い」を求めるのか』島薗進、NHK出版、2023
「なぜ『救い』を求めるのか」というタイトルから、「人間はどうすれば救われるのか」ということを説く本かな、と当初想像していた。
実際、第1章においては、苦難の人生から死によって救われること、あるいは生きている間に魂の再生を経験すること、さらには新たな「精神的な高みやいのちの尊さの体得」(p.49)などが、物語や詩や歌などを通して得られる事例を紹介してある。
「救い」とは「苦難や悲しみに耐える力、深いなぐさめや希望、そしてより良き生への意欲を促すような語りかけ」「苦難や悲しみを負って生きる人間同士の共感、また、その共感を踏まえてともにより良き生へと歩んでいくことへの呼びかけ」(pp.51-52)なのである。
しかし、第2章以降は、「救い」を与えようとする宗教、「救済宗教」と呼ばれるものが歴史の中でいかに変遷し、社会に影響を与えてきたかを、宗教史的に説き明かしてゆく。
筆者にとって、最も関心を引かれたのは、人類に差別・排除・蔑視・抑圧をもたらしているのは救済宗教だということである。その最たるものは戦争であろう。
巷ではよく「一神教は好戦的だ」「多神教は平和的だ」と通俗的に語られる。しかし著者によれば、その区分は適切ではなく、一神教/多神教にかかわらず「救済宗教」こそが攻撃性を持つ。救済宗教は「すべての人が救われる」ことを説きつつ、「その教えを受け入れない者は救われない(存在を許されない)」という矛盾を抱えているのである。
また救済宗教は、帝国主義や植民地の拡大とも結びつき、武力統治を側面から支えてきた(p.82)。また、弱く貧しい庶民を懐柔することで、階級社会を正当化する役割も担ってきた(p.85)。
本書は、日本独特の救済宗教の展開も紹介している。特に中央の権力と結びついてゆく神道と比較して、地方分散化、民衆化してゆく救済宗教としての仏教集団の歩みが描かれており、それが因果関係は無いものの、ヨーロッパにおける宗教改革と似ていることを指摘している。
15世紀以降、救済宗教は民衆のものになってゆき、その延長線上に、新宗教(その代表的なものとして、黒住教、天理教、金光教など)の登場がある。
それてさらにそのような日本独特の救済宗教の流れから、オウム真理教や統一協会なども現れてくるのである。
第3章では、19世紀以降の宗教学の始まりとその発展、「救済宗教」という言葉がどのように生まれ、研究されてきたのかを論じられている。
トレルチ、ウェーバー、マルクスなどドイツの哲学者の宗教論が紹介されてゆき、特にウェーバーの宗教史に注目して、それを大まかにわかりやすく解説し、有名な「カルヴァンの二重予定説が資本主義の発展の契機となった」という学説に至るまでを見てゆく。
ただし、資本主義が発展してゆくにつれて、宗教は次第に社会の表舞台から後退してゆくことも、ウェーバーは暗示している。プロテスタントは救いの確証を得ようとして勤勉に働くけれども、次第に「救い」から離れて、「ただ働き続ける人」になっていってしまうのである(pp.126-129)。
さらに著者は、ヤスパースによる、人間が「限界状況」(死、苦悩、闘争、負い目)に直面し、それを越えられない時にこそ、人間は「実存」というものを自覚せざるを得ないという考えに触れている。この実存の自覚が、人間の救済というものと深く関わってくる(pp.133-136)。
そして最終的には、アメリカのベラーの紹介をもって、これらの宗教学者、哲学者たちが、自分自身の救いを巡って格闘する中で、救済宗教の意義を研究し続けたことが、我々にも影響を与えていることが説かれる。
第4章では、近代科学の発展や、現世の幸福や充実こそ重要であるとする思考を根底に置く「宗教批判」と「世俗化論」に直面することによって「救済宗教以後」の時代がやってくることが論じられている。
「宗教批判」の最たる存在はマルクスとニーチェである。この2人の共通点は、救済宗教が「現実の状況との直面を避けて、問題をずらして擬似的な安らぎを」(p.166)弱く貧しい民衆に与えようとしているとしている点である。
また、科学の発展や合理性の浸透、生活の個人化などによって起こる「世俗化」によって、近代以降は宗教がどんどん後退してゆく。
しかし、世俗化によって救済宗教の影が薄くなっていっても、科学だけでは人間が直面する様々な問題を解決することはできない。そのままでは人は救われない。
そこで宗教界の動きは「救済宗教以後」という局面に移ってゆく。
その1つは、新しい(知識層の宗教離れとは対照的な)民衆による信仰復興である。それは、日本で言えば天理教のような新宗教の台頭であり、あるいはキリスト教の世界で言えば、福音派やペンテコステ派の庶民層への広がりである。
もう1つは、エリート階級の世俗主義の限界が意識される中で興隆してきた「スピリチュアリティ」だ。スピリチュアリティは瞑想からアルコール依存症の自助グループまで、様々な展開を見せているが、いずれもヤスパースが指摘したような「限界状況」に直面した人間が、「従来の宗教のように救済を強く唱えるのではなく、死や死別による限界を自覚した上で、その事実に向き合って心折れるようなことなく生きていくことを促し支える」(p.185)ものとなってきている。
このスピリチュアリティは「救い」と無関係なわけではない。
ただ、救済宗教のように「信じれば救われる」「信じなければ救われない」という二分法を人間に要求するのではなく、もっとおおらかである。そして、それは個々人の死に直面するチャプレンや臨床宗教師によるグリーフケアなどの働きに結実してゆく。
あるいはそのような専門家ではないファシリテーターによって導かれるスピリチュアル・ペインの癒しも行われるようになってきている。
それも一種の「救い」であり、スピリチュアリティの世界は救済宗教と全く無関係ではなく、相互補完的なものと考えられるのである(p.192)。
このように本書は、救済宗教が力を持っていた古代から、衰退しているように見える近代以降までを概観するが、最後に、これまでとは違った地域でキリスト教やイスラームが再び勃興してきている事実や、コロナ禍による若い世代への深刻な影響などを根拠としながら、民衆の貧困や孤独に対峙する救済宗教の再興を予測している。
「人間とは何か」「自分とは何か」そして「いかに生きるか」を問う人間にとって、救済宗教は決して過去のものになったわけではない。救済宗教との対話はこれからも続いてゆくであろう、とする。
いささか長い要約となったが、このように本書は比較的短時間で読める小さなサイズの本でありながら、非常に広い視野で救いの宗教について見直すのに有益な内容を凝縮してある。
確かにこの本は、「いかに救われるか」をひとつの宗教観の立場から「説教」(説法)するのではなく、宗教を「外」(p.199)から見る立場をとっている。しかし「救い」をメインテーマとする宗教者にとって、こうやって客観的に自らの信じているものを見つめ直す視点は必要であろう。
また、あくまで客観的な叙述ではあるが、それでも人が何に「救い」を求めているのか、宗教者は何を説き、現代においてどのような実践を求められているのかを考える上で、大きなヒントを読み取ることができる本だと思う。
『なぜ「救い」を求めるのか』というタイトルは、「それを著者が教えてさしあげましょう」ではなく、「あなたはどう考えますか」という問いかけなのではないだろうか。
読む価値のある1冊だと思う。
よろしければサポートをお願いいたします。
