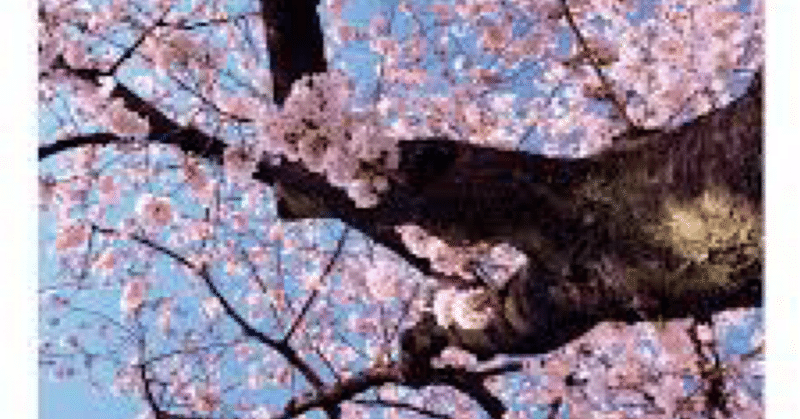
中村一義『春になれば』が出た頃に(音楽レビューエッセイ)
桜の開花情報が出て、その情報は一分咲きから二分咲きに更新され、僕はそれを実際に確認することもできない日々の中で、目の前のことが落ち着いたら目黒川に行って桜でも見たいな、と思っていた。
目黒川の花見は高校の近くだったこともあって、よく行った。
疫病が蔓延してからは売店などが無くなったらしい、今ではやっているのだろう、あの焼き鳥やイカ焼きを高校生の時は高くて買えなかった、しかし桜はその数年の間にも構わず咲き続けていたのだろう。
このところの生活といえば、部屋に篭って小説の新人賞を書いていて、他に参加している同人誌の原稿もあり、集中力を保つために、気晴らしの外出以外は早寝早起きの生活習慣を維持しながら机にずっと向かっていた。
選考に引っかかるかもわからないのに書くのは酷く恥ずかしいのだが、その原稿はこの秋から冬にかけての問題意識について書いていて、長くイメージはあったのだが、実際に書き始めた時は大体ZAZEN BOYSの十二年振りのアルバム『らんど』が出た、まだ寒さの厳しい風が吹く頃だった。
その頃の僕は自分がちゃんとしたカタチのものを書き上げられるか心配だったのだが、『らんど』が出たこと、向井秀徳が変わらずに、そして確かな進歩を遂げて、新加入したベースMIYAと共に、確かに冷凍都市で軋轢の中に暮らす僕の精神を強く突き動かす音楽を届けてくれたことは、救いと言って良かった。
恥ずかしいことながら、初めての新人賞の原稿ということで、評価されたいという気持ちも無いではなかった僕は肩に力が入り過ぎていたのだろう。
なかなか上手く書けずにいて、大変なことになってしまうかもしれない、と思っていた。
しかし、向井秀徳がインタビューで、アルバムの最終曲「胸焼けうどんの作り方」の終盤に聞こえる向井の声「どげんだっちゃよか」(博多弁で、どうなってもいい、のニュアンス)が入っていることについて、「結局こうにしかならない、これが俺だ」と言っているの読み、向井ですらこうなのだから、俺にできることをやるしかない、という気になった。
それからは毎朝にコンビニに行ってエナジードリンクを買って外の空気を吸い、ZEZEN BOYSを一通り聞きながら原稿を読み返して、音楽を止めて原稿を書き進める、という生活になった。
この原稿については書き終えてからあまり月日が経っていない(実際に出版社に応募したのは昨日だった)こともあって、あまり言いたくないのだが、去年に大江健三郎が死に村上春樹が新刊を出したこと、映画界で言えばジャン・リュック・ゴダールが死んだこと、音楽界で言えば、高橋幸宏と坂本龍一が死んでチバユウスケが死んだこと、最近では鳥山明まで亡くなった、そうやって僕を支えてきてくれた人たちが僕が僕自身を支えられる前に去っていく中で、自分のまだ筆の未熟な二十二歳の作家志望としての限界を突き詰めたいという気持ちは少なからずあったように思う。
大江健三郎は、1985年に発表した文芸評論で、文学とは言葉で未来の地平を押し広げることにある、と書いていて、それを僕は去年に岩波書店の雑誌「世界」の再掲載で読んで、本当にそうだよな、と純粋に思った。
僕の年齢は大体大江が芥川賞受賞作「飼育」を書いた年齢と同じぐらいで、はっきり言って僕は大江とは作家としてのレベルは違うのだが、大江が去った今になって、少なくとも自分の言葉の地平は押し広げることが出来た、という実感は得ることが出来た。
村上春樹は、作家は一年に一冊の小説を書いて十年経てば成熟してくる、と書いていて、僕はそれを額面通りに受け取り、ならば十年は諦めずに新人賞に書き続けよう、と覚悟を決めて書き始めたのだった。
奇しくも、そして不遜なことを言えば、新人賞を提出した日には、ラテンアメリカのノーベル文学賞作家ガルシア・マルケスの最後の未完の著作「出会いはいつも八月」の日本語訳が発売された。
僕は大体そのような2024年の春に生活していた。
その制作期間の間には、最近話題の柴田聡子を筆頭に、優れた新譜が出ていたのだが、大体原稿に意識の殆どを割いていた僕は、一度通しで聴いただけのものが殆どになってしまったのだが、中村一義「春になれば」だけは、原稿の最後の方を書いている時に、何度となく聴いた。
その曲は中村一義のシンプルな曲調で、繰り返しコーラスに「春になれば」と歌っていた。
この曲が出たのは三月二十日で、まだ風が冬の底冷えが残る温度で気晴らしに煙草を吸う僕の側を吹き抜けていて、しかし確かに花粉が飛んでいて、僕はよくクシャミをしていた。
この前に参加している同人誌の、音楽を作る友人の曲制作の風景をドキュメンタリーで撮影していた時に、cero「Summer Soul」は五月リリースだったという話になり、そのリリースと制作時期のズレのことを考えて、それは「予感」なのかもしれない、という話になった。
僕は中村一義がしきりに「春になれば」と歌うコーラスを聞きながら、それは僕はいつにこの曲が作られたのかは分からないけれど、確かに今の僕は季節的にも生活的にも冬の最中にいるようで、ただ中村一義が「春になれば」と繰り返し言い聞かせるように歌ってくれたのだから、それはいつ来るか分からないとしても、「予感」として信じることが出来たのだった。
中村一義は、僕が先に書いた向井秀徳のバンドNUMBER GIRL、くるり、スーパーカー、といった僕が非常に大きな影響を受けた所謂97年世代のミュージシャンで、「金字塔」はまさに僕の生活に根付くランドマークだった。
彼らが今でも変わらず音楽を僕の耳に届けてくれることは非常に嬉しいことだ。
曲の話をする時に作家の話はあまりしたくないのだけれど、「金字塔」には若い中村一義の宅録の雰囲気やその青さと必死さが出ていて、素晴らしいアルバムだ。
そして「春になれば」はその中村一義がキャリアを積んで書いた曲だということを十分に分からせてくれる。
エイジズムの蔓延するこの社会で、作家が年齢を重ねて確かな習熟を見せてくれることは、何より青年期を終えていく僕にとっての救いでもある。
そして僕はその中村一義や先に挙げた作家たちの決定的な作品を出した年齢を、「春になれば」のAメロの歌詞「ああ、気づいてみれば、今、僕はもう、君の歳を行く。」というように過ぎ去っていく。
僕の年齢になると、僕は二年間浪人していてまだ新人賞の原稿を書いているなどフラフラしているが、現役で大学に行った同級生は春から社会人になる、という年齢で、僕は彼らに羨望と応援の気持ちを持ちながら、自分自身や社会に対する責任やモラトリアムの終わりを感じながら生活している。
二十二歳の青年としても、大学に入って作家を志して二年が経った売れもしていない不安定な作家志望としても、何より、中村一義がバンド100sの代表曲「キャノンボール」で歌っていたように、「僕は死ぬように生きていたくはない」という心持ちだった。
あの向井秀徳でさえ、音楽をやることでしか生を実感出来ないと言っている。
僕が書き上げた原稿は誰も読むことはないかもしれないが、それでも僕は書き上げて確かな生の実感を得ることが出来たし、それだけでも十分に、また先に挙げた作家たちのように何かの仕事をできるようになるまで、書き続けようという気分になれたのだった。
原稿を書き終えた気持ちは、長いこと誰にも会わず部屋に閉じこもっていたのもあって、誰かに話したかったのだが、参加している同人誌は今月末の締め切りで、誰にも話せそうにないので、そちらの合間に書いてしまった。
こういうことを書くのは酷く恥ずかしいことなのかもしれないし、中村一義についてもう少しちゃんと書けば良かったのかもしれないが、僕は音楽レビューの専門でもないし、これが僕と中村一義の新譜の確かな距離感で、素直な感想と言えた。
僕がこの先も小説を書き続けるかは分からないし、何より評価されるのか分からない。ただ、その「春になれば」という予感だけは、この長い冬の中で書き続けてきて、そして同人誌の原稿に向き合っていく僕の中に確かにあった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
