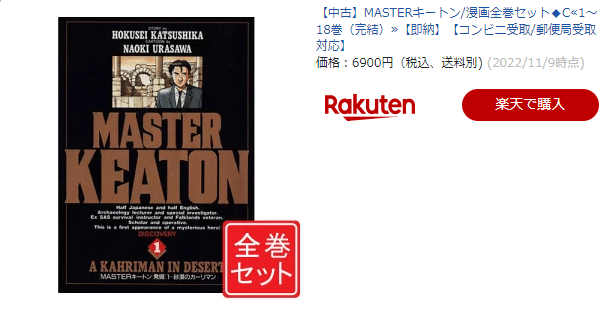「鶴巻温泉の碁会所へ、東海大学囲碁将棋部」
こんにちは。
IGOcompany-Uです。
囲碁をビジネスに起業して「宇佐美囲碁教室」っていう教室を運営したり、様々な場所で講義したりして、囲碁でご飯を食べてます。
先日、後輩に教室をお任せして、
本日は、武蔵小杉の永代塾囲碁サロンにて、宇佐美囲碁教室の木曜教室・入門レッスン・交流会がございます。インストラクターは俵・古屋でお待ちしています。写真は、意味もなく昨日行った秋晴れの高尾山です。 pic.twitter.com/nFgXvimLXk
— USAMI (@sakinohaka0520) November 3, 2022
お世話になった鶴巻温泉の碁会所へ挨拶に行ってきました。
僕は珍しく所用でお休みでして、お世話になった鶴巻温泉の碁会所に挨拶に向かっています。 pic.twitter.com/nU2RHDnrBK
— USAMI (@sakinohaka0520) November 3, 2022

僕は大学の時に囲碁を覚えまして、1年の社会人経験を経て、その3年後くらいには囲碁インストラクターになってました。
その当時の囲碁業界で働く人は、ほとんどが元院生か、あるいは全国大会の上位入賞者ばっかりだったの、ホント異色だったと思います(横のつながりもなかったんで、誰だコイツはって感じだったかもしれません)。
最初の頃の棋力は、三段もなかったですしね。。。
囲碁は、どうやって覚えたのかというと、この碁会所に乗り込んで強引に教えてもらいました。ほとんどルールも分からないくせにイキナリ単機突入してきた若造はさぞかし空気が読めなかったことでしょう(笑。
当時は、今よりももっと「強くなったら遊びにおいで」といった空気感があった時代です。よくめげずに毎日通ったものです。。。
遠藤さんっていう席亭の人に、ホント良くしてもらって(この人のエピソードはとても書けないんですが、めちゃくちゃ凄い人です)、お世話になりっぱなしでした。囲碁の師匠は誰ですか?って訊かれたら、遠藤さんですね。
社会人になってからも数年に一度はご挨拶に伺ってたんですが、コロナもあって、ちょっと間が空いてしまいました。
僕が教えてもらっていた時は、たしか70歳近くだったようなイメージで、今もお元気かなぁと(ちょっと不安に思いながらも)訪ねてみたんですが、そんな心配は全然いりませんでした。89歳になっても毎日テニスをするくらい元気なようです。本当に良かった!
挨拶の後は、近くだってこともあり、
10年以上ぶりに母校の東海大学へも。



ふと思い出したんですが、高校生の僕は「マスターキートン」に憧れていたので考古学をやりたくてこの大学に来たんでした。結局、ヨーロッパ文明から、卒論は「EU世界の展望」みたいな経済寄りのテーマになりましたけど。
まあ、全然受験勉強なんてしていなかったので、どこにも引っ掛からなかったら1年くらい浪人して美大に行ってみたいなぁってオボロゲに考えてたりもしました。
東村アキコ先生の「かくかくしかじか」でも書いていましたが、田舎の高校生なんてそんなものです(笑。市内に塾なんてありませんでしたしね。
幸いなことに、学校の中では成績の良い方だったので推薦をもらって進学できまして。合格が決まった時は、東京で一人暮らしが出来る!って、めちゃくちゃ嬉しかったのを覚えています(※実際には神奈川ですけど)。
まあ、何か話は逸れましたけど、囲碁将棋部にも寄ってみました。
東海大の囲碁将棋部にも顔を出してみました。。。 pic.twitter.com/9fNg0VMeVP
— USAMI (@sakinohaka0520) November 3, 2022
後輩たちに囲碁を教えたりして、何故か話が弾んで「もっと教えて欲しいです!」って感じになったので、迷惑じゃなければ、また教えてあげるね、とLINEを交換したり。(仕事じゃない)大学生との距離感が難しいので、ちょっと緊張しましたね。。。
まあ、僕も、誰か教えてくれる人がいたらもっと上手くなれたのになぁってずっと思っていた人間なので少しは後進に対して良いことをしようかなと。
今月中に、1回くらい行ってみようと思います。
囲碁将棋部のTwitterをフォローしたりも。彼らは望星会の企画したスポーツ大会で囲碁将棋部が7部門中、バスケ、卓球、バドミントンの3部門を制して優勝したのを知っているんでしょうか(笑。
何故か、めちゃくちゃ運動が出来る囲碁将棋部でした。
更新が止まっている昔の「ホームページ」が残ってまして、僕の名前もありましたね。平成16年度の春季リーグでは7勝0敗の全勝、秋季リーグでは2勝碁5敗だったようです。僕の記憶では、どちらも好成績だったはずなんですけど、全然違いました(笑。
まあ、この時は囲碁を覚えて2年目くらいだったので、そんな実力だったと思います。
鶴巻温泉の碁会所に行ったり、大学に寄ったりすると、なんか懐かしさがあって良かったです。他の大学で囲碁の講座を担当したこともあるので、母校でも開講しないかなぁとか、ちょっと下心的な期待(?)もしつつ、まあ、後輩にご飯でもご馳走してあげようかと思ったりしています。
本日は、そんなツラツラとしたnoteでした。
毎日noteがどうにか続いています。今日で250記事目のようです!拙い文章ですが、最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
良かったら下のバナーから教室の案内が見れますので、覗いてみて下さい。
サポートありがとうございます。コロナの影響もあり、今囲碁界はどんどん縮小していっています。どうにかしたいと思っている方は多いと思います。まずは小さな一歩から、囲碁の本を買ったり、近くの囲碁サロンに行ってみたり、周りに囲碁を教えてみて下さい。サポートは囲碁普及に使わせて頂きます。