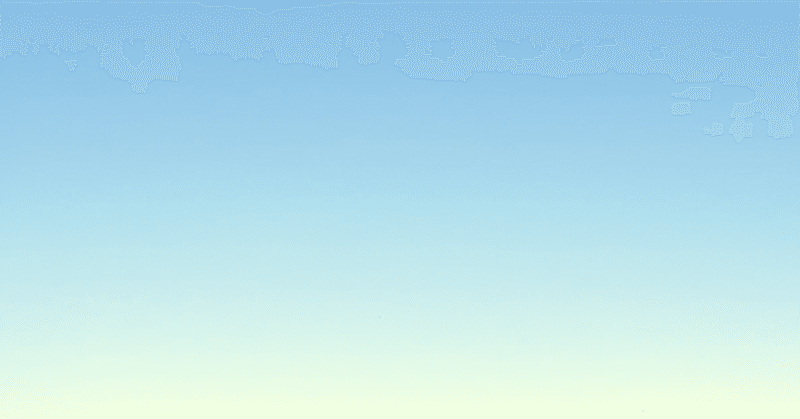
ちゃんとしようよ
2022年10月26日(水) 晴れ
快晴だ。風はすっかり冷たいけれど、陽が当たると少し汗ばむくらいに暑い。今日はどんな話をできるだろうか、と考えながら歩く。ローソンでトイレを借りて、南アルプスの天然水を購入した。そしてカウンセリングルームのインターホンを押すと、先生が戸惑ったような表情で出てきた。予約した日付が間違っていたのだ。
俺が『(10月)26日で』と言ったのを、先生は『(11月)26日で』と受け取っていたらしい。その確認が甘かった。しかし、先生を責める気にはなれなかった。俺は以前に予約をすっぽかしたことがあって、そのときはキャンセル料もとられず、むしろ「予約をすっぽかしても大丈夫だった」という体験をさせてもらったのだった。どうしても話しておきたいことがあったわけでもないし、それならそれで、と思うことにした。
前回のカウンセリングを思い出す。「ちゃんとしようよ」についての話だ。そのときは仕事のトラブルに巻き込まれていたこともあって、どうも鬱っぽい状態が続いていた。その経緯とか、自分がどう考えてどう対処できたかとかそういった説明をしていくなかで、「ちゃんとしようよ」という言葉がポロっとでてきたのだった。それは、俺が普段は決して口にしない言葉だった。あまりに道徳的すぎて、それなのに漠然とし過ぎていて、口にする意味がない言葉だと思っていた。しかし、俺が日頃抱える憂鬱や、社会との軋轢のなかで感じている違和感を言葉にするのなら、「ちゃんとしようよ」の一言に尽きるのかもしれない。
「"ちゃんとしようよ"というのは道徳の話です。これを言葉としても持っている人はたくさんいるんです。でも、感覚として持っている人は少ない」
と先生は言った。つまり、「ちゃんとしようよ」と言う人はたくさんいるけれど、本当に心のうちで「ちゃんとしようよ」と思っている人は少ない。たいていの人は平然とルールを破り、自分の問題は棚に上げて、なんとなくそれを言った方がよさそうだというノリのなかで、「ちゃんとしようよ」と言っているに過ぎない、ということらしいのだ。しかし、俺の場合は感覚としてそれを持っていて、心のうちで「ちゃんとしようよ」と思っているがゆえに、そのシンプル過ぎる標語を口にできない。ちゃんとするためには自分がちゃんとしていなければならないし、ちゃんとしていない自分も認めなければならない。そして、ちゃんとしていない人にもちゃんとできないタイミングや事情があって、それをフォローし合ってこそ社会はちゃんとできるのだから、「ちゃんとしようよ」と舌先三寸で言ったところで実際なんの解決にもならず、日頃の地道な心がけとか、言葉遣いに注意を払っていくことでしか「ちゃんとしようよ」は体現できない。って、あらためて言えばそういうことになるんだけど、そんな自分にとって当たり前すぎることをわざわざ他人に説明したことはなかった。
しかし、当たり前だと感じていることにこそ自分を苦しめる規範意識が隠されている。そして、「ちゃんとしようよ」の奥にどんな反応や感情があるのか、この機会に探っておく価値はあるのかもしれないと先生は言った。たいていそこにあるのは恐怖とか不安とか怒りで間違いなくて、俺もおそらくそうなのだけど、何に対しての恐怖なのかが問題だろう。そして、先生との問答を繰り返していくなかで、突き詰めるとそれは「戦争が起こること」という結論になった。
戦争というと国家と国家のものを思い浮かべるけれど、それだけではなくてもっと個人的な、日常に潜んでいる戦争もあるだろう。国家規模の戦争だって、正確に分解してみれば個人の戦争の表現なのかもしれない。不条理な暴力がまかりとおる、日常生活における戦争。家庭での、学校での、会社での、電車での。あらゆる場面で起こる暴力。差別。怒号。強迫。俺はそれが怖くてしかたない。できることなら逃れたい。どうやらそういうことになるらしかった。そこには俺の傷つきやすさ、というか、現実に起こっていることとそうでないことの区別がつきづらく、自分自身の価値が否定されるように感じやすいことと関係があるようだった。その「否定されるような感じ」がどれほど現実に見合った感覚なのか、それを検討していくことがカウンセリングでやっていることのすべてと言えるかもしれない。
俺もちゃんとしない人間になろうとか、戦争を生き抜けるタフな人間になろうとか、そう思って努力したこともあるし、いまだってその願望を捨てきれてはいない。その方が楽だって思うから。だけどそうはなれないだろう。俺だってさ、暴力で他人を支配してしまいたいときだってあるんだぜ。まったくやってらんねえよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
