
「橋の上の怪異、青ゲット殺人事件」
なぜだか100年以上にわたって語り継がれている未解決事件である。不思議な出立ちの犯人による不思議な犯行の行い方が、猟奇性だけでなく、何か魑魅魍魎の仕業のような匂いを醸し出しているからだろうか。

1906年(明治39年)2月11日、福井県三国町の回船問屋(船主のために積荷を集めたり、船主と契約を結んで積荷を運送したりする中間業者)である橋本利助商店に吹雪の夜、訪問者があった。 訪問者は青の毛布(ゲット)をかぶり、同店の番頭である加賀村吉(30歳)に面会を求めた。 怪しいながらも村吉に取り次ぐと、青ゲットの男は加賀村吉の親族からの使いで村吉を迎えにきたと言う。
「親戚の婆さまが急病で倒れたので、すぐに来て欲しい」
外はほとんど吹雪であり、村吉はやや訝しんだが、親族の一大事ということもあり、 村吉は青ゲットの男と共に親戚の元に出向いた。
その2時間後、今度は三国町玉井にあった村吉の自宅にも青ゲットの男が来訪し、新保村から来て親戚の婆さまが重病の床で「三国のおっかさんに会いたい」と言っている旨を告げ、 話を聞いた村吉の母キク(50歳)も、青ゲットの男とともに吹雪のなかに消えていった。
またもやその1時間後、再び青ゲットの男がやってきた。 母キクを連れ出した時と同じ理由で今度は村吉の妻ツオ(25歳)に声をかけた。 ツオは隣家の荒谷マス(13歳)に子供の面倒を頼んだ。
村吉の妻が連れ出されてから40分後、また青ゲットの男が訪ねてきた。青ゲットの男は村吉の7歳の長男、3歳の長女も連れ出そうとしたが、留守番と子守を任されていたマスは不審を抱き、こんな雪の日に承知できないとその申し出を無視した。青ゲットはそれでも食い下がったが、結局マスを言いくるめる事ができず帰って行った。
翌朝、三国町と新保村を繋ぐ新保橋という橋の中央のあたりに大量の血液があるのが近所の大工により発見された。さらに橋の欄干が、バッサリと無くなっていたそうだ。


事件の第一報を受けた三国警察は遺体無き殺人事件として捜査を開始した。警察はこの新保橋にて誰かが殺害され、遺体を下に流れる九頭龍川に投げ込んだのではないかと考えていた。その後の捜索で加賀家の裏手に流れる竹田川に小舟がとまっており、その船縁に血液が付着していることが明らかになった。そして、村吉の妻ツオの遺体が竹田川の下流の川底で発見された。2月14日、三国警察が警察部保安課、福井警察署の応援を得て九頭龍川一帯を捜索すると、九頭龍川の河口付近で母キクの遺体を発見する。しかし村吉の遺体は発見できなかった。
さらなる捜査で新保村の親戚に病人など出ておらず、使いを頼んだ事実もなかったことがわかっている。この青ゲットの男、目撃者の証言によると「男の年齢は三十歳ぐらいと思われるが、人相については手ぬぐいをほおかむりにしてアゴで結び、その上に青毛布を頭からすっぽりかぶっていたのでハッキリ分からない」ということだった。 三国署は重大事件としてこの事件を扱ったが、有力な手掛かりを得るには至らず、1921年(大正10年)にこの事件は時効を迎えた。

色付き毛布(ゲット)について
ゲット(毛布)という呼び方は「ブランケット」からきている。1337年、イングランドのトーマス・ブランケットという人物がブリストンに織物工場を設立し、寝具用の毛布を初めて生産したことから羊毛織物一般をブランケットというようになったという説と、フランスのボーヴェという地で産出される白い毛織物をブランシェと呼んでいたことから転じて、英語読みでブランケットと呼ぶようになったという説があるそうだが、その実は定かではない。
しかし、明治40年代における毛布は贅沢品のひとつであり、当時毛布と呼ばれるものは国産ではなく、全てが輸入品であった。当時デパートなどで売り出された毛布の値段は4〜15円、100円もあれば、百坪の土地に30~40坪の家が買えた頃であり、犯人もそれなりに財力のあった者であろう。しかも、明治時代に流行した毛布は青ではなく赤である。当時は寝具というよりは赤毛布をマント代わりに体に巻き、防寒具のように使っていたようだ。特に赤毛布は人気で、地方から東京見物に出てきていたお登りさんがよく使っていたようだ。暖かいうえに、仲間とはぐれないためのいい目印になったからだ。

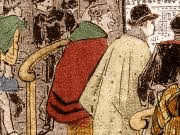
ゲットの着用がそれほど珍しく、奇妙な出立ちであったわけではなさそうだ。しかも、マントではなく、顔を隠すために使っている。村吉の家族は知っている顔であった可能性も考えられる。毛布のスタンダードカラーが赤なら、なぜ目立つ青を選んだのかは不思議だ。
赤マントの怪人
「赤マント」との関係性もよく引き合いに出されるが、青ゲットの男は頭部に巻き付けており、マントのようにしていないばかりか、何なら赤でもない。
「赤マント」というのは、正確には「赤マントの怪人」で、子供たちの間で流布された都市伝説の一つである。赤いマントをつけた怪人物が子供を誘拐し殺すというもので、1940年代に東京から発生した都市伝説である。さらに赤マントは「青いマント・赤いマント」や「赤い紙・青い紙」などへの亜種のバリエーションもある。

地域性や時代設定から確実に関係性は薄そうなのだが、赤ゲットの出立ちと通じるものもあり、連想して語られるようになったのだろう。青ゲット事件は怪奇事件というよりは、未解決大量殺人事件だ。
妄想と考察
橋本利助商店がどれほど歴史のある商店かは知らないのだが、村吉の苗字は橋本ではなく加賀であり、この商店は身内による会社運営ではなかったのだろうか。若干30歳の若さで加賀村吉は橋本家の身内を押し除けて番頭になった可能性もある。村吉はかなり仕事ができる男だったのであろう。商家における番頭は、使用人の中では最高の地位を持つもので、10歳前後から丁稚として住み込みで働き、手代という地位を経て番頭となる。番頭になりようやく自宅通勤となるケースが多いらしく、結婚も番頭まで許されないことが多いようだ。村吉は上の子が子供が7歳になることからも、23歳にはすでに番頭となっていた可能性が高く、結婚はもっと前だった可能性を考えると、随分若くから番頭として店を仕切っていたようだ。もしかしたら犯人は過去に橋本利助商店で働いていたものである可能性もある。
親戚の名前を騙り、一人ずつ家族を呼び出せたことからも、村吉の家族の情報に詳しく、さらに家族だけに標的を絞っていることからも、村吉に恨みを持つもののの犯行の可能性が高い。番頭への競争に負けたものだろうか。しかも当時はまだ高価なものであったゲット(毛布)をつけていたものなのだから、その辺の山賊などではあるまい。
ただ、北國新聞を読むとやや気にかかることがある。村吉の遺体がなかったことだ。村吉の家族の遺体は発見されているのに、村吉自身の遺体は発見されていない。記事には一才書かれていないのだが、商店に青ゲットの男は本当に訪ねてきたのであろうか、こうして100年経った伝承では村吉が最初に連れて行かれたとあるが、それは果たして本当だったのだろうか。村吉に恨みを持つのなら、もっと惨憺なやり方で遺体を放置しても良さそうだ。
当時高級な毛布を購入することができ、村吉の周辺の血縁者もよく知っているもので、一人ずつ親近者を誘き寄せることができるもの。もしそれが村吉本人であったなら、完全犯罪を成し遂げどこかにうまく逃げることができた事になる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
