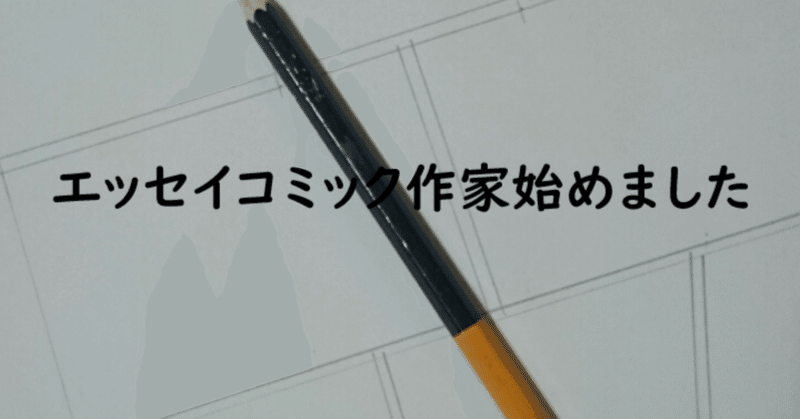
エッセイコミック作家始めました 第四話
全国キャンペーンも終盤を迎えた夜。福岡での出来事だった。私達はいつものようにもてなしを受けていた。放送局にふぐのコースをご馳走してもらい、満足感たっぷりでホテルに戻った。延岡清太郎が「飲み足りないから君の部屋で飲み直したい」といって来た。私の心は慌て放題だった。子供の頃に憧れていた俳優さんが、私と二人きりで飲みたい、と言ってきたのだ。場合によっては口説いてくるかもしれない。そして……。
『男女が真の友人になる事は無い』と言った人がいる。どんなに仲が良い友人でも、何かをきっかけに、男女関係の意識をする事があるというのだ。時には年齢や立場の差を越えてしまうのが男女なのだ。確かに高梨とはそうだったのかも知れない。漫画家のたまごと編集者という立場を越えて男女の関係になった。しかし流石に延岡清太郎とそんな事になるとは、想像の片隅にもない。しかし、急速に意識し始めている自分がいる事を否定出来なかった。
高梨とはもう1年以上体の関係はない。かつて恋人関係だった事を微塵も感じさてはくれない。高梨の心の中に私はもういない。私の心にも高梨はいないと思う。
私は動揺しながらも延岡清太郎を部屋に入れた。
部屋に入った瞬間に、私の意識が変わるのが分かった。延岡清太郎を、俳優の鎧を外した一人の男として、可愛らしささえ覚えようとしていた。このまま、あんな事やこんな事を……と受け入れ態勢を取ろうとしたが、結局何も無かった。延岡清太郎は缶ビール2本を喉に流し込むと「ごちそうさん」と言い残し、あっさりと部屋を後にした。
安堵と落胆が頭の中で社交ダンスを踊っている。私はこれもいつか漫画のネタにしようと決め、浴室に入った。テレビに出始めてからメイクを覚えた。そしてメイク落しも覚えた。まずはメイクを丁寧に落とし、シャワーを浴びた。バスタオルを髪に巻き、素肌にバスローブを着てベッドに潜る。テレビでも観ようとリモコンに手を伸ばしたその時、ドアがノックされた。
「はい」
私はドアの前で、そう返した。少し間を置いて「延岡清太郎です」と返ってくる。
「どうしました?」
私は自分の格好がどうであるかを忘れて、ドアを開いた。次の瞬間には、強烈なアルコールの匂いが鼻を刺し、唇に熱いものを感じた。延岡清太郎は私を押しながら部屋の中に進み、乱暴に私をベッドに倒した。続け様に唇を奪い、その唇をバスローブから露になった乳房に押し当てた。それからはごく自然になるようになってしまった。そう、あんな事やこんな事が実際に起きてしまったのだ。もう、漫画のネタには出来ない。
それからは、何も無かったかのように、全国キャンペーンは終わり、ドラマ『エッセイコミック作家始めました』が放送当日を迎える。
全国キャンペーンや、延岡清太郎がドラマ界に戻ってきた、という話題が功を奏したのか、ドラマは大成功に終わった。放送中の平均視聴率18.7%を叩き出し、大和放送は歓喜に沸いた。それと併せて『DESAIRE』の発行部数も伸び、トンボ出版の評価は上がった。『エッセイコミック作家始めました』の増版も決まった。当然、私の立場も上がった訳である。私に対する待遇も上がる。トンボ出版も、大和放送も、連載を持っている他の出版社や新聞会社から過剰過ぎる接待を受ける。
「これは完全な妬みだな」
私の発言を否定するような動画が、動画投稿サイトにあがった。困惑する私を慰めるために、高梨はわざわざ私の仕事場に来てくれたのだ。理由がどうであれ、それが嬉しかった。
一馬の父としての自覚が出てきたのか、お土産も持って来ている。最近話題の新食感チーズケーキを買ってくれた。
延岡清太郎との一夜があって以来、高梨を異性として考える事は無くなっていた。でもこうやって時々意識させてくる。本当にずるい男だ。
私は麻島まりか先生のように仕事は遅くない。ネームの打ち合わせも一発で終わる。優秀な作家の仕事場に、担当編集者が度々顔を出す必要もなく、彼と会う機会が減っていた。
「そうなんだ」
「ああ、恐らく、トンボ出版を妬む何者かの仕業だよ」
「それだといいのだけど?」
「お前は気にしないで、今まで通り描け」
高梨の男らしい横顔を眺めていた。もう気持ちは延岡清太郎に傾いている。もしまだ私に気持ちがあるなら誠意を示して欲しい。妻子と別れて、一馬と本当の親子になって欲しい。その気持ちがあるなら一発逆転はまだある。ただ、それは今じゃない。今、妻子と別れて私と一緒になったら、私は略奪したとして叩かれる。
「うん、それにしても卑怯だよ?」
仕事場のパソコンのディスプレーには、同じ動画が繰り返し流れている。誰が何の意図で作ったのか、さっぱり分からない。
「まあ、そんなもんだよ。それだけ俺たちが妬まれる存在になった、という事だ」
五分間程の、極めて悪質な動画。
映像は私の住むマンションの前から始まる。
漫画家でコメンテーターの灰谷由、つまり私は番組内で嘘の発言をした、という前提で進められる。撮影者が、どんな人物であるのか、動画からは確認できない。声はボイスチェンジャーで変えてある。
「何で私の家が分かるの?」
「有名人にプライバシーは無いんだよ」
「恐い」
本当にそう思った。
私がひったくり事件を目撃した、と言ったその日にそのような事件はなかった。念のために一週間前まで遡って調べたが、やはり事件の記録はない。けして広い道ではないが、人通りの多い道だ。ここで公然とひったくり事件が起こるとは考えられない。仮に起こっていたとしても、目撃情報が無いのはおかしい。つまり、私は、テレビに出るために嘘を吐いている、という事が結論付けされる。解釈を広げると『エッセイコミック作家始めました』の信憑性も疑われる。
という内容。
正直、怒りというよりは笑えた。悪戯にも程がある動画は、全くの嘘だらけ。こんな嘘吐きに、嘘吐き呼ばわりされるとは、呆れてものも言えない。
「確かに手段は酷いけど、こいつらは、こいつらでチャンネル登録者数を増やすために必死なんだよ。奴等がターゲットに選んだんだから、名誉と思わないとな」
高梨の存在を心強く感じた。落ち込む、というよりは驚きが強い。でも今は落ち込んでいるふりをした方が良いみたいだ。
「まぁ、トンボ出版はこの動画に動じない構えだ。しばらくはこんな事が続く。それにいちいち反応はしていられない。新聞社も男性誌の出版社も同じく『特段問題無し』というスタンスをとるだろう。しかし大和テレビだけは、そうはいかない」
「えっ、何で?」
「お前の発言を生放送した当事者だからな。もしあれが動画通り嘘だとしたら、大和テレビは信用を失う」
相変わらずデリカシーの欠片もない。やっぱり一発逆転は無いかも。
「そうか」
私は肩を落とすふりをした。高梨はその肩を抱いてはくれない。きっと、そんな心境にはなれないのだろう。私の淹れた紅茶には興味も示さず、自分が買ってきたペットボトルの炭酸飲料を、ガブガブ飲んでいる。
「あの、なんて言ったっけ、お前が貶めた経済評論家?」
貶めた……首を傾げる間もなく私の口から、あの名前が飛び出した。
「藤堂晶」
「そう、その藤堂何がしの時と同じ失態は繰り返したくない。場合によっては番組終了も余儀なくされる事態だろう大和テレビはナイーブになっているだけだ」
「そっ、そんなに」
少しだけ気分が落ちた。そんな私の顔を高梨が覗き込む。
「お前、もしかして……いや、何でもない。お前は自分の立場を守るために、嘘を吐く様な人間じゃないよな。それに、そんな直ぐ分かる嘘を吐くような愚かな人間でもない。コンビニ強盗事件だって本当だったし、漫画にした話も全部本当の話だった、そうそう」
何でもない、とは言いながら、結局は思った事を全て言っている。なんて馬鹿な奴なのだろう。でもそんなところに惹かれたのだと、昔の事を思い出してみた。
「信じてくれて、ありがとう」
本当に嬉しかった。恋愛感情はどうであれ、彼は守ってくれそうな気がした。
「まあ、これからもこんな事あるだろうけど、いちいち気にするな。いちいち気にしていたら、心が持たない」
それが別れの合図かの様に、高梨は肩掛けの鞄を手にした。
「ごめんね」
私はしおらしい女を演じてみた。延岡清太郎に強引に体を奪われて以来、男の恋しくなっていた。一馬に兄弟を作ってあげたいという気持ちもあったと思う。忘れたはずの男に、抱いてくれるかも、という淡い期待をしていた。しかし現実は期待通りにはいかない。漫画のような展開を現実は許してくれない。
「どうしたんだよ、急に?」
「いや、なんか嬉しかった」
「はぁ」
高梨はあからさまに怪訝な顔つきをした。
「だって、わざわざ来てくれたんだもの」
「そりゃ、そうだろ。あれだけしつこく言われたら、来ない訳にはいかないだろ」
素直じゃないところが憎らしい。でもそれも嫌いではない。
「あれ、ありがとうね」
「あれ?」
「あの、お土産」
「いったい、何を言っているんだ。お前が何も食べていないから、買ってこいって言った弁当だろ。担当編集者は作家さんの使い走りじゃないのですよ。俺は他の仕事で忙しいから、あんまり困らせないで下さいね、灰谷センセ」
そう言い残し、一度も振り返る事なく、高梨は去っていった。
ドラマ『エッセイコミック作家始めました』フィーバーが落ち着いた。私に対する誹謗中傷は加速している。
これは想定内の事である、と強がってみた。高梨達から事前に、必ず『灰谷叩き』が始まる事を伝えられていた。『有名税』という言い方もされるらしい。注目を浴びている有名人はその代償として、プライベートが明かされ、根拠のない噂が飛び交うのだ。噂や誹謗中傷は物凄い勢いで拡散される。辛いがこれは越えなきゃいけない試練なのだ。この悪天候が過ぎるのを耐えて待つしかないのだ。待てば風向きが変わる。その時、私は真の漫画家になれるのだ。
必ず通らないといけない道。覚悟は出来ていた。覚悟は出来てはいたが意外と堪える。そして苛立つ。
『灰谷叩き』は嘘ばかりだ。
ー母は献身的で優しい人物だったー
ー母は父の度重なる暴力に耐えていたー
ー父は私が小さい頃に亡くなっているー
作品の内容を真っ向から否定する、悪意に満ちたものばかりが、紙面やネット内を騒がせた。私を肯定や応援するような記事も、浮かぶのだが直ぐに沈んでいく。『週刊誌のスクープやネットのニュースは嘘ばかりだ』と色々な人から聞いていたが、ここまで酷いとは思わなかった。奴等は100%と純度の高い嘘を記事にしている。奴等はこんな嘘で金を稼いで心が痛まないのだろうか?こんなんで報道の自由とか訴えているとは情けない。
私に対する誹謗中傷や嘘記事が横行する。ネット民がそれに援護射撃を加える。この非常事態にトンボ出版や大和放送は、事態の打開を図って事実調査を行うと発表した。
「これも我々の仕事だ」
と高梨は言うけれど、真情は複雑だったと思う。いつものように能天気な笑顔をみせてはいたが、目の奥は笑っていなかった。相当、心労が祟っているのだろう。可愛そうに。そして申し訳ない。
「ねえ、これだけは信じて」
「なんだよ。今、忙しいから今度にしてくれるか」
本当に忙しいのか否かは分からない。でも高梨が私を避けようとしている事は明らかだった。
「いや、どうしても言いたい」
「えっ」
戸惑う高梨の表情に一瞬怯んだが、口は止まらない。
「もし、記事が本当だとしても、何の為に私は嘘を吐く必要があるの?」
「漫画を描く為だろ」
あっさり一蹴する。
「元々、エッセイコミック作家を志望していなかった事くらい、知っているよね?母の事も父の事もこの仕事をする前からずっと言っていたよね?」
「ああ、そうだな」
「それを知って、漫画を描けって言ったのは、あなた達の方だよね」
「まぁ、確かにね」
そう言うと「ごめん」と付け加え、高梨は応接間を出て行った。心が苦しくなってきた。この世から消え去りたいとも。もう、自分自身でも、何が本当で何が嘘なのかわからなくなってきている。この行き場の無い気持ちを共有したかった。私は直ぐに思い浮んだ延岡清太郎に連絡をしてみたが、いつまでも通じない。折り返しの連絡も無かった。
まさかと思ったが元USAGI CITYのMAHOROが私に嚙みついてきた。グループを脱退してソロ活動を始めたものの、なかなか上手くいかないもどかしさと、悪い噂が拡散される怒りを、誹謗中傷で弱り切った私にぶつけてきたのだ。
この時MAHOROはグループ時代の名を捨て、本名の坂下真帆で活動していた。いわゆるシンガーソングライターというのになったのだが如何せん歌が上手くない。けして酷くは無いのだろうが、USAGI CITYのカエデの圧倒的な歌唱力と比べられてしまう。
曲をリリースしてはUSAGI CITYの真似事と揶揄され、USAGI CITYの熱狂的ファンからは裏切り者と叩かれてしまう。
私はMAHOROの今の状況を案じ、世間から非難を浴びる同士として寄り添いたいと願いっていた。彼女のSNSのDMにメッセージした事もあったが、返事は返ってこなかった。
そんな時、MAHOROは暴露系と呼ばれる人気ユーチューバーの映像に出演したのだ。それは編集の出来ない生ライブ配信だった。数日前の告知が拡散されていて、あまりネットを見ないようにしていた私も知る事となった。
私は同士の苦しみを知りたくて、ついノートパソコンを開きその動画を見てしまったのだ。
まずタヌキの覆面を被ったユーチューバーが出てきて、視聴者に対して軽い悪態を吐く。そして「今日は凄い大物が登場だぞ」というセリフでMAHOROが登場する。髪型も色も化粧の仕方も違うけど、間違いなく私の知っているMAHOROだった。
ほとんどがUSAGI CITYの暴露だった。
USAGI CITYは元々MAHOROとギターの丈太郎とベースの田中アツロウの三人組だった。MAHOROはキーボードとメインボーカルを担当していた。USAGI CITYの楽曲の多くはMAHOROが作曲していて、世間が知るきっかけとなった『微熱』もMAHOROが手がけた。
私はUSAGI CITYが三人組でMAHOROがボーカルもしていた事を知らなかった。私が知った時にはカエデが既にいた。申し訳ないがカエデがいたから知ったのだと思う。
「当時からカエデと丈太郎は付き合っていた」
MAHOROの暴露に、タヌキマスクが「え~っ、マジで!マジで!」と大袈裟に反応する。
「えっ、今も?」
私が聞きたいと思った事を、タヌキマスクが聞いてくれた。
「うん、今も付き合っているはず、少なくとも私がいた頃までは付き合っていた」
そもそもカエデは他のバンドのボーカリストで、それを彼氏である丈太郎が強引に引き抜いた。当然、MAHOROは受け入れ難たかった。高校の時から三人でやって来たのに、今更何?と感じた。でも圧倒的なカエデの歌唱力を知って認めざるを得なかった。MAHOROはUSAGI CITYに足りないのが歌唱力だと分かっていたのだ。自分達が売れて、自分の作曲力が評価されるためにカエデの加入を歓迎するしかなかった。
「『微熱』はカエデちゃんが作詞になっているけど、本当はMAHOROちゃんなんだよね」
また私が聞きたい事だ。
「そう、『微熱』は3人時代に私が作詞作曲をした曲。カエデが歌うようになって少しだけ歌詞を変えたらいつのまにかカエデが作詞になっていた」
「それって、丈太郎君の策?」
「そう」というMAHOROの顔は曇っていた。
私は興味本位でUSAGI CITYやMAHOROでネットの検索をかけてみた。MAHOROに対する擁護の声も多いが、それ以上に非難する声が拡がっている。
MAHOROの暴露が30分も続き終盤を迎えた。そろそろ終わりかなと思った時にタヌキマスクがこう切り出す。
「漫画家の灰谷由さんがUSAGI CITYの大ファンでMAHOROちゃんと個人的に話した事あるって言っているけど」
「ああ、あれは全くの嘘。USAGI CITYのファンかも知れないけど、私との関係は嘘。大塚と池袋の間の公園になんて行った事も無いし、コンビニでソフトクリームなんか買った事もないよ。私ね、蚊が嫌いだからそもそも公園に行かないの。ましてそこで飲食をするはずはない」
落ち着いてきたMAHOROの怒りがヒートアップする。
「じゃあ、USAGI CITYのロゴも?」
「あれも全くの嘘。USAGI CITYのロゴは私の完全なオリジナルなんです。高校の時には既に出来ていたので、東京に来てから誰かの影響で出来たなんてありえない」
そんな訳ないよ。めちゃくちゃ喜んでくれたじゃない。私はその時のノートを今も持っている。
「あの漫画家は売れる為に平気で嘘を吐く人。でもそれを何も確認しないで発売しちゃう出版社も悪い。知っていながら何も言わない丈太郎も悪い」
相手が嘘を言っているとはいえ、トンボ出版を悪く言われた事は申し訳ない気持ちになる。
「そうか、大変だったんだね。俺はMAHOROちゃんを信じるよ」
と言いながらタヌキマスクがMAHOROの肩を優しく叩いた。
「きっとあの漫画家と丈太郎は気が合うかも」
「そうだよね。丈太郎君と灰谷由さんでユニット組めばいいんじゃないの?」
「それいいかも」とMAHOROは大笑いをした。
「ユニット名はUSO CITY」
「それ最高!私、USO CITYに楽曲を提供しようかな」
私はノートパソコンをたたみ、それを頭の上に持ち上げていた。「嘘吐きはあんたの方じゃないの!」と叫びながらノートパソコンを床に投げつけた。ディスプレーは割れ、キーボードのキーが幾つか散乱した。床には小さな凹みができる。
私は膝から崩れ落ち、声を上げて泣いていた。
『灰谷叩き』に追い打ちを掛けたのが麻島先生の死だった。
〈麻島が死んだ〉
突然の電話。久しぶりに高梨の声を聞いた。高梨の声は異常に震えている。
「えっ、えっ、どういう事ですか?」
〈詳しい事情はまだわかっていない、でも死んだ事に間違いは無い〉
「えっ、えっ、どっ、どういう事ですか?」
〈とにかくそう言う事だ。俺から聞いたと言うなよ。君との不用意な連絡は止められている。でもこの話はしない訳にはいかないだろう〉
漫画家麻島まりかは、自身の自宅で職場でもある『アトリエMARIKA』で自殺を謀った。発見は死後、数日経ってからで腐敗が始まっていた。残された遺書には『もう疲れました。楽になりたい』と記されていたらしい。創作力が沸かず仕事が減って、自暴自棄に陥ったのだとマスコミは報じた。
麻島まりか先生の自殺報道が、大きく扱われる事はなかった。麻島先生にはこれといった代表作も無く、マスコミへの露出もほとんど無い。無名な作家の死をマスコミが大きく扱うはずもなく、このまま麻島先生という存在が、漫画界から消えていくのでは、と心を痛めていたところだったが、マスコミの対応は一転し拡大報道に変わった。私が麻島先生のアシスタントをしていた事を知ったマスコミは一斉に、今の私の状況と自殺の原因を結びつけたのだ。
ー麻島まりかは、飼い犬に噛まれたー
ー麻島まりかは、灰谷由に殺されたー
ネット内は、灰谷陰謀説を唱える声の、大合唱となった。
高梨から麻島先生の葬儀日程と葬儀会場を伝えられた。
〈一応伝えたけど、行かないほうが懸命だ〉
これが高梨の意見。
「行かないほうが不誠実だと思うけど」
これが私の答えだった。私は麻島先生の葬儀に出掛ける事に決めたのだった。
麻島先生の通夜が営まれる山梨の斎場には、私の姿を捉える為のマスコミが集まった。
斎場に到着すると私はカメラに囲まれる。マスコミにもみくちゃにされながらも、無言に徹し中へ進んだ。
受付に香典を預け、芳名長に名前を書く。会場内の椅子に座り、通夜が開始されるのを黙って待った。会場も祭壇もそれ程大きくは無かった。時間が近付くと席が埋まっていく。どの顔も悲痛に満ちている。嗚咽を交えながら泣き崩れる者も多かった。
葬儀が始まっても泣き声は止む事はなかった。
私は僧侶のお経を聞きながら、麻島先生の事を考えてみた。麻島先生とはそれ程長い付き合いでなかったが、良くしてくれたような気がする。創作が上手くいかず時折沈む事もあったが、終始明るく振舞っていたような気がする。
焼香を済ませた参列者に、頭を下げる二人は、恐らく麻島先生のご両親なのであろう。横顔しか確認できないが、二人とも歳は50代後半から60代前半といったところだろう。二人共は辛さを隠せてはいない。特に母親は悲痛の面持ちが深い。子供を亡くす、という事は想像以上に辛い事なのだろう。
通夜が終わり、私は会場を後にしようと席を立った。また、マスコミに囲まれるであろう。それに備えて覚悟を決めていた。なるべく他の参列者や、遺族の迷惑にならないタイミングを計って、外に出ようとしたその時、背中から声が掛かった。
「灰谷先生。灰谷由先生ですよね?」
「はい」
私は振り返った。顔は強張っていたに違いない。
「灰谷先生、最後に娘の顔を見ていってもらえますか?」
声の主は麻島先生の母親だった。
「よろしいのですか?」
「ええ、勿論。どうぞ、まりかの顔を見て、お別れを言ってあげて下さい」
麻島先生の母親の目の下には、はっきりと隈が浮かんでいる。
「でも私……」
声を詰まらせた私に、麻島先生の母親は、優しく言葉を掛け続けた。
「灰谷先生。けして報道されているような事は無いですよ。娘はどんな些細な事も、私に話すような子でしたが、灰谷先生の悪口は聞いた事はありません。まりかは元々神経の細い子だったんです」
麻島先生の母親は、白いハンカチで目頭を押さえた。
「子供の頃から、大人しく繊細な子でね。明るくはしていましたが、落ち込んで臥せってしまう事も多く、いつかこんな日がくるのでは、と案じていました。守りきれなかった私達の責任です。東京での一人暮らしを許してしまったばかりに。漫画としての生活を許してしまったばかりに」
そう言うと、再びハンカチで目頭を押さえた。
「そうだったんですね」
「ごめんなさい。湿っぽい話になっちゃって。さぁ、まりかの顔を見てあげて下さい」
対面する前に、麻島先生の在りし日の顔を思い浮かべてみようと考えた。
在りし日、とは言っても二年近く麻島先生の顔を見ていない。私は遺影を基に、元気だった頃の麻島先生の顔を思い出してみた。
棺桶の小窓を開け、久しぶりに見た顔は、頭に浮かんだ麻島先生の顔から程遠いものだった。胸が詰まり、息苦しくなった。麻島先生の顔には化粧を施してはあるが、窶れみすぼらしかった。
「麻島先生、有難うございます」
そうは言ってみたものの、面影すらない顔を見ても、実感が沸かない。麻島先生の死を受け入れるのには、まだ時間が掛かるのかもしれない。
私は冷たい麻島先生の顔を撫でながら考えた。
精神を壊して自殺を選んだ人の最後は、こんなにも哀れなのだろうか、と。それから止め処なく疑問が浮かんだ。私が離れた後、彼女はどんな心境で過ごしていたのだろう?恋人は居なかったのかな?誰にも相談出来なかったのかな?と。
麻島先生の葬儀から自宅へ戻るタクシーの中『DESAIRE』の休載の知らせが届いた。事実調査がうまく進んでいないらしい。事実調査も進んでいないし、ほとぼりが冷めるまで休みなさい、という事なのだろう。反論したい気持ちはあるが、それを抑えて、トンボ出版の考えに従った。スポーツ新聞と、男性誌の連載はこれを機会に終了した。
痛いのは『ウイークデイ』から長い休みを貰った事だ。影響力の高い媒体であるテレビの出演が無くなった事で、悪い噂が一層広まる可能性を危惧した。案の定、ネット民はこれを事実上の降板と騒いでいる。捏造を投稿した者を特定して、名誉毀損で訴えようとも考えたが、それも出来なかった。ここはじっと耐えて、騒動が収まるのを待つしかないのだ。
だって、私は間違っていないのだから、自信を持って待っていればいいのだ。すぐに疑いは晴れる。
だって私は間違っていないのだから。
嘘など吐いていないのだから。
休載期間は思った以上に長かった。蓄えは充分にあるので生活の心配はない。辛いのは漫画が描けない事だ。ネタも時間もたっぷりあるのに、漫画が描けないのは私にとって酷な事だ。お預けを食らった犬の気持ちが理解できる。
元USAGI CITYのMAHOROがした暴露話はボヤで終わった。カエデと丈太郎を敬愛するUSAGI信者たちが鎮火してくれたのだ。
そもそもMAHOROには話を盛る癖があるらしい。私は知らなかったが、メジャーデビュー当時に年齢を偽った前例があるそうだ。理由は分からないが、丈一郎と田中アツロウより二つ下で、カエデより一つ上の生まれ年でプロフィールが公開された。後にカエデを除く3人が同級生だと発覚し、年齢詐称が発覚する。事務所の記載ミスだという事で話しは収まったが真相は定かではない。
『微熱』は私の作詞作曲と訴えていたが、それも少し違うらしい。『微熱』の作曲は丈一郎もかなり関わったそうだ。主になるメロディをMAHOROが提案したので、作曲家としてMAHOROの名を使ったに過ぎず、歌詞もカエデが加入してから大部分は変わったそうだ。
私に噛みついたのは、きっと少しでも注目をされたかったのだろう。自身の承認欲求を満たすために、あった事を無いと言ったのだと思う。
麻島先生の件もなんとか静まってくれた。麻島先生の母親がネットニュースの取材に応じ、真実を話してくれたのだ。
色々な事があり過ぎて、色々な事がある事に慣れてしまっていたけど、あのタヌキマスクから連絡が来たのには流石に驚いた。住所をどこで知ったのか、私の自宅宛てにその手紙が届いた。封筒の裏にはちゃんと本名の松川俊太と記されていた。
まず、奴はタヌキマスクではなく、レッサーパンダマンである事を知り驚いた。そして自身の手がける動画への出演依頼だった事に驚いた。
奴はMAHOROの言いっ放しじゃ公平じゃないから、私の意見も聞きたいと言っているのだが、そんな罠に引っ掛かる程、馬鹿ではない。私は丁寧に断りの文章を書き、レッサーパンダのイラストを添えて返信した。
とりあえず何とか落ち着きは取り戻した。落ち着いたとはいえ、仕事はそう簡単に戻っては来ない。またどこかのアシスタントでも入ろうかと考えたが、一度売れてしまったプライドがそれを許さない。漫画を描きたい、という気持ちが日を追う毎に強くなり、気が沈んでいく。
でも荒んでばかりもいられない。私には一馬という大切な存在がある。この暇な時間が、天から与えられた、一馬との関係を埋める為の時間だと思えば、受け入れる事が出来た。長い間、あの憎き母に預け放置してきた事を、償う時間とも言えるかも知れない。
ただ、外に出る気にはなれず、保育園の送り迎え以外は、引き篭もり気味の生活が続いていた。食事は出前が中心で、日用品はネットで注文する。一馬とも自宅で過ごす事が多い。その殆どの時間をお絵描きに費やした。
リビングのテーブルを退かし、フローリングの上に模造紙を敷き詰めて、二人でお絵描きをした。私の絵を見て「すごーい、じょうずー」と喜ぶ一馬の笑顔で癒される。仕事が無くなり漫画も描けず、ネットで袋叩きにされている、という過酷な環境で一馬の笑顔は唯一の救いだった。
「おかあさん、つぎはネコをかいて」
今日のテーマは『動物』。一馬は青のクレヨン、そして私は赤のクレヨンを使って、動物を描く。
「いいよ。じゃあ一馬は犬を描いて」
「うん、わかった」
汗を拭うのも忘れクレヨンを走らせる一馬の横顔が、亡くなったあの憎き父、いや、あの優しい父と重なる。特に鼻の膨らみや、顎のラインが父と似ている。私は我が息子の横顔を愛しく眺めながら、父との最後を思い出していた。
麻島先生の遺影と、遺体の顔に差があったように、棺桶に入った父の顔と、遺影の顔には大きな差があった。始めて父の亡骸を見た時、変わり果てた顔を見て、直ぐにそれが父であると認める事が出来なかった。
父の最後の顔は、この世に未練を残しているようにみえた。そこから母への恨みが強くなっていった。
「おかあさん、だいじょうぶ?」
「えっ」
一馬の声で、私は正気を取り戻す。どうやら少しの間、意識が飛んでしまったようだ。
「おかあさん、これってネコじゃないよね?」
驚く一馬の顔から、模造紙に目を移した。
「えっ」
私は言葉を失った。
「おかあさん、これだれ?」
模造紙に描かれた一つの絵が私を凍らせた。一瞬で血の気が引き、次第に息が荒くなる。全身の力が抜け、膝ががくがくと震えだした。手から落ちた赤いクレヨンが、模造紙の上を転がっている。
それは女性の体に覆いかぶさり、暴力を振るう男性の絵だった。
ここには一馬と私しかいない。間違いなく私が描いた絵だ。怯え泣きもがく女性は見覚えがある。鬼の形相をした男性の顔も記憶にある。
「ねえ、これおかあさん?」
一馬は母の絵に指を刺した。
いや……これは……多分……
「一馬のお婆ちゃん」
私は消え行く声を、必死に絞り出した。
「じゃあ、こっちがおかあさん?」
両親の脇で、一人の少女が膝を抱えながら震えている。
「そう、これがお母さん」
咄嗟の判断が間に合わず、幼い子供にありのままを答えてしまった。僅かな時間の中、いったい何がおきたのだろうか。私の心が混乱に陥った。
何だ、何だ、この症状はヤバイ。もはや末期じゃないか。この状況から抜け出し、早く本当の自分を取り戻さないといけない。
コミックエッセイの仕事も、テレビの仕事も復活したい。早く全てを取り戻して、私らしく活き活きと過ごしたい。一馬が小学校に進学する頃までには、何とかして復活せねばいけない。私への疑いが晴れ、世間の風向きが変わったら再びチャンスが訪れる。その時は今の状況が漫画のネタに変わるはずだ。
「一馬、ごめん」
私は力の限り、一馬を抱きしめた。
「どうしたの?いたいよ」
「ごめんなさい。少しお仕事の事を考えていたの。これは新しいお仕事の絵なの。ごめんね」
模造紙を丸めソファの裏に隠すと、そこにスケッチブックを広げた。
「ごめん、猫だったね」
そう言い、私は猫の絵を描いた。丸々太った猫が、マタタビを舐めている様子を絵にしてみた。その横で一馬が犬の絵を描いている。
「おかあさん、ネコ、じょうず」
「一馬の犬も上手に描けているよ。この舌を出しているところが可愛いね」
「おかあさん。これしたじゃないよ。このイヌはパンをたべているんだよ」
「そうか、ごめん、ごめん」
一馬に謝ってばかりもいられない。とりあえず動こう、何かをしないと本当に駄目になってしまうと拳は握ったものの、実際に何をしたら良いのか分からない。私は乏しい知恵を巡らせていた。すると見慣れない物が目に入った。普段なら特別気に留める事のない物だったが、今の私には特別な物に思えて堪らない。
麻島先生の葬儀で着た喪服が、クローゼットに仕舞われず、リビングの壁にハンガーで吊るされたままになっている。そのポケットから何か白い物が出ているのだ。それは4つ折にされた一枚のレポート用紙だった。マスコミに囲まれたどさくさに紛れて誰かが忍び込ませたのだろう。私は躊躇せずそれを開いた。そこには〈灰谷さんが心配です。連絡下さい〉と書かれていた。差出人は杉山江里菜。聞き覚えがあるような、無いような名前。私は迷わず書いてあった電話番号に電話を掛けた。
鼓動と発信音が重なる。程なくして電話が繋がった。相手は少し臆するように〈はい〉と発した。
「もしもし、あのう、こちらは杉山さんの携帯電話でしょうか?」
〈はい、そうですが〉
「私は灰谷と申します」
〈あっ、灰谷さんですね。良かった、もう掛かって来ないかと思っていました〉
相手のトーンが一気に上がった。私の心拍も一気に上がる。
「そうですか。伝言を見つけたのが今だったので」
〈そうだったのですね。でも良かった〉
声から安堵が伝わる。
「申し訳ございませんがどなたでしょうか?」
返ってきたその答えに、驚愕した。
〈杉山江里菜と申します。杉山の妻です〉
「杉山、えっ、えっ、え、つ、つ、つま?」
〈ええ、杉山昇の妻です〉
「アノ、スギヤマノ、オクサンデスカ?」
何で片言なんだろう。情緒が不安定過ぎて、思考が現実に追いつかない。
〈はい、杉山の妻です。生前は大変お世話になりました〉
「杉山、えっ、えっ、えっ。あの杉山は結婚していたんですか?」
杉山江里菜はクスッと笑い〈ええ。結婚していましたよ。子供も二人います〉と答えた。動揺が更に深くなる。スマホを握った掌から汗が滲み出ている。
あの杉山は既婚者だった。ゲイでもオカマでもなく、ノンケの親父だったのだ。確かに劇団には所属していたが、結婚を機会に辞めているらしい。
「私、ずっと勘違いしていました。ごめんなさい」
〈大丈夫ですよ。夫はあんな感じなんで、誤解されても仕方ないです〉
嘘のように明るい声だ。でも嘘を吐いているとは思えない。
「しっ、仕事は?杉山……さんはちゃんとお仕事をしていましたか?」
〈ちゃんと毎日会社に通っていましたよ。ああ見えて真面目で、会社での評価は良かったのですよ〉
「でっ、でも、サンライズマートで働いていたじゃないですか」
〈あっ、あれはお小遣い稼ぎです。子供達を大学に入れる為に貯金していたので、自分のお小遣いは自分で稼ぐ、ってコンビニでバイトをしていました〉
杉山江里菜は夫に無理をしないように言ったらしいが、少しでも子供の為にお金を残したいって、無理をしてバイトをしていたそうだ。
「そうだったのですね。全く知らなかった」
杉山江里菜はまたクスッと笑った。
〈そんなに困ってなかったんですけどね。でも頑張って行っていました。夫にはコンビニに行かないといけない別な理由があったんですね〉
「それって、どういう意味ですか?」
私の胸がジワジワと熱くなっていく。
〈灰谷さんの事を心配していました。ちびちゃんが心配、ちびちゃんが心配、って口癖のように、ずっと言っていました〉
「そっ、そうなんですね」
杉山は私の事を案じていた。私の挙動や言動が元で身を滅ぼすのだろうと心配して、私の近況を知る為、そして私を守る為にサンライズマートでバイトをしていたのだ。
〈灰谷さん、今、色々大変でしょ?〉
「ええ、まあ」
〈それでね、あの言葉を思い出して、夫の変わりに灰谷さんを守ろうと思って、近づきました〉
近付こうと思ったものの、連絡手段が分からず、直接の接触を図ったのだ。
〈一応、出版社やテレビ局にも連絡したんですが、取り合ってもらえず、ちょっと大胆な作戦に出てしまいました〉
「そうだったのですね」
これを機会に私と、杉山江里菜の付き合いが始まった。杉山江里菜、いや、江里菜さんは献身的に私達親子を支えてくれた。買物をしてくれたり、食事を作ってくれたり、私が出来ない事は全てしてくれた。
江里菜さんに誘われて、初めて杉山家に来た。今日は私達に昼食を振舞ってくれるそうだ。
家に篭っていると、心が荒んでくる。事実、ここ数日体調が芳しくない。胸というか鳩尾の辺りに違和感を覚える。江里菜さんは荒んだ心を癒すために、こうやって外出の機会を作ってくれたのだ。
杉山家は豊島区のタワーマンションの17階にある。なかなかの家だ。そこそこの収入や信用がなければ買えない代物だろう。江里菜さんの実家が近くにあるらしく、この場所を選んだという。
ローンの支払いが残っているらしいが、夫の生命保険やら犯罪被害者給付金やらで賄っているそうだ。両親の支援もあり、私達の面倒をみる事ができるという。
平日なので江里菜さんの子供達は学校に行っている。うちの一馬は幼稚園、いや、保育園を休ませて連れてきた。せっかく美味しい料理を作ってくれる、と言うので親子で甘える事にした。
部屋は生活感に溢れているが、小奇麗にされている。所々、杉山昇が生きていた痕跡が残っている。それは飾られた写真であったり、ハンガーに吊るされたネクタイであったり。私は居間に置かれた、小さな仏壇に手を合わせた。仏壇には小さな折鶴が飾られていた。
「ねえ、由ちゃん、記者会見か何かを開いて本当の話をしたら」
江里菜さんは料理を盛り付けながら、優しく声を掛けてくれた。今日は中華料理の油淋鶏を作ってくれるそうだ。夫の好物だったらしい。生姜と刻んだ葱がたっぷりと入ったソースを、揚げた鶏肉に掛けている。
「記者会見かぁ、そうなんだよね」
「夫も喜ぶと思うよ」
遺影の顔は笑っている。幸せに満ちた表情だ。
「今更、何を言っても、誰も信じてはくれないよ」
悪代官と越後屋さえ私に疑いをかけている始末だ。私はマスコミとネット民の恐さを嫌という程、味わってしまった。
「きっと、これまでも多くの有名人が、この嘘だらけ地獄に落とされてきたのだと思う」
「恐い世界ね」
「本当、そう。まさか、そのターゲットに自分が選ばれるとは全く思っていなかったけどね」
一馬は大人しくお絵描きをしている。お絵描き道具は江里菜さんの子供達のお下がりだ。
「嫌ね。うちの子供達が芸能人にでもなりたい、と言ってきたらどうしよう」
「その時は私が身を持って止めてあげるよ」
事実とは別に『灰谷叩き』のネームがほぼ固まりつつある。
わざわざ北海道の自宅まで行って、ご近所さんや知人、親戚に取材したらしい。出どころは明らかにされていないが、若い頃の家族写真などを入手し、それを記事と併せて公開した。 中身が偽りであっても、生の声や写真を加える事で信憑性が増す。
「沢山の嘘、嘘、嘘、嘘の塊の上を少ない真実で塗り重ねる。あたかもそれが事実であるかのように報じる。それが奴等のやり方なんだよ」
「なるほどね」
江里菜さんは大げさに感心する仕草をした。その様子に杉山昇を重ねた。私には永遠に分からない事だが、夫婦というのは影響し合うものなのだろう。仕草が大げさなところや、お節介過ぎるところが似ている。
「江里菜さんは、記事を読んだの?」
「ちょっとだけね。でも、直ぐ嘘だって分かった。だから読むのを止めた」
私、灰谷由の母である美津子は、夫の正一に度重なるDVを受けていた。警察に相談しようと考えた事もある。何度も離婚を考えたが由を育てる為に耐えていた。幼い頃から母に対する父の暴行を目にしていた由には出来る事は、目を逸らす事だけだった。精神的に追い詰められていた由は、父が母にしている暴力の事を他者に尋ねられても、それを頑なに認めなかったという。そして次第に心を閉ざすようになり、漫画に救いを求めた。
由が9歳の時、父は仕事現場での事故で亡くなる。そこから母は昼夜問わず働きに出る。夫の残した借金を返しながら、女手一つで由を育てた。高校を卒業したら由は、献身的に自分を育ててくれた母を棄てて東京に逃げた。
漫画家になりたい、という夢を果たすために。
「母が異常な人だったから、私も友達に避けられるようになったの」
「うん、そうなんだよね。漫画で読んだから知っているよ」
「でも、私の奇行のせいになっているの」
私は思わずため息を吐いてしまっていた。江里菜さんは子供をあやすように「うん、うん、それは酷いね」と頷いてくれる。
「父が子供の頃に死んだって、そんな訳ないでしょ。何で、そんなとんでもない嘘を書けるのよ。父はあの母の勝手わがままに耐えて行き続けたのよ。最後は心労から色んな病気を患い、それが発端で癌に侵され死んだのよ」
私は拳を固めた。そう、父はあの悪魔に殺された。癌が発覚しても母は父を放置した。
「由ちゃん、辛い想いをしたのね」
江里菜さんは流れた涙をエプロンの裾で拭っている。
「漫画の編集者に色仕掛けで近付いた、って」
「そんなの全くの嘘なんでしょ?夫も言っていたわ。ちびちゃんは、担当編集者にいいように弄ばれているって。鼻先にニンジンをぶら下げて走らされた馬のように」
「馬……。私は鼻先に漫画をぶら下げられて走らされていたのね」
私は思わず笑ってしまった。杉山が言いそうなフレーズだ。
「そう、叶わない夢を餌に、ただただ遊ばれているちびちゃんが不憫だって、嘆いていた」
叶わない……叶ったけどね。あんたのお蔭でね。
「あいつ、そんな事を言っていたんだ」
「そう、本当に心配していた」
「そうなんだ」
二人は仏壇の遺影を見た。杉山は不自然に笑っていた。元が何の写真であるかは知らないが、カメラを向けられて無理やり笑わせられたのだろう。元役者とは到底思えない不器だったけど優しく明るい奴だった。
「メディアって嘘ばかりなのね」
江里菜さんは話を戻した。夫の事を考えて辛くなったんだと思う。絵里奈さんは気丈に振舞うが心中は穏やかでないと思う。私がいなければサンライズマートの仕事はしていなかったかも知れないし、あの時、私がレジに残っていたら犠牲にはならなかった。
「嘘ばかりのメディアには腹が立つけど、たいした発想力だと感心もする。正直、羨ましいとさえ思う。この発想力が私にあれば、もっと早く漫画家として成功していたに違いない。コミックエッセイ作家ではなく、ストーリー漫画家として大成していたかも」
「今から、そっちを目指したら。私には何も出来ないけど応援はするよ」
「ありがとう。でも、それは無理。私にオリジナルのストーリーを描く才能はない。自分が一番それを知っている」
「そうなんだ、余計な事を言ってごめんね。でも全く発想力が無いとは思わないな。事実、うちの夫をゲイの売れない役者だと思っていたし」
「ごめんなさい。本当に勘違いしていた。しかも何年間もずっと」
江里菜さんは首を横に振って「それはしょうがないよ。あの人、あんな人だから」と言ってくれた。二人はお互いの顔を見合って笑い合った。江里菜さんといると、本当に癒される。彼女を私に贈ってくれた杉山昇に感謝する。
「ねえ、由ちゃん」
「えっ、何?」
「ご飯食べようか」
「あっ、そうだよね」
テーブルに豪華な食事が並び始めた。一馬は何も言われないのに、お絵描き道具を片付け洗面所で手を洗っている。
「いただきます」
三人で声を合わせた時、喉に何かが込み上げてきた。何故だろう、空腹のはずなのに吐き気を覚えた。
「由ちゃん、どうしたの?大丈夫?」
「ちょっと、急に気持ち悪くなってきて」
あれから体調が悪い日が続いていた。運動もしないし、特に健康に気を使っていた訳でないけど、病とは縁が無かった。漫画のためなら連続の徹夜も平気で、叩かれても体調だけは維持していた私が臥せっていた。時々吐き気を覚えるが、胃や腸が傷む訳でもなく、咳や発熱も無いので病院にはいかず。ただただ寝て過ごしている。なんか男性に頼りたくなって延岡清太郎に連絡してみたが繋がらない。高梨の顔が浮かぶが連絡ができない。一馬は黙って一人で遊んでくれている。
一馬がいなかったらこのまま、ソファで寝そべりながらミイラになっていたかも知れない。ノートに自分がミイラになった姿を描いてみれるくらいだから、まだ元気なのかも知れない。
今日は絵里奈さんが弁護士を連れてやってくる。記事の嘘を証明して訴えようという提案だ。正直億劫だったが、絵里奈さんとなら楽しくできそうな気がした。
弁護士が来る午後3時より早く江里菜さんが来るという。一旦話を整理してから弁護士を駅まで迎えに行くと言っていたが、単なる口実だろう。私達の生活が心配で様子を見たいんだと思う。私は完全にその優しさに甘えてしまっている。
江里菜さんは宣言通り早めに来た。弁護士を迎えに行く時間より三時間も早い午前12時に、サンライズマートの代名詞であるガテン弁当を買ってやってきた。
弁当が二つなのは江里菜さんなりの配慮なんだと思う。体調を崩し食欲を落としている私と、5歳の子供ならガテン弁当を余してしまうくらいだ。
江里菜さんが食卓の用意をしながらこう言った。
「ねえ、由ちゃん。そのままでいいから聞いて」
「はい、何?」
「最近、生理きてる?」
気が動転した。
「そういえば、しばらく無いかも」
「あなた、もしかして妊娠してるんじゃない」
「えー、うそ、うそ」
「心当たりないの?」
江里菜さんは手を止め私の反応を待っていた。
「心当たり……あります」
ある、ある、ある。
「もしかして例の編集者?」
江里菜さんは気まずそうな顔をしていた。
「いや、違う」
「えっ、じゃ誰?」
どうしようか迷ったが、絵里奈さんを信じて名前を喉から絞り出した。
「俳優の延岡清太郎」
江里菜さんは目を丸くした。
「トレンディドラマの帝王?」
「そう、トレンディドラマの帝王。ドラマで私の父役を演じた事をきっかけに」
「付き合っているの?」
「付き合ってはいない」
「おじさんだよね」
「そう、私より二回りも上」
「既婚者だよね」
「だから、付き合ってはないんだって」
「やっちゃったの?」
私は首を縦に振った。
「避妊は?」
私は首を横に振った。
「それっていつ?」
「3か月前くらい」
「生理はいつからないの?」
「ちょうどそれくらい前から」
江里菜さんは口を手で覆い、考え込んだ。
「病院行こうか?一緒に行ってあげるよ」
「えっ、本当に?えっ、いつ?」
「今日、これから」
「今日、これから?」
「そう、これから。通っている産婦人科とかあるの?」
ある。いや、ない。一馬を産んだ時の事は覚えていない。覚えていないという事は旭川で産んだのだろう。産んですぐにあの女に預けたのだろう。悪い記憶は全て旭川に置いてきた。
一馬は澄んだ目で私を見ていた。悪い記憶なんて言ってごめんね。あの時は確かに良い話じゃなかったの。でも今は違うの。あなたを産んで良かったと心の底から思っている。
「産婦人科……」
「そう、産婦人科。がん検診とかで行った覚えないの?」
「ない。東京で知っている産婦人科はないの」
「そう、分かった。うちの子達を産んだ病院に行こう。凄く丁寧で親切な病院だから大丈夫」
「あっ、はい」
という流れで私達は産婦人科に向かった。タクシーの後部座席に一馬を挟んで3人で並んだ。絵里奈さんは何かを言いたそうだが、それを押し殺して進行方向を黙って見ていた。一馬は児童誌の付録にあったひらがな本を開いていた。あひる、いるか、うま、と小さな声で読んでいる。
もし本当に妊娠していて産んだら、この子はお兄ちゃんになる。そう考えると心が弾む。しかし間違いなく私は仕事がなくなる。延岡清太郎に相談したら、認めて生活費を渡してくれるだろうか。おろせ、と言われるに違いない。もし、それを無視して産んだら、勝手にした事だと言われるだろう。かと言って、今更、高梨に家族と別れてもらい、結婚してもらうのも違うと思う。
どの道に進もうが、その先はいばらの道だ。今の私は漫画のストーリーはおろか自分の未来さえ想像できない。頭の中がそれ以外のものでパンパン膨らみ、想像が入るペースが無いのかも知れない。
自分が発してきた言葉や、漫画で表現してきた事と、事実を擦り合わせいく。どのピースも合いそうで合わない。下絵は浮かぶが、そこにはっきりとした線や色が乗って来ないのだ。たまに輪郭さえ浮かばない過去もあった。
タクシーは私の知らない町に進んで行く。杉山家の子供たちは、この先の病院で産まれたらしい。これから通う事になっても不自由はしない距離。自宅からはそんなに離れていないはずだが、来たことの無い場所。東京にはまだそんな場所が多い。
「ちびちゃんは愛が欲しいんだ」
江里菜さんが突然、口を開いた。私は黙って次の言葉を待った。なすび、にんじん、ぬりえ、一馬のひらがなはなの段に進んでいた。
「夫がいつも言っていた。ちびちゃんは愛が欲しいのだって」
気が付け私の頬に一筋の涙が流れていた。この言葉が私を楽にしてくれそうな気がした。
「愛が欲しいから、背伸びしようとするところがあるって。愛が欲しいから自分を大きく見せようとしている。由ちゃんは、見えない鎧を重ねて脱げなくなっているのよ」
「見えない鎧……」
「そろそろ、それを脱いでみたら。背伸びせず等身大の灰谷由で戦ってみたら」
病院は思った以上に大きく綺麗だった。専用の駐車場もあり、タクシーが停まるスペースもあった。大きなクスノキで沢山の鳥達が羽を休めていた。産婦人科専門の医院だというが、看板を見なければ総合病院だと言われても疑わない。こんな近くに、こんな大きな産婦人科医院があるなんて、全く知らなかった。知ろうという気がなかった。
受付けを済ますとエスカレーターで二階の待合室に進んだ。キッズスペースもあったが、一馬は私達二人の間に座ってひらがなの続きを始めた。絵里奈さんは私の腰を優しく摩りながら時折笑みを見せてくれた。一馬も真似をして腰を摩ってくれる。
「灰谷由様」
私の名前が呼ばれる。心臓がドクドクと響き始める。絵里奈さんは「いってらっしゃい」と言いながら腰をポンと叩いた。一馬も真似していた。私は満面の笑みをみせ「いってきます」と返した。
看護師に検尿用の紙コップを渡されトイレに向かった。尿を提出すると検査結果が出るまでの間は別の検査が行われた。
不思議だ、何の記憶も無い。出産の記憶は旭川に置いていったとして、こうやって検査をした記憶が無いし、看護師らが使う言葉のひとつひとつが新鮮だった。五年で検査方法が変わったのか、いや、そんなはずは無い。問題は私の記憶なのだ。
検査を含め妊娠していた期間の記憶がすっかり抜けている。その間も仕事をしていたはずだ。妊娠中は誰のアシスタントだったのだろう?その先生に妊娠の話をしたのだろうか?サンライズマートの仕事もあった。大きくなっていくお腹を見て、杉山等は何を言ってくれたのだろう?全く思い出せない。
そもそも、なんで母に一馬を預けたのだろう。父を苦しめ、私を苦しめた母に、大切な我が子を託すのだろうか?
ー見えない鎧を脱いで、等身大の自分で戦う―
杉山夫婦が私の鎧を一枚一枚剥がしていく。
私は担当編集者の高梨一樹と付き合った事はない……家を飛び出し東京で始めた生活が寂しくて彼に愛を求めた……彼に興味を持ってもらいたくて色々な嘘を吐いた……嘘のかさぶたは次第に硬くなり皮膚と同化していく……そしてだんだん元の自分が消え、違う自分が姿を現してくる。
診察室の前には椅子が並べられ、そこに座って待つように言われた。既に5名の女性が座っていた。お腹の大きい人はほとんどいない。みんな、私のように妊娠の結果を待つ人なのだろう。明らかに私より若い子もいれば、私と同じ若しくは私より上と思しき女性もいた。ここからは江里菜さんや一馬は見えない。みんなも心細く感じているのだろうか。
からくり時計が16時を示そうとしていた。そういえば15時に来る予定だった弁護士はどうなったのだろう。絵里奈さんならちゃんと連絡してくれたと思う。そうじゃなきゃ今頃駅で待っているかも知れない。だとしたら申し訳ない。もうこれ以上誰にも迷惑はかけたくない。
順番通りに私が呼ばれ診察室に入った。黄色いシャツに白衣を羽織った女性の医師が、私の顔を見て笑みを見せた。
結果、妊娠はしていなかった。
落胆はなかった。逆に少しホッとした気がする。
他の婦人科系の病気の可能性もあるので、念のために違う検査もするよう勧められた。私はそれに従った。少し時間が掛かるというので、それを江里菜さんに伝えようと思ったが、止めた。今はまだ全てを認めてしまうのが怖かった。
終
こんな僕ですがサポートをして頂けると嬉しいです。想像を形にするために、より多くの方に僕の名前・創作力・作品を知って欲しいです。 宜しくお願いいたします。
