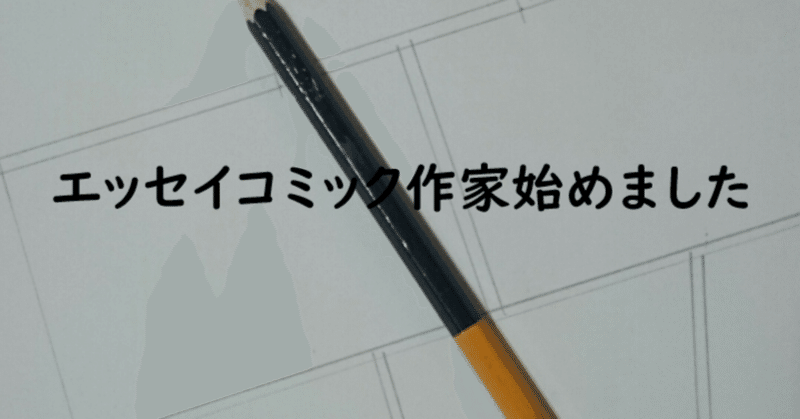
エッセイコミック作家始めました 第三話
旭川空港着のエアドゥが定刻通り羽田を離陸した。灰色のアスファルトが消えると、一瞬にして黒みかかった海が映った。景色を楽しむ余裕のない私は、音楽を聴いて気を紛らわす事にした。イヤホンを両耳に刺しスマホの音楽再生アプリを起動させるが気圧で耳がつぶれて何も聞こえてこない。音量を上げると少し聞こえてきたが、隣のおじさんがあからさまに怪訝な顔をしたのでアプリを閉じた。
目を瞑り昨日の仕事を思い出す事にしよう。少しでも気が紛れる事が出来たら有難い。
トンボ出版の音楽部門がUSAGI CITYの特集誌を出す事となった。まぁ、流行りに乗ったというやつだ。同時にインターネット上で映像も配信するらしい。映像配信は特集誌を買った方への特典じゃないかと高梨が言っていた。私が『DESAIRE』での連載で度々USAGI CITYへの愛を訴えていたので、このオファーを引き受けてくれたらしい。光栄にも私との対談コーナーが設けられた。ファンとしてこんな嬉しい事はない。
ここ数日間は、地下時代から追いかけていたUSAGI CITYに同等の立場で会える事の嬉しさより、あの女に会う、『一馬が私を受け入れてくれるだろうかという不安の方が勝っていた。
漫画を描いていない時間は常に気持ちが重たかった。撮影現場に向かうタクシーの中で何度か嗚咽を覚えた。60後半と思しき猿顔の運転手が、バックミラー越しに「車酔いですか」と優しく声を掛けてくれた。「明日、父と私を裏切った母と会うんです」と言える訳もなく、かといって遅刻する訳にもいかず「いえ、大丈夫です」と答えた。
性なのか癖なのか、こんな状態なのに漫画のネタを拾おうとしている。私は窓から遠くを眺めながら、時折運転手を観察していた。髪は黒いが、根本が白い事から染めている事がわかる。深いほうれい線の横の頬は、酒酔いのように赤く染まっていた。
車酔いだと思われる客を乗せているからなのか、凄く優しい運転だった。動いていないと感じる、といっても言い過ぎではないような気がする。急にハンドルを切る事も無く、強くブレーキを押す事もなく静かに進んで行った。
赤信号でタクシーが止まった。運転手は自分が客の頭の中で似顔絵にされているとは知らず「一旦止めますか」と振り返ってくれた。私は申し訳なく思いつつ「大丈夫です」と言って耐えていた。
世田谷の大きな音楽スタジオが現場だった。私は控え室で撮影の準備をしていた。ため息を繰り返す私に、作り笑顔のヘアメイクさんが「緊張してます?」と声を掛けてくる。私も作り笑顔で「ええ、まあ」と返した。
こういう時に限って高梨は来ない。まぁ彼は私のマネージャーでは無いし、この企画の関係者でもないから仕方ない。もし今彼が現れたら「やっぱり一緒に来て」と言ってしまいそうで怖かった。彼に対する借りは利子をたっぷりつけて返した。また貸を作りたくない。
ほとんど手を付けていない弁当の包装紙の裏に、さっきの運転手の似顔絵を描きながら時間を潰していると、撮影が始まる知らせが届いた。USAGI CITYの準備が終わり、予定より20分押しで撮影が開始される。私が先にスタジオに入って待機し、USAGI CITYの四人が入って来る。
確かにあの時の初々しさというか、謙虚さというか、はつらつとした感じは薄れていた。世間慣れというか、業界慣れというか、そういうのが見えて、スタッフさんに対してもどことなく横柄に見えて、挨拶もまともに出来なくなっていたけど、でも、でも、でもあの時とさほど変わらない四人が私の目の前にいる。時々四人のぎくしゃくした瞬間が垣間見えるが、キーボード担当のMAHOROに闇さえ感じたが、いつも通りUSAGI CITYは格好いいし可愛い。
―当機は仙台上空を通過中―
薄っすら聞こえたアナウンスが現実に引き戻す。間違いなくあの女に近づいている。私が訪問したら母はどんな顔をするのだろうか。一馬は私を覚えているだろうか。母が私を良い風に説明しているはずはない。きっと死んだとでも言っているだろう。母は母で一馬との生活が楽しいのかも知れない。預けてから五年間一度も連絡をしてこないという事は、そういう事だと思う。だからと言って情けをかけて、このまま預けっ放しにはしたくない。借りを作ったままなんて嫌だ。子供を育てるのは親の努めだよね。当たり前の事をやり直すだけ。
『漫画の題材として生活に子育てを加えた』いつかそんな事をいう奴も出てくるだろうが、覚悟はできている。誹謗中傷も含めて私は描く事に決めたのだ。
USAGI CITYとの対談は30分程で終わった。4人には次の仕事が迫っているらしい。トンボ出版が用意したアコースティックギターに、4人の目の前で私が4人の似顔絵を描いてそれを渡した。その似顔絵が書かれたギターを中心に記念写真を撮って、四人は退室した。「ありがとうございます」と笑顔を見せてくれたが、本心は彼等にしか分からない。ここ数年、こんなインタビューを何度も受けてきたのだろう。同じ質問に同じ答えを返してきたのだろう。そう思うと心が痛む。突然出て来た漫画家とインタビューだと言われてもテンションは上がらないだろう。ワンピースの尾田先生や、ドラゴンボールの鳥山先生だったらあんな億劫な顔をしなかったような気がした。まだまだ私には実績が足りない。ヒット作を沢山出して、もっと有名にならないといけない。私が大物漫画家となった時にもう一度USAGICITYと対談してみたい。そんな事を考えていた。
私はスタジオに残り、単独のインタビューを受けた。インディーズ時代のUSAGI CITYの話や今の活躍について汗をかく位の熱量で話をした。
「もし宜しければ、漫画を描きましょうか?」
「えっ、どういう事でしょうか?」
驚きからか、担当編集者は動きを止めた。正に目を丸くして私の次の言葉を待っていた。
「USAGICITYへの想いというか、地下時代から追いかけてきた気持ちみたいなものを漫画にして描きます。勿論、必要なければ結構ですが」
「いやいや、必要ないなんて事はございません。正直、ページが埋まらなく困っていました。いやぁ、本当ですか。本当に漫画を描いて頂けるのですか?」
気が付けば他のスタッフも手を止めて集まっていた。少女漫画の主人公のようにキラキラした目で私を見ている。
「ええ、勿論です。本業は漫画家なんで」
「そうえすね」
重い空気が漂っていたスタジオが、一瞬にして笑いに包まれた。あのヘアメイクさんも本当に笑っている。私は自分に出来る事をただ提案したに過ぎない。それがこんなに喜んでもらえる。心の芯が震えていた。
「5ページくらいならすぐに描けると思います。如何でしょうか」
「ありがとうございます」
担当編集者が深く頭を下げる。私は「いえ、いえ、お役に立てて光栄です。勿論、この流れも漫画にしますけどね」と言い、また笑いが起きた。
私は意気揚々とスタジオを後にした。手厚い送迎を受けトンボ出版が用意したタクシーに乗った。カバンに忍び込ませていた弁当の包装紙を出した。朝からの出来事は充分漫画にできる。流石にUSAGI CITYの名前は出せないかも知れないが、なんとかドラマチックに仕上がりそうだ。包装紙の空いた部分に今日あった人達の顔を描いて、気を紛らわそうと考えた。自宅の住所を言いながら、弁当の包装紙を拡げていると、既に描かれていた顔が振り向いてこう言った。
「何か良い事があったようですね。来た時よりかなり顔色が良いですよ」
6月の旭川は思った以上に寒く、軽装で来た事を後悔した。実家に行く前に上着を買わないといけない。旭川駅行のバスは発車まで20分もある。こちらの人には普通の事かもしれないが、長い間東京に住んでいたせいで20分は長く感じる。ちょっと贅沢だがタクシーに乗る事にした。
運転手は流石に猿顔ではなかった。
「上川神社の方面に向かって欲しいのですが、まずは洋服を買いたいので服屋さんに寄って下さい。どんな店でも大丈夫です。とにかく何かを着たい」
タクシーは真っ直ぐな道を軽快に進んで行く。牧場と田園風景、住宅地に近づいても空と山を塞ぐ物は何もない。窓の外の景色は懐かしいはずだが、感傷にふける気にもなれない。
駐車場のあるショッピングモールの洋服屋で、店頭に重ねてあったグリーンのカーディガンを掴んだ。最近メディアに出る事が多くなって、これでもお洒落になった方だ。このカーディガンが今の服装に合わないのは何となく分かった。しかしゆっくり探している時間はない。外にタクシーを待たせている。最近少しは儲けてきて貯えもあるけど、長年の貧乏性が抜けない。頭の中でタクシーのメーターがカチカチと上がる音が聞こえる。一応サイズがSである事だけは確認した。店員さんに「すぐ着るので、そのまま下さい。あっ、値札は切って下さい」と言うのは流石に恥ずかしかったが気にしていられない。
私は店を出ながらカーディガンを羽織った。なんか強くなれたような気がした。強烈なバリア機能を持った防護スーツを手に入れた気がする。
私はヒロインになる為にこの地に降りたのだ。そう、私は悪から我が子を救うヒロインなのだ。もし駄目でも漫画にしちゃえばいい、という保険は一旦忘れてヒロインに徹する事にした。グリーンのスペシャルカーディガンを羽織っっている間は無双状態になるのだ。
私はタクシーの中で何度も自分がヒロインであると念じ、目的地に着くと「おつりはいりません」と一万円札を叩きつけタクシーを飛び降りた。
しかし私の武者震いは出端が挫かれる結果となった。
「ない」
私が、あの女と過ごしたアパートは無くなっていたのだ。小学校の帰りに近道として利用した脇田家の私道もある、葡萄の木がある隣の江田さん宅もある、その隣の和菓子処『みかみ』も昔と同じく細々営業しているようだ。『名物きたきつね最中』と書かれたボロボロののぼりもそのままなのに、あのアパートだけは無い。庭にバスケットゴールのあるお洒落な一軒家に変わっていた。
私が小学5年の頃、新築で引っ越ししたはずだから経っても25年だ。事件のあったあのボロアパートが築45年で今も立派にある事を考えると、取り壊すにしては少し早すぎる気がする。並んで建っていた同じ造りアパートはそのままだった。
いったい何があったのだろう。もしかしてと思い同じ造りのアパートの郵便受けを確認したが『灰谷』の名も、母の旧姓の『平田』も、私が知る限り最後に付き合っていた『石川』の名前も無かった。
頭の中が、月曜日の麻島まりか先生のケント紙のように真っ白になった。私はスペシャルカーディガンの胸元を摩りながら「どうしよ、どうしよ」と狼狽えた。母と思しき苗字は無いが一応、一軒ずつベルを鳴らしてみようか、それとも隣の江田さん宅か『みかみ』を訪ねてみようか迷った。しかし指も足も、心さえも凍り付きその選択肢を許さない。あの女に怯えながら過ごす私に、誰一人として手を差し伸べなかったこの町に留まる事が出来ない。私は何も考えずただひたすら走った。心の声は押し殺して走った。
国道まで出てきて私の足が止まった。息が上がっている。体が熱くなりカーディガンを脱いだ。ゼエゼエと息を切らしながら考えた。まだ方法はある。だって私はあの灰谷由だよ。強盗に襲われたコンビニの小窓から抜け出し、家でその強盗と戦った灰谷由だ。アシスタント先の先生の穴を埋め、出版社の窮地を救った灰谷由だ。魔法が使えなくても、剣や盾が無くても、仲間がいなくても独りで戦うヒロインなのだ。
「何かないか、何かないか、何かないか、何かないか」心の声が、口から零れ、次第に大きくなる。13回目の「何かないか」を発した時に思い出した。この辺に伯母さんがいる。父の姉である光子伯母さん夫婦が営むクリーニング店がある。あの世話好きの伯母さんなら母の居場所を知っているはずだ。ここにきて記憶が滝のように蘇る。
私はイコマクリーニングのある町に向かって勇みよく歩き出した。道中は昨日約束したUSAGI CITYの漫画の構成を立てる事にした。まだ正式なオファーが来た訳ではない。5ページでも3ページでも対応できるように準備をしておこう。それがプロってもんだ。最悪オファーが無かったら連載に回せばいい。
軸は決まっている。地下時代のライブ帰りにバッタリMAHOROに会った話にしよう。ライブを見た帰り道にサンライズマートを見つけて、ずっと食べたかったあまおうソフトクリームと『週刊ヤングセブンズ』を買った。近くの公園のベンチに座り、あまおうソフトクリームを舐めながら、街灯の薄明りで『週刊ヤングセブンズ』を読んでいると、大きな荷物を背負った背の高い女性が現れた。荷物の中身がキーボードであるとすぐに分かった。暗くて顔ははっきりしないが、モデルのようなスタイルからMAHOROだと分かる。右手には私と同じあまおうソフトクリームが握られていた。
「MAHOROさんですよね」
気が付けば声を掛けていた。
「えっ、知っているのですか?」
ステージ上の彼女は常に凛として大人っぽい。でも今、目の前にいるのはどこにでもいつ様な可愛い少女だった。
「勿論です。USAGI CITYのファンなので。ちょうどライブを見て来た帰りなんです」
「ええ、嬉しい」
と言いながらMAHOROは私の隣に座った。そしてあまおうソフトクリームを一口含んで「おそろですね」と笑った。
「ずっと食べてみたかったんです」
「私は三回目なんです。ここ最近大塚でライブがあった時は必ず食べるんです。頑張った自分へのご褒美的な感じで」
「ちょっと高いですかなね」
「そうなんです。ちょっと高いけど、サンライズの季節限定ソフトは美味しいので」
サンライズマートの商品が褒められて、何か誇らしかったの思い出した。そしてこの時、MAHOROとUSAGI CITYをもっともっと好きになったのも思い出した。
彼女は単なるファンの私に夢を語ってくれた。USAGI CITYという名前があみだくじで選ばれた事も『大人可愛いと』いう言葉をキーワードに楽曲制作をしている事も打ち明けてくれた。私は漫画家を目指している事も、サンライズマートで働いている事も、あまおうソフトクリームをつまみ食いしようとして、一緒に働く友人に見つかり未遂で終わった事も話した。
「私、勝手にUSAGI CITYのロゴなんか書いちゃったんですが、見てもらえますか」
「ええ、そうなんですか。見たいです」
私はカバンの中を探って、お茶のシミが付いたノートを渡した。MAHOROはパラパラと捲り、USAGI CITYの四人が漫画キャラ化されたイラストと、ロゴを見つけて目を輝かせた。
「ええ、可愛い。ヤバい、めちゃくちゃ可愛いです。USAGI CITYのイメージにぴったりです」
「ですよね。USAGI CITYの事をいっぱいいっぱい考えながら考えたんです」
「わぁ、嬉しい。USAGI CITYの事をいっぱいいっぱい考えてくれたんですね」
私はUSAGI CITYが絶対売れると確信していた。予想通りUSAGI CITYはメジャーデビューを果たした。デビュー曲のジャケットデザインにUSAGI CITYのロゴが入った。美術部出身のMAHOROがデザインしたという事だが、間違いなく私の描いたロゴが影響されている。私は今回の漫画のオチとして私のデザインとオリジナルを並べる事にした。
5ページで足りるかな。今から連絡して8ページもらうかな。連載と別けたら収まるよな。と考えているとイコマクリーニングの前にいた。
店は記憶のままだった。赤いトタンの平屋の建物で、大きなガラス窓から店内全体が見える。店の前には店名が書かれたワゴン車が停まっていた。
少しだけ足が鈍くなった。ちょっとした懸念材料が頭をかすめたのだ。光子伯母さんは父の実姉だ。父側の身内として母の悪事を捉えているはず。でも、完全に父の味方という訳ではない。母の悪事に一定の理解を持って許している。懐が深いというか、お人好しというか、母の口車に乗せられて、私の訴えを子どもの戯言だといって信じてくれなかった。私にとって厄介な人物でもあった。二人の娘も陰険であまり好きではない。
私は恐る恐る店に近づき、店内を覗き込んだ。店頭に光子伯母さんはいない。全く知らない女性が接客していた。店の奥の作業場にも人影は見えない。
もう一度看板を確かめた。店名は光子伯母さんの嫁ぎ先のイコマクリーニング。そしてもう一度店内を確かめた。そこに光子伯母さんはいない。夫の隆史おじさんもいないし、店頭の女性はいとこの泰代さんでも、和代さんでもない。パートさんだろう、生駒家にはない優しそうな女性だ。歳は私より五つ六つ上というところだろう。
私は「また空振りかぁ」と言葉を零し、肩を落とした。その時、聞き覚えのある少ししゃがれた声が聞こえてきた。
「由ちゃんかい」
私は振り向いた。そこには記憶よりしわしわで、少し小さい光子伯母さんがいた。伯母さんは私を強く抱きしめ、大型犬のようにワシワシと撫でながら「ごめんね、ごめんね」と繰り返した。
ほのかに香水の匂いがした。懐かしい匂いだった。伯母さんは昔から好んでこの香水を使っていた。父の葬儀で着ていた喪服からも同じ匂いがしていた。
「漫画みたよ。おばさん、和代に教えてもらい、あなたの描いた漫画をみたのよ。大変だったんだね。私達兄弟が守ってあげれなかったから、あなたに苦労をかけてしまった。ごめんね、本当にごめんね。あぁ、ごめんなさい。会いに来てくれてありがとうね」
光子叔母さんに会いに旭川に帰って来たんじゃない。でも、わざわざ否定はしない。
「うん、私は大丈夫。こうやって元気にやってる」
思い出した。光子伯母さんは馴れ馴れしい人だった。汗ばんだ手でベタベタ触ってくるのが嫌でたまらない。
「そうか、そうか良かった。東京にいるんだよね」
「そう、東京。さっき旭川に着いたばかり」
「そうか、そうか」
光子伯母さんは、なかなか私を離そうとしない。髪留めのピンが時々私の額にあたり痛い。
「そう、寒くて途中でカーディガンを買った」
「そうか、お母さんには会って来たのかい」
ようやく解放された。叔母さんは真っ直ぐ私の目を見つめてきた。私はそれを逸らしイコマクリーニングに目を移した。パートの女性は接客を終えたらしく私達の様子を見ている。
「いや、まだ」
「お母さんにちゃんと謝ってきたのかい」
謝る……いったい何を謝ると言うのだろうか。この人は真実を知らない、知ろうとしない。やっぱり厄介な人だ。
「お母さんいなかった」
この場を早く去りたい。でも去る訳にはいかない。 やっと落ち着いてきたばかりの鼓動がまた速くなっていく。
「えっ、そんな事ないでしょう。そうか、そうか入院中だったわ。見舞いに行こうと思ってこれ買ったんだもの」
叔母さんは笑いながら、桃がいっぱい入ったビニール袋を見せた。桃は母が好きな果物だった。叔母さんの優しさを利用して自分の好きな物を買わせている。相変わらず姑息な人だ。
「入院?」
心配しているフリをした。それって何?一馬の世話は誰がしているの?
「入院って言っても、大したこと無いのよ。この間転んでお尻の骨を折っちゃって、大事をとって入院しているだけ。大したこと無いのよ」
「入院、そうか。でも、家も無かった」
「えっ、どこの家さ」
「神楽岡」
言葉が急いでいる。一刻も早くこの場を離れて、この匂いを忘れたい。
「あら、やだ、神楽岡の家なんてっとっくにないよ。今は春光の市営住宅にいるのよ。ねっ、和代」
気が付けば、店の中にいたはずのパートの女性が私の後ろにいて「そうよ、由にもちゃんと連絡したよ」と発した。
えっ、この人、光子伯母さんの次女の和代さん?中学時代にバレー部の市選抜に選ばれた和代さんなの?バレー部でキャプテンもしながら、市一番の進学校に進学した優等生の和代さんなの?正月に灰谷家の本家で、皆に馴染めずすみっこで漫画を描いていた私をからかって苛めた和代さん?まるで面影のない姿に私の頭が混乱に満ちてくる。更にこの場を去りたい気持ちが強くなる。
私は再び走り出していた。
そしてすぐに止まって振り返った。
「ねえ、お母さんの入院している病院ってどこ?」
「金星橋の八條病院。知ってるでしょ」と光子伯母さんが言うと、和代さんらしい女性が「東病棟の8階よ。一番奥の6人部屋」と続けた。
私は二人の前に戻り「お願いだから叔母さんは来ないで。あの人に大切な話があるの」と言い放った。二人は明らかに顔色を変え、明らかに言葉を失っていた。私は正義感を振り絞って「二人はもうあの人に近づかないで。あの人は二人が思うような人じゃない。二人は騙されているの」と言おうとしたが、それは飲み込んだ。この気持ちは漫画にぶつけよう。漫画を見て真実を知ってもらおう。
「ありがとう」
私はちゃんとお辞儀して、作り笑顔で手を振り、タクシーを拾った。
病室に入ってすぐにあの女を見つけた。正確に言えば一馬を見つけたんだ。もっと正確に言えば、ベッドの横の椅子に大人しく座る男の子を見つけて、それが一馬であると確信したのだ。顔なんて知る訳ない。記憶にあるのは生まれたばかりの丸々した猿顔なのだから。でも一馬だって分かったんだ。
「おかあさん」
私はうたた寝する母に声を掛けた。母はゆっくり瞼を開き「由」と呟いた。一馬は母と私の顔を交互に見ている。
「由、由が来てくれたんだね」
「光子伯母さんが教えてくれた」
私はぶっきらぼうに答えていたた。他の患者さんが妙に思わないよう、これでも気つけているつもりだ。
「ああ、みっちゃんね。もうすぐ来てくれる時間よね」
母はそう言いながら時計を確認した。
「伯母さん来ないよ。私が来ないようにお願いしたから。用事があるなら後で電話でもして」
必要以外の事は話さない。骨折の経緯を聞いたり、心配したり、社交辞令だとしても絶対にしてあげない。勝手に漫画にしている事を謝るつもりなどさらさらない。病院のベッドで不自由をしている姿を見ても、この女には怒りしか沸いてこない。
「ああ、そうなんだね。とりあえず座りなさい」
一馬は気を利かせて立ち上がり廊下に出て行った。私はその背中を目で追いながら、その椅子に座った。一馬の温もりを感じながら「率直に言うね。一馬を東京に連れて行く。私が育てる事にした」と伝えた。それ以上の事を説明する必要はない。私が漫画で成功している事は知っているはず。子供を育てる環境が整った事は察しが付くはず。
「あんた、まだそんな事を言っているの」
母は呆れ顔でそういった。やっぱりこの女は私を蔑んでいる。動けない状況を利用して殴ってやりたいと思ったが、ここは堪える事にしよう。この女のせいでせっかく掴んだ夢を手放す訳にはいかない。
「私、本気なの」
母は首を捻った。あんたに出来る訳が無い、とでも言いたいのだろう。母は手を伸ばしながら「あんたね」と言った。私は掴もうとした手を振り払い、言葉を遮った。
「もう決めた事なの。私、本気で一馬を育てる」と言った時にカバンの中のスマホが震えた。私は廊下に出て談話ルームに向かった。談話ルームの端の椅子には一馬が座り、静かに絵本を読んでいた。一馬は私に気が付くと笑顔を見せた。よく見ると私に似ている。そして高梨にも似ている。特にはっきりとした二重が高梨と似ている。
電話の相手は、光子伯母さんの次女の和代さんだった。いつ登録したんだろう。丁寧に今の苗字の根本と、旧姓の生駒を並べて登録している。私は戸惑いながら通話ボタンをタップした。
〈由、おばさんに会えた?〉
「うん、会えた、今、病院」
〈そうか、良かった。今日の由、何か変だったから心配で〉
「大丈夫。ちゃんと話出来ている」
一馬は絵本を本棚に返して、椅子に座り直した。カバンからぬりえ本とクレヨンを出してぬりえを始めた。時々、私を見ては笑顔を見せてくれる。白い歯を見せ微笑んでくれるのだ。
〈わかった。安心した。この後どうするの?〉
赤のクレヨンを握って一生懸命塗っている。私にもこんな無垢な頃があったんだろうか。
「特に決まってないけど」
ねぇ、なんのぬりえなの?恐竜かな?それとも流行りの戦隊ヒーロー?
〈うちに来てご飯でも食べに来るかい?旦那と息子に会わせてないしね〉
「和代さんちかぁ」
上手く塗れたのだろうか、一馬は私にぬりえの途中を見せて得意げな顔をした。うん、上手く塗れているよ。色合いのバランスがすごく良い。枠もはみ出していない。センスが良いのは私似かしら。
〈八條病院も近いし、仕事が終わったら母さんを連れて行くついでに由を拾うよ〉
「そうか、でも……」
胸が熱くなっていく。なんだろうこの感覚は。
〈うん、おいで、おいで〉
「いや、ごめん。やっぱりすぐに帰るわ。仕事が溜まっているの」
〈そうなんだ。残念だわ。売れっ子漫画家さんだもんね〉
「ありがとう」
力が入り過ぎたのだろう。クレヨンが本をはみ出し、机を汚してしまった。一馬は舌を出しておどけてみせた。
〈まあ、ほどほどにしなさいね〉
「そうだね。心配かけてごめん」
〈したっけね。今度帰って来る時は前もって連絡してね〉
「うん、そうする」と言いながら電話を切った。わたしは一馬に駆け寄り、ティッシュペーパーで机のクレヨンを消した。
「一馬君だよね」
「そうだよ」
「ぬりえ好きなの」
「うん、だいすき」
「そうなの、上手だね」
私はぬりえ本を手に取り、それを眺めた。一馬は嬉しそうにはしゃいでいる。
私はクレヨンをころころ転がしながら「何色が好きなのかな?」と訊き、一馬は「だいだいいろかな」と答えた。
「そうなんだね。だいだいいろいいよね」
私も暖色系の色が好きでカラーページでは好んで使っている。
「ねぇ、ねぇ」
一馬は甘えた声で私の顔を見上げた。
「うん、どうしたの?」
私は腰を落として、一馬の目線に合わせた。
「ママだよね、ボクのママだよね」
一瞬、心臓が止まりそうになった。私は零れる涙をカーディガンの裾で拭いながら「わかるの?」と一馬の頭を撫でた。一馬は「ママ、ないてるの?」と私の顔を覗き込み「ボク、ずっとママをまっていたよ」と続けた。
私は思わず一馬を抱きしめた。加減が分からず強く抱きしめ過ぎたのかも知れない。でも一馬は痛そうにはしていない。
「保育園に行ってるの?」
一馬はつまらなそうに首を横に振った。
「じゃあ、幼稚園」
また首を振った。5歳にもなるのに保育園にも幼稚園にも行かせてないのか。そして自分の入院先に連れてきて気を使わせている。あの女っぽい。でも非難はできない。そもそも育児を放棄したのは私の方だ。
「そうか、毎日偉いね」
「ひとりであそぶのすきだからへいき」
「そうか、でも皆で遊びたいでしょ」
一馬は少し考えて、申し訳なさそうに「うん」と頷いた。
「そうだよね。お絵描きもお友達と一緒なら楽しいよね」
一馬はまた「うん」と頷いた。
「ママと一緒に暮らすかい」と心の声が零れてすぐに後悔した。流石にそれは早すぎる。そして幼い子供に判断できる事ではない。こういう事は焦らず、慎重に進めないといけない。裁判になる事も覚悟している。しかしそんな不安を一馬の言葉が打ち消した。
「うん、ボク、ママといっしょにかえる。これからずっとママといっしょにいる」
よっぽどあの女と暮らす事が苦痛だったのだろう。あの女に気を使って静かに本を読んだり、絵を描いたりするのは、あの頃の私と同じだ。
一馬は小さな手で、私の手を握った。私は一馬の手を握り返した。このまま連れて帰ろう。罪悪感からでも、正義感からでも無い、私の心の奥にあったまた別の感情が芽生えた。
一馬を病室の入り口前で待たせ、中に入った。そして私は驚く母にこう言った。
「母さんごめん、一馬は連れて帰る。一馬もそれを望んでいる。後の事は責任持ってやる」
人生初めての子育てだったが、案外うまく行っている。高梨等の助けを借りて乗り切っている。勝手に連れて来たので手続きは大変だったが、なんとか終える事が出来た。母が特に何も訴えてこないのでスムーズいけたが、もし母が拒否でもしたら大変な事になっていただろう。変な噂が広がり、漫画家生活を終わらせないといけなかったかも知れない。
何より、一馬が利口なので助かっている。言う事を素直に聞くし、わがままを言わない。あの女の料理がそれ程不味かったのか、私の超初心者料理を美味しそうの食べてくれる。あの女が何もしなかったせいか、着替えや片付けなど、自分の事は自分でしてくれるのだ。私の仕事が詰まって、相手を出来ない時は、黙ってお絵描き等をして暇を潰してくれる。
私は死後の世界とか、霊とかオカルト的な事は信じていなかった。そいう類の者は漫画の中だけのものだと思っていたが、一馬の利口をみると、亡き父が傍で見守ってくれていたとしか思えない。自分が仕事人間であるが故に、娘に苦労をかけた事を後悔しているのだろう、と思う事にした。勿論、これも漫画の材料にする。
一馬という存在が女神になったのだろうか、私の仕事は恐い位に順調だった。『DESAIRE』の連載に、スポーツ新聞と男性週刊誌の仕事が加わった。いずれも日常のニュースなどを私なりに捉えて、一コマの漫画にするものだったので、それほど難しい作業ではない。作成も手書きからデジタル作業に変えたので、アシスタントを雇う事なく、子育てと併せても難なくこなせた。
USAGI CITYの特集誌の評判も良く、お蔭でUSAGI CITYのファンを取り込む事ができた。
一コマ漫画の仕事とUSAGI CITYの特集誌の評判により、私の名前が色んな層に広がった。それが相乗効果となり『DESAIRE』の売り上げは更に伸び、私は最大の貢献者となる。トンボ出版で行われる月に一度の打ち合わせでの待遇が、どんどん良くなっていく。天丼が鰻丼に変わり、それが特上寿司に変わっていく。最初は、馬鹿みたいに持ち上げられ、くすぐったかったが、次第に過剰接待にも慣れてきていた。
そんなある日、私は朝のワイドショー『ウイークデイ』のゲストとして、テレビ局のスタジオに呼ばれた。
漫画家アシスタントと、アルバイトの掛け持ちの極貧生活から、コンビニの事件をきっかけに、シンデレラストーリーの主役の座を勝ち取った女性漫画家。そして女性が男性と対等に働く時代を推進する雑誌『DESAIRE』の連載作家、若者から絶大な支持を受けるUSAGI CITYのファン代表として、数台のカメラが向けられた。
緊張してはいなかった、といえば嘘になるが、想像以上に落ち着いて取材の臨めたと思う。目の前に並ぶ著名人達に少し心が浮かれたが、すぐに私もその一角なんだ、と思える事ができた。自分でも不思議な位落ち着いていられる。
事前に収録したドキュメント風のVTRと併せて、司会者のインタビューが進んだ。
「お父様の病気を知らされた時はどう思いました」
「ええ、本にも描いてありますが、最初は信じられませんでしたね」
父が自分の病に気が付き検査を受けた時、肺癌のステージは既に4まで達していた。この事実を公にする事で、定期検査と、家族が変化に気が付いて病院に連れて行く事の重要性を訴えた。
「何か変だと思った時は、直ぐに病院に行ってください」
この発言がスタジオ中の関心を集める中、コメンテーターの一人が私に噛み付いてきた。彼の名は藤堂晶、辛口コメンテーターとして話題の人物だった。若くしてビジネス書を三作ヒットさせた官僚出身の経済評論家である。経済以外にも多方面への関心と知識があり、ついついそこに毒舌を吐いてしまう癖がある。
日本を代表する大物音楽プロデューサーが亡くなり、世間の話題がそれに集中した時も「確かに日本の芸能界における功績は高いかもしれませんが、アイドル中心のエンターテイメントを作ってしまった事は、実際は悪影響ではないでしょうか?特に芝居や音楽の分野についてはそれを強く感じます。テレビ業界が衰退しているのは正にこの影響ですよ。私は優れた音楽や優れたお芝居を観たいです。日本の報道機関がこんなに長い時間を費やして、情報発信する程の人物であるとは思えない。もっと政治や事件に時間を使って欲しい」と言い、世間の非難を受けた。
つい先日もこの番組で「日本のサッカー選手は、マスコミに対し判で押したように同じような対応しかしない。言う事も全く同じ。ふてぶてしくて可愛げない。何かマニュアルでもあるのでしょうか?」と言って物議を交わした。
辛口コメンテーター藤堂晶は、ネット世界の代弁者として若者からの強い支持を得ていた。
そんな彼の構えた銃口が、私に向かってきたのだ。
「あなたは実のお母様や、仕事仲間の死を踏み台にしてお金を稼いで、心が痛まないのですか?」
私は一瞬言葉を詰まらせたが、直ぐに反論した。
「漫画は表現方法の一つです。私がやっている事はあなた方がテレビや雑誌やネットでやっている事と同じです。あなた達はどんな表現も許されて、漫画はそれを許されないのでしょうか?漫画を馬鹿にするのは許しません」
「別に僕は漫画を馬鹿にしていませんよ。あなたの心を疑っているのです」
私の反論を待っていたかのように、余裕な顔で構える藤堂に怒りを覚えた。
「勿論、心が痛む事もあります。でも身を削ってでも真実を伝えたい、という気持ちが勝っているのです」
「真実?」
藤堂はあからさまに首を捻った。
「本当に真実なんですかね?余りにも出来すぎ、というか、疑惑が生じていますが」
私の反論を待たず、元お笑い芸人でメイン司会者の長崎孝太が二人の間を割り、この状況を笑いに換え、その場を収めた。
とりあえず、番組進行の邪魔をしないように、これ以上の口撃を慎んだが、テレビ局を去っても怒りは収まらなかった。私はけして話を大きく盛ってなんかない。全て事実を忠実に描いている。確かに自分の醜態を晒された母の心中は、穏やかではないと思うが、それ以上に私は辛い経験をしてきたのだ。私の漫画を読む事で、同じ環境にいる女性の励みになって欲しいし、母のような人間が自分自身の愚かさを知り、家庭を顧みるきっかけになって欲しい、と何度も頭の中で繰り返した。そんな事情も分からないで過ちの正義の旗を振りかざす、あんな類の人間は苦手だ。私を苛め。教室の隅っこに追いやった奴等と印象が重なる。いやぁ、本当にイラつく。今すぐ、この感情を何かにぶつけたいが、それをしてしまったら負けのような気がする。『DESAIRE』の編集長や高梨には、誹謗中傷の挑発に乗るな、と念を押されていた。だからこの感情もいつか漫画のネタにしよう、と考え心の引き出しに仕舞う事に努めた。
私は『漫画』という強力な武器を得たヒロインなのだ。この剣を振りかざし己の母を制圧した。同じようにあの男も制圧してやろうと強く誓った。
しかしこれを漫画のネタにする機会は訪れなかった。それよりずっと凄い、というか、私に都合が良い出来事が起こったのだ。そもそも漫画のネタにして、対決する程の相手でなかったのかもしれない。
あの放送から程なくして、藤堂に女性問題のスキャンダルが浮き上がったのだ。それから芋づる式に彼の負の話題が浮かんでくる。面白い事に、かつて彼の先導を追いかけてきたネット民達が、それを拡散させているのだ。反社会勢力との付き合いや、素行の悪さなど、ある事、無い事、色々な話題が飛び回った。そして彼は番組を降板させられる。私は愉快で堪らなかった。愉快で、愉快で堪らない。あいつは私の剣を受ける事もなく、自ら沈んでいったのだ。不戦勝と言い替えてもいい。
ただ、良い話ばかりではなかった。USAGI CITYのキーボード担当のMAHOROが電撃卒業するという噂が飛び込んで来た。ネタ元は『ウイークデイ』のプロデューサーだった。
ちょうどUSAGI CITYの新曲を聞きながら連載の一コマ漫画を描いていた時だった。『ウイークデイ』のプロデューサーから電話があり、唐突に取材を受けて欲しいと伝えてきた。
私は手元のノートを広げた。漫画にするために、これまで会った人の似顔絵を描き溜めていたノートには、そのプロデューサーの似顔絵もあった。艶やかでハリのある肌に、見事に禿げ上がった年齢不詳のプロデューサーの似顔絵を見ながら通話を続けた。まあ、年齢不詳について私が何か言える立場ではない。30後半の今でも20代と間違えられる。年齢不詳のプロデューサーからしても私は年齢不詳なんだと察する。
「USAGI CITYのMAHOROさんがグループを突然辞めるそうなんです。それについてコメントが欲しいです」
「えっ、それって本当ですか?」
私はノートをUSAGI CITYのページに変えた。凛とした演奏をするMAHOROと、あまおうソフトクリームを舐める可愛いMAHOROと、悲しい表情のMAHOROがいる。
「ええ、そうなんでよね。こちらは確証を得ていまして、今夜、自身のSNSで報告があるらしいのですよ」
「いつ……MAHOROはいつ卒業するのですか」
「それが本当に突然でして、今晩を持ってグループを辞めるそうなのです。USAGI CITYは3人編成に変わり、MAHOROさんの制作した楽曲はそのまま使うそうです」
マスメディアの最先端である、テレビ局のプロデューサーが、ここまで具体的な事を言うのなら真実なのであろう。
特にテレビ局に行く必要もなく、この電話での取材という事だったので快諾したが、真鍮は穏やかではない。大好きなUSAGI CITYのメンバーが一人減るのだ。しかも私が唯一個人的に話をした事があるMAHOROが辞めるのだ。
改めて担当ディレクターから電話があり、取材が始まった。
取材が始まると、壊れたダムのようにMAHOROに対する想いが溢れ、気が付けば涙が零れていた。一緒にサンライズマートのあまおうソフトクリームを食べて夢を語り合った。後に彼女が作曲した『微熱』がSNSで大バズりしメジャーデビューを果たした。
確かにあまおうソフトクリームを食べた時からグループのあり方について悩んでいた。特集誌の撮影の際も暗い顔をしていた。度々、彼女を救えるチャンスがあったのに、それが出来なかった自分を責めていた。
その日の夜、MAHOROが自身のSNSで卒業を発表した。詳しい理由は語らなかったが、グループ内の亀裂ではないと言っていた。グループは音楽活動を継続し、自分はソロ活動に専念するという事らしい。人気グループを作曲者として牽引してきたMAHOROの脱退に世間は大きく揺れた。ネットではこのニュースがトップに上がり、様々な憶測が拡がった。
翌日の『ウイークデイ』では私の電話取材が放送された。ドラマの番組宣伝で来た主演女優が私の悔いる泣き声につられ、目頭を押さえた。USAGI CITYからMAHOROが離れる事は悲しい。なのに変な高揚感が生まれた。確証はないがMAHOROとの繋がりは太くなりそうな予感がした。
放送後、プロデューサーからお礼の電話があり「『ウイークデイ』のコメンテーターには興味ありませんでしょうか?」と問われた。
最初は何を言っているのか分からなかったが、番組に週一度のレギュラー出演をして欲しいと言う事だと理解した。しかもあの憎き藤堂晶の穴を埋めるというのだ。こんな愉快な事はない。
「子供が四月まで保育園に入れないので、それまでは連れて行って構いませんか?」
「ええ、勿論です。弊社は女性の社会進出に積極的な取り組みをしております。局には託児室もあるので、是非ご利用下さい」
断る理由はない。
「分かりました。なんとかスケジュールをつくりますね」
「それは助かります。ありがとうございます。灰谷様のお気持ちを裏切らぬよう努める次第です」
年齢不詳のプロデューサーが、深く頭を下げる様子が頭に浮かんだ。
「こちらこそ宜しくお願いします。何とか番組に貢献できるよう頑張ります」
『DESAIRE』での連載は新シリーズに突入した。私の誕生から、母からの虐待と不倫、あれやこれや、があり漫画家として成功するまでのストーリーは終了し、漫画家として、そしてシングルマザーとして奮闘するストーリーへ移った。『DESAIRE』はそもそも働く女性をターゲットにした雑誌だったので、雑誌の趣旨と連載漫画の内容が、ようやく追いついたとも言える。
テレビのワイドショー『ウイークデイ』のコメンテーターとしての評判も上々。私の出演する火曜日の数字(視聴率)は最も良いらしい。漫画を初め、強盗殺人事件、立てこもり事件、家族問題、子育て、苛め問題、不倫。これ等を実体験から語れる者は、私以外にいない。スポーツ新聞や、週刊誌の連載を持っている事もあって、政治経済から芸能、スポーツ、性事情等の情報にも強くなった。まぁ、自分で言うのは憚れるが、私は日本一のワイドショーコメンテーターなのだろう。
『ウイークデイ』は、午前七時五十六分に放送が開始される。私等サブ出演者は、七時には楽屋に入っていないといけない。番組で保育園が不足している事を訴えたせいか、予定より早めの入園が決まった。平日は、一馬を保育園に預けているのだが、番組に出演する火曜日は、朝が早いため預ける事が叶わず、放送局に連れて来ている。放送二時間半の間、一馬は大和放送の楽屋で、Eテレの番組等を観ながら、一人で大人し遊んでくれている。
時々、スタッフが様子を見に行ってくれるのだが、問題が報告された事は一度もない。本当に面倒の掛からない子供だ。
そんな事も後1年程で終わる。来年の四月には義務教育が始まるので、連れて来る訳にはいかない。でも、何の心配もない。一馬なら自分で支度をして、ちゃんと戸締りもして学校に行ってくれるに違いない。冷たい朝ごはんを食べさせてしまう事に、若干の抵抗はある。自分は冷たい朝ご飯でさえ、食べさせてもらえなかったとはいえ、作ってさえあれば、何でも良いとは思っていない。出来立ての朝ごはんを親と一緒に食べる事が、理想だと思っている。一馬にはできるだけそうしてあげたいのだが、週に一度だけ我慢をして欲しい。一馬はそれを理解してくれるはずだ。幸いにも通う予定になっている小学校は、自宅からは近く、通学の心配も無い。何かあった際は、高梨に世話をしてもらう事にしている。一応、高梨にとって一馬は自分の子でもあるのだから、この提案を断るはずはない。
今日も番組が始まった。テレビ局の外庭に、司会者の長崎孝太と局のアナウンサーの前川仁美、気象予報士でタレントの大田誠が、並んでスタートする。今朝は生憎の雨で三人は傘をさして、カメラに向かって番組のスタートを告げる。私達コメンテーターと他のキャストは、スタジオでその様子を見守っている。大田さんの天気コーナーの間に、長崎さんと前川アナがスタジオに戻り、改めて挨拶が行われる。
「改めまして、おはようございます」
挨拶が済むと、本題へ入る。
この日は、重い心臓病で闘病中だった、大物ミュージシャンの訃報から始まった。そして大臣の失言問題に進む。VTRではマスコミにマイクを向けられた野党の女性議員が、その大臣へ辞任を促す言葉を、強い口調で発する様子が映し出されている。私達はその後に振られた時のコメントを考える。
「灰谷さんどうですか。真田大臣本人はそんな意図がなかった、と弁明していますが、私の耳には単なる言い訳にしか聞こえませんが」
「そうですね、女性としては腹立たしい発言ですね。気分が悪いです。地元の後援者へのリップサービスでしょうが、これが本題発言になる、という認識が無かったのでしょうか?脇が甘いというか、世間ずれしているというか、大臣としては相応しくない発言だと思います」
テレビ画面の向こう側にいる、ネット民達を意識しなければならない。奴等は味方でもあれば敵にもなり得る、面倒な存在だ。私はここ数ヶ月でその事を学んだ。この読みを間違えると、痛い目にあう。こうやって当たり障りの無い事も言いながらも、そこに自分の個性を交える。それがこの世界で生き抜く術なのだ。
この日も、番組の終盤で私の出番がやってきた。
最近日本で頻発している引ったくり事件。その現場を大和放送のカメラが捕らえた。自転車に乗った女性の背後から、一代のバイクが忍び寄り、肩に掛けたブランドバックを強引に奪っていく。女性は自転車ごと倒れ大怪我を負う。
驚愕の映像にスタジオは悲鳴が飛び交う。私はそれにコメントを求められた。
「同じような現場を目にしたばかりです」
心臓がバクバク鳴っている。そう、つい最近、いや、昨日の晩だ。私は同じような光景を目にしたばかりで、記憶が鮮明だった。まだその恐怖から癒えていない状態での映像は、私の身体を熱く燃やした。
「本当ですか?」
「ええ、昨日の夕方です。出版社で打ち合わせをした後の帰宅中でした」
スタジオ全体が、私の口元に集中している。
「へえ、こんな事もあるのですね」
「ええ、こちらも驚いています」
「詳しくお聞かせ願えますか?」
「ええ、勿論です」
上からの指示があったのだろう。フロアディレクターがこの話を、深堀りするように促した。
番組終了まで3分を切っている。最後は日本列島に近づく低気圧の情報で締めくくる予定であったが、私の発言で番組の構成が変わる。申し訳なくもあり、嬉しい感情もある。
「自宅マンションの目の前です。正に今のVTRと同じような状況です。私が見たのは自転車ではなく歩行者でした。私の前を歩く女性の鞄が、後ろからやってきたバイクに持っていかれたんです。驚きましたよ。見た時は一瞬、息が止まりました。相手は三十代後半と思しき男です。黒の上下を着た男です」
高揚しているのが分かった。鮮明すぎる記憶が次から次へ、甦ってくる。
「ほう、それで」
残り時間を気にしながら、長崎孝太は私のコメントを続けさせた。
「被害者女性は、倒れた時に軽く壁に肩をぶつけたようで、肩を押さえていました。幸いにも命に別状はなかったですが、あと数センチずれていたら、マンションの壁に頭をぶつけて、どうなっていたかは分かりません。肘を擦りむき少し血が流れていました。とにかく無事で良かったです」
スタジオ内が緊迫感に包まれる。五台あるカメラのうち三台が、私の一挙手一投足を捉えようとしている。
「犯人はどうなったのですか?」
「犯人は逃走しました。私は警察と救急に通報し、被害者女性の救助をしました。とにかく驚きました。今も思い出して震えています」
番組は先ほどのVTRを再度流し、注意を促して終わった。そして、出演者同士の簡単な挨拶を済ませ、一馬の居る楽屋に足を進めようとした。その足をフロアディレクターの声が止めた。
「灰谷さん、さすが持っていますねえ」
満足げな彼の表情に安堵した。後ろから別なディレクターが駆け寄り「もう、ネットがざわついていますよ」と、またまた満足げの表情をしている。私はそのディレクターが見ていたスマホを覗き込んだ。番組の公式SNSにコメントが寄せられている。〈引ったくり、恐いですね。気をつけなきゃ〉〈灰谷さんも経験されたんですね。身近な事だと恐怖を覚えました。教えてくれた『ウイークデイ』に感謝です〉
始まりは肯定的なコメントが続いていたが、否定的な、いや、攻撃的なコメントが、凄い勢い追いかけてくる。〈灰谷の発言、嘘っぽいな〉〈灰谷、番組に残りたいために、また嘘をついたんじゃないのか〉〈灰谷ならありえる〉〈そんな事件に遭遇しているのなら、番組の冒頭で言えばいいのに〉〈被害者が灰谷だったら良かったのに〉
ディレクターが、慌ててスマホの画面を閉じた。私は「大丈夫ですよ。ネットってこんなもんですよ。非難には慣れました」と気丈に振る舞った。
「灰谷さん、犯人の顔を見ましたか?」
二人の会話に、番組のプロデューサーが割って入ってきた。
「ええ、一瞬でしたが、見ましたけど」
「そうですか。覚えていますか?」
私は目を閉じ、天を仰いだ。すると記憶が甦ってくる。
「ええ、覚えています」
年齢不詳のプロデューサーの口から、白い歯が零れた。一瞬、歯が光ったように感じたのは、気のせいだろう。漫画の見過ぎや描き過ぎで時々、現実世界に漫画描写を見てしまう。
「じゃあ、絵を描いて下さいませんか」
まるで神棚に祈るかのように、プロデューサーが手を合わせた。後ろのディレクター達は「おお!」と声を漏らした。
「絵ですか?」
「ええ、犯人の似顔絵を描いて下さい。それを明日以降の放送で使います。勿論、ギャラは別途お支払いいたします」
そう言われ、私はスケッチブックに犯人の似顔絵を描いた。自分で言うのも何だが、流石に漫画家だ。我ながら上手く描けている。下書きはせず、マジックペンを走らせ、かなり詳しく犯人の特徴を描いた。プロデューサーと、二人のディレクターは「おお!」と声を揃えた。
楽屋に戻ると、一馬がいる。大人でも少し多いくらいの楽屋の中華弁当をペロッと平らげ「お腹いっぱい」と笑っていた。
翌日、私の描いた似顔絵が電波を伝った。そして瞬く間に全世界へ拡散された。
朗報が届いたのは、私の処女作『エッセイコミックライター始めました』が発売されて四ヶ月が経った頃だった。この作品が映像化されるというのだ。驚きの多いこの一年だったが、これもなかなかの驚きだった。漫画家にとって、自分の作品が映像化されるのは相当な誇りだ。映像化をされる事を夢見て、漫画家を目指す者も少なくないはずだ。映像化どころか漫画家になる事さえ半ば諦めかけていた私にとっては、この驚き、嬉しさは例えようがない。
二時間のスペシャルドラマで、制作と放送は『ウイークデイ』と同じ大和放送が行う。既にメインのキャスト候補も挙がっているらしい。主題歌はUSAGI CITYが作る事もほぼ内定している。
私以上に浮かれているのは、悪代官と越後屋っぷりが板についてきた『DESAIRE』編集長と高梨だ。トンボ出版社にとって出版作品の映像化は悲願だったらしい。長年、漫画や文芸作品を世に出してきたトンボ出版社だが、映像化された作品は意外と少ないのだ。出版物の映像化は、原作やそれを連載する雑誌の売り上げ向上に拍車を掛ける。勿論それは会社の評価をあげる事にも繋がり、担当編集者の社内での立場が良くなるのは歴然としている。ある編集者が売れないイラストレータを、漫画家に育て、その作品がヒットし、国民的アニメとなった事で、編集者から取締役まで駆け上がった事はあまりにも有名な話だ。悪代官と越後屋の前にそのビッグチャンスが転がってきた。彼等から受ける打ち合わせという名の接待は、銀座の高級しゃぶしゃぶ屋に昇格した。
私の漫画家デビューがそうであったように、作品のドラマ化もとんとん拍子で進んでいく。鉄は熱いうちに打て、といわんばかりに急発進していく。キャストや脚本家が決まると、瞬く間に撮影が始まった。
撮影が進み、放送日が近づくとPRキャンペーンが始まった。妻に浮気をされる夫、つまり私にとって父の灰谷昇一を演じる延岡清太郎と、原作者である私がペアにされ、撮影の合間を縫っては、全国の放送局や、イベント会場を回る事となった。
今まで何度も瞼に浮かんだ過去の闇を、自らの手で光を当て、他人の手が更に広く照らす。これ以上、愉快な事などあるはずがない。
延岡清太郎といえば、私が子供の頃、沢山のドラマに出演している超大物俳優だ。トレンディドラマの帝王と言われていた事もあった。多少荒削りな演技ではあるが、その個性と日本人離れの端整な顔立ちでかなりの人気だったのを覚えている。最近ではバラエティ番組のゲストや、クイズ番組の回答者としての露出が多く、世間の印象はタレントとしての認識が強いが、私にとってはやっぱり彼は俳優の中の俳優なのだ。確か、海外アニメの吹き替えなんかもしていたと思う。そんな延岡清太郎が、私が描いた漫画原作のドラマに出演するのだ。大和放送のドラマに出演する事が二十年ぶりという事を売りに、大規模な全国PRキャンペーン行脚を行うという事だ。
この作品において私の父は、重要な役割を担っている。とはいえ、転勤、出張で家に居る事は少なかったし、既に亡くなっているので露出度は少ない。無論、延岡清太郎の出番も少なく、撮影中から全国キャンペーンに参加する事が出来たのだ。
全国キャンペーンは、首都圏から近い地域から始まり、最後は大和放送の全国放送番組に出まくって締めくくる事になった。その間の一馬の世話は高梨に任せた。
まずは日帰りで東海や東北、北関東の地方局へ。その局の生情報番組に出演し用意されたコーナー等に参加して、最後に番組の宣伝をするという流れだ。
延岡清太郎とも次第に打ち解けていく。初めは彼の持つオーラにおどおど緊張しまくっていたが、時間が経てば、次第に緊張が解れ距離が近くなっていく。今は、戦友というか親友のような関係になってきた。この関係も番組が放送されたら、終わりなんだろうなあ、と寂しささえ覚え始めていた。
延岡清太郎のクランクアップが済むと、全国キャンペーンは加速する。移動距離も伸び一泊する事も多くなった。その度に地方局からもてなしを受ける。ご当地の美味しい物を食べ、その喜びを延岡清太郎と共有するようになった。
アルコールが入ると延岡清太郎は饒舌になる。
「僕は君のような、魅力のある女性に惹かれるんだよ」
歯の浮くような台詞を平気な顔をして言うのだ。
「嘘でも嬉しいです」
「嘘じゃないよ、本当に君には魅力を感じている」
「ありがとうございます」
「もしかして僕は誰にでもこんな事を言う奴だと思っていないかい?」
「違うんですか?」
延岡清太郎の手が私の太股を摩っている。明らかなセクハラだが相手は大物俳優の延岡清太郎だ。悪い気はしない。
「違うよ。こう見えて初心なんだよ」
「そうなんですか」
「そう、今まで口説いた女はこれだけだよ」
そう言って右掌を広げた。
「えー、五人ですか?」
「まさか、五万人だよ」
そんなやり取りにも慣れてきた。
こんな僕ですがサポートをして頂けると嬉しいです。想像を形にするために、より多くの方に僕の名前・創作力・作品を知って欲しいです。 宜しくお願いいたします。
