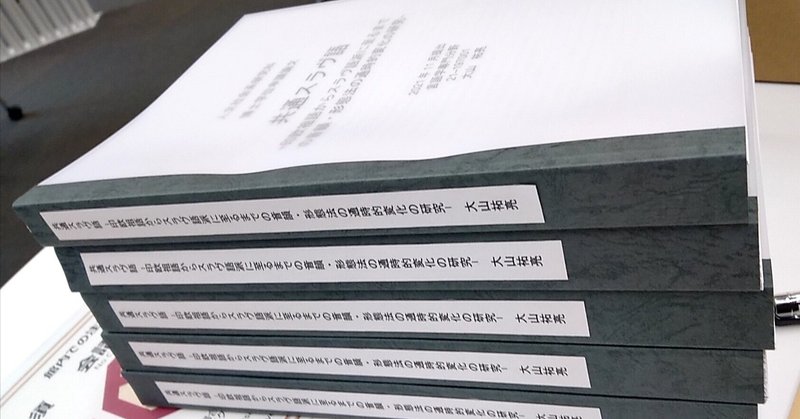
ある博士の愚痴(博士論文の序文)
説明
これは、昨年の3月に東京大学大学院人文社会系研究科に提出した博士論文の最初につけてあった序文です。この部分の著作権は当然私が所有していますし、南原賞に応募した原稿ではこの部分は削除しましたので、今後著作権が私から離れることもありません。
博士論文本体はありがたいことに第13回南原繁賞を受賞できてしまっため、書籍としての出版が決まっています。
しかし、この序文の内容は南原賞に応募した原稿に含まれていないため、東大の文学部2号館図書室に一部入っている博論製本版に入っているだけとなっています。ただでさえ450頁近くあるので少しでも原稿を短縮したかったというのが削除の主な理由ですが、かといってこのまま事実上のボツとして2号館図書室に眠らせておくのも惜しいと思いました。ですので、ここで公開してしまおうと思います。
内容ですが、主に博士予備論文の執筆の途中から執筆完了までの間(2019年9月-2021年3月)の心情の吐露と愚痴です。この間何があったのかはご想像にお任せします。では、以下が本体です。
序文本体
研究者なんてなるもんじゃねえな、と思わない日は少ない。以前友人たちと居酒屋に集まったときに、「これからはいかに自分の研究を社会に還元していくかを考えなきゃいかんでしょ」と皆口々に言っていたのが、もう6年程前[注:2016年]の話だけれども頭から離れない。
この論文[注:この序文がもともとついていた博士論文の本体]を読めばわかるように、私の専門は比較言語学である。しかし、比較言語学が社会に対して何ができるか、と考えると、言語系統の悪用を阻止するであるとか、極めて後ろ向きなものしか思い浮かばないが、これは比較言語学の本質ではない。最近は比較言語学が学問としての研究に値するものなのかという根本的な点についてもかなり疑問を抱くようになってきたし、まして、それが金銭的に何の役に立つのかと問われると完全に答えに窮してしまう。この問いについて考えるのが嫌で仕方なかったから、日本を飛び出して、多少なりとも他人の人生に貢献することができそうな日本語教師になる方に気持ちが傾いた。最終的な決心がついたのにはまた別の要因もあったが。
「別の要因」については以下の過去記事をご参照ください。
このような問いや、世間の人文科学に対する風当たりの強さを抜きにしても、中学校や高校の同級生が毎日仕事に行って、中でも数人は結婚して、子供がいて…というのを目にすると、私は20代後半にもなって一体何をやっているんだろう、という感覚が常につきまとう。一応述べておくが、日本で考え得る博士号までの最短コースを歩いてきてこれである。やっぱり研究者なんてなるもんじゃない。
くだらない身の上話は置いておいて、本論文に話を移すと、この論文は副題を長くして、題目を単に「共通スラヴ語」としてある(なぜか副題が半角スペース[sic. 正しくはハイフン]で登録されてしまったのだが、手書きの棒が短過ぎたのかもしれない)。これはMeillet(1934)の書名Le slave communを意識したものである。Meilletのアイディアが数ある先行研究のうちでもっとも説明の方針が良く、方法論に対する理解も極めて正確であると私が勝手に評価しているためである。この題目は、自らの方法論を過信しがちな(ものだと私がやはり勝手に評価している)近年の研究の傾向を再考すべきである、という私の見解を反映したものであると同時に、題目に負けないような質の高い研究をしろよ、という自らに対する激励でもある。結果がどうであったかは私にもわからないし、私が判断できることでもない。
この論文の内容は、学部時代からの私の研究の集大成といえるものである。例えば前舌化の環境は2016年4月2日の午前1時頃に思いついたものであるが[注:わたしにとっては学部3年と4年の間の春休み。この時期の精神状態はわたしの人生でも最悪なものでした]、この博士論文の文章の大半は2019年秋に書き始めて、1年半ほどでこしらえたものである。はっきり言って、東大の言語学研究室の歴史上、この論文ほど安産であった博士論文もないだろう。実際に、執筆過程においては、何か言いたいなと思った箇所にはすぐに啓示が降りてくるし、曖昧な直感を言語化するのもうまくいって、吃驚するほど順調に進んでしまった。
それでも、元々わかりやすい文章を書くのがヘタクソだという自分の欠点もあり、いまいちちゃんと文章で伝えられているか自信がない(先生方、いつもすみません)。一応自己分析をしたことがあるが、三つほど原因があるようである。一つ目は、自分にとって当たり前の知識を省略してしまう癖で、読む人のことが考えられていない(ただし、これは博士課程に入ってからかなり改善したと思う)。二つ目は、無意識に自分の思考を追う形で文章を展開してしまう癖で、本題をしっかりなぞるようにあとで修正してやらないと話があっちへ行ったりこっちへ行ったりして徐々に脱線してしまう。正確を期すためにここを補足しなくちゃ、ここも補足しなくちゃ…とどんどん付け加えていくと、最終的に本筋がなんだったか著者にも読者にもわからなくなってしまう。三つ目は、つい書くのに熱が入ってしまい、一文が長くなる癖である。一体これらの点が誰の参考になるのかはわからないし、序文を真面目に読む人などほぼいないと思うが、一応教訓として記しておく。
コメント:「気を抜くと一文が長くなる」これはガチ。
一方で、論文を書き始めるに至るまでの過程では、それなりに大変なこともあった。そもそも、比較言語学は研究対象の言語がある程度以上わかっているのが前提であるから、ある程度語学として対象言語を勉強しておくことは必須であるし、正確を期すためには電子テクストではなく写本を確認しておくのが正式な作法である。ということで趣味と実益を兼ねて写本(の写真版)を見ながら勉強するのだが、実際に見てみるととにかく読みにくいのである。例えば、スラヴ語比較言語学ではお馴染みの古教会スラヴ語(フライジング断片を除く)では、写本はグラゴール文字かキリル文字のどちらかで書かれている。このうち、スプラシル写本(Codex Suprasliensis)などのキリル文字写本は、多くの場合私でもそこまで判読に苦労しない(キリル文字写本の本気はもっと後代のものである)。問題はグラゴール文字写本の方である。出版されたテクスト(例えばゾグラフォス写本(Codex Zographensis)の校訂など)を見てみると、キリル文字がものすごく整然と並んでいて、あたかも完全な形で残っているかのように錯覚させられる。
しかし、実際に自分で例えばアッセマーニ写本(Codex Assemanius)の写真版を見て実際に読もうとしてみると、最初の数葉からしていきなり高い壁となって立ちはだかってくる。状態が悪い箇所の場合、出版された活字と突き合わせつつ、目を皿にして探してなんとかうっすらと見えるか見えないかみたいなことがほとんどである。大抵は薄かったり潰れていたりして、そこにその文字があると思って見なければとても私には判読できない。二種類のイェル(Ⱏ とⰠ)についても、左側にマルが見えたり見えなかったりして、本当に校訂本の転写で合っているのかと頭を抱えることが一度や二度ではない。左上が欠けるとg(Ⰳ)とx(Ⱈ)も前後の文脈からしか判断がつかない。状態が悪い所ではe(Ⰵ)とo(Ⱁ)の区別さえ潰れていて判然としないことがある。時折顔を見せてくれるі(Ⰹ)君が唯一の癒しである。
電子テクストは一応存在するが、見たところ福音書の本文だけをマタイから順に並べる形(要するに普通の四福音書)をとっているため、写本(アプラコス福音書という種類)の順番にはなっていないし、福音書本文の引用の間にある出典の説明や、文脈を補足するために引用の直前に追加される一節が載っていない。本当はそういう所の翻字の方が参考にしたかったりする。それでもアッセマーニ写本の場合、最初の数葉さえ乗り切ってしまえば後はもう綺麗なものである。むしろ最初の数葉は写本を甘く見るなという洗礼であるかのように感じられるくらいである。写本の見栄えもよく、読んでいて気分がいい。
そうこうしているうちに日が傾いてきて、ふと、20代半ばにもなって私は何をやっているのだろう、と急に冷静になる[注:この箇所の執筆時、わたしは26歳]。外で子供達が元気に遊んでいる声が耳に入り、あの子達がやっていることと私がやっていることは一体何が違うのだろう、という疑問が生じてくる。子供達の親の年齢は下手したらわたしよりも低いんだろうな、と思ったりもする。マックス・ウェーバー先生は『職業としての学問』において、
ある写本のある箇所について「これが何千年も前から解かれないできた永遠の問題である」として、なにごとも忘れてその解釈を得ることに熱中するといった心構え––これのない人は学問には向いていない。そういう人はなにかほかのことをやったほうがいい。
と述べておられるが、私が「なにかほかのことをやったほうがいい」人間の方に近いことは言うまでもない。しかし、かといって他のことができるわけでもないので、これでよかったような気がしないでもない。苦痛にならぬ程度に好きなことをやって、それで生きていけるのなら、それ以上の環境はないと思う。毎日昼寝できるならなお良いのだが。
なお、残念ながら、このように写本と格闘している時に本業である比較言語学のアイディアが降りてきたことは一度もない。アイディアが降りてきやすいのは風呂、トイレ、布団の中、そして散歩道である。
それでも、こういう作業は徒労にはならないと信じている。私が写本に多少は気を遣うようになったきっかけのひとつに、(中・新)エジプト語の学習経験が挙げられる。エジプト語のヒエラティックのパピルスは、状態が比較的良い箇所でさえどの文字と解釈するべきかわからない例が山ほどある。年代・地域による字体の差がグラゴール文字の比ではない。また、ヒエログリフの碑文についても、ほとんど摩耗してしまって見えない箇所を半ば作文のような形で補って出版されているような例がある。そして、そのような例が文法書に例文として採用されてしまうことさえある。すなわち、文法書に載っている例文が実在しない可能性があるということになる。何かの現象を何らかの理論で説明したとしても、その現象を示唆する箇所自体が校訂者の作文である可能性がある。
これは恐ろしいことである。本論文では比較言語学の方法論に細心の注意を払ったが、元の言語事実が存在しない可能性があるというのは方法論以前の問題である。そのような状態から、まず信頼のおける読みを文献学によって確立し、言語学的な解釈を行い、比較言語学で通時的な変遷を辿るという作業は、最早一人の人間の手には負えないように思われる。かといって複数人で分担するのも、現状では各人の価値判断の基準がかなり異なるため難しい。比較言語学の成立の基礎には文献学があるので、文献学が崩れてしまうと比較言語学も崩れてしまうことになる。
このような問題から、さらに視野を広げてみると、この比較言語学という分野にこそマクドナルド化(リッツァ 1999)が必要なのではないかと思われてくる。マクドナルド化は、基本的には「合理化にともなう、意図せざる結果としての非合理化」(伊藤 2007: 71)という逆説を指すが、人間の手に依存しない制御がかえって利点になるこの分野では、いつどこで誰がやっても同じものが出てくるようになるということは、むしろ歓迎すべきことではないだろうか。
例えば、私はこの論文において、規則性仮説を原則として、最節約原理で仮説を評価したらどうなるか、という基準を一貫して用いている。分析の道具立てを変更したり、全く新しい仮説が提出されたり、この評価基準自体を変更したりといったことがない限り、本論文の結論を変更することは基本的に不可能である。すなわち、データを仮説評価装置に通して結果を得る、というこのプロセス自体には(少なくとも方法論及び研究倫理的に正当とみなされる形では)人間の意思が介入することがほとんど出来ないように方法論を整備してある。多少懐疑主義に振れ過ぎたかな、とは思うが。ともかくこれらを踏まえると、若干無理矢理な部分もあるが、比較言語学のマクドナルド化は、おおよそ次のような感じでまとめられる。
効率性:規則的な音変化に説明方法の選択肢を限定することなど
計算可能性:仮説の妥当度の算出を可能とすること
予測可能性:同じデータと仮説評価装置を用いれば同じ結果が得られるようにすること
制御:方法論的に妥当な手続きに恣意的な判断が介入する余地を生じさせないこと
これに基づいて、とりあえず頻度の高い基礎語彙や主要な接辞・語尾等を文献学的にしっかり確定させさえしてしまえば、あとは機械的に手順に沿って比較することで、なんとか比較言語学を成立させるところまで持っていけるのではないだろうか。
現代ではあらゆる面で何かと批判を浴びがちな人文学であるし、その中には私からみて不当な批判というのも多くあるが、仮説の優劣、すなわち何を以て優れた研究であると見なすのかという基準を決めるのに恣意的な判断が介入しうるという点については、確かに改善する必要があると思う。
何を以て研究の進展と看做すのかという基準が共有されていないと、各人が自分の仮説にとって有利なデータを確証バイアスという衣に包んで投げつけ合うばかりということになってしまいかねない。そうなると、結局は特定の教条を支持するかしないかの問題になってしまうから、論文は説得の文言を並べたものにならざるを得なくなってしまい、どんな価値判断からその結論が出てくるのかを明確にしていないから、学派間で合意が得られない、ということになってしまうのだと私は考えている。祖語の再建形にトレンドが存在するというのも、結局は研究者の威信や師弟関係ベースで陣取り合戦をやっている結果なのでは、と思えてならない。より妥当な仮説・説明・解釈等を追求する(数学以外の)学問の営みにおいて、それっぽい意見で他人を説得するという自己満足の追求に何の意味があるだろうか。この論文では、何が比較言語学的な研究として認められるもので、何が学問的でないのか、という境界線をはっきりと設定し、さらに仮説の評価基準の設定の重要性を強調しているが、それは上のような問題意識が背景にあってのことである。
一方で、現在では、オープンサイエンスが世界的な潮流となっていることもあり、調べ方さえ知っていれば多くの論文がインターネット上で入手可能であるし、写本でさえスキャンされたものが徐々に公開され始めている。一歩間違えれば前提条件も過程もブラックボックス化してそれっぽい結論だけが弾き出されるという魔法の道具と化してしまいかねないため、人文情報学の隆盛が無条件で善であるとは考えていないが、それでもこれらを利用しない選択肢はない。我々が生きるこの時代においては、文章を研究として成立させるための方法論的前提が頭に入ってさえいれば、(非常に困難だとはいえ)独力で研究をすることは一応可能であると思われる。
その分野の研究に用いられるデータを十分によく把握し、仮説評価の基準さえはっきりさせておけば、あとは方法論的に妥当な範囲での発想力の勝負であり、この点においては、大学に所属していることは絶対的に有利な条件であるとはいえない。それを踏まえると、人文学カルテルとしての大学は既に役目を終えたといえるのではないだろうか。むしろ、立場的な制約だけは所謂在野の方が少ないといえる。
別の見方をすれば、大学における(人文学)研究者の立場が厳しくなるにつれて、本来それよりも遥かに厳しい立場の在野研究者に相対的に光が当たりやすくなっているのかもしれない。これは本来であれば大学の研究者の待遇改善に声を上げるべきところなのだろうが、逆に研究の裾野を拡大する機会と捉えた方がいいような気が私にはしている。研究費・研究時間をどう調達するかよりも、研究の質をどう担保するかという問題の方がおそらく解決しやすいのではないか、とも思う。いずれにせよ、学問の名に値するものと学問の名に値しないものの厳密な境界線を方法論的にしっかり設定できるかどうかが、人文学の運命を分ける重要なポイントになるのではないかと考えている。
さらに大学の内部に目を向けてみると、やはりマックス・ウェーバー先生が、大学における教師の役割について、
「諸君は、百人の教師のなかのすくなくとも九十九人は人生におけるフットボールの先生ではないということ、いな、およそいかなる人生問題についても「指導者」であることを許されていないということ、を忘れておられる」
と述べておられる通り、文学部に入ったからといって人生の難問への答えそれ自体は手に入らない。手に入るのはせいぜい過去の人間がその問題について何を言っているかを調べる方法くらいのものである(これは知識を増やすためのものとしては実用的かつ重要な技術なのだが、一般的に人生にオカネという名の幸福をもたらす類のものではない)。
むしろ私の場合、研究を進めれば進めるほど、世間に対して顔向けできないというような漠然とした羞恥心や、数年先の自分の人生さえ見通せないような不安感が人生にさらに暗い影を落とすようになってきた。幸い私は特別に、本当に特別に運の良い人間であったが、そういう体験があるので、ずっと文学部にいた私でさえ、わざわざ大学で人文学の講座を開講して、学生にとって貴重な人生の数年間をそれに消費させるだけの価値はあるのだろうか、と疑うようになってしまった。
少なくとも、私の専門である比較言語学については、大学の外での研究が可能であると確信している。その点を考慮すると、大学の中に話を限定しなければ、人文科学の未来はそこまで暗くないのではないだろうかと思う。現在人文学全体にかかっている淘汰圧が何らかの形でプラスにはたらくことを願うばかりである(尤も、大学の外において、余暇に研究をするだけの余裕がある人間がどれだけいるかという点はかなりの不安要素である。怠惰な私だったらゲーム、ネットサーフィン、昼寝で時間を潰すであろうことは疑いようもない。『在野研究ビギナーズ』の荒木優太先生らをはじめ、在野の研究者の方々にはただただ敬服するばかりである)。私自身も、別のことを生業とされながら御自身の研究をまとめられて発表をされた方を存じ上げている。そのような方こそ、人文学の明るい未来を切り開く希望の光として賞賛されるべきである。
さて、ここまで言いたい放題言ってしまいましたが、以下は謝辞になります。…(以下、謝辞のため省略)
補足
まず、わたしは社会不安障害というのを抱えています。といいつつも、社交だけでなく締め切りとかでもかなり不安を感じやすいので、度を超えた心配性という程度のものだと解釈してくれると助かります。そういう人間が書いた文章だと把握するとちょっと解像度が上がるかもしれません。なお、この心配性、意外と役にたつもので、締め切りの遥か前から爆速で研究を進めるターボエンジンみたいな役割も果たしてくれます。メンタルはゴリゴリ削れますけどね。おかげで(元から無茶な日程であるものを除き)締め切りで苦労したことがありません。
この文章は博士課程の在学中に書いたものです。当時はまだ就職先も決まっていなかったため、就職に関する不安がどんよりと心を覆っていた時期です(「運の良い人間だった」のくだりだけ就職が決まってから慌てて付け加えたような記憶があります)。常勤職を手に入れた今となっては、そういう不安はほとんどなくなってくれました。メンタルの安定マジ大事。逆に言えば、3年後の未来も見えない状況で、100年後を見据えた研究なんぞできるはずもないのです。
また、当時は学派の枠にとらわれずに自由に浮動するインテリゲンツィヤとしての在野研究に期待を寄せていましたが、今はそうでもありません。今の私の中で支配的な考えは、「そもそも比較言語学って本当にやる意味ある?」です。まあ、少なくとも今のところは、世間的にも比較言語学が学問分野として認められていますし、今いる大学がわたしの研究に価値を認めてくれて、パトロンみたいになってくれているので、支援があるうちは続けますけれども。
ただ、今の比較言語学の潮流は徹底的に壊さないと先がないなとは感じています。来年書籍化される博士論文の本体は、最終的には比較言語学という分野それ自体の解体と再構築を目的としています。それが成っているかどうかを判断する資格はわたしにはありませんが、比較言語学は一歩間違えると妄想の方向に突き進んでいってしまうぞ、という注意喚起だけはできているのではないかと思います。出版されたらぜひ第一章だけでも読んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
