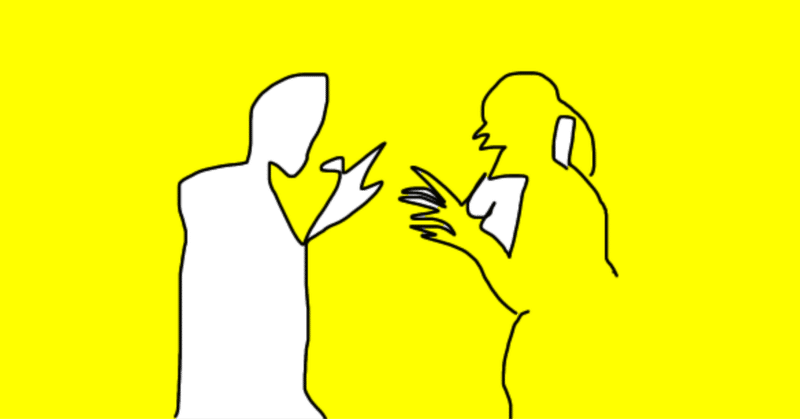
『人生が整うマウンティング大全』山本圭氏との対談希望(人間学)
発売と同時にベストセラーという著者にとっては羨ましい(マウンティング)な1冊。潜在的に人間が持つインサイトを見事にテーマにしたことがベストセラーの要因なのだろう。内容を読んで気がついた点を列挙してみた。
「駐妻マウンティング」という言葉があるが、実は帯同家族のメンタル問題は深刻化している。単純に考えても、夫、もしくは妻の海外赴任に帯同するということは、今までの人生で培ってきたキャリアを強制的に中断されてしまうことになる。さらに見知らぬ土地に住むことになるので、ストレスは半端ない。しかも、子供教育の問題から生活習慣の問題などだけでなく、言葉の問題からの孤独感、悩みを打ち明けると同じ日本人コミュニティーの噂話の遡上に上げられてしまう。実はメンタル問題に陥る人の半数が帯同家族なのだ。
「ニューヨーク駐在マウント」とあるが、実は現在の企業の若者からは海外赴任は避けられることが多く、2度、3度とベテランが赴任するより仕方ない状況に陥っている。そのベテランは定年を前にした50代であることもあり、闘病病などの既往症や高血圧などから、心臓や脳の病気を海外で発症するリスクが極めて高い。しかも、日本人は日本国内の国民皆保険制度に守られていることから、病院に行くタイミングが遅い。つまり、我慢に我慢を重ねてから医者にみてもらうことになり、手遅れになるリスクが高いのだ。
後半にDX、MXというくだりから筆者はIT業界に生息していると想像できるが、優秀な東大卒はIT業界に少ないので、「東大卒否定マウント」があるのだろう。同じように、本当に優秀な人は留学ではなく、海外に教えに行くという「留教」をする。
オーストラリアのアボリジニに対する実験で、その空間把握の能力が西洋人より遥かに高いにも関わらず、IQは低いという結果から、グローバル指標として普遍的なものではないという意見もある。
1/3ほど読んで、後はザッと目を通しただけだが、ここに例として列挙されているマウンティング例は、筆者のつき合う人たちの人生環境から生まれるものだ。したがって、同じようなレベルならば「なるほど」となるが、それが違うと、似たものレベル同士はこうなのか、となる。
そこで提案だが、マウンティングの原理を明らかにした上でのマウンティング大全という構成にならないものだろうか。つまり、人間の心理的な原理があり、それがマウンティングを誘うとこうなる。あるいはマウンティングタイプA、マウンティングタイプBに分類され、こうこうこういう場合は、発信者と受け手はタイプAになるはずだ、などの心理分析があると、長く売れる本になるような気がする。
方法として、最近『嫉妬論』(光文社新書)を著した山本圭氏と対談をやってみると、これらは明らかになるのではないだろうか。たとえば、人類最初の嫉妬であるカインとアベルの物語から、良性嫉妬、悪性嫉妬の分類など、マウントフルネスに理論的な背景をビルトインすることができるはずだ。そうなれば、コンテンツに深みが増し、不易な要素が高まる。
Creative Organized Technology をグローバルなものに育てていきたいと思っています。
