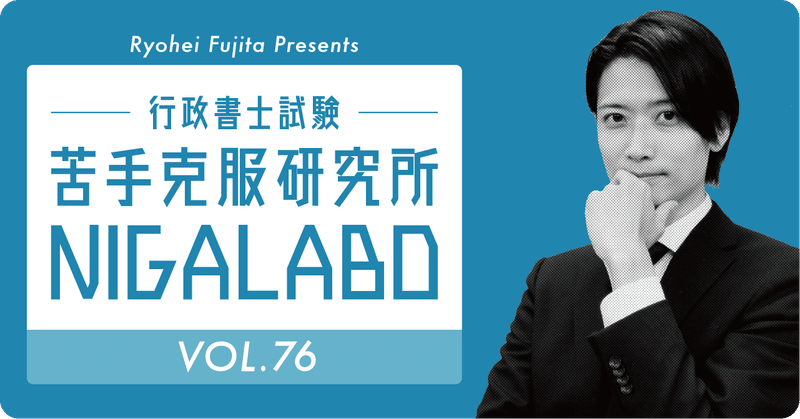
第76回 苦手克服研究所 民法「制限行為能力者」
みなさん、こんにちは。
伊藤塾行政書士試験科講師の藤田です。
それでは、今回も一問一答をやっていきましょう!
今回取り扱うテーマは、
民法の「制限行為能力者」です。
題材としては、「令和2年度 問題27 肢5」を扱っていきます。
まず、「令和2年度 問題27 肢5」を以下に示します。
肢5 制限行為能力者が、相手方に制限行為能力者であることを黙秘して法律行為を行った場合であっても、それが他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは、詐術にあたる。
……
いかがでしょうか?
結論からいうと、肢5は正しいです。
以下、理由を解説していきます。
肢5は、制限行為能力者の詐術についての知識を問う問題です。
まず、民法21条は、「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」と規定しています。
そして、同条における「詐術」とは、制限行為能力者が行為能力者であることを取引の相手方に信じさせるために行う術策をいいます。
そして、制限行為能力者であることを単に黙秘するのみでは「詐術」にはあたりませんが、他の言動等と相まって相手方の誤信を強めさせたような場合には、「詐術」にあたると解されています。
本問でこれをみると、「他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは、詐術にあたる」とあります。
したがって、肢5は正しい、ということにあります。
制限行為能力者の詐術についての知識は、基礎的かつ重要なものなので、この機会に押さえておきましょう。
今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく
予定ですので、日々の勉強の息抜きに
ご活用ください。
