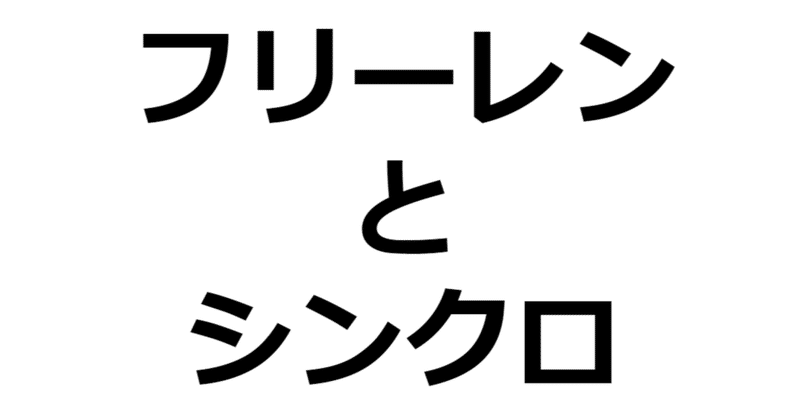
【葬送のフリーレン】フリーレンとシンクロする:植田正治写真美術館を再訪
漫画「葬送のフリーレン」では、過去に行ったことをもう一度行うことが度々あります。ただ、過去のものとは何かが異なっており、それを「過去の押韻」と呼んでいます。
本記事では、現実の世界で「過去の押韻」を経験したことを紹介し、その経験が葬送のフリーレンのエピソードとどのようにシンクロしているかを考察したいと思います。
テーマ全体の説明については、以下の記事を御一読ください。
本記事では、昔に訪れた植田正治写真美術館を、今の私が再訪した経験を紹介します。
以下で引用する葬送のフリーレンのエピソードは、単行本全5巻までの内容を含むので、ネタバレを避けたい方は読むのを止めて下さい。
植田正治とは
植田正治先生は、世界で最も注目された日本人写真家です。
以下、リンクからの引用です。
生地(鳥取県境港市)を離れず、山陰の空・地平線・そして砂丘を背景として、被写体をまるでオブジェのように配置した植田正治の演出写真は、写真誕生の地フランスで日本語表記そのままにUeda-cho(植田調)という言葉で広く紹介されています。
植田正治写真美術館とは
植田正治写真美術館とは、植田正治先生の作品が展示された美術館です。
以下、リンクからの引用です。
当館は自然豊かな大山山麓に位置し、建築家・高松伸設計による館内からは水面に映る“逆さ大山”が楽しめます。
過去に訪れた時の状況
私が大学生の時に、この美術館を訪れました。
植田正治先生の写真集は何冊か購入しており、こんな写真が撮れれば良いなと、憧れていた記憶があります。
写真以外でも、どことなく幻想的で浮遊感がある作品が好きで、植田正治先生の作品は自分の価値観のど真ん中にあったような気がします。
再訪した時の率直な感想
率直に言うと、こんなに小さかったっけ?と思いました。
たぶん一周するのに、やろうと思えば20分位で出来てしまうくらいの展示物の量でした。
過去に訪れた時の記憶には、多少の思い出補正があったのかなと思います。
展示物自体については、過去と同様にカッコイイなと感じました。(素人っぽい感想でスミマセン)
再訪した後に考えたこと
考えたことは3つあります。
植田正治先生が貫いたこと
今回訪問して、植田正治先生に対して抱いていた印象が少し変わりました。
初期の作品や後期の作品での、人や物を徹底的にディレクションした「演出写真」が、植田正治先生のアイデンティティだと感じており、実際そのような写真に大学時代憧れていました。
ただそうすると、中期の作品である「童暦」や「小さい伝記」に見られる、スナップ写真的な作風に、若干の違和感を感じていました。
今回訪問して、自分の中でその違和感は解消しました。
どの時代でも一貫して、植田正治先生は、「写真を撮るという基本的な行為」に真摯に向き合い楽しんでいたのだと気づきました。
「童暦」や「小さい伝記」においても、自然に被写体を撮っているようにみせて、実は被写体にカメラを意識させた上で、シャッターを切っていたそうです。
つまり、上記の作品は「演出写真」として撮っていたということです。
これは一種のリアリズムに対するアンチテーゼであり、カメラを意識せずに写真を撮ることは不可能だと認めた上で、そのカメラも含めた「写真を撮るという基本的な行為」を楽しもうと考えていたのだと思います。
上記の視点で「童暦」や「小さい伝記」を細かく見てみると、確かにカメラを向けられた時の独特の緊張感や不自然さを、被写体が醸し出しているのが確認できます。
そしてその独特の雰囲気が出るところを、植田正治先生はレンズ越しに楽しんでいたのではないかと思います。
長々と書きましたが、植田正治先生がよく使っていた「写真する」という言葉が、まさに今まで述べてきたことを端的に表しているのかなと思います。
植田正治先生の作品の時代性
植田正治先生の作品は、個人的に時代性があまりないと考えています。
構図と余白に徹底的にこだわった作品は、たとえ白黒写真であっても、普遍的な魅力を放つものだと思います。
ただ今回再訪して、1つだけ時代性を感じたものがありました。
それは被写体が醸し出す独特の緊張感です。
植田正治先生が生きてきた時代の大半は、写真が貴重なものでした。
それ故に、1つの写真を取るために時間を掛けたり、被写体の方もカメラを向けられるのが珍しく、独特の緊張感を出していました。
ただ現代は、日常のどの場面にも写真が存在し、被写体もカメラにすっかり慣れてしまっています。
カメラを向けられた時の、被写体が醸し出す独特の緊張感や不自然さは、もう現代では再現できないのかもしれないと考えると、初めて植田正治先生の作品に時代性を強く感じました。
新しいことに挑戦すること
1980年代に入り、植田正治先生はファッション写真の分野に挑戦します。
70歳を超えた中での挑戦であり、もちろん大学時代もその事実は知っていましたが、歳を重ねた上で再訪し、改めてその事実を確認すると、その凄さをさらに強く感じました。
年齢的に老いてもなお、好奇心を保ち精神的に若い姿は、尊敬できるものでした。
以下で引用する葬送のフリーレンのエピソードは、単行本全5巻までの内容を含むので、ネタバレを避けたい方は読むのを止めて下さい。
葬送のフリーレンとシンクロしたところ
対応する葬送のフリーレンのエピソード
この経験と共通点があるな、と思った葬送のフリーレンのエピソードは、フリーレンとクヴァールが再び対峙した場面です。
腐敗の賢老クヴァールは、"人を殺す魔法"を開発した、偉大な魔族の魔法使いです。
クヴァールと植田正治先生で、関連することは3つあります。
・攻撃魔法に対する真摯さ
明確には描写されていませんが、勇者一行の冒険の時代は、属性攻撃が主流だったと考えられます。
下の場面のデンケンの攻撃に見られるように、老齢の魔法使いは火や風などの属性攻撃を使う場面がよくあるのが上記の根拠です。

その時代において、おそらく無属性の魔法で、人体を直接破壊するという、「攻撃という基本的な行為」を真摯に突き詰めて考え、"人を殺す魔法"を開発したクヴァールは、植田正治先生の写真に対する姿勢に通ずるものがあると考えています。
・開発した魔法の時代性
勇者一行の冒険の時代には、猛威を振るった"人を殺す魔法"ですが、現代までに徹底的に研究され、人類の魔法使いの誰もが使える魔法になり、それに対する防御魔法も装備も豊富になりました。
"人を殺す魔法"に対する反応も、昔は強い恐怖の反応が見られましたが、現代では「ああ、一般攻撃魔法ね」といったような、緊張感のない反応になったと推察されます。
これは今回再訪して感じた、カメラを向けられた時の反応の時代性に通じるものがあります。

・魔法に対する好奇心
"人を殺す魔法"を防がれたことに対し、クヴァールは狼狽えるどころか、防御魔法の弱点を冷静に分析して、対策を的確に実施しています。
これはクヴァールの魔法に対する強い好奇心を表していると考えており、それは植田正治先生の写真に対する好奇心に通じるものがあります。

ちなみに反例として、魔族の中でも、自分の魔法が攻略されるとは一切考えず、狼狽えてしまっているアウラという魔族も登場します。

シンクロしたところまとめ
葬送のフリーレンに登場するクヴァールは、攻撃魔法に対する真摯さ、開発した魔法の時代性、魔法に対する好奇心という観点で、私が再訪して感じた植田正治先生の凄さに通じるものを感じました。
まとめ
多少強引な関連付けではありましたが、いかがでしたでしょうか?今後も私が経験した「過去の押韻」と、それが葬送のフリーレンとどのようにシンクロするかを、いくつか記事にしていく予定です。
長くなりましたが、最後まで読んで頂きありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
