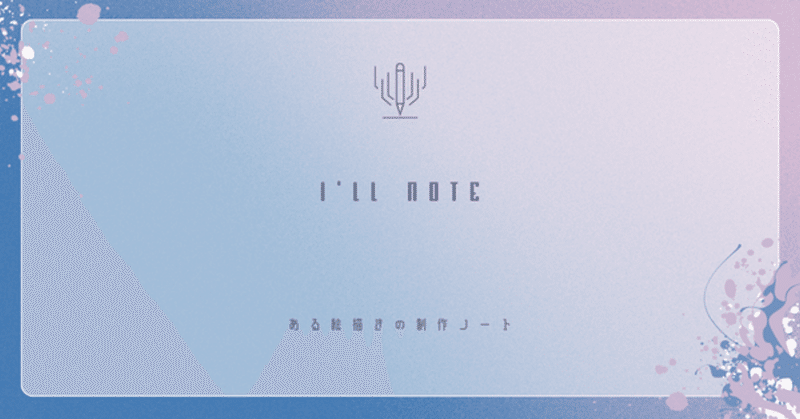
生成AIがどうなってもプロのクリエイターが勝つ理由
※この記事は、私が一個人として調べ考えたことをまとめたものです。私見を扱った内容であり、対抗言論を前提として発表するわけではないことを記しておきます。
はじめに:生成AIが映画界に進出した未来
2030年、生成AIの飛躍的な進歩により、PCのGPUを1時間走らせておけば2時間の映画を出力できるようになりました。
その映画生成サービスは(仮に)Googleが運営しているとします。新海監督作品のようなアニメとか、ハリウッド並の数十億円規模の映画を、サブスク月々3980円で誰でも作れる画期的なサービスです。
自分好みのストーリーを鑑賞できると評判で、なぜなら過去のビッグデータや自ら学習させた個人情報で、感動のツボを抑えた映画が自動生成されるからです。
生成した映画は、「YouTube Movie(仮)」にアップして収益を得ることが可能です。しかし、最後まで再生される映画はほとんどありません。多くの作品が飛ばし飛ばしで見られる上、サジェストされないからです。
身元のわからないアカウントがランキング上位を行ったり来たりしていますが、それはアルゴリズムの最適化でサジェストされやすくなり、たまたま閲覧数が伸びただけで、特筆して面白いわけではないようです。
大量の生成映画と競合状態を作り出し、既存の商業作品と潰し合うせいで、良いものが話題にも登らなくなってしまいました。「この生成映画が面白い!」というレビュー記事も、AIで書かれたもので参考になりません。
それでも、街から映画館がなくなったわけではありません。映画上映は未だ特別な体験型エンターテイメントであり続けています。
映画館で上映されるのは、きちんと資本を人的リソースに回した歴史ある制作会社の作品で、生成AIはほとんど使っていません。
なぜ映画館に大バズりした生成映画が上映されないかと言うと、AI生成物に著作権が認められないからです。権利の大元が不明瞭なため、商業ビジネスでは流通できないのです。
街ではまだ映画館には人が集まりますが、それでも大規模な映画館はだいぶ消えてしまいました。タダで映画を観る方法が無数にあるからです。そのため、映画会社もちゃんとした作品を作るのは一年に数本という規模になっています。
ある男が、自分の生成映画に限界を感じ、新しいスパイスを探していたところ、現在公開中の映画に面白いテイストがあることを発見しました。
男は映画を前衛的なクオリティに仕上げようと思い、最新映画をAIに学習させられないかと考えました。たまたまその映画の一部がネットで配信されていたので、取り込んで新しい生成映画を出力し、それをYouTubeMovieにアップして収益を手にしました。
最新映画がマウントされたことに気づいたのは、元の映画をチケットを払って鑑賞した人でした。この件を映画制作会社に報告しましたが、「AIの学習と利用はフェアユースに基づくため、訴える価値はない。利用が明らかに証明できなければ逆告訴もありうる」と消極的な返答が返ってきました。
これは、私が想像した「2030年の映画界」です。結論を先に申しますと、こんな未来はおそらく起こらないと思います。この寓話は、今の問題が全てスルーされ、欧州のAI ACTが有名無実化された世界の話です。
現実はそんなにすんなりと行かない、という話を今回は書きたいと思います。長くなりますので、休み休み最後までお読みください。
ほとんどのクリエイターは反AIではない
さっきの話は、今のイラスト界隈で実際に起きたことに基づいています。
イラスト投稿サービスでのAIイラストの氾濫、SNSで手書きを騙るAI絵師、AI禁止のプラットフォームでのAI生成物による収益化、DLSiteなどの同人DL市場の占有、この状況はかなり知られていると思います。これにより、既存の技術で戦ってきたクリエイターは経済的損失ばかりでなく、AI生成物による嫌がらせも多発し、精神的な負担にも晒されています。
私は実際、画業を営んでいて直接的に「AIクリエイターは商敵」と感じたことは一度もありませんが、プラットフォームのサジェストを埋められると、不利益にはなりませんが間接的に不利にはなります。
だからと言って、私たちクリエイターのほとんどはAIとの秩序ある共存を望んでいます。クリーンかつ不利益がないのであれば、AI技術にアシストしてほしいくらいに思っています。だから基本的にAI規制に賛同すれば「反AI」なんてレッテルは貼られたくないですし、AI規制派をラッダイト呼ばわりする風潮などは心外です。
「AI画像生成・生成系AI問題まとめwiki」の中のトピックには、クリエイティブの各業界からの声明がまとめられています。(AI規制派のwikiでAI生成物を使ったソシャゲがガンガン広告を出してるのは皮肉ですが…)
それを要約すると、大体3つになります。
①生成AIの技術的発展は望ましいものであり、それを阻害する意図はない。
②AI学習そのものは否定しないが、学習元の権利者には許可、もしくは相応の対価が支払われるべきである。
③現在、著作権者の権益が脅かされる事態が起こっており、生成AI使用による権利侵害は容認できない。
つまり、ほぼ全ての業界団体は AIの発展を支持しており、しかしクリエイターの権利は保護されるべきであると一貫しています。(この要約にAIは使ってません(笑)
これはクリエイターが所属する団体の公式声明であり、頭の硬いおじいちゃんが勝手に決めていることではないのです。私もこの声明には概ね賛成です。この文章をきちんとお読み頂ければ、AI規制論の全てが「反AI」と一括りにするのはおかしいことに気づくはずです。
私たちが危惧しているのは、生成AIを使うユーザーのモラルが壊滅的なため、その脅威が脱法的に存在しているという事実についてです。
思い出してほしいのですが、「AI学習禁止」と提示し、「AIに私の絵を学習させないでください」と言った絵師に対して、LoRAを作成し生成画像を送りつけた匿名アカウントがいました。つまり、ルールがなければモラルも働かない人たちをどうするのか、という議論の延長にあるのです。
例えば、日本刀が現代で単純所持が禁止されているのは、振り回すやつがいるからです。誰も日本刀が意思を持って暴れ回るからとは思いません。人間が日本刀を振り回すと困るから刃物全般に規制があります。皆んな日本刀が悪だとは思ってませんし、日本刀がもっと鍛造されるなら世界的な産業になり得るのですが、それはないでしょう。「街でポン刀振り回す奴がいてかなわん!法で規制してくれ!」と訴える人に、「反日本刀」というレッテルを貼るような言説はさすがに納得できません。
つまり、私たちクリエイターはAIが憎いのではなく、AIを使用した無秩序な立ち回りが可能であることを問題視しているのです。
この部分を履き違えたり、論点をずらして批判する人がいますが、権利や権益をテーマに論理を交わさなくては話が噛み合わないのは当然です。そういった交通整理がされていない議論は、結局水掛け論にしかならず、不毛です。
「生成AI」は果たして安全なビジネスなのか?
さて、これから話を進めるためにAI開発における現状をおさらいしたいと思います。
ご存知の通り、OpenAIやStabilityAIを始め、AI開発企業は世界中の企業・団体から訴訟されまくってます。
その訴訟は現行法では通用しにくい内容ばかりです。なぜなら、そういう既存法と規制の網の目を潜って先端IT技術で時代を作ってきたのがテック企業だからです。門前払いされる訴状も多く、裁判も判決にはかなりの時間を要すると思います。
そこでテック企業側の主張を読んでみると、傾向は一緒です。「AI学習には著作権は適用されず、生成AIでのデータの利用はフェアユース(正当な利用)であるため、収益化に違法性はない」とし、フェアユースの成立プロセスについて専門的な説明を加えて論証しようとします。
私から言わせてみれば、「テクニカルな説明で陪審員を煙に巻くつもりだな」とは思ってしまうのですが、技術的に見れば一理はあるそうです。
問題は、「フェアユースならばAIの利用で既存の権利者にフリーライドして利益を得ることが許されるのか」という根本的な論点がどうなるかです。
この結論が出るには、残念ながらあと数年は要するでしょう。欧州のAIACT施工までの2年間、AI開発企業はのらりくらりかわしながら生成AIサービスが既成事実化するのを待っているのかもしれません。
テック企業がなぜ権利侵害のテーマに真っ向から反論しないのかを自分なりに考えたのですが、以下の条件があることに気づきました。
①学習データの無断利用と収益化が前提でなければ、世界中の知的財産をクローリングして利益を出すビジネスモデルが成立しえない。
②データセットを開示してしまうと、明らかな権利侵害や無許可での商業利用を指摘されかねないため、開示には非協力的である。
③AIによって権利を希釈し、ロンダリングした上で有耶無耶にすれば、著作権問題が超法規的に黙認されうる状況を作り出すことができる。
この3つの条件が鼎立するからこそ、生成AIの技術的台頭があり、逆にこの一つでも成り立たなければ、この巨大な塔は建造できなかったのではないでしょうか。
特に今HOTな問題となっている非合法の性的画像が画像生成AIのデータベース「LAION-5B」でかなりの数が発見されており、その運営による削除作業が進んでいます。
なぜ製品化する前にこのような穴を塞いでおかなかったのか、私は普通に疑問なのですがそれだけリリースを焦っていたということなのかもしれません。
LAION-5Bのデータベースを検索できるサービス、https://haveibeentrained.com/で、例えば「anime」と検索すると、見事に版権画像、2次創作作品がぼろぼろ出てきます。


あまりに露骨すぎて、スクショ貼った私が責任取らされかねません(笑)。しかもこのスクリーピングされたサイトは、おそらく海外の無断転載サイトです。
これはさすがに、と思いますがそれでもセーフなんでしょうか…?(あまり大きな声では言えませんが、この無断転載サイトを著作権違反で潰せばデータセット自体もモニョモニョ…)
ただ、この大元のデータベースから各AIが完全に参照しているわけではなさそうです。各AI開発企業は自社のデータセットを公開しません。
データセットはこれだけ色々な方面から開示しろと言われてるのですから、違法性がないならさっさとオープンにすれば良いはずですが、どのテック企業も一向に出したがりません。それは後ろめたい何かがあり、それを見せると即死ぬ心臓部であるから晒したら負け、みたいな感じなのかもしれません。かなりの憶測で恐縮です。
つまり、まともなポジションからビジネスを始めてしまうと、現在の生成AIビジネスがここまで一気に成長することはできず、また秩序のある開発プロセスを要する必要があるため、市場進出に出遅れる可能性があった、というのが正直なところなのではないでしょうか。
安全に画像生成AIを広めるには、バロック絵画などの著作権切れの作品から「レンブラントの新作を作れる」みたいな謳い文句から始めるべきだったのではないかと私は思うのですが、どうして最先端テイスト美少女イラストとかポルノとかそういう方面から始めてしまったのでしょうか…?
「生成AI」という商業ジャンル自体の評価が、こう言った画像生成系のやらかしに引っ張られ、イメージダウンしていることは否定できないでしょう。
それでも、GAFAMは多額な投資をして生成AI産業を盛り上げることに必死です。
穿った見方をしてしまえば、最近のGAFAMの業績は冴えず、ビッグテックの影響力に翳りが見え始めています。(それでも世界で見れば強すぎるくらいなのですが) AIブームの潮流に乗り、投資をかき集めるための起死回生策、競合他社とのチキンレースによって、コンプラ的に未熟な生成AIビジネスに賭けたのではないか、と私は勝手に推測しています。
しかし現状を鑑みると、あまりにやり方がグレーすぎるというか、拙速すぎます。このままでは機能的ナーフは避けられないように思います。それまでどうにか時間稼ぎをしたいのがAI開発推進派でしょう。そして、現状よりナーフされたAIは活用の機会を「現状」より失うという予測可能な事実もあります。だからこそ、そのダイレクトな衝撃はどうしても避けたいはずです。
生成AIが「キャズムの壁」を越える未来
「キャズムの壁」とは商品が一般的に流通し始める特異点を指すマーケティング理論です。
私は正直、素人なので専門的な断定はできません。しかし、現状で生成AIの言説に対して違和感を感じていることが3つあります。
①経済的合理性
②生成AI評価の信憑性
③開発企業の収益性
①は、よく「AIは仕事を奪うか」という論題で語られます。どんな議論があるにせよ、画像生成AIの導入で契約を切られたイラストレーターがすでに出ているのは事実であり、全ての人が失職するわけではないにせよ、最終的にAIが目指す汎用AIは人間の頭脳労働を代替しうるのは間違いなく、技術の進歩と共にその可能性は高まるはずです。
ここで産業革命と違うのは、機械の生産は機械の開発と製造と管理運用に大量の雇用や職種が発生したということです。しかし、生成AIに携わる人間はテック企業の従業員だけであり、開発側に回らる人以外は一方的に雇用の価値が減少していくはずです。この産業分野が多様な産業を生み出すことはほぼないでしょう。つまり、テック企業だけが一人勝ちする構図になってしまいます。
ただ、生成AIで儲けるはずのビッグテックすら大量のレイオフを実施し、今やシリコンバレーは雇い止めされた技術者がホームレスになり溢れかえっているそうです。いや、「 AIは労働から人類を解放する」ってそういう意味ではないと思いますが…。
②は、現在の生成AIブームを批判する記事に比べ、AI推進派の記事や意見ばかりがメディアに出回っていることへの違和感です。それはそうだという話かもしれませんが、「これから来るぞ」と世間が吹聴するものに乗っかるのがメディアという生き物であり、逆張りすると周りが生成AIを使い始めた時に恥をかきます。また広告収入などでテック企業経由で入ってくる収益もあり、スポンサーに楯突くわけにも行かないでしょう。穿った見方かもしれませんが、提灯記事を書くにはそれなりの経済的メリットがメディアにもあります。これに現在の検索アルゴリズム(腐り切ったGoogle検索機能)が加味して、バイアスのかかった意見ばかりを目にするのかもしれません。
③ さて、肝心の「生成AI開発企業は儲かっているのか?」という話ですが、日本語の経済解説はほとんど提灯記事です。
これらの記事の方が参考になります。
どうやら、うまくいっていないのは間違いないようです。なぜ2023年期の決算報告が出てこないのかはちょっとわかりませんでした。
ひとまず、かなりダメダメなGoogle検索の代替として使われ始めたChatGPTはさて置き、画像生成AIの生成物が市場でどう出回っているかを見たいと思います。
・YouTubeや非出版広告のサムネイル画像
・アダルトコンテンツ(同人DL作品、ポルノ動画、海外運営ソシャゲなど)の素材
・個人流通サイトでの作品としてのデータ取引
…ほぼ以上です。
逆に、この条件以外であのマスピ顔を見かけることがあるでしょうか?
なぜこれほど氾濫しているのに街中で見かけないかと言うと、AI生成物が一般市場で「商品」という認識がされていないからだと思います。
思い出してほしいのですが、海上保安庁がパンフレットに生成画像を使って炎上したことがありました。これは勝手に誰かが火をつけたとかではなく、AI生成物があまりに黒に近いグレーであることを人々が認識しているため、社会的な逆風に晒されただけです。
実際、私も稀にあるクライアントとの取引ではAI生成物が忌避されている雰囲気を感じますし、こちらも必ず確認されます。それゆえにまともな企業の契約では、見かけることはまずありません。
信用ある企業が使えば炎上する確率が限りなく高い、それだけ「グレーすぎて手が出せない代物」をあえてコストカット名目で使うメリットがないのでしょう。厳しい話ですが、イラストレーターのイラスト一枚の単価は、大概コンビニバイトのほうがマシに思えるレベルです。(売れまくっている人の話は別です)それだけ世の中に絵で食っていきたい人がたくさんいて、そのためにダンピングせざるを得ない業界でもあります。そんな中で、あえて生成画像を使うメリットはたかが知れてるような気がします。
総論として、技術のコンプライアンスの低さからBtoBの販路拡大が閉ざされている現状を変えるには、クリーンなシステムであることを証明する必要がありますが、そこをオープンにすることで技術的なナーフは避けられず、それによってビジネスの衰退もありえるというのが画像生成ビジネスの現状なのではないでしょうか。つまり、収益を上げるためならばクリーン化して企業に使ってもらうべきだが、クリーンにすれば学習元を削らざるを得ずコンプラを遵守すれば機能は削減せざるをえず、それゆえ逆説的に現在のシェアに影響を及ぼすジレンマがある、と私は思います。
ChatGPTはすでにアプリに組み込まれ、その便利さは多くの人に共有されています。画像生成AIともにテキスト生成系も権利的な問題を抱えていますが、画像生成AIに関しては利用するメリットを市場経済には今一説得しきれていないように思います。というか、全てをなし崩しにする以外に画像生成系は現状維持すら難しい状況になりつつあるように見えます。
私はテキスト系生成AIはよほどの規制が入らない限り、キャズムの壁は越えそうだなと思っています。しかし画像生成系は根源的にナーフの可能性が高く、しかも市場から生理的に嫌われているので現状維持はかなり苦しいのではないかと思います。少なくとも、クリーンなシステムでなければ生き残る可能性はほぼゼロでしょう。
プロが生成AIを使わない方が望ましい理由
ここまで読んでくださった皆さま。ありがとうございます。でも謝らなくてはいけません。
ここからが本題です(汗)
生成AIの未来は、正直なところ世界でわかる人はほとんどいないでしょう。
アメリカの司法省とGoogleの対立、欧州のAIACTとビッグテックに対するDSAの適用、ニューヨークタイムスとOpenAIの裁判(その他の数多くの裁判)、ビッグテックの揃い踏みの減収、その全てが不確定要素であり、それ一つで趨勢がガラッと変わるような争点ばかりです。
私のような素人が予測しうるものではありません。なし崩し的に冒頭の世界になることもありますが、Winnyのように規制されて地下に沈む可能性もあります。
WinnyなどのP2P技術は、一時期デジタル流通革命と謳われ、アスキー()とかがムックを出しまくってました。しかしゲームやDVDなどの割れデータが大量に流通し、ウイルスに感染した個人データが流出して祭りになったり、あの時代もかなり異常でした。しかしWinny開発者の逮捕から一気に風向きは変わり、P2Pは著しく形を変えるか、地下に潜ってダークウェブになりました。
「永遠だと思ってた」権威の没落が、ここ数年で立て続けに起こっています。芸能界を支配していたジャニーズ事務所、いずれ世界の覇権を握ると言われた中国、今後燃料エンジンに代替すると言われたEV、新たな市場世界を作ると言われたメタバース、誰もが絶対視していた繁栄が急変する出来事が突然起こります。
人々の期待値と現実が比例しないのは不思議なことですが、これが現実であり、諸行無常なのだと思います。
ここでする話は、生成AIがどうなるかではなく、「クリエイターが生成AIと共存する未来はどういう形なのか」を巡る仮定の話です。
「クリエイターはAIを使い共存する」という未来があるかと考えたら、私はYESだと思います。今後、デジタル制作ツールの背後でAIが動くのはほぼ間違いないでしょう。AIはプログラミングの上位互換であり、その性能の高さをスポイルする理由がないように思います。
しかし、全てのクリエイターがAI生成物を使うようになるかと言えば、私はNOだと思います。AI生成物を作品に組み込むということは、コラージュ職人になるのと同義語です。自分にそれなりの技術や知識があるなら、そこまでプロンプトに頼るメリットはあまりありません。
実際、私も画像生成をしたことがありますが、完成品を本当に自分の思い通りにするなら、自分で描いた方が確実に早いです。自分の作風モデルを完全に熟知したAIが私の今のテイストを完全再現してくれるなら話は別ですが、その環境作りのために私はどれだけの絵を描かないといけないのでしょうか。
仮にクリエイターが出力した素材を切り貼りするのが仕事になるなら、最終的に工程もAIで代替できることにはならないでしょうか。そうなれば、最初からプロントで適当に出力したものを提示するAIクリエイターと全く同じ条件になります。
実際のところ、アイデアだけであればこれまで消費に徹してきた人の頭の中にもあります。プロンプト生成という、プロでもアマでも同じ技術水準で競うなら、おそらく決定的な優劣はほとんどつかないでしょう。
ですから、ロジカルに考えて生成AIに対する依存度が高いほど、プロとしての存在証明が難しくなります。それは生成AIに対するアレルギーがなかったとしても、どうしても市場原理でそうなってしまうように思います。
仮にLAIONが完全にクリーンなライブラリとなり、権利問題もクリアした上で画像生成AIが浸透し、AIを使うクリエイターが増えるとしたら、市場に蔓延した生成AIに対する忌避感は今より薄れるはずです。
しかし、その環境は技術を磨いてきたクリエイターにどういう影響を及ぼすでしょうか。
私はそれを考えるのに、遺伝子組み替えと食品添加物が参考になると思います。
なぜ生成AIと結びつけるのか疑問に思われるでしょうが、構成物に対するアレルギー感情では同類のものと考えられます。現に、魔女狩りに近い因縁があるのは大して変わりません。
「アートも心の栄養である」と言えば納得する方もおられるでしょうか。
現在でも遺伝子改変で新しい動物、植物の品種を生み出すことは可能です。しかし生命倫理や遺伝子組み替えによる生物学的リスクがあり、今では加工成分の原材料に使われているくらいで、それすら懐疑的な議論があります。
食品添加物に至っては、人間の味覚からすると食品添加物が多ければ多いほど美味しく感じます。しかし健康面での影響から、食品内容物への添加物の記載は義務付けられています。
私は少なくとも、AI生成物は表示が義務付けられないまでも、これらの加工技術の一端として人々に認知されていくのではないかと思います。技術的にクリーンかどうかは問わず、です。
特に根拠があるわけではないですが、ある作品を購入する時に「生成AIを一部使っています」と言われたら、99%ポン出しで10ピクセルくらい動かしただけ、というのは腑に落ちません。せめて全体の何%くらいがAI製かくらいは知りたいです。それが厳密にわかるシステムはおそらく不可能です。その誤魔化しの技術はいつだってイタチごっこだからです。
従って、販売作品や版権にAI生成物を利用するにしても、「AI成分はない方が望ましい」という判断になります。
それを押し切って「手書きです!」というのは景品表示法違反です。ですから、いかにAIの手が入っていない作品であるかを証明できれば、相対的に価値は上がるはずです。
高級料理に例えれば、もし贅沢に美味しいものが食べたいと思えば、天然の伊勢海老がゴロッと入ったお吸い物とか、高級食材の素材の味を活かした料理を食べたいはずです。
しかしそのお店に入って、980円のロブスターに化学調味料を大量にぶっかけたものが出てきたらどう思うでしょうか。そのお店は少なくとも高級料理店ではやってはいけないはずです。
同じような理由で、企業が案件をクリエイターに発注する時、高額な報酬を出すのであれば、ちゃんとしたプロを選択するでしょう。一ファンだって、どこでAIに頼っているかわからないクリエイターより、不器用に意地を張るような作家を応援したいはずです。
しかし、AIの使用は何らかの形でデジタルの作業環境には関わってくることは間違いありません。少なくとも、アプリの制御に使われているAIか生成AIかの線引きは多少あるでしょうが、時間と共に有名無実化していく可能性があります。
では、その線引きと棲み分けをどうすればいいのでしょうか。
(長くなりましたので、次節でまとめたいと思います。すみません10,000文字越えそうです。長くなり申し訳ありません。)
クリエイターはAI時代をどう生きるべきか
前節で「AIを使わないクリエイターは相対的に価値が高くなる」という話をしました。
これは条件としてだけでなく、例えば「AI生成物と同程度のクオリティを実現するプロ」がいたら、比較してそれでもAIが勝つのでしょうか?
結局のところ、「人間のハンドメイド」という強みは、ミケランジェロ以前の時代から今後も不変のままだと思います。
「手作りの比類なき技術」はこれからも芸術の本質を捻じ曲げることはできないでしょう。AIを使ってすごいものを作るのは当然どころか前提であり、人間が積み上げたものですごいものを作れば、それを誰もが当たり前とは言わないはずです。
今後、AI時代のクリエイターは、四種類に分かれると思います。
①AI生成物をポン出しするだけの人
②AI生成物をアレンジして作品を構成する人
③機能や素材の一部で生成AIを使用する人
④完全に自分の技術力でやっていく人
おそらく、デジタル作業環境でのAIの使用は今後避けることは不可能です。あえて「AI技術を使わないアプリで作成しています」と宣言するのもナンセンスです。
多かれ少なかれ、生成AIに対する忌避感が薄れるほどAIの使用は一般化するのは時間の問題かもしれません。そこで重要なのは「AIを絶対に使わない」と意地を張ることではありません。
AIを使っているかいないかは外部検証に任せ、クリエイター本人がどれだけ自分の表現を自分の手で追求するか(AI技術に依存しないか)、またその追求が証明できる形で作品に反映させることだと思うのです。
それが可能なのは、完成作品だけをポンと見せるだけでなく、プロセスエコノミーをクリエイターが確立し、過程やストーリーを見せることで信用を重ねていくしかありません。デジタルは無限に誤魔化しの効く技術です。ですから、手の内を見せデータを分析にかけられても埃の出ないやり方をしていくしかないと思います。
(余談ですが、デジタルの絵師がここまで逆風に晒されるなら、油彩とかペン画など一点モノの絵画の市場の方が道がある可能性すらあります。だって、AIより絵の上手いイラストレーターがAI製を疑われるって、そんな理不尽さを抱えながら耐える必要があるのでしょうか…?)
あるWEBマーケティングのカンファレンスで、AI時代のSNSは「人間性の発信が求められる」というコンセンサスだったそうです。私はそうだろうな、と思いました。ある程度均質な情報はChat GPTを駆使すれば生み出せますが、その情報に付加価値をつけるのは「個性」しかありません。
しかし、個性や人間性は二次元のキャラクターのように設定で何とかできるものではなく、経歴や実在の人物としての裏付けがどうしても必要です。
だから、自分のセンスと腕と意志で作り続けていることを証明し、個性を確立したクリエイターは自らの信用や実績を武器に活動を続けられるはずです。
ここまで読んでいただけたらお分かりでしょうが、これはAI生成技術を使わないと宣言するクリエイターとは≒の関係です。いくらハンドメイドにこだわっても、顧客にメリットを提示できなければ絵に描いた餅になってしまいます。「AIを使っていないように見せる」ことが鍵なのではなく、「AIを仮に使っても作家性を固持できる」ということの方が重要であるように思います。
まとめると、
①AI技術のカンストが起きても、人間のハンドメイドの価値そのものは毀損されないが、デジタルの活動でその証明をすることは難しい。
②できる限り自分の表現を行う姿を表明することで、AI技術を使用したアプリを使用しても作家性の提示は可能である。これにより相対的にAIクリエイターよりも市場価値が高くなる。
③しかしそれには一定の技術力、信用と実績、一人格としての承認が必要である。
以上が私の考える「AI時代のクリエイターの生存戦略」です。
なんか回りくどいですね。本音を言うと「 テック企業め余計なことしやがって…」とは思いますが、19世紀の裁断職人も茅葺き職人も同じことを思ったわけで、今したり顔でAI推進してる方々も、いつAIやアンドロイドにお役御免にされないとは言い切れません。
まあ根も葉もないことを言えば、人間という存在自体が、完全上位互換のアンドロイドが安価で流通するなら、一人残らずこの世の経済には必要ないわけで…。うっ頭が。
これからAI時代が来るとしたら、それは人間がAI以下のことをしていてはいけない時代だということです。AIによって人類は労働から解放されるどころか、より高度な競争に晒されることになるような気がします。
昭和初期には暑い日は午前中で仕事を切り上げる「半ドン」という慣習がありましたが、機械化が進みPCが普及し、全自動化が進んでもどんどん労働は高度に、長時間になっていきます。私はAIが人間を競争社会から解放するなど夢物語であると思います。
しかしAIが高クオリティの均質的な仕事をする傍ら、「人間らしさ」が差別化の鍵となるのは間違いなく、だからこそ逆説的にヒューマニズムの時代が到来するかもしれません。
ユヴァル・ノア・ハラリの著書「サピエンス全史」は、「文明の発展は幸福を保証しない」という真実を浮き彫りにしています。ではどうして人間が幸福を手にするかというと、人間性、あるいは生物としての肯定感を取り戻す瞬間であると私は思います。
だからこそこの時代、既存の権威が倒れ新しい秩序が求められる瞬間、AIが人類すらも駆逐しかねない不安の中で、人間にとって何が大切なのかを再確認するには、AIも反面教師の一つにすぎないのかもしれません。
そこで人生の教師をAIに求めず、自分の頭でどうあるべきかを考える時、初めてAIは人間の道具になりうるのではないでしょうか。
そして、多くの人々に思想や感情を伝えられるクリエイターは、最も独立した人格をもつべきであると私は思います。
クリエイターは人々の感情や思想に影響する作品を作ることが可能です。それゆえに作品を通して人を癒したり元気づけたりすることができます。そういう人たちこそ、AIに代替されてはいけないでしょうし、安易に作家性を捨てるべきではないと私は思います。
今の子供たちが「将来は小説家になりたい、映画監督になりたい、イラストレーターになりたい」と目を輝かせる時、「いや、それはAIがやるから別のことを考えなさい」と大人たちが言わざるをえない時代が来ないよう、私たちが今諦めないのも大切なことだと思います。
最後までお読み下さった皆さま、お疲れ様でした。もう終わりです。ここまでおつきあい下さり、ありがとうございました。
この後は編集後記のようなものです。すみません、もう読まなくていいです…。
おまけ(読まなくて結構です!)
私がAI生成画像を初めて見た時、冷や汗が止まらなかったのを覚えています。
「終わったな…」と正直思いました。少なくとも、今後女の子のイラストでお金をもらうことはないんだろうな、と思いました。
そして「絵師もAIを使うべきである」というナラティブをまともに信じ込み、1週間以上業務にブリッジできないか模索しました。
しかし、自分が使ってみてはっきり思ったのは、「プロンプト打ちが楽しくなさすぎるし、生成にも思ったより時間もかかるし、プロンプト打ちのリテイクも面倒臭い」と、そして「この時間で簡単な絵は描けてしまうぞ…」という根も葉もない結論でした。
今ならもうちょっと当時より改良はされてるんでしょうが、それでもちょっと絵を描ける人なら画像生成AIに依存するメリットがほぼありません。むしろ、AIを使ったとバレたらブランドに傷がついてしまう世の中です。私はプロとして技術を磨いてきた身、いくら楽で利確しようがその意地を曲げることはできません。
しかし、今後私が「AIを一切使いません」と断言はしません。例えばクリップスタジオに搭載されたAI補助機能が優れていたらたぶん使います。それを使った作品を世に出して「AIを使っていません」とは言えないでしょう。
知らずのうちに機能のシステムに実装されているかもしれませんし、いくら化学調味料が嫌いとは言え「アミノ酸を料理に使いません」と言えないのと同義です。
「お前はAI規制派なのにAIを使うな」という指摘は的外れです。先に述べたように、一般社会に認められるクリーンなAI技術なら、私たちクリエイターは喜んで共存の道を選ぶでしょう。
あれだけブラックボックスとしか思えない代物は、さすがにコンプラ的に厳しいです。
そもそも画像生成AIが高性能なだけならここまで批判はされないはずです。グレーな技術を限りなく黒に近いやり方で振り回されるのが皆んな迷惑なだけです。
私がこの記事を書いたのは、同じクリエイターで胸を痛めたり病んでいる人が現在進行形でたくさんいることを肌で感じたからです。
生成AIを批判すると、なんかとんでもない火の玉が飛んでくるのが、悲しいかな現実です。
だからと言って黙って言わせておくのも違います。だから多少火の粉を浴びてでも、きちんと言いたいことは言うべきだと思いました。
私はSNSは一切やってないので、正直今の界隈の雰囲気はわかりません。タイミング的にどうだろうという気持ちもないわけではないですが、現状胸を痛めている人がいる以上、何かできないだろうかと思いました。
私も二次創作同人をやっていた時があり、その頃接していた才能ある若い絵師たちが今どんな気持ちで絵を描いているのか、想像したりします。
ただ一つ言えることは、絵師のメンタルは「画像生成AI以前と以後」で全く違うだろうなということです。
私も一枚絵のイラストを描くのは好きですし、美少女を描くのも好きです。だからこそ余計に気持ちがわかります。
夢を持って、学校を出たらプロになると思っていた若い絵師たちの心情を思うととてもやるせないです。
だからこそ、私の意見はちゃんと伝えようと思いました。
こんな長分、誰が読むのかわかりませんが、ここで示したことを根拠に私は正々堂々とやっていくつもりです。その過程で損することなどいくらでもあるでしょうが、私たちがなぜ芸術やエンターテイメントを楽しむかと言えば、そこにヒューマニズムへの共感があるからです。
ヒューマニズムなくして芸術などあり得ません。
利益を出す、バズるのが目的なら、それは別にアートである必要はありません。ぶっちゃけパチンコでも当たる時は当たります。
だからこそ、芸事の世界に飛び込んだ人間なら、簡単に自分のやり方を曲げてはいけないと思います。
今、あらゆる方面から絵師に対する逆風は強いです。でも、しんどいから今筆を置いてしまうことは未来の可能性をゼロにするだけです。せめてしがみつく気持ちがあれば、1%であろうと未来は切り拓けるはずです。
だからこそ、同志として「諦めるな」と言いたかったのです。ぶっちゃけ、絵を描く人はみんなライバルですし、ライバルがいないに越したことはありません。でも、全員が脱落するレースなんてのは明らかにおかしいのです。
だからこそ、ここで屈する気持ちにはなれませんし、理不尽さと戦う立場に置かれている全ての人は、私にとっては同類であり仲間です。
こういう時だからこそ、手を取り合うことは恥ずかしいことではありません。
本当に、最後の最後に言っておきたいことがあります。クリエイターはヒューマニズムの体現者であるからこそ、人々にものを伝える資格があると私は思います。
収益や評価を求めるなら、そのクリエイター自身の思想もAIに代替されうるでしょう。「人間はなぜ表現せざるを得ないのか?」ということを、今は突き詰めて問われている時代なのかもしれません。
私は己の思想を信じて、これからもやっていきす。
***
あと、手前味噌で恐縮ですが「 AIの使い道がないくらい頭おかしい漫画」を描いてます。よろしければ応援してくださると幸いです。
ここまでお付き合い頂き、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
