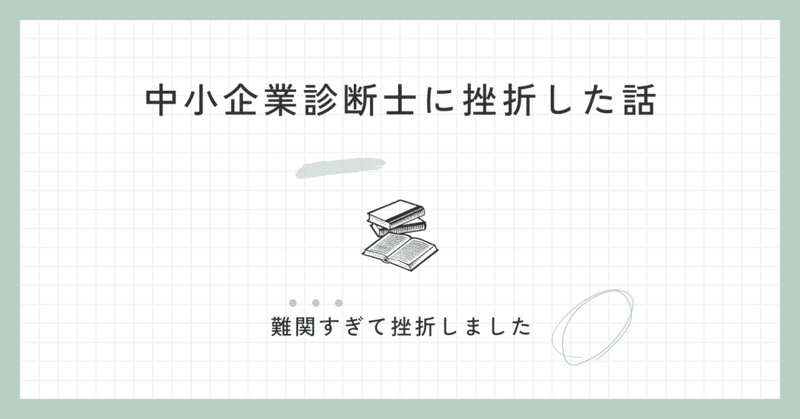
中小企業診断士に挫折した話
はじめに
私は今まで、IT系のキャリアを築いており、過去にIPA主催の国家試験である、基本情報処理技術者試験、応用情報処理技術者試験などに合格をしてきました。
今回は普段のIT資格とは異なりますが、中小企業診断士について語りたいと考えてます!
中小企業診断士について
取得を志した経緯、勉強履歴について
<取得を志した経緯>
①独立の可能性が見出せそうと感じたため。
現状の会社員としての仕事にはもちろん満足してますが、所属会社の肩書きが無くなったら自分は何ができるのだろう?と漠然な不安を感じた瞬間がありました。
独立を想定して、働きながら取得できる資格があるか調べたところ、中小企業診断士が良いと考え、学習を決意しました。
大学では管理工学を専攻しており、試験範囲との重複が多かったため、今までの学びを活かしながら、効率よく知識のインプットができるのでは?と思い、独立向けの他の資格(例えば社労士や行政書士)では無く、この資格を選びました。
②業務に活かせそうと考えたため。
中小企業診断士は経営で使う知識を幅広く学べるイメージがありました。
例えば、当試験は1次試験だけでも次の7科目を学ぶことになります。
・企業経営理論
・財務会計
・運営管理
・経済学、経済政策
・経営情報システム
・経営法務
・中小企業経営・政策
私の仕事では、多種多様な業界のITシステムに触れる機会があります。ITシステムの利活用は業務と密接に関わっている事から、会社の業務プロセスやビジネス知識が深まれば、新規クライアントを担当する場合も、効率よく顧客のIT環境をキャッチアップできるのではないかと考えました。中小企業診断士で学べる知識はその下地になりうるのではないかと期待していました。
<勉強履歴>
学習環境
2022年度、社会人6年目(転職3年目)の11月のタイミングで学習を開始しました。
また、独学ではなく、「スタディング」という、通信講座を契約し、盤石な体制で学習を進めました。当時は考えが甘く、翌年2023年の試験で完全合格を目標としていました。
予備知識があることから、自分ならいけると、軽い気持ちで学習を始めました。
学習期間
結果的に4ヶ月程度で学習を辞めてしまいました。
<その原因>
①1次試験の難易度が想定以上に高かった。
②理想と現実のギャップに悩まされた。
①について
学習して初めて気づきましたが、中小企業診断士の1次試験の難易度はそこそこ高いと感じました。
1次はマーク式試験となります。過去に受けてきたIPAの情報処理技術者試験もマーク式+記述の形式となりますが、IPAのマーク式は大半が過去問の使い回しであり、過去問を回しているだけでも確実に点数が安定します。
IPAの試験傾向から他の国家試験のマーク式も過去問の流用で、簡単なものだと誤認していまた。笑
一方中小企業診断士の1次試験は過去問と同類の問題も出ますが、毎年オリジナル問題も多く、傾向が掴みづらいと感じました。
頻出のテーマの絞り込みも可能ですが、それでも7科目の学習となるので、学習量も膨大なものとなります。
私は4ヶ月勉強しましたが、1次試験の、どの科目も40点〜60点の幅で安定がせず、勉強した成果を肌で感じることができずに苦しみました。
果たしてこのまま勉強を継続しても点数が安定するのか?自信を持てませんでした。
②について
【理想】
2023年度に完全合格をする事を目指していました。
【現実】
4ヶ月本気で勉強したのに、1次試験の点数すら安定しませんでした。
今まで学習した資格は、比較的短期間で、受験レベルに達する事ができていた事から、本当にこの試験に合格できるのか?と疑問に思うようになりました。さらに診断士は2次が難関と言われていることから、合格までの道のりがとんでもなく遠く感じました。
1次で苦戦するレベルなので、そう感じるのも無理は無いですね。。
この理想と現実のギャップにより、一気に学習意欲が無くなってしまいました。さらにSNSを見ると1次試験に2ヶ月で合格しました!等といった、優秀な他人の実績を目にしてしまう機会もあり、その他人と比べてしまうことで更に理想と現実のギャップが肥大化してしまいました。
この試験について思う事
①中小企業診断士は難関試験である。
②資格勉強を通して得られる知識は役に立つ。
③中長期的目線で、合格目標を立てるべき。
①について
上記の通り、学習範囲の広さ+試験問題の難しさから間違いなく中小企業診断士は難関試験と言えます。
学習時間の目安が1000〜1500時間とされていることから、働きながらの取得を目指す場合、相当な覚悟が必要になります。
②について
中小企業診断士の1次試験では、分野の異なる7科目を学び、2次試験では、記述試験の形式で事例企業に対する経営の助言を行います。
この事から、幅広い知識の引き出しを作ることができ、かつその知識を使い、企業の課題を改善する、実践力を付けることができる試験と感じました。
私は1次試験で挫折してしまいましたが、知識の引き出しを少し増やすことができた実感はあり、また知識をインプットする段階では、とても楽しく勉強をできていました。
③について
社会人が受験する事を想定すると、働きながら1000〜1500時間を捻出して、勉強をする事が必要になります。
その為、1年で合格しようとは思わず、中長期的に2〜3年かけて取得する方が現実的です。
予備知識の有無で勉強時間に差異は生じますが、予備知識がある人こそ、自身を過信せずに現実的な計画を立てる事が重要と考えます。
最後に
・中小企業診断士の失敗体験記に該当する記事は少ないと考え、本記事の執筆に至りました。他にも色々な資格の記事を書いているので、もしお時間があればご覧いただけると嬉しいです。
・私は挫折してしまいましたが、今でも中小企業診断士は魅力的と考えていますし、いつかは再チャレンジしたいと考えています。その際には2〜3年の学習計画を立て、中長期的な目線でチャレンジしたいと思ってます!
・長くなりましたが、最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
