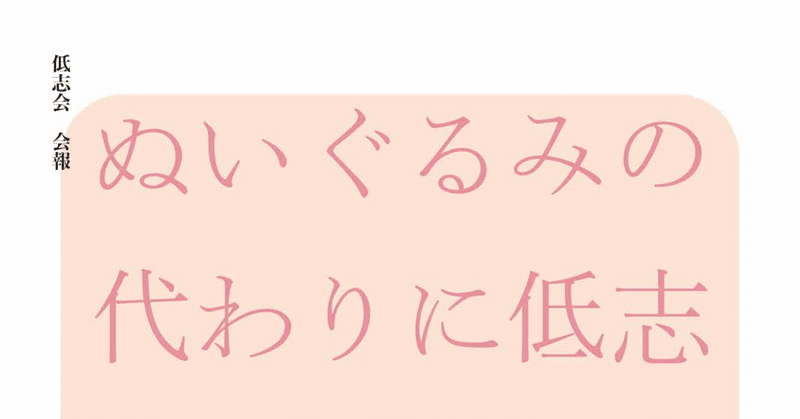
中年の思想──「低志会会報 第2号」感想
サークル「低志会」の会報第2号(特集:ファンシーキャラクター、正式なタイトル:ぬいぐるみの代わりに低志会の本を抱いて媚を売る、つまりそれが祈り Vol.2)を通販で入手して読んだので、感想を書いておく(書いている途中で話がまとまらなくなってしまったが、まあ出さないよりは出しておいた方がいいので更新しておく)。ツイッターで相互フォローの方もいるが、面識はないため敬称は略しておく。
低志会は、正式名称を「志が低いアニメ愛好会」という。オガワデザイン、noirse、安原まひろ、てらまっとの中年男性(?) 4人で構成されるユニット的な集まりで、ツイッターでよくスペースを開き、アニメの話をしている。主な活動はアニメ語りと会報発行という小規模なものだが、会員はそれぞれの職業や批評同人誌などで活躍していて、会の存在が日本経済新聞のコラム欄で取り上げられたこともあるという。
私は会員の一人が運営するサイト「週末批評」を経由して存在を知り、スペースを聴くようになった。そこでのアニメ語り自体はゆるい雰囲気のもとで行われているが、単にゆるいだけではなく、人生の蓄積が言葉の節々に出てくる。とりあげる対象は主に現行アニメだが、たいてい途中で脱線し、押井守や『けいおん!』を使ったたとえ話が頻出する。この「これは昔でいうアレだよな」という中年特有の語り口も、肩の力が抜けていて、聴いていて癒される。個人的な聴き心地としては、ラップグループ・スチャダラパーの近年のアルバムのそれに近い。
◆2項対立を全うする文章
そんなサークルなので、「ファンシーキャラクター」をテーマとした今回の会報は、ほとんど彼らの自己紹介めいたモノになっている。
オガワデザイン「リラックマの、もう死なないもののこと」は、リラックマに代表される単純な設定のファンシーキャラクターを、複雑で生々しい物語の登場人物と比較して「すでに死んでいる」「もう死なない」存在として語る。noirse「多摩とカニエの旅」は、サンリオピューロランドに、多摩ニュータウンのもつチープで人工的な雰囲気を重ね、そこに息苦しい現実からの解放をみる。安原まひろ「ゆるキャラ・イズ・デッド」は、ひこニャンや『あずまんが大王』に90年代サブカルのエッセンスとしての〝ゆるさ〟を見出し、その後継者たちから同要素が失われてしまったことを嘆く。
3つの短いエッセイに共通するのは、ゆるキャラに現実からの解放を見出していること、そして、「現実/ゆるキャラ」という2項対立を奇をてらわずに全うしていることだ。若者が評論的な文章を書くと、どうしても2項対立をひっくり返したり、注を大量に入れたりと工夫を凝らしがちになる。これは経験の浅い自分の「言葉の軽さ」への嫌悪・不信感に由来するもので、なかなか抗えない。一方、3人の記事には人生(祖母の死、mixiでの黒歴史、多摩センター)が自然に挿入され、言葉にも重みが加わる。
この重さはどこから来るのか。中年男性が「ゆるさ」を発揮するためには、その背後にそれなりに安定した職業が不可欠であり、実態は不明だが、各会員も「ゆるくない」労働や生活を営みながらこれらの文章を書いていると思われる。身体は衰え、時間はなく、場合によっては支えるべき家族もいる。志の低いアニメなんかみている場合ではない。そんな厳しい現実のなかで、それでも「ゆるさ」や志の低さを求めてしまう。語り口をこえて伝わってくるこの矛盾、異常さこそが重みとなり、シンプルながら味わいある文章を可能にしているのかもしれない(単に文章の上手い人が軽めのエッセイを書いたら自然とこうなるだけなのかもしれない)。
◆もてあました身体をどう扱うか
残る1人、てらまっとの「もう一つの『おにまい』(2)──オオサンショウウオと成熟の問題」は他と比べると少し複雑な内容で、とても面白かったので、自分なりに噛み砕いた要約メモを残しておく。
この記事は、「身体だけが先に成熟してしまう」ことを人間にとっての問題として論じたものだ。普通に考えれば、成熟した身体にはセルフケアやパートナー、それらを得るための安定した職業が必要であり、それらを得ることが〝成熟〟とされる。だが、現実的には全員が〝成熟〟することは不可能なので、少なくない人々は「成熟に失敗した者」として後半生を過ごしていかなければならない。
評論家・大塚英志はこういう人々──要するに昔風のオタク──に、「ぬいぐるみ(=幼い頃から触れているサブカルチャー)を抱きながら成熟をやり過ごす」ことを説き、成熟の問題に向き合わないことをすすめた。これは会報タイトルの元にもなっている言葉だが、現代ではもう魅力的に響かない。みな、現にぬいぐるみを抱えながら生きているからだ。大塚はオタクが連合赤軍やオウム真理教のように暴走しないための処方箋としてサブカルチャーを提示しているのだが、私たちはサブカルチャーへの依存が、また別の方向の暴走につながった事例に囲まれて生きている。今や問題は、成熟をやり過ごすか否かではなく、成熟を〝いかに〟やり過ごすか、成熟した身体をいかに自分で慰めるか、ということに移行しているのだ。
『おにまい』は、この現代的な問題に対する一つの回答となっている(らしい)。そのオープニングでは、この成熟の困難がパロディ化され、問題そのものが無効化される。逆に本編では、まひろは妹・みはりに女性の身体を強制的に与えられ、身だしなみや生理への対応を通じて、自分の成熟した身体への寄り添い方(セルフケア)を学んでいく。
この本編とオープニングの違いが、現実の視聴体験にも対応する。本編は、自分の身体を自分でケアする「丁寧な生活」を美しく描く。もちろん、現実の視聴者に都合のいい妹は存在しないし、ドギツい萌えアニメである本作で「丁寧な生活」を描くことはそれ自体ギャグやパロディのようなものなので、視聴者がそれを真面目に受け取ることはない。だが、冗談めかしながら、不真面目には受け取ることはできるかもしれない。そもそも、真面目な社会から不適合の烙印を押された人々にとって、真面目なメッセージを受け取ることは苦痛でしかないのだから、結局、社会を丸ごと否定するのでも、リアルな成長を描いて勝者の立場から倫理を押し付けるのでもない、フィクションを通した〝半分真面目な〟成熟の受容こそが、「成熟に失敗した者」たちに残された「最良の慰め」となるのだ。
◆中途半端な思想、中年の思想
この文章は大まかに要約すれば、「いかに成熟をやり過ごすか」という巨大な問題に対して、「良質な萌えアニメを見るべき」というアドバイスを与えるものになっている。「志が低いアニメ愛好会」のメンバーが書いているのだから当然の回答なのだが、いかにも中途半端(または不真面目)で、真面目な人たちからは嫌悪の対象となりそうな内容でもある。
とはいえ、そもそも中年は、存在そのものが中途半端で不真面目だ。ライフステージの節目となるこの年齢で、ものの考え方がガラリと変わってしまう人も少なくない。たとえば、記事のテーマである「成熟論」の祖として有名な江藤淳は、40歳前後を境にして、リベラルな近代主義者から右派を代表する論客へと自らの立場を変えたことで知られる。代表作『成熟と喪失』は、この転向の真っ最中である35歳のときに書かれたものだが、これまた思想的な意味でも左右の中間に立つ不確かなものだった。
それは、どのような意味で不確かなのか。30代前半までの江藤が並走していた近代主義者たち(たとえば丸山眞男)は、世界を偶然的なもの、変更可能なものとしてみることが、個人と社会の変革につながると考えていた。これは、平たく言えば「精神的に若くあれ」ということの言い換えだ。一方、晩年の江藤淳に似た保守的なひとびとは、世界の現実を必然として受け入れ、変更不可能性を強調する「老いの思想」の持ち主だ。
若くあることを求める思想と、老いを受け入れよと迫る保守思想。江藤が批評の世界に定着させた「成熟」は、この二つの思想が入り混じった問題設定だ。それは、個人が変化することの価値を説いている点では若い。だが、江藤は男性の「成熟」を、「母の喪失」という必然を受けいれ、家長として振る舞うこととして定義していて、これは明らかに老いの肯定となっている。世の中のどうしようもなさを、苦渋を舐めながら受け入れる作業こそが、(この辺りで話がまとまらなくなり、就寝)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
