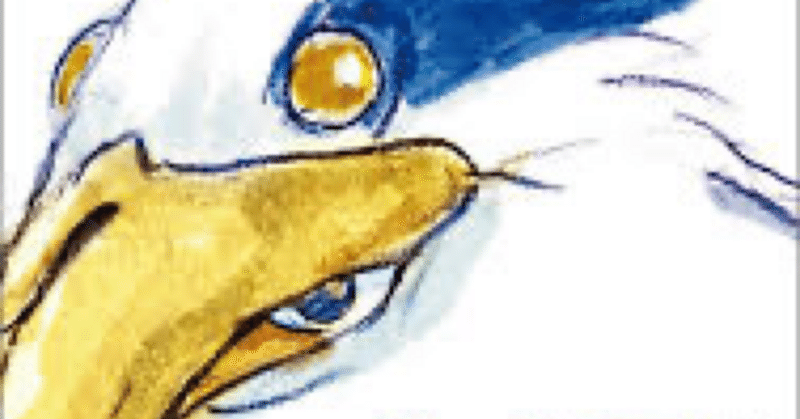
『君たちはどう生きるか』メモ
◆義母と実母のWヒロイン体
一見して最も異常なのは、度を越した近親相姦スレスレのマザコン的態度だ。
前半の義母との交流は大変エロチックに描かれており、義母から主人公、主人公から義母とお互いに意味ありげな視線を注ぎあっていた。とくに、父と義母のキスを隠れ見るシーンなどはそういうタイプのポルノの導入にしか見えない(私だけかもしれないが…)。
さらに後半では若き日の実母が実質的なヒロインとして登場し、実母と共に義母を取り戻そうと奮闘することになる。つまりこの作品では、いわば義母と実母がWヒロインの役割を担っているのだ。インタビューによると本作は「ずっと自分が避けてきたこと、自分のことをやるしかない」というコンセプトで作られたという。主人公である眞人少年のマザコンぶりは、おそらく宮崎監督自身のそれを投影したものなのだろう。
◆ファンタジー的想像力の敗北
ヒロインが母親しかいないということは、知らない女性と恋に落ちたり、外の世界に冒険する力や気持ちが失われていることに繋がっている。実際、宮崎作品としてはファンタジー世界に魅力がなさすぎる点、同じ構造を持つ『千と千尋の神隠し』と比べても明らかなパワーダウンが見られる。
逆に冒頭の屋敷を描いたシーンはとても魅力的で、ライターの前田久は「この一連の過程で描かれる、戦前の日本の風景と和装の人々の所作が、実に美しい。こうした描写の積み重ねだけで、一本の映画を作り上げてほしいと思わず感じるほどだ」と書いている(私も同感だ)。
しかし、実際に航空機会社社長の息子であった宮崎監督にとっては、屋敷の美しさはいわば「現実の美しさ」であると考えた方がいい。異世界より現実世界である屋敷の方が美しいということは、あれほど強力だった宮崎駿のファンタジー的想像力が、自身の幼い頃の思い出に負けてしまっているということなのだ。さらに言えば、この力関係によって世界間の移動に迫力が消えていて、これが異世界に行って帰ってくるタイプの映画としては致命的な欠陥となっているようにも思える。
◆自分の衰えをテーマにするメタフィクション
しかし、これを単なる宮崎監督の衰えとは見ない人もいる。本作の中で宮崎監督にもっとも立場が近いのは異世界の創造主である大叔父だが、彼を現在の宮崎監督のメタファーとして見ると、この作品は一種のメタフィクションとして捉えることができる。崩壊寸前の異世界がスタジオジブリを暗喩しているというわけだ。
そしてこう見ると、異世界が現実にパワー負けしている本作のバランスは、加齢とともにファンタジー的想像力を失いつつある宮崎監督とスタジオジブリの現実を見事に反映している。もちろん実力が衰えているのは事実なのだが、その衰えを作品のテーマとして昇華しているのではないか、というのがこの解釈のポイントだ。
◆宮崎駿VS宮崎駿
この解釈をとると、本作は「宮崎監督が宮崎少年にスタジオジブリを継承しようとして拒否される(ついでに母親といちゃつく)」という、実に奇妙なストーリーになってしまう。当の宮崎監督が継承してくれと言っているのに、なぜ宮崎少年はそれを断ってしまうのか。
ここでのキーワードは、劇中のセリフでも出てくる「悪意」だ。宮崎監督はこれまでの作品(特に『もののけ姫』以前のもの)で、薄汚れた大人と無垢な少年少女たちを対比的に描いてきた。そこには当然、「俺たち大人はもう手遅れだから、せめて新しい世代の子どもたちに理想や希望を引き継ごう」という監督の想いがこめられていた。
ところが、現実の子ども=宮崎少年は利己的で嘘もつく、無垢でも何でもない存在である。宮崎少年としては、自分はそんな監督の理想に応えられるような無垢な人間ではないので、とても引き継ぎなどできない。なので、大げさな理想を引き継ぐよりは、外に出て青鷺のような(鈴木敏夫のような)友達を作るよ、と冷淡な返事を返すことになる。
◆本家『君たちはどう生きるか』と真反対のニヒリズム
ここで表現されているのは、教養と反省によって人生はより良く生きることができるというムードに満ちた本家『君たちはどう生きるか』とは真反対のニヒリズムだ。
宮崎監督=大叔父が生涯をかけて積み上げてきた異世界は、子どもからは継承を拒絶され、無理解な後継者たちのメタファーとしてのインコ(さまざまなモノの隠喩だ)のずさんな扱いによって崩壊する。宮崎監督自身もその崩壊と運命をともにする。辛うじて残っているのは、宮崎少年の中にある異世界の記憶だけだ。しかし、それもやがて忘れてしまうだろう、と青鷺に言わせて、物語は終わる。
もし、この記憶が宮崎少年の人生にポジティブに影響し、彼が外の世界に果敢に飛び出していくというのなら、それはまだ明るい結末と言えるだろう。しかし、主人公には宮崎少年が投影されているわけで、おそらく彼はこの後、最終的に大叔父と同じような人生を辿ることになる。つまりここでは、かつての宮崎アニメにあった「子どもたちがより良い未来を切り開く」という進歩的な観念が完全に切り捨てられ、ただ不毛な人生が循環するだけの殺伐とした世界観が提示されているのである(『もののけ姫』的世界観をさらにネガティブにしたものと言ってもいいだろう)。
◆「私はこう生きた、君たちはどう生きるか?」
以上のように、最終的に提示された世界観はかなり絶望的なものだが、だがしかし、ラストシーンは決して暗いものではない。それは、これが宮崎監督が宮崎監督自身の内面を描いた映画であり、社会や観客に対するメッセージというものがまるで欠如していることから来ている。
この映画は、設定からして観客の感情移入を徹底的に拒んでいる。戦中が舞台なのに、主人公が飛び抜けた富裕層なので、まったくその悲惨さが描かれない。心情描写や論理をスキップして、映画の進行から観客をあえて振り落としているようにすら見える。なぜそんな邪道なことをするのか。そう考えた時、本作が最初から観客を突き放して「自分の物語」だけを語ろうとするプライベートフィルムだったと考えると辻褄が合う(それ以外の解釈では、この作品は構造だけが提示される不気味な作品としてしか鑑賞できないと思われる。もちろん、それはそれで良い)。
そしてこのプライベートさが、ラストシーンの不思議な明るさを支えている。自分の人生はこのように殺伐としたもので、あれほど満ち満ちていた外の世界に対する夢も萎え、最後には母親に対する執着や失望感しか残らなかった。しかし、そんなに悪い気分でもない。また、君たちの人生がどうなるかは知らない。本作を見終わった後には、かつての作品が発したような重苦しいメッセージではなく、「私の人生はガラクタを積み上げるだけのくだらないものだったが、振り返るとそんなに悪いものじゃないし、君たちの人生もたぶん大丈夫なんじゃない?」というような、そんな軽やかな後味が残るのだ。
◆参考サイト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
