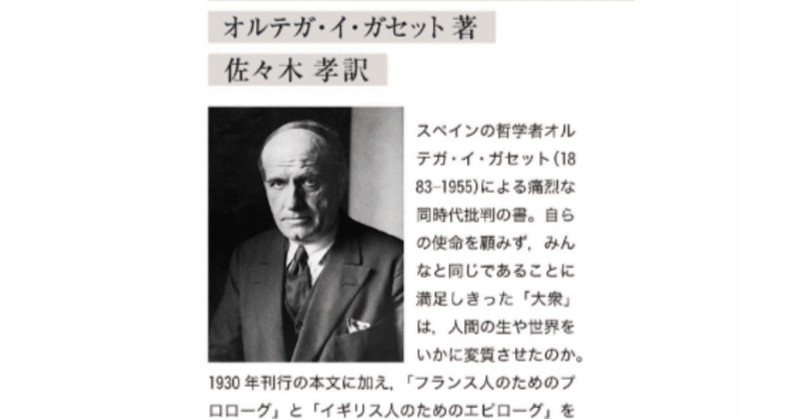
大衆化した人間の典型としての専門家
以下の続きとして。
分科会の専門家たちのインタビューを読んでいると、この本の内容を思い出さずにはいられない。
原本は1930年発行。なのに、彼ら専門家たちの愚かさの理由は、全てこの本に書かれている。本当に困ったものである。
いや、他人事ではない。影響力は少ないとはいえ、私自身も気をつけねばならない。
この本に関しては、この3年間多くの方々に取り上げられてきたので今更感はあるが、自分の備忘のために多く引用させて頂いた。
以下、2020年に出版された岩波版(佐々木孝訳)より。太字及び()内は引用者。
「1.密集の事実」より。大衆が定義される。凡俗であることに満足しきっているだけでなく、「満足していること」を根拠にマウントを取りに来る人間だ。
大衆とはあくまで「平均的な人たち」のことを言う。
大衆とはおのれ自身を特別な理由によって評価せず、「みんなと同じ」であると感じても、そのことに苦しまず、他の人たちと自分とは同じなのだと、むしろ満足している人たちのことを言う。
いまや大衆は、自分たちがカフェーで話題にしたことを他に押しつけ、それに法としての力を付与する権利があると信じているのだ。
現代の特徴は、凡俗な魂が、自らを凡俗であると認めながらも、その凡俗であることの権利を大胆に主張し、それを相手かまわず押しつけることにある。
「8.大衆はなぜ何にでも、しかも暴力的に首を突っ込むのか」より。彼らの言葉がなぜこんなにも軽いのか、それはあまりにも「慎重さに欠ける」からだ。
人はおのれの内部にいくばくかの思想を持っている。それらに満足したり知的に充足しているとみなすことにしてしまう。自分以外のことに何一つ不足を感じないので、自己の思想に限られたレパートリーに最終的に落ち着くことになるのだ。自己閉塞のメカニズムがここにある。
彼の魂の生来の自己閉塞性は、自分の不十分さを発見するための前提条件、つまり他人と比較することを妨げる。比較することは束の間だけ自分自身から出て、隣人の身に置き換えることと言えよう。しかし凡庸な魂には、崇高なる運動であるこの置き換えが不可能なのだ。
彼はたまたま自分の内部に溜まった一連の決まり文句、偏見、観念の切れっ端、あるいは意味もない語彙を後生大事に神棚に祀ったあと、天真爛漫としか説明しようのない大胆さをもってそれらを相手かまわず押し付けている。
知性の規律正しい養成と実践の少ないことは、知識が多いか少ないかではなく、話したり書いたりする人たちが通常示す、真実に向き合うための用心や注意が常に欠如しているところに現れている。
(中略)
正しく判断するための基本的な必要条件すら満たさない事態を引き起こす注意の欠如こそが問題なのだ。
私たちの考えの理由が議論されるときのその対話こそが共生のための最良条件であると信じることなのである。しかし大衆化した人間が議論を受け入れたなら、自己喪失に陥る。そして自分の外にあるその最高審判を尊重すべきとの義務を本能的に拒否するのだ。
「11.満足しきったお坊ちゃん」の時代 より。彼らの自信は、根拠なき万能感と視野の狭さにより成立している。つまり駄々っ子に過ぎない。
大衆というこの新しいタイプの心理学的構造を研究するなら、次のようなことが見出される。
第一に生は容易で余裕があり、悲劇的な制限も無いとの生得的かつ根源的な印象。そこから一人ひとりの平均人の内部に支配と勝利の感覚が見出される。
第二にこの支配と勝利の感覚は、平均人に、自分の道徳的ならびに知的資産を良きもの、完璧なものとみなすほどの自己肯定へと向かわせる。こうした自己満足は、外部からのすべての示唆に心を閉ざし、他人の意見に耳をふさぎ、自分の意見を厳しく検討せず、他者を考慮に入れない考え方へと導く。
(中略)
こうして彼は、あたかも彼や彼の仲間だけがこの世に存在しているかのように行動するだろう。
したがって、第三に彼は自分の凡庸な意見を配慮も内省も手続きも保留もなしに、つまり「直接行動」様式にのっとって主張しながら、あらゆることに介入してくるだろう。
(中略)
現在そこら中を歩き回り、ところ構わず自分の野蛮性を押し付けているこのような人物は、実のところ人類史の中の甘やかされた子供なのだ。甘やかされた子供はひとえに相続することしかしない相続人である。
(中略)
世界の文明によって生み出された生の余裕のなかでのみ、前述のような特徴を取り揃えた人間、またそうした性格によって作り上げられた人間が登場することができたのだ。
「12.「専門主義」の野蛮」より。彼らには、本物の知を構成する断片が与えられている。でも、それは全体のほんの一部にすぎない。しかし彼らはそれで満足しきっている。本物の知を手に入れることなど望まず、ただマウントをとることにしか興味がない。
発展するために科学が必要としたのは、科学者の専門化だった。それは科学それ自体ではなく、科学者の問題だった。科学そのものは専門主義的ではない。
もしそうなら、事実上、科学は真実であることを止めるだろう。(中略)(実験科学が)数学や論理学や哲学から切り離されてしまえば真実ですらないだろう。
分別ある人間になるためには知らなければならないことがいろいろあるが、彼はある特定の科学しか知らない。(中略)特別に開拓した狭い風景の外にあることについては何も知らないことを、一つの美徳であると宣言するまでになり、総合的な知的好奇心を偉そうにディレッタンティズムと呼ぶのである。
補:ディレッタンティズムとは「専門家以外の者が道楽や趣味として学問や芸術を楽しむこと。」で、「真の美的体験に備わるべきたいせつな何かを欠いているという意味で、否定的ニュアンスが含まれることが多い。」という。
研究者を効果的に使うためには、科学を小さな部門に分けること、その一つの門に閉じこもって他のことには関与しないというのはあり得る。方法の堅固さと正確さのためには、知識のこうした過渡的かつ実践的な分節化は許される。その方法の一つを機械のように用いて仕事をすればよく、豊かな成果を挙げるには、それらの方法の意味とか基礎について厳密な考えを持つことさえ必要ないのだ。
(中略)
しかし、こうした事態は、とびきり奇妙な人間の血統を創り出した。事前の新事実を発見した研究者はどうしても天下を取ったような気分になり、自分に対する人格的な自信を持つはずだ。自分を「ものを知っている人間」と見なすのもある意味では理にかなったことだろう。事実、彼の中にはない諸々の他の知識の断片と一緒にすれば、本物の知を構成するであろう何某かの断片が与えられている。(中略)専門家は、世界の中の自分の一隅だけは実に良く「知っている」。しかしその他すべてに関して、完全に無知なのだ。
政治、芸術、社会慣習、そして自分の専門外の学問において、彼は原始人のような完全に無知な態度をとるだろう。その際にも、他の専門家たちを認めずにーーここが逆説的なのだがーー力強く自信たっぷりな態度なのだ。彼を専門家にするにあたって、文明は彼を自ら閉じこもり、自分の限界内で満足する人間に作り上げてしまった。しかし、まさにその自律と自信の内的感覚そのものが、彼を自分の専門領域の外でも支配的位置に立ちたいという願望をもたらすのだ。
以上より、
現代の科学者は大衆化した人間の典型である。
オルテガ恐るべし、としか言いようがない。
しかし、この内容によれば、「陰謀論で満足している人間」も大衆だな。
そういう意味では専門家が陰謀論に陥りやすいのは当然といえば当然、なのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
