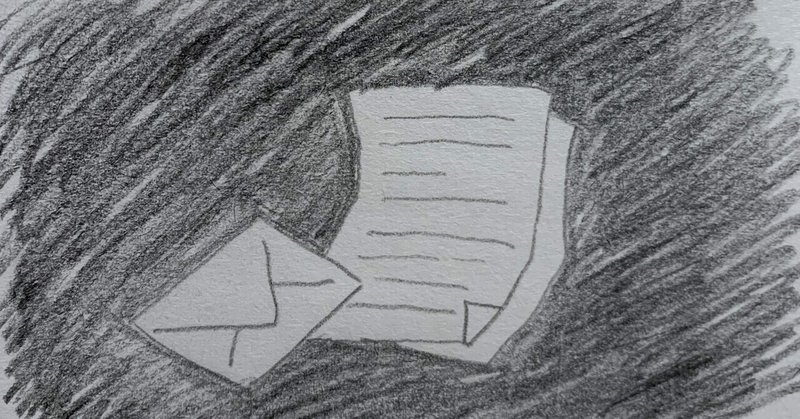
マントルおじさん 最終回「レクイエム」
「ところで、さっきわしが料理をしていたとき、君は何をしてたんだい?」
スプーンでカップの中のコーヒーを掻き混ぜながら、マントルおじさんが私に尋ねた。
私は何も飲んではいなかった。
「おじさんの書斎らしき部屋で、ヒトラー関連の本を読んでいたんですよ。でもヒトラーの写真集なんてものがあってびっくりしましたよ。購入する人もあまりいないでしょうね」
「でも君はその写真集を見たんだろう?君だって私と同じディレッタントだよ」
「いや…、はは…まあ…」
マントルおじさんはコーヒーを一口飲んで息をついた。
その姿からは抽象的なものさえ何一つとして読み取れなかった。
「君はヒトラーのどんな写真に惹かれたんだい?演説中の姿かい?」
「いえ、違います。私が興味を惹かれるのは彼の笑顔の写真だとか、彼以外の人々も一緒に写っている写真です」
「ヒトラー以外の人々も?」
「ええ。他の人々の中にヒトラーが『いる』
というのが不思議なんです。ヒトラーのような人物が、人々の中に混ざって写真に写っている。これが何か私にしこりのようなものを感じさせるんです」
「うーむ」
マントルおじさんは唸った。そして残りのコーヒーを啜り、さて、と言って椅子から立ち上がった。
「君もそろそろおうちが恋しいだろう。タクシーを呼んであげるからもう帰りなさい」
こう告げてマントルおじさんは他の部屋へと姿を消した。
タクシーが到着した。
私の頭を一瞬疑問がよぎったが黙殺することにした。
この世に不思議なものなどない。
ただ人間がそう感じるだけ。
運転手はウサギだった。そのウサギはちゃんと運転手が被る帽子をかぶっていて、その姿はピーターラビットの世界を思い出させた。
マントルおじさんは玄関まで見送りに来た。
そして私に一緒に食事ができて楽しかったよ、と言った。
私は微笑み、その言葉に含まれた意味など決して穿鑿するものかと自分へ対して舌を出した。
私はタクシーの後部座席に乗り込んで、マントルおじさんへ手を振った。
向こうも笑顔で手を振りかえした。
ウサギの運転手はアクセルを踏み込んで発車させた。
タクシーが走り出して20分ほど経った頃、運転手が話しかけてきた。
「お客さん、クラシックはお好きですかい?」
私は、口を動かすたびにピクピクと揺れる運転手の髭を見ながら、はい、好きですよと答えた。
運転手はそんならいい、と言ってカーステレオのスイッチを押した。
ワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』が流れてきた。
「あたしはクラシックが好きなんですよ。人生、時間は限られてるから、聴くものも厳選しなくちゃあ」
私を乗せた、音楽好きのウサギが運転するタクシーは地球表面へと戻ってきた。
しかも運転手は親切に私の家まで送ってくれ、代金はいらないと言った。
私は「それなら家からニンジンを持ってきましょうか」と言おうと思ったが、安直なジョークとして相手の気分を害するのではないかと心配になってやめた。
「いいんですよ。あのおじさんはあたしをよく使ってくれるし、あなたとも音楽の話ができて嬉しかったし。またいつかお会いしたときに、ニンジンでもご馳走してくれれば結構でさあ」
タクシーは淡い光を発しながら遠ざかっていった。
私はしばしその場に立ち尽くし、やはりニンジンを持ってきてやればよかったと悔しくなった。人生はこういうことばかりだ。
3日後、マントルおじさんの死を知らせる手紙が届いた。
差出人はあのタクシー運転手だった。
私は数多湧き出てくる疑問を頭から追い払いながら、手紙を読むことだけに集中した。
あのウサギはこう書いていた(日本語で)。
貴女がお帰りになられた翌日の朝、マントル様はお亡くなりになりました。
お伝えすることは私としても非常に辛いのですが、自死でした。
自宅の牧場でピストルで。
第一発見者は私でした。
そして、よく探したのですがマントル様の遺書は見つかりませんでした。
マントル様のご遺体は亡くなった翌日に鳥葬に付しました。
貴女のお住まいになる国ではこの鳥葬はきわめて珍しい方法だと思われますが、私どもでは一般的な埋葬方法でございます。
とにかく、この手紙では事実のみをお伝えすることにいたします」
私は手紙を読み終えた。マントルおじさんの自殺。マントルおじさんの自殺。
完
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
