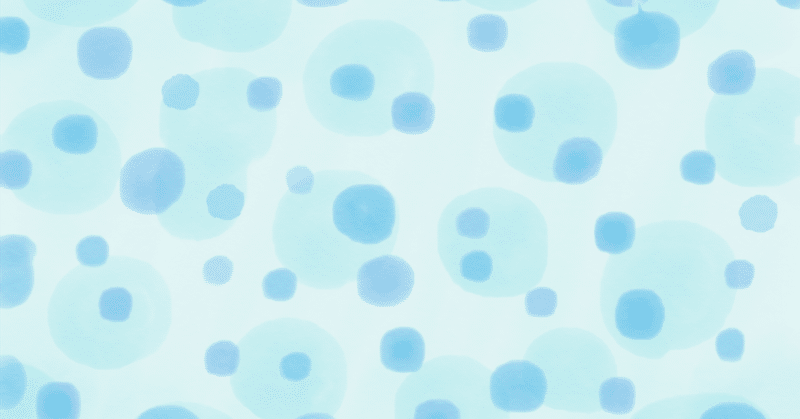
Photo by
hananono
明倫館(日本教育史:幕末)
明倫館(めいりんかん)は、長州藩の藩校。水戸藩の弘道館、岡山藩の閑谷黌と並び、日本三大学府の一つと称された。
毛利氏は大江匡房や広元を祖とする家柄で、学問を重んじる伝統を持ち、享保3年(1718)、5代藩主毛利吉元が明倫館を創建した。
江戸時代に全国で300近くあった藩校のうち12番目に出来たもので、三の丸(堀内地区)の旧明倫館は940坪の敷地内に、孔子、孟子などの木主を納めた大成殿を中心に配置され、左右に剣術場、槍術場、砲術場などの武道場が館の外周を形成していた。
藩主吉元は、明倫館初代学頭の小倉尚斎とともに幕府大学頭林家の塾である昌平坂学問所に学んだ林家朱子学の正系であったので、藩学の構造、教育内容、儀式等多くが昌平坂学問所を模範としたものであった。
「明倫館」の名称は、当時の侍講、2代学頭となった山県周南の命名による。出典は「孟子」の滕文公編(上)の三章。
「上に立つものが教育の力によって人間の道を明らかにして教え導けば、下、人民はみなそれに感化されて互いに親しみあい国は大いに治まる(皆、人倫を明らかにする所以なり)」
明倫館は、設備、教育内容ともに全国でも有数の藩校とされる。嘉永2年(1849)に現在地(江向)に移転するまでの130年間にわたって、ここで藩政を担う藩士育成のための教育が行われていた。天保11年(1840)吉田松陰(当時11歳)が藩主毛利敬親に「武教全書」の御前講義を行ったことは有名。なお、現在は旧明倫館の石碑が建つのみで当時の遺構はない。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
