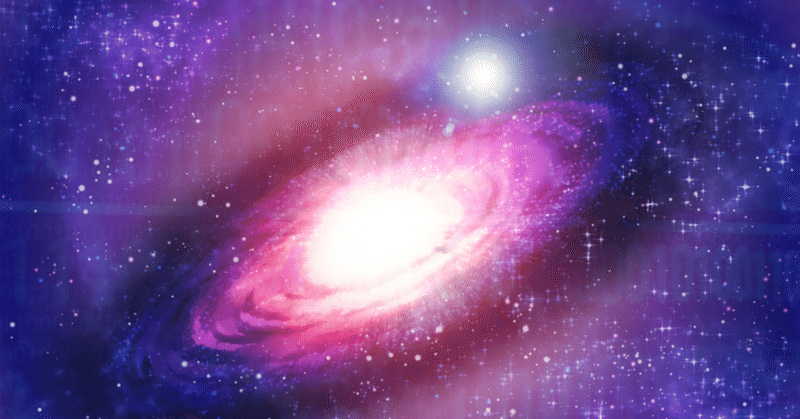
【オリジナル小説】ブラックホール病
ねぇパパ
「ねぇパパ、私はいつまでここにいなくちゃいけなの?」
娘のシルビアが曇りガラスの向こうに何か絵を描きながら言った。
「そうだね、もう少し、かな」
「もう少し?もう少しってどのくらい?」
屈託のない目でこちらを見てきた娘を見て唇を噛み締めた。
「そうだな…」
考えるふりをして下を向いた。いろんな感情が私を襲ってきたのを娘に悟られたくなかった。
「ねぇパパ!」私に考えがあると言わんばかりにシルビアが声を上げた。
「パパのいた場所で一緒に暮らせばいいんじゃない?」
「パパのいた場所…」
「チキュウって言うんでしょ?小さい頃お話ししてくれたじゃない」
「地球か…」絶対に無理だ、無理なんだよシルビア。
私の顔が曇ったのを見てシルビアは慌てて謝ってきた。
「私の体じゃ無理なんだったよね、ごめんねパパ」
「違う…シルビアは悪くないんだよ…」小さく呟いた言葉は看守に遮られた。
「すみませんがお時間です。」
まだここにきて10分も経っていないのにそんなことを言うのか。くそっ、私が弱い人間でなければもっとシルビアと話せたのに…もっと一緒にいることが出来るのに。
「あの、もう少しだけでもシルビアと話させてくださ…」
曇りガラスのだった向こう側から唸り声が聞こえた。
ハッとして声のする方を向くと黒々とした怪物がいた。
「ネェパパァ…」その怪物は執拗にガラスのこちら側にいる私を見ながら唸っていた。看守が私の肩を掴んで椅子から立ち上がらせた。「すみませんがお時間です。」
ガラスの向こうの、怪物の目の奥に語りかけるように「また来るよ」と言ってその場を去った。ドアを閉めるその時までずっとあの怪物が私を呼んでいた。
「ねぇパパ」と。
あの子の母親
「あの人間、まだここに来てんのか」
「あの調子じゃもしかしたら食われるかもな」
「まぁ娘に食われるんだったら親として本望なんじゃないか」
地球からそんなに遠くない、と言っても簡単に来れるわけではないこの星の名前はシルビアと言った。奇しくもあの人間の娘と同じ名前だった。
「にしてもあの人間もよく生きてこれたよな」
「それがよ、あの娘、自分がブラックホール病だと知らないんだと」
「はぁ?」
「であの人間は騙し騙し娘をここまで連れてきたらしいぜ」
「騙し騙しって一体どうやって…」
ブィーブィーとサイレンが二人の会話を遮った。
「もうそんな時間か」さっきのサイレンは空調食堂が開店した合図だ。あんまり腹減ってないけどな、と思いながら二人で食堂に向かう。食堂にはすでに人だかりができていた。(ここで言う「人」は地球人にとっては「人ではないもの」になるが。)順番にカプセルをもらう列に混じってさっきの会話の続きを促した。
「で、どうやってあの人間はここまで無傷で来れたんだ?」
「いやそれがさ…」
「母親を食わせながら来たんだろ?」
「えっ」二人の後ろに並んでいた一回り大きいやつが答えた。
「あいつの父親が母親を捌いて、ここに来るまでの間母親の肉をあの娘に食べさせてたってよ。しかも娘にはそのことを言ってないらしい。」
「なんで知ってんだよ」
「俺、あの娘のカウンセラーの子と付き合ってっから」
二重の事実に驚きながら二人は顔を見合わせた。そして二人同時に叫んでいた。
「俺も狙ってたのに!」
ブラックホール病
ブラックホール病とはいえど解決策はあるはずだ。
そう思って人間の年月の半分を使ってきた。きっと彼女にも何か理由があって発症したんだ。その理由さえ突き止めれば…と考えていた矢先、サイレンが鳴った。
あぁまた1日が過ぎ去ってしまう。時間をかければかけるほどその症状は悪化して最終的には…死んでしまう。いや消えると言った方がいいだろうか。
ブラックホール病は簡単にいうと共食いをしてしまう病気だ。
最初は近くの小さな惑星同士がぶつかってブラックホールになった。まぁブラックホールなんてよくあることだと思っていたら実は片方の惑星がもう片方の惑星をブラックホールという、まぁ人間で言う「口」で食べていたのだ。惑星同士の共食いだったわけだ。惑星を共食いした惑星は少しずつ大きくなって私たちが住めるような快適な場所に変わっていった。そのことを知ったお偉いさん方が視察を送り込んだはいいもののそこで貰ってきてしまったのだ。病原菌を。
視察に行った一人が同僚を食べ出した。その姿は怪物だった。どろどろした真っ黒な姿で同僚の名前を執拗に呼びながら食べていたのだ。そして面白いことにその同僚を食べ終わった後、元の姿に戻ったのだ。しかも食べていた時の記憶がないようで自分の口の周りについた血を拭って驚いていた。「誰がこんな嫌がらせをしたのか!」と。
その後、自分が同僚を食べてしまったという事実を知ってしまった彼は消えた。文字通り、消えていったのだ。まるでブラックホールのように蒸発しながら。
私は調べた。視察に行った彼と食べられてしまった彼の同僚を執念深く調べ上げるつもりだった。この建物にはいつくもカメラが設置されていて、その時の映像がしっかりと記録に残っていたからだ。
そして視察に行った他のメンバーは隔離という形でこの建物の厳重な場所に監禁されている。
はずだった。
まだ何が原因かもわからないのに監禁されてたまるかよ、とメンバーの一人が脱走したのだ。それが広まるのはあっという間だった。
空気中で感染していることがわかってからのお偉いさん方の対応はやけに遅く感じた。検討するしないのおままごと会議しているからこういう大事な場面ですぐに判断できないんだ!と各方面から叩かれ、さらにはその中の一人がブラックホール病にかかってしまい、今やこの惑星シルビアに口だけ達者な権力者はいなくなった。
そうなってからの住民たちは各自で役割分担をしながら生きている。
私はここでは医者であり、ブラックホール病の研究者だ。
大丈夫。
「俺たちってさ、生まれた時からこのカプセル飯じゃん?」
背中についた酸素ボンベのようなカプセルを指差しながら一人が言った。
「ん?あぁそうか、そうだな。それで?」
「いやなんかさ、このカプセルじゃない飯が本に載ってたなぁって思って。俺らの前の前の世代とかってそうだったわけじゃん?どんな感じなのかな、飯って。」
「さぁな、口を動かさないと食べれないらしいけど」
「口って喋らない分にはなくても困らねぇよな」「まぁな」
なんて呑気に喋っていたところにいつもとは違うサイレンが鳴った。
その場に一緒にいたものはみんなシンと静まり返った。このサイレンは感染者だ。
ずっと離れていてはやはりダメだ。どうにかして私はあの子と一緒にいなくては。
大丈夫、だってこの惑星に来るまでは二人っきりでも大丈夫だったじゃないか。
こっそりと警備の目をくぐり抜けあの子の元へ向かう途中だった。身体中が熱く燃え上がってきたのだ。
「痛い!」叫んだ声が近くの警備員に聞こえたらしい。「どうしました?!」と声をかけながらこちらへ駆け寄ってきてくれた。
「い、痛いんです!体がぁいだぁい…」
喉から搾り上げた声が呻き声に変わっていく。
「パパが呼んでる」
シルビアはそっと椅子から立ち上がり耳をすました。
「うん、やっぱりパパの声だ」
だからと言ってこの牢屋のような白い部屋から抜け出すことはできない。
それにこの部屋から抜け出せたとしても看守が何人もいるのだ。
「どうしよう…」と途方に暮れていると奥から声がした。「大丈夫」と。
「その人間から離れて!」
私もいつかこうなるのではないだろうか?そう思いながら発する言葉にためらいを感じながら、体を震わせているシルビアの父親から警備員を離した。
「でも…」という警備員に「私はここの医者だ」と説明した。
もしかしたら…と思いながら少し離れたところでビクンビクンと体を震わせているシルビアの父親の様子を見る。
「あの…助けなくていいんですか?」
「もう少し待ってください」もう少し、多分もう少しで…変わった!
シルビアの父親はあの黒いどろどろとした怪物の姿に変わった。
「ひっひぇぇぇぇ!こっ殺される!」腰を抜かした警備員に言った。
「大丈夫です、あの怪物は私たちなんか食べませんよ」
「え…?どういうことですか…」
怪物はゆっくりとした動きで辺りを見回した。そして動きがピタッと止まったかと思うとある方向へと歩き出した。やっぱり。
「シルビアのいる部屋の通路を解放してください、全て。」
無線で看守やその近くの警備員に語りかけた。
一番愛する人
しっかりとした足取りで歩くそれは見ているものを驚かせた。
中には腰を抜かしてしまうものもいたが、ほとんどの人がそっと見守った。
「…ルヴィア、マッデデパパガイグガラ」
喉の奥の奥、心からの叫びのような呻き声が行く先々で響き渡った。
「あの…先生、僕たち大丈夫なんでしょうか?」
「何がですか?」
「その…あの怪物の後をついていったりして」
「大丈夫です。」
彼女にはキッパリと言い放つ確信があった。いや今までの研究では確信を得られなかったがシルビアの元へ行く彼女の父親の姿を見て確信に変わったのだ。
最初の犠牲者だった彼はどうして同僚を食べてしまったのか。
初めは近くにいたから食べられたのだと思った。
しかし脱走した視察メンバーがブラックホール病になって食い殺したのは近くにいた家族ではなく少し離れた場所に住んでいた恋人だった。
次にお偉いさんの一人が食い殺したのは孫だった。まだ3歳の誕生日を迎えたばかりでそれはそれは溺愛していた。見せてとせがんでもいないのに誕生日に撮ったという写真を見せてくれるほどに。
そうなると最初の彼と同僚の関係が気になった。
調べていくうちに分かったのは彼が同僚に好意を持っていたことだった。
それはどの事例を見ても当てはまった。
犠牲者はみんな自分が一番愛する人を食べていた。
そして自分が食い殺してしまったことを知ると消えていった。それは悲しいほどに納得できるような、でもそうであってほしくない結果だった。
ずっと一緒にいるからね
「俺、愛する人とかいないんだけど」
「じゃ感染しないんじゃね?」
「でも俺のこと一番に思ってくれてる子が…」
「いねぇな」
「…なら安心だな…」
無線で流れてくる博士の仮説とも確信ともとれる話に皆は頷いていた。
「だけどそれじゃあシルビアってやつは特殊だな」
「確かに、消えてなくなってねぇよな」
「んで今度は父親の方が怪物になったろ?なんでだ?」
「…俺さ」
「ん?どした」
「俺、犬と一緒にいたんだよ。ガキの時に。」
初めてみる相棒の顔に少し戸惑いながらその次の言葉を待った。
「でもよ、そいつあっさり死んじまったんだよな。結構歳食ってたみたいで、まぁ寿命ってやつだな。」泣きそうな顔なのに少し笑っていうもんだからこっちが涙を流さないようにしなくちゃならなくなった。
「んで火葬してもらって骨だけになったそいつのさ、骨を食べたんだ」
「っはぁ?!」でかかってた涙が引っ込んだ。
「なんかさ…一緒にいたかったんだよ。ずっと一緒にいれると思ってたからさ。このまま一緒に死ぬんだと思ってた。」
「待て待て待て!お前骨食ったのかよ!どうやって食ったんだよ!てか他のやつは気が付かなかったのかよ!」
ニシシと笑った顔にはさっきとは違う少しスッキリした雰囲気があった。
「なんか、みんな同じこと考えてんのかもな。好きだから一緒にいたいって。」
「だからって食うなよ…」
パパが近づいてきてる!
誰も居なくなった白い部屋で椅子に座って耳を澄ましていた。
もしかして私の病気が治ったのかな?だから迎えにきてくれてるのかな?
ママがいつの間にかいなくなった時は本当に悲しくて寂しくて苦しかったけど、パパがいつもそばにきてくれて「大丈夫、パパがずっと一緒にいるからね」って言ってくれた。だからもう私は泣かなかった。
絶対に病気を治してそれでパパと一緒に…一緒に…ずっト…イッショニ…
まただ。なんでかな、パパのことを考えると眠たくなる。
寝ちゃだめ!もうすぐパパが迎えに来るんだから!
「シルビア」「パパ!」
それは見るに耐えない光景だった。
お互いがお互いを喰らいあっているのだ。
「せっ先生〜!」一緒についてきてくれた警備員が弱々しく叫ぶ。
「怪物同士で食い殺そうとするなんて…」
予測と違った、いやこうなることも予想はしていた。
もうこれは一つの賭けに出るしかない。右腕…いや左腕の袖を捲り上げた。
「せっ先生?!何してるんですか?!」
「いいですか、ここまでついてきたんだったら最後まで頼みますよ!」
「なっ何をですか?!」
「私が死んでもこの親子は必ず助けてください。いいですね!?」
警備員が返事をするのを待たずに怪物になった二人の間に自分の左腕をねじ込んだ。たぶん娘のシルビアの方だろう、その左手に食らいついた。
「っっ!!」想像を絶する痛みに耐えながら父親の方に顔を向けて言った。
「あなたは食べなくていいんですか?」
声が届いたのだろうか、その顔、いや大きな口は彼女に食らいつこうとしていた。
「どうかこれでこの親子が元の姿に戻りますように」目を閉じて覚悟を決めたその時、大きな口の前に警備員が覆いかぶさるように立っていた。何かを私に叫んでいるようだったが意識が遠のいてよく聞こえなかった。
名前を呼ぶこと
「それであなたは助かったんですね」
何十台ものカメラが壇上にいる私を映し出していた。
インタビュアーは私の言葉を待っていた。
「はい、あのバ…あの警備員がいなければ私は確実に死んでいました」
その言葉を待っていましたと言わんばかりにフラッシュがたかれる。
「ではブラックホール病の新薬開発でのお話をお聞きしたいのですが、新薬開発にはあの親子が携わっていると聞きましたがそれは本当でしょうか?」
「シルビア・ミラーとシリウス・ミラーについてはこの後本人たちが質問を受け付けますので」
割ってはいってきたのは右腕のない警備員の姿だった。
「申し訳ございませんが、今はセレス先生…セレス・リーの質疑応答の時間になります。ご理解いただけますよう…」と何食わぬ顔で言い放ってはいるが全く、油断も隙もない。
あの後、私とシルビアの父親の間に割ってはいってきた警備員は右腕を持っていかれた。それはもう見事なまでな食いっぷりだったそうだ。(本人談)
そして私の左腕はおかしなことに大きな咬み傷だけで済んだのだ。私の勝手な推測だがシルビアだった怪物は自分が一番愛していた母親を食べていたからそこまでお腹は空いていなかったのではないだろうか?
その証拠に警備員は父親の方にガッツリ右腕食べられちゃったわけだし。
シルビアの父親は愛する娘ではなく、さっき顔見知りになったばかりの男の腕を食べてしまい悶え苦しんだらしい。シルビアはというと、私の腕から溢れる血を飲んだだけで吐き気がしたそうだ。そして元の姿に苦しみながら戻った。
私がこの作戦の結果を予測し実行するまでには時間がなかった。だからほとんど賭けだったのだ。それなのにこの男ときたら…ちらりとそばに立っている警備員の顔を見ると目があった。嬉しそうに「どうしましたか?セレス先生」と耳元で囁いてきた。しっしっと手を振ってそばまできた顔を追い払う。それでも嬉しそうなのだからおかしなものだ。
「まだっ先生の名前をお聞きしてっ、いませんーっ!!」
腕を噛みちぎられながらいう言葉じゃないと思ったが言わないと後悔しそうだった。
彼女の第一印象はとても頭の回転が速い人だと思った。そしてとても優しいのだということも声から感じ取った。
「その人間から離れて!」と叫ぶ声には誰も死なせたくないという強い意志があったからだ。なぜかその瞬間から彼女のそばを離れてはいけない気がした。たとえ目の前の人間が怪物に変わっても、だ。
シルビアさんがいるという部屋まではとても遠く、そしてたどり着いたら帰ってこれないのではないかという不安を煽る道のりだった。
先生は無線でずっとみんなに今通っている場所を伝えていた。その声がなければ道の途中で精神的に参ってしまっていただろう。
それほどまでにセレス先生の声は力強く、優しかった。そして一番の理由は声がとても素敵だったのだ。ハスキーなはずなのになぜか透き通ったような魅力的な声だった。「あぁその声で自分の名前を呼んでもらえないだろうか…」なんて考えている間に先生はあの怪物同士の恐ろしい間に飛び込んでいた。
はっきり言って自分は怖がりで臆病だ。警備員なんて仕事も本当はもうやめようと考えていた。それでも彼女が怪物に食われそうになっているのを見たら体が勝手に飛び出していた。
「二度とそんな真似しないで、スイ」と彼女にきつく言われたがきっと無理だと思う。あの声が自分の名前を呼んでくれるのなら、何度だって自分はセレス先生を助けに行くだろう。
「では怪物化した患者が名前を呼ぶわけですね?」
「そうです、その人にとって一番愛する者の名前を呼びます。その声に反応しないように。反応すればあなたの居場所がすぐにバレます。そして怪物化した患者は興奮状態に陥り食らいつきます。」
「…」インタビュアーたちは何度もあのおぞましい映像を見たのだろう、一瞬会場が静かになった。
「研究の結果、怪物化した患者の多くが視力ではなく聴覚を使っていることが判明しました。」
ざわめく会場の端の方で二人の親子が次の出番を控えていた。
「パパ、あのね」
「ん?どうしたんだい?」
「緊張しちゃってるの」
「パパもだよ、シルビア」ふふっと笑い合った二人をスイが呼んだ。
「ミラーさんこちらへ」
「なんかコイツ面白いじゃん?」と思われたそこのあなた!! そうです!そこのあなたです!よかったらサポートしてくださぁあああああいぃ!!!! 創作作品を制作するための資金にさせていただきます! よろしくお願いしまあああああああああああああああああああすっ!!!!💪✨
